音楽理論ライブラリーでは前回までで、コードの基本と、3和音(トライアド)コード、4和音(6th、7th)コードを学習しましたが、まずはコードに関する知識を網羅していこうと思います。
今回は基本コードに響きのバリエーションを持たせる「テンションコード」の解説です。
今まで扱っていたコードは3和音(1+3+5)と4和音1+3+5+7)で、コード機能的にはこれだけでも事足りますが、コードの中には9とか13とか、7以上の数字が書かれているものがありますよね?
これが、今回のテーマである「テンションコード」です。
テンションコードとは?
4和音コードのさらに上に、5和音、6和音と3度間隔で積み上げていったものを、テンションコードと呼びます。
テンションコードは「テンション」の語源の通り緊張感を演出し、ベースとなる3和音コード・4和音コードに豊かな色彩感を付加します。
コードの5番目以降の音を「テンションノート」と呼びます。
例えば、Cメジャースケールをド、ミ、ソ、シと鍵盤を1つ飛ばしに弾いて3度堆積していくと、シの次はオクターブ上の「レ」になりますが、この「レ」がテンションノートになります。
テンションノートとしてして扱われる音は、スケールの2、4、6番目の音と同じになりますが、「4和音コードの上にさらに3度ずつ積んでいく」という発想から、9、11、13番目の音という扱いになります。上の例の「レ」なら9thですね。
テンションの種類は9th系、11th系、13th系の3種ですが、テンションノートも♭や♯して変化したり、複数のテンションノートが同時に付加されたりするので、テンションコードのバリエーションは膨大な数になってきます。
ここでは基本的なテンションコードの作り方と、一般的によく使うテンションコードを解説していきます。
ノンオルタードテンションとオンタードテンション
テンションノートは大別するとノンオルタードテンションとオルタードテンションの2種類あります。
ノンオルタードテンション
ノンオルタードテンションは、♯や♭が付かないテンションノートで、9th、11th、13thの3種があります。
主にダイアトニックノート(臨時記号無しの普通のドレミ)が付加され、比較的素直な響きです。
オルタードテンション
♯や♭がついて変化したテンションノートで、♭9、♯9、♯11、♭13の4種があります。
♯11はメジャー7thコードにつくことがありますが、他はドミナント7thコードに対して使うことがほとんどです。
不協和音ぽい響きになり、一般的にはドミナントコードの機能を強めるために使われます。
テンションノート付加のルール
コードに付加するテンションは、コード機能を損なう音でなければ何でも付けられますが、あまりやりすぎると元のコードの響きが薄まって、テンションコードではなく他のコードになってきてしまうので、だいたい使われる範囲が決まっています。
原則的に適合するコードスケール(メロディーに使いたい音階)の音から選び、コードに付加するテンションは1つから3つです。
テンションコードの表記
テンションコードの表記ですが、注意するのはコードネームに()がついて、()内にテンションが書かれている場合と、コードネームに直接9とか13とかの数字が付いている場合があります。
例を挙げると、C9などと、C7(♭13)などですね。
テンションコードの表記ルールは、原則的には以下のようになります。
- ()無しの形はノンオルタードテンション限定の表記
- ()無しのものは表記されたテンション以下の付加可能なテンションを全て含む
- ()付きのものは()内の音のみ付加
例えば、C7(13)ならC7+13ですが、C13はC7+9+11+13です。
ただし、ギターの場合だと同時に出せる音数も限られていて、5和音以上のコードは演奏不可の場合も多いので、実際は結構アバウトに扱われています。
ですので、ギターの場合は上の例ならC13=C7(13)と考えても構わないと思います。
よく使われるテンションコード
以下、よく使われるテンションコードをあげていきます。
基本的には、ベースとなるコードの3度と7度の音で付加するテンションが決まってきます。
例によってルートをCで書きます。=で結ばれているものは表記違いの同じコードです。
6thコード
9th(場合により♯11も可。11thはアヴォイドになるので不可、sus4としてなら可)
C69=C6(9)
メジャー7thコード
9th、♯11th、13th(11thはアヴォイドになるので不可、sus4としてなら可)
CM9=CM7(9)
CM7(♯11)、CM9(♯11)=CM7(9,♯11)
CM13=CM9(13)=CM7(9,13)
マイナー6thコード
9th(場合により11thも可)
Cm69=Cm6(9)
マイナー7thコード
9th、11th
Cm9=Cm7(9)
Cm7(11)、Cm11=Cm9(11)
ドミナント7thコード
条件により全てのテンションが付加可能
ディミニッシュ系コード
コードスケール(デュミニッシュスケール、コンディミ、オルタードなど)の音を使ってテンションの付加が可能だが、もともと緊張感の高い響きだし、テンションを入れることで「全て短3度音程」という特性が崩れてしまうこともあって、テンションはあまり使われない
オーギュメント系コード
オーギュメント系コードは基本的にメジャー系コードがベースなので9thや♯11thが付加可能で、sus4(場合によって11thと捉えることも出来る)との組み合わせもある
add9コード
トライアドコードに7thを飛ばして直接9thを付加したコードです。
一般的なのはadd9とmadd9です。
add9=1+M3+5+9
madd9=1+m3+5+9
add11、madd11(sus4と違って3度を含む)も考えられますが、あまり使いません。
add13、madd13は6thコードと同じです。
トライアドコード+オルタードテンションはadd表記を使わず()内表記になります。
sus4コード
sus=サスペンスドの略で、3度の音が4度に変化したコードです。
11thコードと似ていますが、コードの中に3度音が含まれません。そのため、メジャーでもマイナーでもない中立的な響きにならます。
あらゆるタイプのコードに対して適用可能ですが、実用上はノーマルなトライアドのsus4か、ドミナント7th系の7sus4がほとんどです。
よく使うsus4コードには下記のようなものがあります。
sus4=1+P4+P5
7sus4=1+P4+P5+m7
M7sus4=1+P4+P5+M7
sus2コード
サスペンスドコードにはsus2コードというのもあって、こちらは3度の音が2度に変化したものです。
別名add9(omit3)とも呼ばれ、これもわりとよくでてきます。
sus2=add9(omit3)=1+5+9
addコード、susコードは省略形のテンションコードという捉え方もできますが、独特の響きかたをするので、敢えてaddコード、susコードを指定して使われる場合が多いです。
――コードのバリエーションとしては、この他に、オンコードや分数コード、転回形コードがありますが、次回はこれらを解説します。


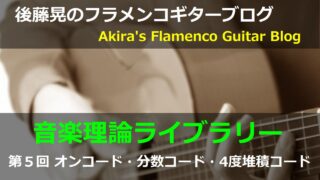
コメント