フラメンコ音楽論では、ここしばらくコード・スケールといった音程に関わる話を掘り下げていましたが、今回からフラメンコの音楽を理解する上で最重要になる「リズム形式」(パロ)の解説に入りたいと思います。
フラメンコにおける曲目、曲名などの扱い
フラメンコ音楽論第3回でフラメンコの音楽単位について触れていますが、セビジャーナス・アレグリアス等の「形式」「曲種」という概念に戸惑うフラメンコ初心者は多いのではないでしょうか。
フラメンコの「形式」「曲種」は、スペイン語だと「パロ」(似た言葉に「ヌメロ」がありますがこちらは演奏曲目の事で必ずしも形式名をさすものではない)と呼ばれますが、この連載では「形式」という呼び方に統一します。
一般の音楽の場合は、曲ごとに固有の「曲名」が付いているのが普通ですが、フラメンコの場合は個別の曲名よりも形式名が優先される事が多く、とくに踊りの場合は個別の曲名は付かずに、形式名のみで呼ばれる事がほとんどです。
しかし、この方式だと、同じ「アレグリアス」と呼ばれる曲であっても、振り付けや音楽の内容は演者によって異なります。
そのあたりが初心者を混乱させる要因になっていそうだし、形式名は「曲名」も兼ねたりするのですが、「分類名」と考えたほうが混乱が少なそうです。
例えば、カマロンのデビューアルバムの1曲目に「Barrio de Santa Maria」という曲がありますが、生物学の分類法を当てはめて「フラメンコ目・ソレア科・カンテーニャ属・アレグリアス種の『Barrio de Santa Maria』(個体名)」という感じでイメージすると理解しやすいのではないでしょうか。
そして、歌の歌詞やメロディー、踊りの振り付け、ギターのファルセータや基本フレーズ、そういったフラメンコの構成要素の全てが形式ごとに分類されているので、学習する時も「形式ごとにネタを増やして、自分なりに再構成出来るように訓練していく」というのがフラメンコ流のやりかたです。
リズム形式の起源
フラメンコの「曲」はリズム形式をベースとして、それにアーティスト各自のオリジナルなものが乗っている、ということがお分かりいただけたかと思いますが、フラメンコの形式はどのようにして成立してきたのでしょうか?
答えから言うと、現在演奏されるフラメンコ形式の起源は古いカンテ(歌)であり、その節回しとリズムが徐々に固定化して「形式」として定着したものです。
カンテの原型は、トナと呼ばれる(ほぼ)自由リズムのものでしたが、やがてそこからシギリージャ系とソレア系に分岐します。
ちなみに、シギリージャ系のほうがトナ直系の古い形式群ですが、後から派生したソレア系のほうが豊かな発展をしてフラメンコ形式の根幹を成すに至っています。
その後、地元の民謡なども採り入れつつ、多くの形式に分化していきました。
シギリージャとソレア、この2つの系統はフラメンコを学ぶ上で最も難関になりやすいところと思いますが、ギターや踊りが付くずっと前から、本当に最初から、あの変態的リズムでやっていたわけですね。
フラメンコのリズム形式には3拍子や2拍子も存在しますが、こうした発生学的な事からも分かるように、フラメンコの持つ独自性の根元は12拍子系のコンパス(シギリージャ等の変拍子系も12拍子の一種と捉えられる)である事は間違いないでしょう。
リズム形式一覧の書式について
今回は、一般的に演奏されるフラメンコ形式を一覧表にしますが、まずは一覧表の書式について解説しておきましょう。
フラメンコ形式は単数形で呼ばれる場合と複数形で呼ばれる場合があり、単数形はその「曲」そのものを、複数形は「形式名」を指していると思われますが、実用上はどちらでも良いと思います。
ここでは原則として単数形で書きますが、複数形の呼び名ほうが一般的な形式は複数形で書いています。
大まかな特徴がわかるように、一般的によく演奏される調性とテンポも書いておきます。
演奏頻度が高い重要形式は末尾に★マークをつけてみましたが、ここではギターと踊り伴奏主体に判断しています。歌伴奏だと★のついてない形式でも重要なものもあります。
調性に関しては以下の呼び名で表記します。
- Eスパニッシュ調=ポルアリーバ
- Aスパニッシュ調=ポルメディオ
- F♯スパニッシュ調=ポルタラント
調性は最も一般的な調を書きますが、他の調で演奏される場合もあります。
テンポは、遅(120BPM以下)・中(120BPMから180BPM)・速(180BPM以上)の3段階で記載。標準的な歌(レトラ)のテンポを想定しました。
また、いわゆる逆輸入系の形式は「逆輸入系」という注釈を付けました。これらの形式は中南米起源と言われていて、南国風のフレージングが特徴です。
以下、①12拍子系、②変拍子系、③3拍子系、④リブレ(自由リズム)系、⑤2拍子系の5つの系統に分けて一覧にしていきます。
12拍子系形式
12拍子系の形式は「フラメンコの母」と言われるソレアから派生したものですが、フラメンコリズムのガラパゴス的発展の頂点であるブレリアは、ソレアの原型をとどめないほどバリエーションが発展しています。
ソレア系の12拍子形式
「フラメンコの母」ソレアを起源とするフラメンコの根幹をなす形式群です。
- ソレア(Soleá)
ポルアリーバ、テンポ遅 ★ - ソレア・ポル・ブレリア(Soleá Por Buleria)
ポルメディオ、テンポ中 ★ - ブレリア(Buleria)
ポルメディオ、テンポ速 ★
カンティーニャ系の12拍子形式
ソレア系のコンパスにメジャーキーの明るい歌を組み合わせた形式群です。
- アレグリアス(Alegrias)
Eメジャー、テンポ中 ★ - カンティーニャ(Cantiña)
メジャーキー、テンポ中 - ロメーラ(Romera)
メジャーキー、テンポ中 - ミラブラス(Mirabras)
メジャーキー、テンポ中 - カラコレス(Caracoles)
Cメジャー、テンポ中 ★
その他の12拍子形式
主に民謡やヒターノの伝承歌に12拍子のコンパスが付けられた形式群です。
- カーニャ(La Caña)
ポルアリーバ、テンポ遅/中 ★ - ポロ(Polo)
ポルアリーバ、テンポ遅/中、カーニャに類似 - バンベーラ(Bambera,Bamba)
ポルアリーバ/Aマイナー、テンポ中 ★ - ロマンセ(Romance)
ポルアリーバ、テンポ中/速 - ハレオス(Jaleos)
ポルメディオ等、テンポ速 - アルボレア(Alborea)
ポルアリーバ、テンポ中/速
変拍子系形式
フラメンコの変拍子は、変則5拍子の形をとり、これは基本的に12拍子の拍のとりかたをずらしたものですが、ソレア系とは違ったフレーズの乗せかたをします。
3.3.2.2.2型の変拍子系形式
ブレリアに類似する変拍子で演奏される形式群で、12拍子のバリエーションと言っても良いでしょう。
- グアヒーラ(Guajira)
Aメジャー、テンポ遅/中、逆輸入系 ★ - ペテネーラ(Petenera)
ポルアリーバ/Aマイナー、テンポ遅/中 ★
2.2.3.3.2型の変拍子系形式
原初のカンテ、トナの直系であるシギリージャの系統で、唯一無二のリズムサイクルを持ちます。
- シギリージャ(Siguiriya)
ポルメディオ、テンポ中 ★ - セラーナ(Serrana)
ポルアリーバ、テンポ中 - リビアーナ(Liviana)
ポルアリーバ、テンポ中 - カバーレス(Cabales,Cabal)
Aメジャーキー、テンポ中 - マルティネーテ(Martinete)
無伴奏、テンポ中 ★ - カルセレーラ(Carselera)
無伴奏、テンポ中、マルティネーテと類似 - トナ(Toná)
無伴奏、自由リズムに近い、シギリージャやソレアの原型 - デブラ(Debla)
無伴奏、自由リズムに近い、トナの近縁 - サエタ(Saeta)
無伴奏、自由リズムに近い、セマナ・サンタで歌われる宗教歌
3拍子系形式
ファンダンゴをはじめたとしたアンダルシア民謡は古くからフラメンコに取り入れられ、カンテ・アンダルスと呼ばれていました。
最も積極的にフラメンコ化されたファンダンゴは3拍子ですので、その系統の形式も3拍子となりますが、これらの3拍子形式は実はかなり変態的なリズムで(とくにウエルバ系)、3/4拍子と3/2拍子のポリリズムの様相を呈しています。
ウエルバ系3拍子形式
ファンダンゴ等のアンダルシアの民謡・舞曲がフラメンコ化した曲種の中でも、アンダルシア西部で発展したものは比較的速いテンポで演奏されます。3/4拍子と3/2拍子のポリリズムで、ベースは3/4拍子なんですが、メロディーやコードが2拍単位で動いたり2拍食って入ったりするのが特徴です。
- セビジャーナス(Sevillanas)
テンポ中/速 ★ - ファンダンゴ・デ・ウエルバ(Fandango de Huelva)
ポルアリーバ、テンポ中/速 ★
アバンドラオ系3拍子形式
アンダルシア中部・東部で発展したファンダンゴは主にアバンドラオと言われるコンパスで演奏され、ウエルバ系よりもゆったりした勇壮なリズムが特徴です。フレージングやコード変化は基本的に3/4拍子で行われ、ウエルバ系のような3/2拍子が入ってきたり2拍アウフタクトする頻度は少なくなります。
- ベルディアーレス(Verdiales)
ポルアリーバ、テンポ遅/中 - ロンデーニャ(Rondeña)
ポルアリーバ、テンポ遅/中 ★ - ハベーラ(Jabera)
ポルアリーバ、テンポ遅/中 - ハベゴーテス(Jabegotes)
ポルアリーバ、テンポ遅/中 - バンドラス(Bandolas)
ポルアリーバ、テンポ遅/中 - ファンダンゴ・デ・ルセーナ(Fandango de Lucena)
ポルアリーバ、テンポ遅/中 - ファンダンゴ・デ・グラナダ(Fandango de Granada)
ポルアリーバ、テンポ遅/中
その他の3拍子系形式
- カンパニジェーロス
Aマイナー、テンポ遅/中、ビジャンシーコの一つ、12拍子や3.3.2.2.2型変拍子で演奏されることもある
リブレ(自由リズム)形式
リブレ(自由リズム)形式は、主にファンダンゴ系の歌の地域や歌手個人によるバリエーションで、カフェ・カンタンテの時代を中心にカンテの技巧を競ううちにリズムを崩して歌うようになったのが形式化しました。
ファンダンゴ・リブレのバリエーションとしては、マラゲーニャ、グラナイーナなどが代表的ですが、アルメリアなどのアンダルシア東部地域及び隣接洲のムルシアを中心に発展した「カンテ・レバンテ」と呼ばれる、複雑な節回しを持つ形式群もあったりと、地域的なバリエーションが豊かです。
リブレ形式は、基本的にカンテのための形式群ですが、踊りの中でも演出の一つとして部分的に自由リズムのセクションがよく使われ、そういう部分を「リブレで」と表現したりします。
また、リブレ形式はギターソロでもよく弾かれます。
ファンダンゴ系のリブレ形式
ファンダンゴのリズムを崩して歌ったものが起源となった自由リズムの形式群です。
- ファンダンゴ・ナトゥラル(Fandango Natural)
ポルアリーバ ★ - マラゲーニャ(Malagueña)
ポル・アリーバ ★ - グラナイーナ(Granaina)
Bスパニッシュ/Eマイナー ★ - ロンデーニャ(Rondeña)※ギターソロ
Dスパニッシュ、ラモンモントージャが始めたスタイルで変則調弦
カンテ・レバンテ
自由リズムのファンダンゴの一種ですが、アルメリア地方・ムルシア地方を中心に発展した、独特の節回しと不協和音を特徴とする形式群です。
- タランタ(Taranta)
ポルタラント ★ - ミネーラ(Minera)
ポルタラント(C♯スパニッシュ・G♯スパニッシュの場合もある) - カルタヘネーラ(Cartagenera)
ポルタラント - ムルシアーナ(Murciana)
ポルタラント
その他のリブレ形式
- ナナ(Nana)
無伴奏、アンダルシア地方で歌われていた子守唄が起源
2拍子系形式
4拍子を含む2拍子系のリズムは、世界で最もスタンダードなリズム感覚であり、フラメンコにも存在します。
フラメンコの2拍子系形式はカディス港に到着した中南米からの引き上げ移民がもたらした中南米の音楽やスペイン北部地方の2拍子の民謡が起源と言われています。
タンゴ系2拍子形式
2拍子系の形式のうち、カディスで発祥してヒターノのコミュニティで発展してきたのがタンゴ系の形式群です。
- タンゴ(Tango)ポルメディオ、テンポ中/速 ★
- タンゴ・デ・マラガ(Tango de Malaga)
Aマイナー、テンポ遅/中 ★ - ティエント(Tiento)
ポルメディオ、テンポ遅 ★ - タンギージョ(Tanguillo)
ポルメディオ/Aメジャー、テンポ速、3連符で演奏されて6/8拍子的になることもある ★
北部起源系の2拍子形式
2拍子系の形式のうち、ガリシア地方などスペイン北部の民謡をとりいれた形式群です。
- ガロティン(Garrotin)
Gメジャー、テンポ遅/中 ★ - ファルーカ(Farruca)
Aマイナー、テンポ遅 ★ - タラント(Taranto)
ポルタラント、テンポ遅、ファンダンゴ系のタランタを2拍子化したもの★
その他の2拍子系形式
タンゴ系・北部起源系のどちらにも属さない2拍子系の形式群です。
- ルンバ(Rumba)
テンポ速、逆輸入系 ★ - コロンビアーナ(Colombiana)
Aメジャー、テンポ中/速、逆輸入系 - ミロンガ(Milonga)
Aマイナー、テンポ中、逆輸入系 - サンブラ(Zambra)
ポルアリーバ/ポルメディオ、テンポ中、アラブ音楽風のグラナダ民謡がフラメンコ形式として定着 - サパテアード(Zapateado)
メジャーキー、テンポ速、リズムはタンギージョに類似 - マリアーナ(Mariana)
ポルメディオ、テンポ遅、リズムはティエントに類似
様々なコンパスで演奏される形式
民謡などがフラメンコ化したものの中には、12拍子・3拍子・2拍子など様々なコンパスに乗せて演奏される形式もあります。
- ソロンゴ(Zorongo)
ポルアリーバ/ポルメディオ、テンポ中(12拍子・2拍子)、グラナダの民謡が起源、タンゴやソレア・ポル・ブレリアのコンパスで演奏され ★ - ビジャンシーコ(Villancico)
スペイン語圏のクリスマスソング。様々な歌があり、リズムも12拍子・3拍子・2拍子など様々なものに乗せて歌われる
――この他にも、マイナー形式は多数ありますが、プロのアーティストでも全部は知らなかったりします。
マイナー形式を発掘してレパートリーに加えるアーティストも多く、有名なアーティストに取り上げられた(または創作された)形式が注目を集めて定着する、ということも多々あります。
そういうマイナー形式や歌単体を指すものを全部挙げて行くと物凄い数になりそうですが、音楽的特徴や発生学的に明確に分類・系統付けできるものは、上記一覧が一般的な範囲だと思います。

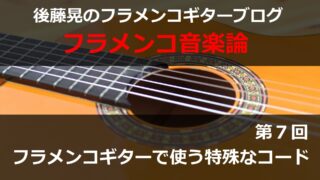
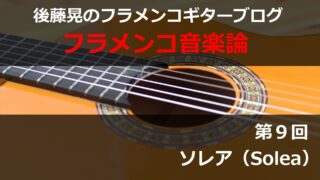
コメント