フラメンコ音楽論では、前回から個別形式の解説に入っていて、前回は「フラメンコの母」ソレア形式の解説をしました。
今回は、ソレアからの派生形式の一つであるソレア・ポル・ブレリア(通称ソレポル)を解説いたします。
ソレア・ポル・ブレリア形式概要
単数形:Soleá Por Buleria
複数形:あまり使われません
主な調性:ポルメディオ(Aスパニッシュ調)
テンポ:130BPMから170BPM
ソレア・ポル・ブレリアは形式名からわかる通り、ソレアとブレリアの中間的な形式で、別名ブレリア・ポル・ソレアとも言います。
日本では略して「ソレポル」という通称で呼ばれたりもしますよね。
ソレア・ポル・ブレリアの調性
ソレア・ポル・ブレリアは主にポルメディオ(Aスパニッシュ調)で演奏されます。
ソレアで使用されるポルアリーバ(Eスパニッシュ調)は重厚さやギターコードの微妙な響きを表現するのに適していますが、ポルメディオはより軽快なリズムプレイに適しています。
ソレア・ポル・ブレリアをポルメディオでやる場合のカポタストの位置は、女性歌手なら4カポ(実音はC♯スパニッシュ)、男性歌手なら1カポ(実音はB♭スパニッシュ)くらいが多いです。
ソレア・ポル・ブレリアはポルアリーバで演奏されることもありますが、同じ形式でもポルアリーバでやるのとポルメディオでやるのでは、コードボイシングやフレージングも変わってくるので雰囲気がかなり変わります。
ちなみに、カーニャやバンベーラはテンポにもよりますが、歌や固有フレーズ以外の部分は「ほぼポルアリーバのソレア・ポル・ブレリア」というのが実態です。
コンパスとフレージング
ソレア・ポル・ブレリアのコンパスは次回取りあげる予定のカンティーニャ系形式とほぼ同様のものですが、強いて言うなら、カンティーニャ系と比べて硬質・男性的なコンパスで演奏される印象で、テンポは130BPMから170BPMくらいです。
昔のソレアの歌はソレア・ポル・ブレリアに近いテンポでしたが、踊りが入るようになってから、だんだんゆっくりしたテンポでも歌われるようになりました。
それと逆に、古典的なソレアのテンポをもう少し軽快にしてリズムのキレの良さを強調したのがソレア・ポル・ブレリアというわけですね。
ソレアはリズムを揺らして演奏されることも多いですが、ソレア・ポル・ブレリアはインテンポでカッチリと演奏されます。
コンパスの特徴は、ソレアと比べて8拍目のアクセントがはっきりしている事でしょうか。
パルマは3・7・8・10・12拍目にアクセントをつける場合が多く、このリズムは中くらいのテンポの12拍子系では共通のものです。
1 2 ③ 4 5 6 ⑦ ⑧ 9 ⑩ 11 ⑫
※○の付いた数字がアクセント拍
ソレア・ポル・ブレリアのフレージングは、1拍目から入って10拍目に解決していくという基本はソレアと同様ですが、コントラティエンポ(裏リズム)や、3連符・16分音符などの細かい音符を多用してテクニカルな印象を強調するものが多いです。
ファルセータやサパテアードの場面では、上記の基本コンパス・フレージングの他、ソレアと同様の「3拍目にアクセントがある3拍子」でとるものや、ブレリアのノリに近い12拍目から入るものなど、様々なバリエーションが入り混じります。
ソレア・ポル・ブレリアのギタープレイ
ソレア・ポル・ブレリア形式でのギタープレイ(ポルメディオでの演奏を想定)に関しても少し解説しておきましょう。
ポルメディオでのオンコード使用
ソレア・ポル・ブレリアの他、ブレリア、シギリージャ、タンゴ、ティエントなどがポルメディオで演奏されますが、このキーは主要コードであるA・B♭・C・Dmのベース音をルートで出してしまうと6弦が使えなかったりして重さや厚みが無くなってしまうため、ポルメディオの調ではベース音をルート以外の音に組み換えて演奏する場合が多く、結果としてオンコード(ベース音にルート音以外の音を指定したゴードン=レヴィット)を常用することになります。
ポルメディオで使用される代表的なオンコードには以下のようなものがあります。
- A7(onG)
フラメンコ音楽論07で解説済 - B♭6(onG)
フラメンコ音楽論07で解説済 - B♭7(onA♭)
フラメンコ音楽論07で解説済 - B♭(onF)
フラメンコ音楽論07で解説済のものに6弦F音を加えたもの - C9(onG)
一般的なC9に6弦のG音を加えたもの - Dm(onF)
一般的なオープンDmに5弦A音と6弦F音を加えたもの
これらのオンコードは()内の音を6弦で鳴らす形になるのですが、重さが欲しい時や、ラスゲアードなどで全弦鳴らすときはこういうオンコードを使います。
これらのコードはフラメンコ音楽論07で解説したものが多いので、具体的なコードフォームなどはこちらを参照してください。
ポルメディオで使う定番進行
ソレア・ポル・ブレリアのマルカールや伴奏パターンは以下のようなコード進行が多いですが、同じポルメディオ形式であるブレリア・タンゴ・シギリージャなどにも共通のパターンです。
- B♭→A
- B♭→C→B♭→A
ソレアと同じようなⅣm(Dm)や♭Ⅵ(F)を含んだ進行もやらないわけではありませんが、ポルメディオのソレポルでは、Ⅰ(A)・♭Ⅱ(B♭)・♭Ⅲ(C)を組み合わせて伴奏するのが最も無難な方法です。
3フレット半セーハでトップノートを動かす
3フレットを半セーハしたまま音階を弾いていくのはポルメディオ形式に共通の動きですが、5弦解放をならしながらやったりするので、B♭(またはGm)のコードトーンと5弦解放のA音がぶつかって微妙な響きになります。
B♭コードを押さえたまま低音弦でベースラインを弾く
ポルメディオ形式では、B♭のコードトーンである2弦D音(小指)と3弦B♭音(薬指)を押さえたまま、人差し指と中指でベースラインを弾いていく弾きかたがあります。
これをやる時の右手の動きは、親指奏法を中心にアルペジオやストローク奏法と組み合わせるのが普通で、これもブレリア・シギリージャ・タンゴなど、他のポルメディオ形式と共通の慣用句です。
これらの他に、半音ぶつかり系のボイシングも多用しますが、詳しくはフラメンコ音楽論07のポルメディオの各項目を参照してください。
ソレア・ポル・ブレリアの歌
ソレア・ポル・ブレリアの歌のうち、ここではソレアがベースになったオーソドックスなパターンを紹介します。書式は以下の通り。
- 12拍子の1拍目を頭にした3拍子で記載
- 1行でメディオコンパス(6拍)
- ○はコードチェンジ無しの拍
- ()内のコードは省略されることもある
- 複数のコードの可能性があるところは「,」で区切る
- キーはポルメディオ(Aスパニッシュ調)で記載
- コンテスタシオン(合いの手)は歌が休みになる部分で、普通は0コンパス(コンテスタシオン無し)から2コンパス
- ※マークが付いている行は省略されることもある
|A ○ ○|○ ○ ○|
|○ ○ ○|A,Dm,B♭,E7,C ○ ○|
|(Dm) (C) B♭|○ ○ ○|※
|○ ○ ○|A ○ ○|※
コンテスタシオン
|A ○ ○|○ ○ ○|※
|○ ○ ○|A,Dm,B♭,E7,C ○ ○|※
|(Dm) (C) B♭|○ ○ ○|※
|○ ○ ○|A ○ ○|※
エストリビージョ(サビ)
|○ ○ C7|○ ○ ○|
|○ ○ ○|F ○ ○|
|(Dm) (C) B♭|○ ○ ○|
|○ ○ ○|A7 ○ ○|
|○ ○ C|○ ○ ○|
|○ ○ ○|F ○ ○|
|(Dm) (C) B♭|○ ○ ○|
|○ ○ ○|A ○ ○|
ディグリー(度数)表記版
|Ⅰ ○ ○|○ ○ ○|
|○ ○ ○|Ⅰ,Ⅳm,♭Ⅱ,Ⅴ7,♭Ⅲ ○ ○|
|(Ⅳm) (♭Ⅲ) ♭Ⅱ|○ ○ ○|※
|○ ○ ○|Ⅰ ○ ○|※
コンテスタシオン
|Ⅰ ○ ○|○ ○ ○|※
|○ ○ ○|Ⅰ,Ⅳm,♭Ⅱ,Ⅴ7,♭Ⅲ ○ ○|※
|(Ⅳm) (♭Ⅲ) ♭Ⅱ|○ ○ ○|※
|○ ○ ○|Ⅰ ○ ○|※
エストリビージョ
|○ ○ ♭Ⅲ7|○ ○ ○|
|○ ○ ○|♭Ⅵ ○ ○|
|(Ⅳm) (♭Ⅲ) ♭Ⅱ|○ ○ ○|
|○ ○ ○|Ⅰ ○ ○|
|○ ○ ♭Ⅲ|○ ○ ○|
|○ ○ ○|♭Ⅵ ○ ○|
|(Ⅳm) (♭Ⅲ) ♭Ⅱ|○ ○ ○|
|○ ○ ○|Ⅰ ○ ○|
ソレア・ポル・ブレリアの歌は基本的にはソレアをポルメディオでやったものですが、ソレアと比べると前半部分の変化が多くなります。
具体的には、最初の節でⅣm(Dm)や♭Ⅱ(B♭)以外にも、Ⅴ(E)や♭Ⅲ(C)に行くパターンがプラスされます。
エストリビージョのC7→F→B♭→Aに関してはほぼ固定ですが、そこまでの持っていき方が伝統的なソレアよりバリエーションが多い感じですね。
もう一つ、歌の伴奏時、エストリビージョの2コンパス目・4コンパス目冒頭のB♭コードに下がっていく部分は、表拍で1・2・3拍目を強調するリズムになる場合が多いのですが、こういう1拍目の表が強いリズムパターンはブレリアに寄り勝ちな(12拍目を頭に感じる)コンパスをソレア側に引き戻す効果があります。
歌の全体のサイズは5コンパスから10コンパスの範囲になりますが、踊り歌の場合、ソレアに比べると最初の節が2コンパスある長いタイプの歌が多い印象で、コンテスタシオン1コンパス入れて7コンパスから9コンパスのサイズが標準的です。
踊りの歌振りとしては、全部で5コンパスとかだと、ソレア・ポル・ブレリアのテンポでは短すぎるのでしょう。
ソレア・ポル・ブレリアの歌には、上記のようなソレアベースの歌以外に、ブレリアの歌や民謡をソレポル化したようなものもあって、そういう歌も入れると相当数のバリエーションが存在します。
なお、ソレアやソレア・ポル・ブレリアの踊りの最後につくブレリアは、最初にソレアベースのブレリアが歌われる場合が多いですが、必ずそうしなければならないわけではなく、民謡(カンシオン)系など異系統のブレリアが歌われる事もあります。

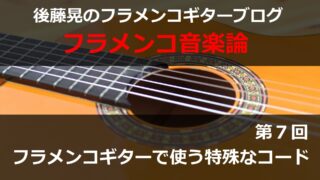
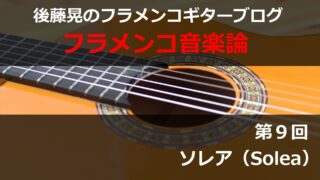

コメント