フラメンコ音楽論では、ファンダンゴ系形式を中心とした3拍子の形式を解説していましたが、今回からファンダンゴからの派生としてリブレ(自由リズム)の形式を紹介していきたいと思います。
自由リズム(リブレ)のファンダンゴの概要
ファンダンゴはもともとアンダルシアに根付いていた3拍子の民謡ですが、フラメンコに取り入れられて以降、カンテの技巧を聴かせるためにリズムを崩して歌われるようになりました。
ファンダンゴ・デ・ウエルバやファンダンゴ・アバンドラオは民謡としてのファンダンゴの原形を残していますが、自由リズム化したファンダンゴはフラメンコのオリジナルなものに変化している、と言って良いと思います。
自由リズム=リブレのファンダンゴはカフェ・カンタンテの時代を通して大発展して、歌い手個人によるバリエーションが多数出現してきました。
例えば、後述するマラゲーニャ、グラナイーナなどは、マラガ、グラナダなどのファンダンゴが元ネタになり、フラメンコの歌い手によってアレンジされたものが形式化したものです。
リブレのファンダンゴは、基本的にはカンテソロのための形式群なのですが、踊りの中に演出としてリブレのパート(ファンダンゴ系とは限りませんが)を入れることは良くあります。
ファンダンゴ・リブレの歌伴奏について
自分は歌手ではないので、歌そのものや歌詞などを専門的に解説する事はできませんが、ここでは伴奏者の視点で解説していきます。
ファンダンゴ・リブレの歌伴奏は、形式ごとに基本的な展開と伴奏者がやるべき事がだいたい決まっているので、まずは、それらを覚える事が大切です。
自由リズムのファンダンゴのコード進行
自由リズムのファンダンゴは、ファンダンゴ・デ・ウエルバの記事で解説した6コンパスのコード進行が基本になりますが、セクションごとにギターで合いの手を入れて、歌い手が出す最後の♭Ⅱ→Ⅰの音程を捉えて締めくくります。
以下に、リブレのファンダンゴの基本的な展開をまとめます。書式は次の通り。
- 複数のコードの可能性があるところは「,」で区切る
- キーはポルアリーバ(Eスパニッシュ調)で記載
- 自由リズムなので拍子や小節線の概念は無いが、1行がファンダンゴ・デ・ウエルバの1コンパスに相当
- サリーダの部分は省略
- グラナイーナの場合は5度上(Bスパニッシュ調)に移調
- ※マークは合いの手
- 合いの手に関しては、書いていない行も歌の間の取り方などによっては入れていく
G7→C→※
C→F,G7
G7→C→※
C→G7
G7→C
C7→F→E
ディグリー(度数)表記版
♭Ⅲ7→♭Ⅵ→※
♭Ⅵ→♭Ⅱ,♭Ⅲ7
♭Ⅲ7→♭Ⅵ→※
♭Ⅵ→♭Ⅲ7
♭Ⅲ7→♭Ⅵ
♭Ⅵ7→♭Ⅱ→Ⅰ
歌伴奏は歌詞も聴きながら判断する
自由リズムの歌は、歌い手によって自由に伸縮させられるため、コード進行が分かっていたとしてもコードを変えるタイミングや落ちをつけるタイミングが難しいものです。
音程だけ聴いていても、歌い回しに遊びも多く、迷うことがあるのです。
そういう場合、もう一つの判断基準として「歌詞」を意識して、歌詞の位置で今どのあたりまで来ているかを判断します。
歌詞的に落ちがつく前に、ギターが先に落ちをつけてしまうのはおかしいので、音程が落ちたかな?と思っても歌詞(音節)が切れるところまで待って、そこで間髪入れずに合いの手や締めくくりを入れるのがベストです。
以下、個別の形式ごとにもう少し細かく見ていきましょう。
ファンダンゴ・ナトゥラル(Fandango Natural)
単数形:Fandango Natural
複数形:Fandangos Naturales
主な調性:ポルアリーバ(Eスパニッシュ調)
テンポ:自由リズム
ファンダンゴ・ナトゥラルは最もスタンダードなリブレ形式で、ファンダンゴ・デ・ウエルバの歌のラインをそのまま自由リズムでやっているようなものが多いです。
カンテの場合、単に「ファンダンゴ」と言うと、普通はこのファンダンゴ・ナトゥラルを指しますが、踊りの場合はファンダンゴ・デ・ウエルバの事を指していたりする事も多いので、ここでは差別化させる意味で「ファンダンゴ・ナトゥラル」と呼ぶ事にします。
また、後述するマラゲーニャやグラナイーナもファンダンゴ・ナトゥラルの一種ですが、ここではそれらに分類されない、もっとファンダンゴの原形に近いものをファンダンゴ・ナトゥラル形式として扱います。
ファンダンゴ・ナトゥラルはマラゲーニャなどと比べると短い歌い回しで簡潔に歌われることが多く、上で書いた基本コード進行通りの場合が大半です。
ファンダンゴ・デ・ウエルバ等と同様に、主にポルアリーバで演奏され、カポタストの位置は女性歌手は6カポ(実音B♭スパニッシュ)、男性歌手なら3カポ(実音Gスパニッシュ)くらいが中心です。
ファンダンゴ・ナトゥラルの前奏・間奏
ファンダンゴ・ナトゥラルの前奏・間奏などの部分は、ファンダンゴ・デ・ウエルバと同じような3拍子や、それを少し崩したリブレで演奏される場合が多く、ファンダンゴ・デ・ウエルバの前奏・間奏に弾かれるマルカールやファルセータがそのまま使用される事も多いです。
マラゲーニャ(Malagueña)
単数形:Malagueña
複数形:Malagueñas
主な調性:ポルアリーバ(Eスパニッシュ調)
テンポ:自由リズム
マラゲーニャは、マラガのファンダンゴが元ネタになったファンダンゴ・ナトゥラルのバリエーションですが、歌は技巧を凝らして、たっぷりと間を開けて歌われます。
マラガ産のファンダンゴ曲種は他にベルディアーレス、ハベーラス、ハベゴーテスなどがありますが、民謡のファンダンゴの原形に近い3拍子(アバンドラオ)でやっているのがベルディアーレスやハベーラス、カフェカンタンテで聴かせるために、フラメンコの歌手がマラガのファンダンゴを元に作り上げたリブレ形式がマラゲーニャです。
マラゲーニャは、主にポルアリーバで演奏され(カポタストの位置はファンダンゴ・ナトゥラルと同様)、後歌には、アバンドラオのリズムでベルディアーレスなどが歌われるのが通例です。
ちなみに、ラテンの有名曲である「ラ・マラゲーニャ」とは全くの別物ですので。
マラゲーニャの歌のコード進行
マラゲーニャの歌のコード進行は、6コンパスのファンダンゴ基本進行に経過コードを入れて引き伸ばしたものです。
マラゲーニャのコード進行の特長として、ファンダンゴ基本進行の最初のFコードをG7で代理する場合が多いですが、エンリケ・エル・メジーソ(Enrique el Mellizo)が創唱した「メジーソのマラゲーニャ」と呼ばれる歌は、ファンダンゴ基本進行の最初のFコードが入る位置にAmコードが入ります。
以下にメジーソのマラゲーニャのコード進行例を書いておきます。書式は、上で書いた一般的なファンダンゴ・リブレのコード進行表と同様で、1行がファンダンゴ・デ・ウエルバの1コンパスに相当します。
G7→C→Am→※
Am→D7→G7
G7→C→※
C→D7→G7
G7→C→※→C→Am→※
Am→D7→G7→F→E
ディグリー(度数)表記版
♭Ⅲ7→♭Ⅵ→Ⅳm→※
Ⅳm→♭Ⅶ7→♭Ⅲ7
♭Ⅲ7→♭Ⅵ→※
♭Ⅵ→♭Ⅶ7→♭Ⅲ7
♭Ⅲ7→♭Ⅵ→※→♭Ⅵ→Ⅳm→※
Ⅳm→♭Ⅶ7→♭Ⅲ7→♭Ⅱ→Ⅰ
マラゲーニャのファルセータ
マラゲーニャのファルセータ部分は、完全な自由リズムで演奏する場合もありますが、ファンダンゴ・ナトゥラルと同様に比較的ハッキリした3拍子になることも多いです。
ファンダンゴ・ナトゥラルの場合はファンダンゴ・デ・ウエルバと同じネタを使ったりして、2拍単位のフレージングも多用しますが、マラゲーニャのファルセータはノーマルな3拍子に近いものが多く、フレージングは3拍単位、コードも3拍子の頭で変わる感じで、アルペジオやトレモロを多用した繊細な表現が好まれます。
グラナイーナ(Granaina)
単数形:Granaina
複数形:Granainas
主な調性:Bスパニッシュ調・Eマイナーキー
テンポ:自由リズム
グラナイーナは、グラナダのファンダンゴが元ネタになって、アントニオ・チャコン(Antonio Chacon)によってリブレ形式として確立されました。
前回解説したファンダンゴ・デ・グラナダと紛らわしいですが、ファンダンゴ・デ・グラナダは踊りを伴う民謡色が強いものです。
グラナイーナの歌には、グラナイーナとメディア・グラナイーナの2種類があり、それぞれ長さが違います。
グラナイーナの調性とメロディー
グラナイーナの特徴であるBスパニッシュ調によるギター伴奏スタイルは、チャコンの相方であったラモン・モントージャ(Ramon Montoya)が現在の形を作りました。
Bスパニッシュ調は独特の叙情的な趣があるので、ギターソロ曲としても人気があります。
この調は、平行調であるEマイナーキー寄りの展開になることも多く、とくに曲の一番最後の締めくくりはEマイナーコードで終わるのが通例です。
歌の部分は、もう一つの平行調であるGメジャーキーを主体に演奏されます。
歌のラインとしては、マラゲーニャほどは引き伸ばしたり経過音を入れたりはせず、ファンダンゴ・ナトゥラルに近いですが、技巧的な修飾音符やメリスマ(こぶし)が多いのが特徴です。
グラナイーナのファルセータ
前述の通り、Bスパニッシュ調のグラナイーナはラモン・モントージャが編み出したもので、現在弾かれるファルセータ等も彼がやっていたスタイルがベースになっています。
グラナイーナのフレージングの特徴は以下のようなものです。
- たまに2拍子的になる
- 細かく複雑なモザイク様のアルペジオを多用
- 解放弦やストレッチを使った半音ぶつかりを多用
まさにラモン・モントージャが得意とした弾き方なのですが、これらの特徴をさらに突き詰めたのが、次に紹介するギターソロ版のロンデーニャです。
ギターソロのロンデーニャ(Rondeña)
単数形:Rondeña
複数形:Rondeñas
主な調性:Dスパニッシュ調(変則調弦)
テンポ:自由リズム
ロンデーニャは、本来は前回解説した通り、アバンドラオのリズムを持つロンダ産のファンダンゴなのですが、この形式にはもう一つ、ラモン・モントージャが創作した自由リズムのギターソロのスタイルが存在します。
ギターソロのロンデーニャは、6弦をDに、3弦をF♯に下げて、Dスパニッシュ調で演奏されますが、この調弦はギターの響きを最大限に引き出し、幻想的で繊細な表現を可能にするのです。
フレージングの特徴としては、グラナイーナと同様に、①3拍子をベースとしつつも部分的に2拍子的な感覚が混じる②複雑なアルペジオやトレモロを駆使したモザイク的表現を多用する――といった事が挙げられます。
現在のギタリストも、ギターソロのロンデーニャはラモン・モントージャのスタイルを踏襲しているのですが、それにしても、このラモン・モントージャという人は、グラナイーナやロンデーニャのみならず、一人でフラメンコギターの語彙の1/3くらいを作ってしまったのでは?と思えるくらいの、まさに数百年に一人の大天才ですよね。
――次回はリブレ系ファンダンゴのバリエーションとして、カンテ・レバンテの解説をする予定です。
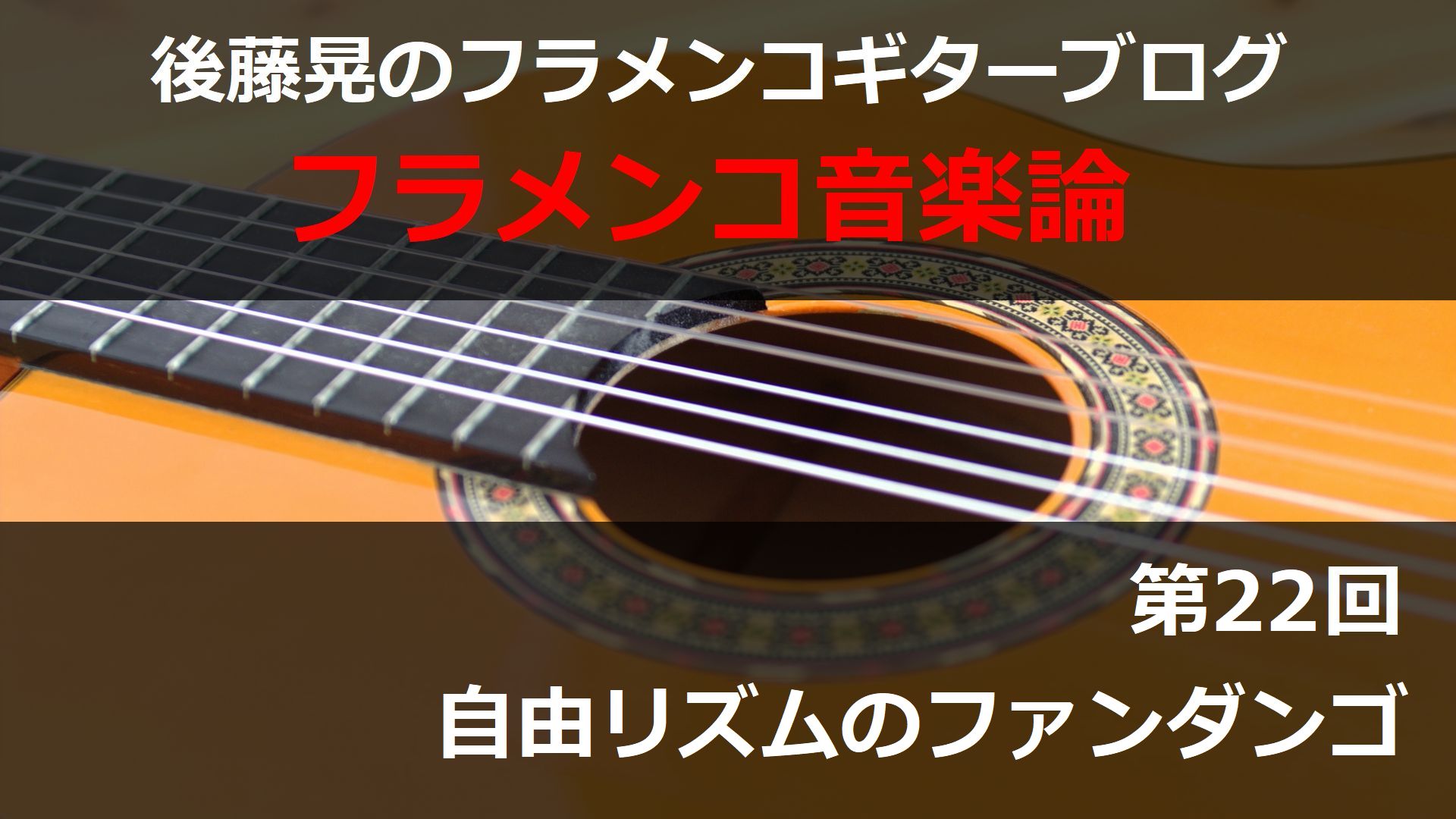
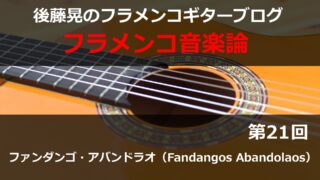

コメント