フラメンコ音楽論では、現在12拍子系の形式について学んでいますが、今回は12拍子系のなかでも「本丸」といえるブレリアを解説します。
ブレリアは「世界一速い3拍子」とも言われていて、最もフラメンコらしいリズム形式です。
ブレリア形式概要
単数形:Buleria
複数形:Bulerias
主な調性:ポルメディオ(Aスパニッシュ調)
テンポ:190BPMから250BPM以上
ブレリアは主にアンダルシアの田舎町であるヘレス・デ・ラ・フロンテラ(Jerez de la Frontera)周辺で発展した形式で、数あるフラメンコの形式の中でもリズムの自由度に関しては頂点に位置するものです。
ブレリアはソレアから派生して、どんどんテンポが速くなっていったものですが、その過程で数多くのリズムバリエーションが生まれ、現在も発展し続けています。
俗に「世界一速い3拍子」と言われていますが、だいたい190BPMから250BPMくらいで演奏され、踊りのマチョなどでは300BPMくらいになることも。
ブレリアのコンパス
フラメンコを始めて日が浅い人は「ブレリアって、なんで12から数えるの?」という疑問にぶつかると思うのですが、これは、ブレリアの元ネタであるソレアを基準にしたカウントで数えているからですね。
12拍子系のリズムはテンポが上がるにしたがって「コンパスの最後に感じていた12拍目がコンパスの頭に感じるようになる」という特性があり、ブレリアのテンポではフレーシングも12拍目を頭にとるフレーズのほうが主流になるため、ブレリアの場合は習慣的に12拍目を頭としてカウントします。
ブレリアに関してはメディオコンパスも多いし、必ずしもソレアベースの12からのカウントが最適とは思いませんが、ソレアからの連続性を考えると、12からのカウントを理解しておく必要があると思いますので、ここでも12からのカウントで書く事にします。
メディオコンパスは、12を頭として5までのカウントで書きますが、6から11までのカウントで数えても構いません。
カウント方法は本人が12拍のサイクルをちゃんと把握できていれば、どんな数え方でも構わないのですが、他の人に伝える時は12からのカウントが一番無難なのではないでしょうか。
以下、ブレリアの基本的なコンパスを8つ(12拍パターン×2、6拍パターン×6)のパターンに分類して解説していきます。
12拍のパターン
まず、フラメンコの手引き書などにのっている典型的な12拍のパターンを解説します。
12拍目から入るコンパス
ブレリアの最もベーシックなコンパスは、ソレアのコンパスの12拍目を頭にとったもので、フレーズは12拍目から入ります。
下に図示した通り、アクセント(○がついた拍)はアレグリアスやソレポルと同じカウントの所に入りますが、上段のパターンはグアヒーラやペテネーラと同一のコンパスですね。
⑫ 1 2 ③ 4 5 ⑥ 7 ⑧ 9 ⑩ 11
⑫ 1 2 ③ 4 5 6 ⑦ ⑧ 9 ⑩ 11
1拍目から入るコンパス
1拍目から入るコンパスは、原型であるソレアのノリが残っているものです。
ソレア・ポル・ブレリアやアレグリアスを速回ししたようなリズムで、フレーズはソレアと同じく1拍目から入ります。
アクセントの位置は上の12から入るパターンと同じで、以下の2パターンが基本になります。
1 2 ③ 4 5 ⑥ 7 ⑧ 9 ⑩ 11 ⑫
1 2 ③ 4 5 6 ⑦ ⑧ 9 ⑩ 11 ⑫
踊りのジャマーダも1拍目から入るパターンが多いのですが、その場合は1拍目と2拍目も強調されたりします。
① ② ③ 4 5 ⑥ 7 ⑧ 9 ⑩ 11 ⑫
12拍目を頭にしたブレリアのカウントの中で、急に1拍目から入るフレーズが出てくるとコンパスを間違えやすいのですが、上手く乗るコツとしては、「頭(12拍目)を1拍休んで入るフレージング」と捉えると分かりやすくなるかも知れません。
休 1 2 ③ 4 5 ⑥ 7 ⑧ 9 ⑩ 11
こうすると、最初が休符という事以外は、上の「12拍目から入るコンパス」と同じになります。
メディオコンパス(6拍子)のパターン
ブレリアのリズムパターンのうち、12拍で数えるものは上記2つのパターンが基本ですが、実際の演奏では、もっと色んなパターンが組み合わさってきます。
そういうリズムバリエーションを全部12拍で把握しようというのは少々無理がありますので、ブレリアのコンパスをメディオコンパス(6拍)単位に分解してみましょう。
以下、ブレリアのメディオコンパスパターンをいくつかの型に分類して解説していきます。
なお、コンパスカウントはソレアの12カウントの前半部分(12から5まで)を使っていますが後半部分(6から11まで)を使ってカウントしても構いません。
3/4拍子型
3/4拍子型のメディオコンパスは、12拍目(6拍目)から入って3拍単位でフレージングしていきます。
⑫ 1 2 ③ 4 5
このパターンは、フレージングの頭拍を1拍目に設定すると、ソレアの基本パターンの1つである「3拍目が強い3拍子」になります。
1 2 ③ 4 5 ⑫
弱起の3/4拍子型
弱起の3/4拍子型メディオコンパスは、上記「3/4拍子型」の逆パターンで、アクセントが「3拍子の後ろ2拍」に来るものです。
12 ① ② 3 ④ ⑤
ギタリストはこのパターンで足を踏む場合もあるし、パルマのパターンにも良く出てきます。
3/2拍子型
3/2拍子型メディオコンパスは、12拍目(6拍目)から入って2拍単位でフレージングしていくパターンです。
⑫ 1 ② 3 ④ 5
ヘレススタイルのブレリアは全編これで演奏する事もあります。
頭のアクセントをずらした3/2拍子型
これは、上記「2分の3拍子型」の変化で、頭のアクセントを1拍後ろにずらしたものです。
12 ① ② 3 ④ 5
ジャマーダの前半や通常コンパスの後半部分に用いられます。
弱起の3/2拍子型
弱起3/2拍子型メディオコンパスは、3/2拍子型の強拍と弱拍が逆転したものです。
12 ① 2 ③ 4 ⑤
あらゆる場面で頻出するパルマのパターンです。③のアクセントが最も強く、⑤はあまり強く出さないこともあります。
1・2・3強調型
踊りのジャマーダなどで1・2・3拍目を強調するパターンが良く使われます。
12 ① ② ③ 4 5
このパターンは12拍コンパスの前半部分で使われる事がほとんどです。
ブレリアのコンパスは細分化して把握
こうやってブレリアのコンパスを分解してみると、最初に挙げた12拍のパターンも、その後に挙げたメディオコンパスのパターンの組み合わせで表現できるということにお気付きでしょうか?
実は、今紹介した数個のメディオコンパス基本パターンの組み合わせで、ほとんど全てのブレリアのフレージングに対応可能なのです。
フラメンコを勉強する上で、ブレリアのコンパスは壁になりやすいものの一つですが、こうして細分化して考える事で理解が早まると思いますので、参考にしていただければ幸いです。
なお、ブレリア含む12拍子系のコンパスについて今回解説した内容をさらに発展させ、3拍子系・変拍子系コンパスとの統合まで試みた「コンパスサイクル理論・6サイクルコンパス」というものを、こちらの記事で解説していますので、是非ご一読下さい。
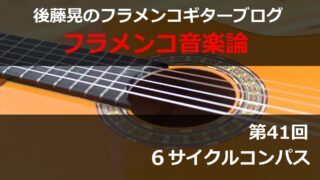
ブレリアのフレージング
ブレリアにおけるギターやカンテ、サパテアードなどのフレージングは下の2つが基本になります。
- 12や1から入って、ソレアやソレポルと同様10に解決するフレージング
- グアヒーラやペテネーラと同様に6にメロディーが解決するフレージング
ただし、ソレアやソレポル、グアヒーラなどに比べてメディオコンパス単位でのバリエーションが豊富で、コンパスをまたぐフレージングも多くなります。
前のコンパスから数拍食い込んで入ったり、逆に数拍あけて入ったり、フレーズの最後も8や9あたりで終わったり、11ウラや12まで行ったり、とにかく遊びが多いです。
ブレリアの調性
古典的なブレリアはポルメディオ(+同主調のAメジャーキーとAマイナーキー)の調性で演奏されるのが最も一般的ですが、とくに決まりがあるわけではなく、様々な歌がブレリアのコンパスに乗せて歌われるため、あらゆるキーで演奏されます。
ノーマルなポルメディオで演奏する場合、カポタストの位置は、女性歌手なら4カポ(実音C♯スパニッシュ)、男性歌手なら1カポ(B♭スパニッシュ)あたりが中心になります。
ブレリアのギタープレイについて
ブレリアでのギタープレイについて、ここではオーソドックスなポルメディオでの演奏を想定して解説します。
ブレリアのマルカールの弾きかた
ブレリアのマルカールはリズム表現と即応性を最優先するため、あまりコードは動かしません。基本は、B♭とAの2コードです。
上手くまとめられるのであれば、いろいろ動かすのも有りだと思いますが、メディオコンパス単位の区切りの中で誰が何をやってくるかわからない状況下では「下手に音楽的展開をつけてしまうと即応性が下がって失敗しやすくなる」という事情があって、こういう形になっているものと思われます。
ブレリアのコードの変わり目
ソレアやソレポルは、1拍目、3拍目、10拍目にコードチェンジポイントが来ますが、ブレリアの場合以下のようになります。
- 12拍目(12で始まるフレーズ場合)
- 1拍目(ソレア的なとりかたの場合)
- 3拍目
- 6拍目
- 10拍目(修飾音ありの場合は9拍目)
この中だと、6拍目のコードチェンジがポイントになってきます。
12拍子で数えた場合のブレリアの6拍目は、メディオコンパスフレーズの頭拍となる他、6拍目にフレーズが解決する場合もあって、その場合、グアヒーラ・ペテネーラ系と同様のフレージングとなります。
ブレリアの歌
ブレリアの歌はバリエーションが多く、ここで全部の歌を解説をするのは無理ですが、最も基本的なのはソレアの進行がベースになったものです。
ソレアベースといっても、ソレアやソレポルよりバリエーションが多彩で、まとめるのも難しいのですが、解説を試みてみましょう。
ソレアベースのブレリアの基本
ソレアベースのブレリアの歌には、いくつかの分岐ポイントがありますので、そこから解説いたします。一般的なポルメディオのキーで書きます。
歌の1節目での分岐
音程的には歌の最初の1節がDmやB♭やCやE7に行くものと、Aのままのものがあり、サイズ的には1節目を1コンパスで歌うものと2コンパスかけて歌うものがあります。
歌の2節目での分岐
2節目でさらに違うコードに行くものと、行かないものがあります。
例えば1節目でDm、2節目でE7やCに行くものもあれば、2節目は1節目の繰り返しだったり、飛ばしてエストリビージョに行くものもあります。
ここまで、エストリビージョに入るまでに、だいたい2コンパスから4コンパスの場合が多いですが、1節目と2節目の間を少し空けたりする場合もあるし、このあたりは半コンパス単位で変化すると思っていたほうが良いでしょう。
エストリビージョでの分岐
ソレアベースのブレリアのエストリビージョ(サビ、締めくくり)は「C7→F→B♭→Aの2回繰り返しで4コンパス」というソレアやソレポルと同様のパターンが多いですが、代理コード的バリエーションとしてD7→Gm7→B♭→Aとか、単純化してC→B♭→Aとか、B♭→Aなどとする場合もあります。
最後、Aに落ちがつく前のB♭のところは、メディオコンパス単位で歌い手が落ちをつけるのを待ったりするので、サイズも不定形です。
エストリビージョ部分の繰り返しもあったり無かったり。
こんな感じで、ソレアベースといってもソレアやソレポルに比べて変化しやすいので、より柔軟な対処が必要になってきます。
ブレリアの歌のコード進行例
以下に、代表的なソレアベースの歌のコード進行例を挙げておきます。コード進行表の書式は次の通り。
- 12拍子の12拍目を頭にした3拍子で記載
- 1行でメディオコンパス(6拍)
- ○はコードチェンジ無しの拍
- ()内のコードは省略される場合もある
- 複数のコードの可能性があるところは「,」で区切る
- キーはポルメディオ(Aスパニッシュ調)で記載
- コンテスタシオン(合いの手)は歌が休みになる部分で、普通は0コンパス(コンテスタシオン無し)から1コンパス
- ※マークが付いている行は省略されることもある
- 9拍目でコードチェンジしているところは本来は10拍目だが、修飾音込みで前倒しで変化する事のほうが多いので9拍目に統一して記載
- 3拍目のコードチェンジは全て12拍目から前倒しで変わることもある
- 9拍目(=10拍目)のコードチェンジは全て6拍目から前倒しで変わることもある
- 全編にわたって半コンパス単位でサイズが変化することがある
ソレアやソレポルでは1節目と2節目は同じメロディーを繰り返す場合が多いですが、ブレリアは変化が増えます。
1節目
|A ○ ○|○ ○ ○|※
|○ ○ ○|A,Dm,B♭,E7,C ○ ○|
|○ ○ ○|(A) ○ ○|※
|○ ○ ○|A,Dm,B♭,E7,C ○ ○|※
コンテスタシオン
2節目
|A ○ ○|○ ○ ○|※
|○ ○ ○|A,Dm,B♭,C,E7 ○ ○|※
|○ ○ ○|(A) ○ ○|※
|○ ○ ○|A,Dm,B♭,C,E7 ○ ○|※
エストリビージョ(サビ)
|○ ○ ○|C7,B♭ ○ ○|
|○ ○ ○|F,B♭ ○ ○|
|○ ○ ○|B♭ ○ ○|
|○ ○ ○|A ○ ○|
|○ ○ ○|C7,B♭ ○ ○|※
|○ ○ ○|F,B♭ ○ ○|※
|○ ○ ○|B♭ ○ ○|※
|○ ○ ○|A ○ ○|※
ディグリー(度数)表記版
1節目
|Ⅰ ○ ○|○ ○ ○|※
|○ ○ ○|Ⅰ,Ⅳm,♭Ⅱ,Ⅴ7,♭Ⅲ ○ ◯|
|○ ○ ○|(Ⅰ) ○ ○|※
|○ ○ ○|Ⅰ,Ⅳm,♭Ⅱ,Ⅴ7,♭Ⅲ ○ ○|※
コンテスタシオン
2節目
|Ⅰ ○ ○|○ ○ ○|※
|○ ○ ○|Ⅰ,Ⅳm,♭Ⅱ,♭Ⅲ,Ⅴ7 ○ ○|※
|○ ○ ○|(Ⅰ) ○ ○|※
|○ ○ ○|Ⅰ,Ⅳm,♭Ⅱ,♭Ⅲ,Ⅴ7 ○ ○|※
エストリビージョ、サビ部分
|○ ○ ○|♭Ⅲ7,♭Ⅱ ○ ○|
|○ ○ ○|♭Ⅵ,♭Ⅱ ○ ○|
|○ ○ ○|♭Ⅱ ○ ○|
|○ ○ ○|Ⅰ ○ ○|
|○ ○ ○|♭Ⅲ7,♭Ⅱ ○ ○|※
|○ ○ ○|♭Ⅵ,♭Ⅱ ○ ○|※
|○ ○ ○|♭Ⅱ ○ ○|※
|○ ○ ○|Ⅰ ○ ○|※
ソレアベースではない歌について
ソレアベース以外のブレリアの歌については、本当にケースバイケースなのですが、例を挙げるなら下のようなものがあります。
- メジャーキーのカンティーニャス様のもの
- ロマンセ(語り歌)やカンシオン(民謡)をブレリアに乗せたもの
- 踊りの後歌などに使われる、各形式固有のメロディーをブレリアにしたもの
- 歌手の創作によるもの
こんな具合で、何でもブレリア化して歌われるため、コード進行もその元ネタに合わせて変化します。
ハレオス(Jaleo,Jaleos)
エストレマドゥーラ地域で歌われるブレリアをハレオ(Jaleo)、ハレオス(Jaleos)と呼んで別形式扱いにすることがあります。
ハレオスの元ネタはエストレマドゥーラ地方の民謡で、コード進行なども独自のフォーマットがあります。
そのコード進行を簡単に言うと、メディオコンパス単位でコードが5度進行・下降進行するものです。
ちなみに、これの2拍子バージョンは、タンゴス・エストレメーニョス、タンゴ・デ・エストレマドゥーラと呼ばれます。
タンゴの形式紹介でタンゴス・エストレメーニョスの特徴やコード進行について書いていますが、コード進行に関してはハレオスもほぼ同様の展開となります。元歌が同じ民謡のメロディーだったりするので。
――今回の記事だけで、ブレリアという形式を全て理解していたただく、というのは難しいと思いますが、ブレリアという形式は「ソレアのコンパスをベースに、即興的にどれだけのバリエーションを展開して遊べるか?」という所に重きを置いて発展してきた結果、現在のような複雑な形になっているという事はご理解いただけたでしょうか?
今回までで12拍子の本流であるソレアからブレリアまでの流れを解説しましたが、この他にも12拍子で演奏される形式はあります。次回からは民謡系の12拍子系形式の解説をしていく予定です。
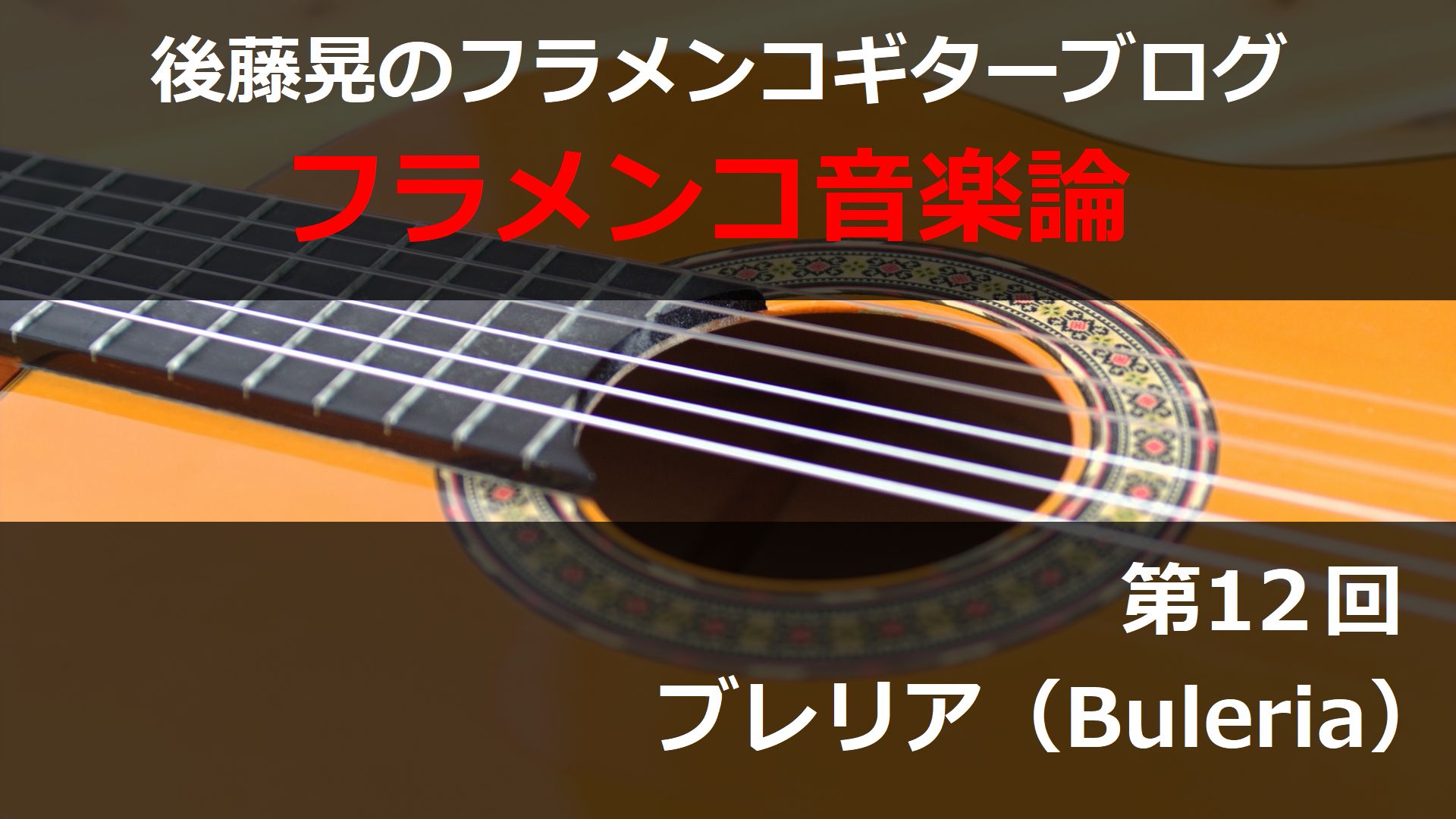
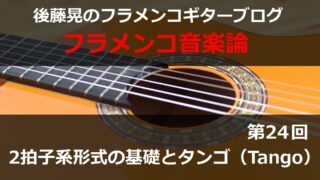

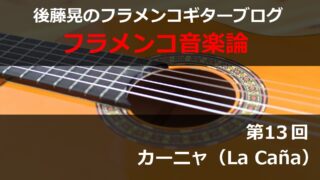
コメント