今、フラメンコ音楽論では「コンパス=サイクル理論」を展開中ですが、これは「フラメンコのコンパスを直感的にする演奏」というテーマで、自分が考案したものです。
「コンパス=サイクル理論」は、フラメンコのリズムをブロック化・シンプル化して扱いやすくしようというもので、前回は2拍子系形式に適用する「4サイクルコンパス」の解説をしました。
今回は、フラメンコを演奏する上で最も重要かつ鬼門となりやすい「6サイクルコンパス」の解説です。
実際、フラメンコを演奏する上で最大のポイントになるところなので、丁寧に解説します。
6サイクルコンパスの基本
6サイクルコンパスは、6拍を1単位としたリズムサイクルで、3拍子系形式・12拍子系形式・3.3.2.2.2型の変拍子形式に対して使用します。具体的な形式名は以下の通りです。
3拍子系
セビジャーナス、ファンダンゴ・デ・ウエルバ、ファンダンゴ・アバンドラオ等
12拍子系
ソレア、ソレア・ポル・ブレリア、ブレリア、アレグリアス、カーニャ、バンベーラ等
3.3.2.2.2型
グアヒーラ、ペテネーラ等
6サイクルの難しいところは、12拍子形式に適用する場合、フレーズやリズムパターンの頭がサイクルの頭の強拍(12拍子なら12拍目)から入る場合と、1拍後ろの弱拍(12拍子なら1拍目)から入る場合があって、混乱しやすい点です。
それに加えて、例えばブレリアなどはコンパスをまたいだフレーズは日常茶飯事だし、ファンダンゴやセビジャーナスも伝統的に1、2拍食って入るフレーズが多かったりで、今やっているフレーズがサイクルのどこから入っているのか?を常時把握する必要があります。
次に6サイクルをキープするためのサイクルパターンを解説しますが、テンポやコンパスの種別によって、これらのパターンを使い分けていきます。
サイクルパターンは演奏しながら足を踏んでキープすることを考えると、なるべく均等な間隔で踏んでいけるパターンが望ましいです。
12拍子で言うと、6サイクル1回=6拍=メディオコンパスで、6サイクル2回で1コンパスのサイズになります。
強拍スタート6サイクル
強拍スタート6サイクルは、強拍(アクセント拍)から始める6拍サイクルパターンで、12拍子系なら12拍目(ソレアカウント)、3拍子系なら1拍目からスタートします。
3.3.2.2.2型は数え方が色々ありますが、コンパスの頭のアクセント拍からスタートします。
●が足を踏む拍、◯は頭の中で数える拍です。
強拍スタート3拍×2
●◯◯●◯◯
一般的な3拍子と同様の感じ方。12拍子で重要な3拍目のアクセントが感じやすい。
強拍スタート2拍×3
●◯●◯●◯
12拍子のフレーズの解決拍である10拍目のアクセントが感じやすい。
頭抜き3拍子
◯●●◯●●
昔のパコ・デ・ルシアなどはブレリアでこんなとりかたをしているが、訓練しないと足が疲れて逆にテンポキープがあやしくなることも。
サイクル頭のみ
●◯◯◯◯◯
テンポが速い場合などは6サイクルの頭拍のみを踏んでいくのが6サイクルキープは一番楽だが、BPMキープは不利になる。
弱拍スタート6サイクル
弱拍スタート6サイクルは弱拍(アクセント拍ではない拍)から始める6拍サイクルパターンで、これを意識するのは12拍子のときです。
遅いテンポ帯の12拍子では、基本的にソレアカウントの1拍目(弱拍)がフレーズやコード進行の頭になっているので、6サイクルもソレアカウントの1拍目から当てはめていくのが基本です。
この場合、使用する6サイクルパターンは以下のようになります。
弱拍スタート3拍×2
◯◯●◯◯●
弱拍スタート2拍×3
◯●◯●◯●
これらは上の強拍スタート6サイクルを1拍ずらしただけですが、強拍スタートのフレーズと弱拍スタートのフレーズが切り替わるときに、コンパスが1拍ズレる事故が起こりやすく、12拍子系最大の注意ポイントとなります。
12拍子で強拍スタートになるか弱拍スタートになるかは、テンポやフレーズによって流動的ですが、最終的にはどんなフレーズが来ても惑わされずに同じ6サイクルを回し続けて、自分の頭の中で強拍スタートと弱拍スタートの感じ分けを自在に行えるようにしないといけません。
3.3.2.2.2型と3拍子にも弱起のフレーズはありますが、12拍子がマスター出来ていれば、その応用で対処できます。
全拍ベタ6サイクル
4サイクルと同様、テンポがゆっくりの場合や、BPMのキープを最優先したい場合は、全ての拍を踏んだほうが安定します。
全拍ベタ6サイクル
●●●●●●
強拍スタートでも弱拍スタートでも同じのっぺらぼうなパターンになるため、強拍スタートと弱拍スタートのフレーズが入り乱れた場合などに6拍のサイクルを見失いやすい欠点がある。
複合型6サイクル
3.3.2.2.2型や、ブレリアの一部などは3拍×2と2拍×3を組み合わせたパターンを使うと、コンパスのアクセント通りになるので一番しっくりきます。
強拍スタート複合型
●◯◯●◯◯+●◯●◯●◯
複合型6サイクルは6サイクルを2つ合体させるので、12拍(12拍子なら1コンパス)で1サイクルとなります。
12拍子を演奏するときは弱拍スタートの複合型を使う事もあります。
弱拍スタート複合型
◯◯●◯◯●+◯●◯●◯●
こちらは標準的な12拍子のアクセントをそのまま踏むことになって、とくにアレグリアスやソレポルのフレーズとマッチングしやすいですが、演奏しながらのサイクルキープにはやや慣れが必要なパターンです。
――これで6サイクルのパターンを一通り解説しましたが、以下の記事では、これらのパターンの実用方法をテンポ別に解説していきます。
ここで名付けたサイクル名を使って解説していきますので、必要に応じて上に戻って確認してください。
超スローテンポの6サイクル
超スローテンポは12拍子の場合、主に踊りのソレアを演奏するためのテンポで、アレグリアスのシレンシオもこのテンポで演奏する場合が多いです。
3拍子系では、ファンダンゴ・アバンドラオをゆっくりやる場合に、このテンポになります。
3.3.2.2.2型はここまでゆっくり演奏することはほとんど無いと思います。
超スローテンポの12拍子
テンポ:65BPMから90BPMくらい
サイクルパターン:全拍ベタ6サイクル、弱拍スタート複合型6サイクル
適合する形式:ソレア(踊りのレトラ)、アレグリアス(踊り)のシレンシオなど
超スローテンポ12拍子のサイクルキープの基本は全拍ベタ6サイクルですが、3拍1組の3拍子で感じるようにします。
BPMよりコンパスのアクセントをはっきりさせたい場合は、弱拍スタート複合型6サイクルを使います。
超スローテンポの3拍子
テンポ:65BPMから90BPMくらい
サイクルパターン:全拍ベタ6サイクル、強拍スタート3拍×2
適合する形式:スローなファンダンゴ・アバンドラオ
3拍子を超スローでやるとしたら、ほぼファンダンゴ・アバンドラオ系で、1拍目から6サイクルをスタートします。
基本は全拍ベタ6サイクルで、3拍ひとかたまりの3拍子を意識します。
サイクルの頭を明確にする場合は、強拍スタート3拍×2のパターンがいいでしょう。
超スローテンポでの倍速6サイクル
12拍子・3拍子ともに、超スローテンポで複雑なリズムプレイをしたい場合、倍速のミドルテンポ6サイクル(130BPMから180BPM)を使用するのが有効です。
足でサイクルキープする場合は強拍スタート2拍×3のパターンが良いでしょう。
12拍子の場合も3拍子の場合も、強拍スタート2拍×3のパターンを1拍目の頭から当てはめますが、本来のコンパスの倍速サイクルなので、1サイクルで元のコンパスの3拍の長さに、2サイクルでメディオコンパスの長さになります。
下に図示しますが、上段が倍速の強拍スタート2拍×3の6サイクル、下段が超スローテンポのソレアやアバンドラオのカウントになります。
●◯●◯●◯/●◯●◯●◯(6サイクル)
1・2・3・/4・5・6・(カウント)
この感じ方なら、ゆったりしたブレリアの感覚で超スローのソレアやアバンドラオを演奏することが可能になります。
スローテンポの6サイクル
ここで言うスローテンポは100BPMから130BPMのテンポ帯で、カンテ伴奏のソレアの速さです。
他には、グアヒーラやペテネーラなどの3.3.2.2.2型をゆっくり演奏する場合や、ファンダンゴ・アバンドラオを速めのテンポでやる場合もこれくらいになります。
このテンポでのカンテソロ伴奏の場合、あまり細かいシンコペーションは使わずに、少し緩急をつけた演奏が映えます。
スローテンポの12拍子
テンポ:100BPMから130BPMくらい
サイクルパターン:弱拍スタート複合型6サイクル、全拍ベタ6サイクル
適合する形式:ソレア(歌伴奏)、スローなカーニャ、アレグリアスのシレンシオ(速め)など
スローテンポの12拍子は、ソレアの歌伴奏の他、カーニャをゆっくり演奏する場合や、アレグリアスのシレンシオを速めに弾く場合はこのテンポ帯になります。
このテンポの12拍子の場合、1拍目(弱拍)から6サイクルをスタートして、基本は弱拍スタート複合型6サイクルを使いますが、メディオコンパスが入った場合、弱拍スタートの3拍×2のパターンや弱拍スタートの2拍×3のパターンを使って適宜対処します。
BPM重視の場面では、3拍子を意識した全拍ベタ6サイクルを使用します。
スローテンポの3拍子
テンポ:100BPMから130BPMくらい
サイクルパターン:強拍スタート3拍×2、全拍ベタ6サイクル
適合する形式:ファンダンゴ・アバンドラオ、ファンダンゴ・デ・ウエルバ(遅め)、セビジャーナス(遅め)など
スローテンポの3拍子はファンダンゴ・アバンドラオになりますが、ファンダンゴ・デ・ウエルバやセビジャーナスをゆっくりのテンポで演奏する場合などもこのテンポ帯になります。
1拍目からサイクルを開始して、基本は強拍スタート3拍×2の6サイクルを使いますが、BPM重視の場面では3拍子を意識した全拍ベタ6サイクルを使用します。
スローテンポの3.3.2.2.2型
テンポ:100BPMから130BPMくらい
サイクルパターン:強拍スタート複合型6サイクル、全拍ベタ6サイクル
適合する形式:グアヒーラ(遅め)、ペテネーラ(遅め)
3.3.2.2.2型だと、グアヒーラやペテネーラの踊りのレトラなどがこのテンポ帯になります。
コンパスの頭から6サイクルをスタートして、使用するパターンは強拍スタート複合型6サイクルです。
BPM重視なら全拍ベタ6サイクルですが「3.3.2.2.2」のアクセントは感じながら全拍踏む感じです。
スローテンポでの倍速6サイクル
スローテンポ(100BPMから130BPM)6サイクルでの倍速取りですが、ファンダンゴ・アバンドラオとか、ソレア系でも踊りのエスコビージャなどでは、倍速のハイテンポ6サイクル(200BPMから250BPM)でカウントするとブレリアの語彙が使えるようになるので表現の幅が広がります。
使用サイクルパターンやコンパスへの当てはめ方は超スローテンポの倍速取りの場合と同様ですが、このテンポでの倍速取りはハイテンポ6サイクル(180BPMから250BPM)を使用することになるので、フレーズ的に完全にブレリアのノリになります。
ミドルテンポの6サイクル
ここで言うミドルテンポは130BPMから170BPMのテンポ帯で、12拍子ならソレア・ポル・ブレリア、アレグリアスなどが該当します。
3.3.2.2.2型やファンダンゴ系、セビジャーナスなどの3拍子形式もこのテンポで演奏する事が多く、6サイクルコンパスの中心的なテンポ帯になります。
一般的にミドルテンポ以上の速さではテンポを揺らしたりはせず、シビアなテンポキープが要求されます。
ミドルテンポの12拍子
テンポ:130BPMから170BPMくらい
サイクルパターン:弱拍スタート複合型6サイクル、全拍ベタ6サイクル
適合する形式:ソレア・ポル・ブレリア、アレグリアス、バンベーラ、カーニャ(速め)など
ミドルテンポの12拍子では、原則として超スローテンポ・スローテンポと同様にソレアカウントの1拍目(弱拍)から6サイクルをスタートさせます。
ただし、このテンポ帯の12拍子は12拍目が頭に感じられるフレーズやリズムパターンも良く出てくるので一番混乱しやすいところです。
12から入るフレーズなのか、1から入るフレーズなのか、しっかりと認識するようにしましょう。
使用するサイクルパターンはスローテンポと同様、弱拍スタート複合型6サイクルが基本です。
BPMキープを最優先する時は全拍ベタ踏みもしますが、少々しんどくなってくるテンポです。
ミドルテンポの3拍子
テンポ:130BPMから170BPMくらい
サイクルパターン:強拍スタート3拍×2、全拍ベタ6サイクル
適合する形式:ファンダンゴ・デ・ウエルバ、ファンダンゴ・アバンドラオ(速め)、セビジャーナス
ミドルテンポの3拍子は、ファンダンゴ・デ・ウエルバやセビジャーナスの標準テンポです。
ファンダンゴ・アバンドラオもこれくらいの速いテンポでやることもあります。
使用パターンはスローテンポと同様、強拍スタート3拍×2を基本にしつつ、BPMキープ重視の場面では全拍ベタ6サイクルも併用します。
ミドルテンポの3.3.2.2.2型
テンポ:130BPMから170BPMくらい
サイクルパターン:強拍スタート複合型6サイクル、全拍ベタ6サイクル
適合する形式:グアヒーラ(速め)、ペテネーラ(速め)
ミドルテンポの3.3.2.2.2型は、グアヒーラ、ペテネーラの歌伴奏のテンポですが、踊りのレトラでもこれくらいのテンポで設定することがあります。
使用パターンはスローテンポと同様で、強拍スタート複合型を基本に、BPM重視の場面では全拍ベタ6サイクルも併用します。
ハイテンポの6サイクル
ハイテンポは190BPMから250BPMのテンポ帯です。
ハイテンポ6サイクルに該当する形式は、ブレリアの他、ファンダンゴ・デ・ウエルバやセビジャーナスを速いテンポで演奏するとこのテンポ帯になります。
ハイテンポの12拍子
テンポ:190BPMから250BPMくらい
サイクルパターン:強拍スタート3拍×2、強拍スタート2拍×3
適合する形式:ブレリア
ハイテンポ12拍子は、ブレリアの標準テンポで、ソレアカウントでいう12拍目から強拍スタートの6サイクルをスタートさせます。
使用パターンは、足の踏みやすさやを考えると、強拍スタート3拍×2と強拍スタート2拍×3を場面によって使い分けるのが良いと思います。
このテンポ帯では上記2パターンでBPMキープも問題無いので、全拍ベタ踏みは無理にやらなくて良いです。
ハイテンポ12拍子では弱起フレーズもありますが、ミドルテンポより頻度はぐっと下がって、コード進行や全体のノリも12拍目(ソレアカウント)が節目になっていることが多いので、その中で1拍目から入るフレーズが来たら「頭を1拍空けて入っている」という感じ方になってきます。
ハイテンポの3拍子
テンポ:190BPMから250BPMくらい
サイクルパターン:強拍スタート3拍×2
適合する形式:ファンダンゴ・デ・ウエルバ(速め)、セビジャーナス(速め)
3拍子の場合はファンダンゴ・デ・ウエルバやセビジャーナスのかなり速い部類のものになります。
使用パターン強拍スタート3拍×2で、全拍ベタ踏みは無理にやらなくて良いでしょう。
ハイテンポの3.3.2.2.2型
テンポ:190BPMから250BPMくらい
サイクルパターン:強拍スタート複合型6サイクル
適合する形式:グアヒーラ(ブレリアテンポ)、ペテネーラ(ブレリアテンポ)
ハイテンポの3.3.2.2.2型は、踊りの後歌のブレリアのテンポです。
このテンポだとグアヒーラもペテネーラもほぼブレリアのコンパスで演奏されますので、ハイテンポ12拍子でとったほうがマッチすることが多いです。
このテンポで敢えて3.3.2.2.2型でとる場合、使用パターンは強拍スタート複合型で、全拍ベタ踏みは無理にやらなくて良いです。
超ハイテンポの6サイクル
超ハイテンポは250BPM以上のテンポ帯です。
超ハイテンポ4サイクルと同様、踊りの追い上げやマチョでの使用がほとんどです。
使用サイクルは、12拍子、3拍子、3.3.2.2.2型のいずれもハイテンポの場合と同様ですが、テンポがあまりに速い場合「サイクル頭のみ」のパターンが良いでしょう。
あまり細かいことを考えてやる余裕もないスピードなので、遅れないように訓練あるのみです。
――今回やった6サイクルのコンパスですが「フラメンコを演奏する上でネックになるだろう事の半分以上がここに含まれている」と言っても過言では無いので、1回の講座で伝え切るのは少々無理があったかもしれません。
文にすると難解に思えますが、最終的には体で覚えて、意識せずとも4拍子と同じように12拍子が感じられるようにしたいところで、今回の講座がヒントになれば幸いです。
次回は別枠扱いにしたシギリージャ系サイクルの解説です。
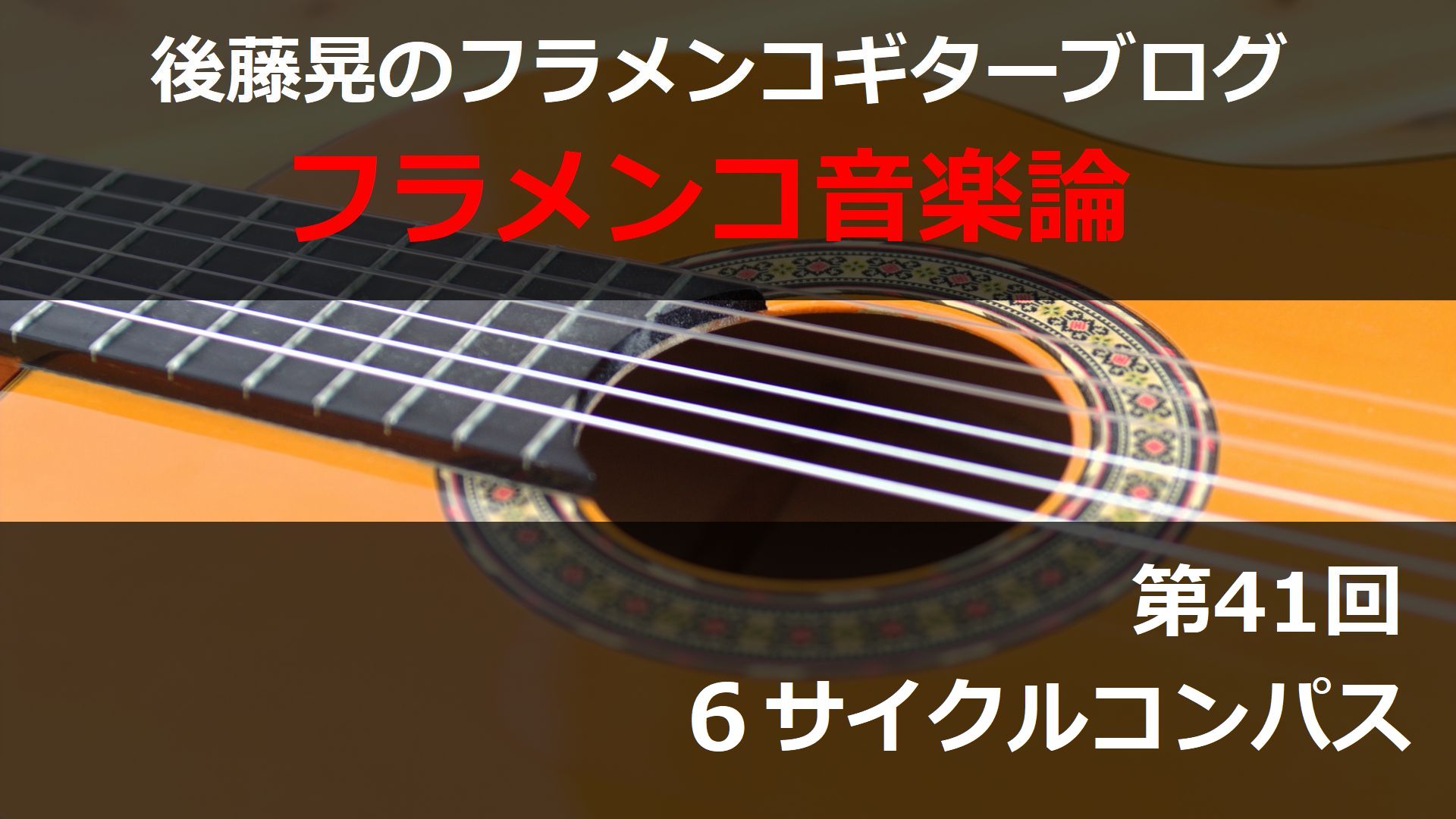
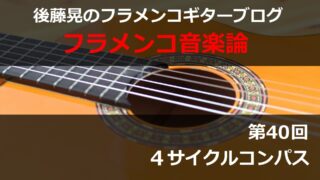
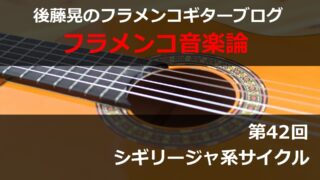
コメント