フラメンコ音楽論では前回、北部起源系2拍子の概要と、代表形式としてガロティンの紹介をしました。
今回は、ガロティンとは兄弟のような関係にあるファルーカ形式の解説をいたします。
ファルーカ形式概要
単数形:Farruca
複数形:普通は使わない
主な調性:Aマイナーキー
テンポ(踊り):70BPMから90BPM
テンポ(ギターソロ):70BPMから160BPM
ファルーカは、スペイン北部のガリシア地方の民謡がフラメンコに取り入れられて成立した形式です。
ファルーカの形式名の語源であるファルーコ(Farruco)・ファルーカ(Farruca)というのは、ガリシア地方からアンダルシアへ来ている移民・出稼ぎ労働者を指していて、「アンダルシア人から見たガリシアのイメージ」といった意味合いでしょうか。
20世紀前半に踊り手のフランシスコ・メンドサ・リオス“ファイーコ”(Francisco Mendoza Rios “El primer Faíco”)が、ギターのラモン・モントージャ(Ramon Montoya)と組んでガロティンとファルーカを舞踊化した事は前回も触れましたが、ファルーカに関しては、歌もファイーコ自身がガリシアの詩集をもとに創作したといいます。
成立の過程から考えて、ガロティンとファルーカは兄弟のような形式と言えますが、長調で演奏されるガロティンは軽妙でユーモラスな曲なのに対して、短調で演奏されるファルーカは曲調も歌詞も重くシリアスなものです。
ファルーカの踊りは男性向けのものとされていて、マッチョな重厚感・悲壮感が強調されます。
カンテについては踊り歌が中心で、カンテソロで歌われる事は少ないのですが、ギターの領域ではギターソロ曲として好んで演奏される形式です。
ファルーカの調性
ファルーカは、Aマイナーキーでの演奏が一般的ですが、ギターソロでは様々なキーで演奏されていて、EマイナーキーやDマイナーキーのものもあります。
歌は同主調のメジャーキー(主調がAマイナーキーならAメジャーキー)の音が混じったりしますが、ほとんどがトニックコードのみの変化で、ⅠmコードがⅠコードに変化するパターンです。
カポタストの位置は、女性歌手なら4カポ(実音C♯マイナーキー)、男性歌手なら1カポ(実音B♭マイナーキー)あたりが中心になります。
ファルーカのコンパス
ファルーカのコンパスは、基本はガロティンと同様、北部起源系の「4分音符1つ+8分音符2つ」という音型を基調とした均等なリズムで、8拍で1コンパスです。
北部起源系コンパスの基本的なことは前回の記事で解説していますので、そちらをご覧下さい。
ファルーカ固有の特徴としては、メディオコンパスの頭である1拍目、5拍目を強調する傾向があります。
① 2 3 4 ⑤ 6 7 8
※○がついた数式がアクセント拍
重々しいリズムになりますが、悲劇的な雰囲気・曲調を強調した結果ではないかと。
ファルーカのマルカールは、上記のような頭が強いコンパスで以下のように演奏されます。1小節4拍、Aマイナーキーで記載。
|E7|Am|
また、ファルーカの演奏テンポですが、踊りのレトラは一般的にガロティンよりゆっくり、70BPMから90BPMくらいが中心です。
ギターソロ曲に関しては、昔のサビーカスなどのスタイルはかなり速いテンポ(130BPMから160BPM)で演奏されていましたが、近年は踊りのレトラのテンポに近いゆったりしたものが主流になっています。
ファルーカのジャマーダ
ファルーカを演奏する上で、注意すべきはジャマーダが倍速になる場合が多い事でしょうか。
例えば、75BPMでファルーカを演奏していて、ジャマーダが入って静止する場合、ジャマーダの頭から150BPMのタンゴでカウントします。
ティエント、タンゴ・デ・マラガ、ガロティン、タラントなどのゆっくりの2拍子形式は、踊りのサパテアードの途中やジャマーダで倍テンポのタンゴに切り替わることがある、ということをティエントの紹介記事の中でお話ししましたが、ファルーカの場合は(倍テンポにならないノーマルなジャマーダもありますが)ジャマーダで倍速のタンゴに切り替わるのが「標準」なのです。
ファルーカのジャマーダはⅣmのコードから入るのが慣例で、例えばAマイナーキーなら下のように演奏します。1小節で4拍=メディオコンパスです。
|Dm|Am|(F) E7|Am|
ちなみに、締めくくりは4小節目(Am)の3拍目で「タンゴのテンポで数えた7拍目」に当たります。
ファルーカの歌
ファルーカの歌は、種類こそ多くありませんが、とてもドラマチックで聴き応えがあるものです。
後半のリフレイン部分は、Dm(Ⅳm)から入るのが特徴ですが、①同主調に行くタイプと、②5度進行するタイプの2パターンに分かれます。
以下に、スタンダードなファルーカの歌のコード進行をご紹介します。書式は次の通り。
- 4拍子(1小節4拍)で記載
- 1行で1コンパス(8拍)
- 1小節に複数のコードが入る場合は半角スペースで区切る
- キーはAマイナーで記載
- 半コンパス(4拍)単位でサイズが変わる事がある
リフレインで同主調に行くパターン
|E7|Am|
|Am|E7|
リフレイン
|Dm|A|
|E7|Am A7|
|Dm|A|
|E7|Am|
ディグリー(度数)表記版
|Ⅴ7|Ⅰm|
|Ⅰm|Ⅴ7|
リフレイン
|Ⅳm|Ⅰ|
|Ⅴ7|Ⅰm Ⅰ7|
|Ⅳm|Ⅰ|
|Ⅴ7|Ⅰm|
リフレインが5度進行のパターン
|E7|Am|
|Am|E7|
リフレイン
|Dm G7|C F|
|Bm7(♭5) E7|Am A7|
|Dm G7|C F|
|Bm7(♭5) E7|Am|
ディグリー(度数)表記版
|Ⅴ7|Ⅰm|
|Ⅰm|Ⅴ7|
リフレイン
|Ⅳm ♭Ⅶ7|♭Ⅲ ♭Ⅵ|
|Ⅱm7(♭5) Ⅴ7|Ⅰm Ⅰ7|
|Ⅳm ♭Ⅶ7|♭Ⅲ ♭Ⅵ|
|Ⅱm7(♭5) Ⅴ7|Ⅰm|
ファルーカとタンゴ・デ・マラガの弾き分け
タンゴ・デ・マラガ解説の時にも少し触れていますが、ファルーカとタンゴ・デ・マラガは、Aマイナーキーでゆっくりテンポの2拍子ということで、ギターに関しては高い互換性があります。
タンゴ・デ・マラガ形式解説

ファルセータに限って言えば、実用上はタンゴ・デ・マラガとファルーカは、ほぼ完全互換と思って良いでしょう。
タンゴ・デ・マラガとファルーカを弾き分けるポイントとしては、主にマルカールとか歌伴奏部分だと思いますが、この2つの形式の違いを一覧にまとめてみましょう。
まず、タンゴ・デ・マラガの特徴は以下の通り。
- ギターソロ曲は少なく、ほとんどがファルーカとして演奏される
- バイレでは女性向けの形式とされていて、振り付けも曲線的で優美なものが多い
- コンパスはタンゴ系なので頭をあまり強く弾かない
- リズムはティエントのように粘ることがある
- ジャマーダは倍速にはならないのが普通
これに対して、ファルーカの特徴は以下になります。
- ギターとバイレ中心の形式
- バイレでは男性向けの形式とされ、振り付けも直線的でマッチョなものが多い
- コンパスは頭を強く弾いて重さを強調
- リズムは粘らせずに均等に弾く
- ジャマーダは倍速になってDmから入る
踊り伴奏の場合、ティエント、タンゴ・デ・マラガ、ファルーカ、ガロティン、タラントの各形式は、ほぼ同じようなテンポ・リズム型になる事が多いのですが、形式ごとの弾き分けを追及するなら、このあたりの事にも拘ってみると良いのではないでしょうか。
――次回は北部起源系2拍子で最も難解と思われるタラントを解説します。

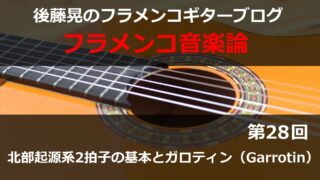
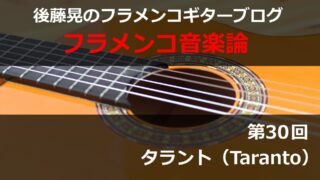
コメント