フラメンコ音楽論では、直近の記事で「北部起源系2拍子」としてガロティンとファルーカを紹介しましたが、今回はコンパスとしては北部起源系2拍子に属しているものの、色んな意味で特殊な形式であるタラントの解説をいたします。
タラント形式概要
単数形:Taranto
複数形:Tarantos
主な調性:ポルタラント(F♯スパニッシュ調)
テンポ(踊り):65BPMから90BPM
テンポ(歌):90BPMから120BPM。リブレに近くなる場合も多い
少し前に、ファンダンゴ系の形式を解説しましたが、そのなかで自由リズム形式のタランタという形式があったのをおぼえていますか?
カンテ・レバンテとタランタの解説
タランタは、3拍子系のファンダンゴが自由リズム化した後、アンダルシア東部のアルメリア地方で現地の民謡の影響を受けて成立した形式ですが、そのタランタを2拍子のコンパスに当てはめて演奏されたものが、今回とりあげるタラントです。
2拍子の感覚で歌われるタランタ=後にタラントと呼ばれるスタイルがいつ頃から存在していたのか?という事は今一つハッキリしないのですが、踊り(バイレ)に関しては、カルメン・アマジャ(Carmen Amaya)が舞踊化してレパートリーに加えた事でメジャーな形式として確立しました。
踊りのタラントはハッキリとした2拍子で演奏されますが、カルメン・アマジャがやっていたものをベースに独自の様式が発展していて、この形式のためだけにおぼえなければならない事が沢山あります。
カルメン・アマジャによって舞踊化される以前は、①3拍子の感覚が強い自由リズムの歌→タランタ、②2拍子の感覚が強い自由リズムの歌→タラント、といった感じで、タランタとタラントの境界は現在よりもかなり曖昧なものだったのではないでしょうか。
タラントのコンパス
タラントのコンパスには北部起源系の2拍子が採用されています。
なぜ、ファンダンゴ系で一般的なアバンドラオのリズムではなく、2拍子のコンパスがついたのか?という疑問に対しては、以下の3つの回答が考えられます。
- タランタのメロディーは元々2拍単位のフレージングが多い
- カンテ・レバンテは他の一般的なファンダンゴより地元(アルメリアやムルシア)民謡のカラーが強く、タランタからタラントに分化する際に2拍子系の民謡の影響を受けた可能性がある
- 3拍子から2拍子にリズムを変えて歌う遊びから発生した可能性がある
次に、2拍子化したとして、何故タンゴ系コンパスではなく、北部起源系コンパスを採用したのか?という事については、リブレの感覚が濃厚に残っているタラントの歌をインテンポのコンパスに乗せるために、メディオコンパスのさらに半分の2拍単位でコンパスを伸縮させる必要があった、という事情があったのではないでしょうか。
つまり「リブレの歌の2拍子化」という目的に柔軟に対応するために、タンゴ系コンパスよりも構造が単純で細分化しやすい北部起源系コンパスが採用されたのではないかと。
このように、リブレベースの歌を2拍子化させているという特殊事情があるため、他の2拍子系形式が実質は4拍子(最小構成単位であるメディオコンパが4拍なので)なのに対して、タラントだけは2拍単位での伸縮が発生する事に留意して下さい。
2拍単位で伸縮するということは、1フレーズが6拍や10拍になることも有り得るわけですが、2拍での伸縮が発生するのは以下のような場面に限定されます。
- 踊りのレトラ部分やカンテソロなどの歌が入っているところ
- 踊りのレトラに入るコンテスタシオンの最後の部分
- サパテアードとギターの合わせフレーズ
- 一部のファルセータ
これ以外の場面では、他の2拍子系と同様に4拍子(メディオコンパス)がベースになります。
タラントの調性
カンテレバンテはF♯スパニッシュ調(ポルタラント)という特殊な調性で演奏されますが、タラントもそれに準じます。
ポルタラントでは、ルートコードに開放弦が絡んでF♯7(♭9,11)というテンションコードになりますが、これ以降、コードネームでF♯7と表記されている所は、ほとんどの場合F♯7(♭9,11)で鳴らすと思ってください。
カポタストの位置は、女性歌手の場合は5カポ(Bスパニッシュ調)、男性歌手なら1カポ(Gスパニッシュ調)あたりが中心です。
ギターのコードワークとマルカール
タラントのコードワークはルートコードの構成に象徴されるように、ギターの開放弦を絡めた半音ぶつかりのボイシングを多用します。
ギターコードのボイシングについては、フラメンコ音楽論07で詳しく書いていますので、そちらの「ポルタラント」の項目を参照してください。
タラントのマルカールは原則的に8拍単位で、普通は2拍単位での伸縮はしません。
コード進行は以下の通り。1小節で4拍=メディオコンパスです。
|G|F♯7|
進行としては超シンプルですが、独自の「それっぽい解決フレーズ」があるので、それらしく弾くにはそういう引き出しをたくさん持っている必要があります。
タラントの歌の構成
タラントの歌伴奏は「タランタ(リブレ)の歌を2拍で区切って伴奏をつけている」という感覚で、常に2拍単位での伸縮を意識します。
ここでは、演奏頻度が高い踊り歌を中心にみていきましょう。
標準的な踊り歌の展開は、以下のようになります。
- 前フリ
- コンテスタシオン
- Aメロ1
- コンテスタシオン
- Aメロ2
- レマーテ(歌はアーイーとかで伸ばして、踊りの足を入れたりする)
- エストリビージョ(締めくくり)
2回挟まるコンテスタシオンはDメジャーコードで、一般的なポルアリーバのファンダンゴで言うと、歌の1節目・3節目のCコードの合いの手部分に該当しますが、レバンテ系のファンダンゴは、このコンテスタシオンのメジャーコードの所を歌わないことで独特の雰囲気を出しています。
6.のレマーテの部分はD7コードで、踊りの足がだーっ、と入ったりしますが、歌い手は「アーイー」等で伸ばしてレマーテが終わるのを待ちます。
その後、エストリビージョ(締めくくり)に入りますが、ここはファンダンゴでいうと最後のG→F→Eの部分をめちゃめちゃ引き延ばして歌っている感じですね。
このように、ファンダンゴをベースとしながらも、ファンダンゴ・デ・ウエルバ等→ファンダンゴ・ナトゥラル→タランタ→タラントと変遷する過程で、原型をとどめないような大きな変化が発生している事がご理解いただけるでしょうか。
タラントの歌のコード進行
以下に、最も一般的なタラントの踊り歌のコード進行を書きますが、サイズは不定形なので、大まかなフレーズごとの進行だけ書いていきます。書式は次の通り。
- ()内のコードは省略される可能性がある
- キーはポルタラント(F♯スパニッシュ調)で記載
- F♯7のコードは原則としてF♯7(♭9,11)で演奏
前フリ
D7 G
コンテスタシオン
D
Aメロ1
(D7) E7 A
D7 G
コンテスタシオン
D
Aメロ2
E7 A
D7 G
レマーテ
D7
エストリビージョ
G G
G (A)
G F♯7
ディグリー(度数)表記版
前フリ
♭Ⅵ7 ♭Ⅱ
コンテスタシオン
♭Ⅵ
Aメロ1
(♭Ⅵ7) ♭Ⅶ7 ♭Ⅲ
♭Ⅵ7 ♭Ⅱ
コンテスタシオン
♭Ⅵ
Aメロ2
♭Ⅶ7
♭Ⅲ ♭Ⅵ7 ♭Ⅱ
レマーテ
♭Ⅵ7
エストリビージョ
♭Ⅱ ♭Ⅱ
♭Ⅱ (♭Ⅲ)
♭Ⅱ Ⅰ7
タラント形式内で歌われるレバンテ系の歌
タラントの歌は、原則的にはタランタがベースになったものですが、タランタ以外のカンテ・レバンテを2拍子化したものがタラント形式の曲中で歌われる場合もあります。
その中で最も良く歌われるのがミネーラのF♯7→Bmからの5度進行メロディーで、踊り歌として頻出するので、おぼえておいたほうが良いでしょう。
タラント内で出てくるミネーラの進行
書式は上のタランタベースの歌と同様です。
前フリ
D7 G
コンテスタシオン
D
Aメロ1
F♯7 Bm E7 A
D7 G
コンテスタシオン
D
Aメロ2
F♯7 Bm E7 A
D7 G
※この後のレマーテからエストリビージョの展開は普通のタラントと同じ
ディグリー表記版
前フリ
♭Ⅵ7 ♭Ⅱ
コンテスタシオン
♭Ⅵ
Aメロ1
Ⅰ7 Ⅳm ♭Ⅶ7 ♭Ⅲ
♭Ⅵ7 ♭Ⅱ
コンテスタシオン
♭Ⅵ
Aメロ2
Ⅰ7 Ⅳm ♭Ⅶ7 ♭Ⅲ
♭Ⅵ7 ♭Ⅱ
※この後のレマーテからエストリビージョの展開は普通のタラントと同じ
後歌のタンゴについて
タラントに限ったことではありませんが、踊りやカンテソロの最後に付けるタンゴやブレリアの歌は、形式毎に決まったネタがあったり、好んで歌われる歌がだいたい決まっていたりするので、それをおぼえておく事で伴奏が楽になります。
タラントの場合は、後歌にタンゴ・デ・グラナダが好んで歌われる傾向がありますが、恐らく音域や雰囲気がマッチするためでしょう。
後歌のコンパスについては、完全にタンゴのノリになります。タンゴのコンパスについてはこちらの記事をご覧下さい。
――次回は2拍子系の仕上げとして、タンゴ系・北部起源系以外の「その他の2拍子系」をやろうと思います。
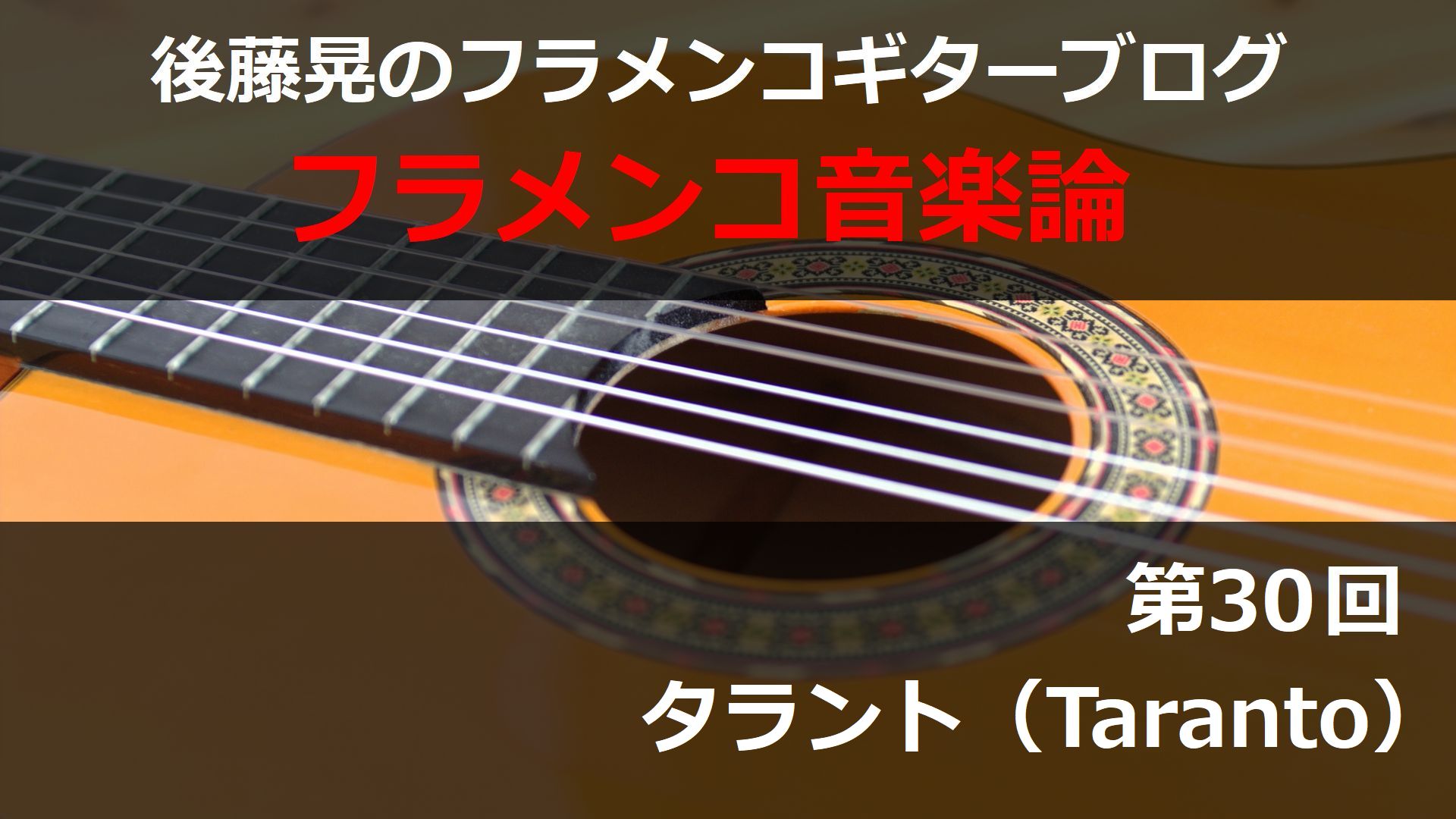

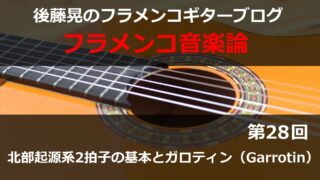
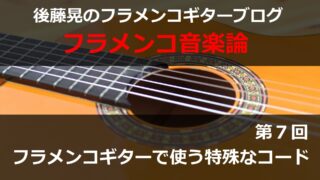
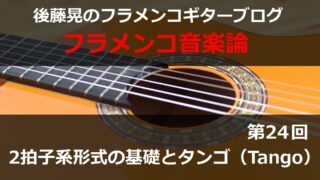
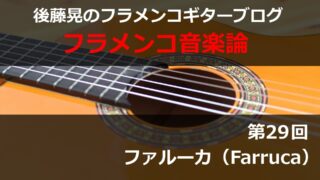
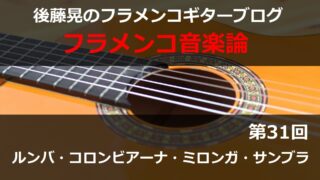
コメント