フラメンコ音楽論では前回、ファンダンゴの発展形として、リブレ(自由リズム)のファンダンゴ系形式について解説しました。
今回は、自由リズムのファンダンゴの中でも、他の歌と異なる雰囲気を持つカンテ・レバンテ(Cante Levante=東方の歌)と呼ばれる形式群をご紹介します。
カンテ・レバンテは、アンダルシア東部のアルメリアや、隣接地域のムルシア、カルタヘナといった地方で発展してきた独特の節回しを持つファンダンゴ系の歌です。
カンテ・レバンテの概要
カンテ・レバンテに属する形式には、タランタ、ミネーラ、カルタヘネーラ、ムルシアーナなどかありますが、どの形式も雰囲気が似通っていて、専門家でも形式の分類が難しいことがあります。
カンテ・レバンテのルーツの一つはファンダンゴですが、もう一つのルーツとしてアンダルシア東部地方やムルシア地方で歌い継がれてきた土着の民謡があり、これらがミックスされたものという説が有力です。
カンテ・レバンテの形式群は「ラ・ウニオンのコンクール」などを通じて、ファンダンゴ系リブレ形式のカンテとして確立してきましたが、アンダルシア東部及びムルシアの土着民謡のカラーが強く出た結果、他のファンダンゴ系の歌とは違った節回しになっているものと推測されます。
カンテ・レバンテの調性
カンテ・レバンテ系の形式は、一般的にF♯スパニッシュ調(ポルタラント)で伴奏が付けられます。
ちなみに、昔はカンテ・レバンテも他のファンダンゴと同じくポルアリーバ(Eスパニッシュ調)で伴奏されていたようですが、レバンテ系カンテの複雑でほの暗い節回しにマッチする響きを追及した結果として、2フレットずらしたF♯スパニッシュ調が編み出されたものと思われます。
ギターのルートコードは解放弦を絡めたF♯7(♭9,11)というのが「基本型」ですが、世界的に見ても、こんなテンションコードがルートコードになってる音楽は類を見ません。
このキーの場合、カポタストの位置は、女性歌手なら4カポから5カポ(実音B♭スパニッシュ調からCスパニッシュ調)、男性歌手ならカポ無しから1カポ(実音F♯スパニッシュ調からGスパニッシュ調)くらいになります。
以下、個別形式を紹介していきましょう。
タランタ(Taranta)
単数形:Taranta
複数形:Tarantas
主な調性:ポルタラント(F♯スパニッシュ調)
テンポ:自由リズム
タランタはアルメリア発祥の歌で、2拍子系の踊りの形式としてメジャーなタラントの元ネタです。
カンテ・レバンテの中では最も演奏頻度が高く、ギターソロとしても好んで演奏されます。
タランタのコード進行
以下に、タランタの代表的な歌のコード進行を図示します。書式は次の通り。
- ()内のコードは省略される可能性がある
- キーはポルタラント(F♯スパニッシュ調)で記載
- F♯7のコードは原則としてF♯7(♭9,11)で演奏
- 1行がファンダンゴ・デ・ウエルバの1コンパスに相当
- サリーダの部分は省略
- ※マークは合いの手。タラントのコンテスタシオンに相当
- 合いの手に関しては、書いていない段も歌の間の取り方などによっては入れていく
D7→G→D→※
(D7→)E7→A
D7→G→D→※
(D7→)E7→A
D7→G
D7→G→F♯7
ディグリー(度数)表記版
♭Ⅵ7→♭Ⅱ→♭Ⅵ→※
(♭Ⅵ7→)♭Ⅶ7→♭Ⅲ
♭Ⅵ7→♭Ⅱ→♭Ⅵ→※
(♭Ⅵ7→)♭Ⅶ7→♭Ⅲ
♭Ⅵ7→♭Ⅱ
♭Ⅵ7→♭Ⅱ→Ⅰ7
普通のファンダンゴとの比較
上に書いたタランタのコード進行が2拍子のタラントを含むカンテ・レバンテ系の歌伴奏の基本となりますが、これをファンダンゴの一種だと言われてもピンと来ない人が多いのではないでしょうか?
そこで、上に書いたタランタの進行を、ノーマルなファンダンゴからの変化がわかりやすいようにポルアリーバに移調して、スタンダードな6コンパスのファンダンゴの展開に対応させてみましょう。
ノーマルなファンダンゴ
①G7→C
②C7→F
③G7→C
④C→G7
⑤G7→C
⑥C7→F→E
ポルアリーバ移調版タランタ
①C7→F→C
②C7→D7→G7
③C7→F→C
④C7→D7→G7
⑤C7→F
⑥C7→F→E
こうしてみると、ベースがファンダンゴであることは分かると思うのですが、所々コードが入れ替わったりしています。
そして、タランタの歌は、全ての段落がD7→Gで始まるのが特徴です。
これはミの旋法のディグリーで言うと♭Ⅵ→♭Ⅱなのですが、一般のファンダンゴは♭Ⅲ→♭Ⅵで始まることが多ので、出だしからして既に違いますよね。
その後も、普通のファンダンゴは♭Ⅲと♭Ⅵ中心のメジャーキーぽい動きですが、レバンテ系は♭Ⅵ→♭Ⅱの動きが中心になります。
全体に♭Ⅲコード(ポルタラントだとDメジャーコード、ポルアリーバのCメジャーコードに相当)に解決する動きが少なく、唯一、♭Ⅲに行く所も、合いの手(コンテスタシオン)になっていて歌わない、というのが普通のファンダンゴと決定的に違うところです。
このあたりが、他のファンダンゴ系の歌と異なり、暗くて渋い雰囲気になっている最大要因でしょう。
ミネーラ(Minera)
単数形:Minera
複数形:Mineras
主な調性(歌):ポルタラント(F♯スパニッシュ調)
主な調性(ギターソロ):ポルタラント(F♯スパニッシュ調)、G♯スパニッシュ調、C♯スパニッシュ調
テンポ:自由リズム
ミネーラはタランタの近縁の歌ですが、その出自はよく分かっていません。
ちなみにスペイン語でMineraは「鉱山」ですので、鉱山の歌=炭鉱節的なものでしょうね。
ミネーラとされる歌は、タランタにそっくりなものも多く、タランタなのか?ミネーラなのか?の分類については諸説ありますが、実運用上は、いくつかの特定の歌をミネーラと呼ぶ他、分類不明なカンテ・レバンテを悠意的にミネーラと呼んでいるように思います。
ミネーラとされる歌で有名なものに、踊りのタラント(2拍子のほう)でもよく歌われる「F♯→Bm→E7→A」という5度進行で始まる歌がありますが、この歌も後半は普通のタランタ・タラントと同様の展開です。
カルタヘネーラ(Cartagenera)
単数形:Cartagenera
複数形:Cartageneras
主な調性:ポルタラント(F♯スパニッシュ調)
テンポ:自由リズム
カルタヘネーラは、カルタヘナ(アンダルシア州の東隣、ムルシア州にある町)の民謡とファンダンゴがミックスされて成立したとされている形式です。
元ネタの民謡は短調のシンプルな歌ですが、カンテフラメンコとしてはアントニオ・チャコン(Antonio Chacon)が歌ったスタイルが有名で、現在、カルタヘネーラの形式名で歌われるものはチャコンのスタイルがベースになっています。
カルタヘネーラの特徴
カルタヘネーラの代表的な歌のコード進行を少し解説しましょう。
カルタヘネーラもタランタと雰囲気がよく似ていますが、歌の前半部分に特徴があって「F♯→BmでBマイナーキー寄りで始まって、次の節でいきなりDメジャーコードに行く」という動きをします。
カンテ・レバンテ系は、D(♭Ⅵ)のコードはD7(♭Ⅵ7)として、Gへのセカンダリードミナントとして使ったり、コンテスタシオンとして歌わなかったりしますが、カルタヘネーラの場合、はっきりと♭Ⅵ=Dメジャーコードへのメロディ解決がみられます。
なんというか、そこだけ唐突に明るい旋律になるのですが、他のカンテ・レバンテよりはノーマルなファンダンゴに近い雰囲気になりますよね。
ムルシアーナ(Murciana)
単数形:Murciana
複数形:Murcianas
主な調性:ポルタラント(F♯スパニッシュ調)
テンポ:自由リズム
ムルシアーナは、アンダルシアの隣接州であるムルシア地方発祥のカンテ・レバンテです。
この形式については、あまり伴奏経験も無いので詳述は出来ないのですが、様々な音源を聴くかぎり、以下の3タイプの歌があるものと認識しています。
- ファンダンゴ・ナトゥラルに近いもの
- タランタやミネーラに近いもの
- D7→Gの2コードで進行した後、そのままF♯に落ちるもの
カンテ・レバンテ系のギターソロ
レバンテ系のリブレ形式はギターソロとしても良く演奏されますが、歌が無いギターソロの曲には、どうやって形式名を付けているのでしょうか?
これについては、ハッキリとしたことはお答え出来ないのですが、自分なりの考えを述べておきます。
まず、F♯スパニッシュ調のリブレ系ギターソロは、ほとんどが「タランタ」として演奏されている印象ですが、C♯やG♯スパニッシュ調の場合は、他と差別化するために「ミネーラ」という形式名を付けるケースが多いように思われます。
このように、レバンテ系のギターソロは調性や演奏スタイル(ラモン・モントージャがギターソロでやっていたミネーラなど)によって形式名(ほとんどがタランタかミネーラ)が付いているというのが実態なのではないでしょうか。
――今回でファンダンゴを主体とした3拍子とリブレ形式の解説は終了で、次回からは2拍子系の形式に移っていきたいと思います。

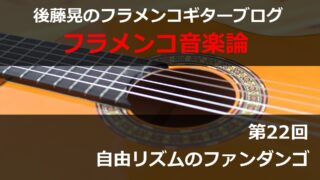
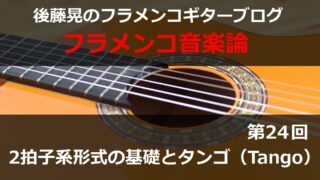
コメント