フラメンコ音楽論では、前回までにフラメンコの3拍子形式としてファンダンゴ・デ・ウエルバとセビジャーナスに使用されている「ウエルバ系」のコンパスを学習しましたが、ファンダンゴ系にはもう一つ代表的なリズムパターンがあります。
それが、今回取り上げるアバンドラオと呼ばれるものです。
ファンダンゴ・アバンドラオの概要
単数形:Fandango Abandolao(このカテゴリーの総称。形式名は個別に付く)
複数形:Fandangos Abandolaos(カテゴリーの総称。形式名は個別に付く)
主な調性:ポルアリーバ(Eスパニッシュ調)
テンポ:85BPMから130BPM
ウエルバ系のファンダンゴがアンダルシア西部で発展したのに対して、アバンドラオ系のファンダンゴは、マラガ、ロンダ、コルドバ、グラナダなどのアンダルシア中部・東部地域で発展してきました。
具体的な形式としてはベルディアーレス(マラガ)やロンデーニャ(ロンダ)などがありますが、アバンドラオのコンパスで演奏されるファンダンゴ曲種を総称して「ファンダンゴ・アバンドラオ」と呼びます。
アバンドラオのリズムの特徴
ファンダンゴ・アバンドラオのリズムパターンは、ファンダンゴ・デ・ウエルバを遅回し(テンポは85BPMから130BPMくらい)でやったような感じですが、3拍子のサイクルをストレートに出すことが多いので、ファンダンゴ・デ・ウエルバやブレリアより分かりやすいビートだと思います。
ギターは勇壮に掻き鳴らすスタイルで演奏されるため、フラメンコの「情熱」というイメージにマッチするのか、日本でフラメンコというと、このリズムがイメージされる場合も多いです。3拍子の「じゃんじゃか、じゃんじゃか、じゃんじゃん」ていうやつですね。
アバンドラオの拍のとりかた
ファンダンゴ・アバンドラオは12拍で1コンパスなのですが、リズムパターンとしては6拍単位(メディオコンパス)で出来ていて、普通に頭にアクセントがついた3拍子でとれます。
① 2 3 ④ 5 6
フレージングやコードの変わり目も、原則的に3拍単位になっているのでウエルバ系より分かりやすいと思いますが、アバンドラオの場合、倍速のブレリアのコンパスによって置き換えられる事もあるので、それは頭に入れておいたほうが良いでしょう。
ブレリアとの関係性
アバンドラオは倍速のブレリアのリズムがミックスされたようなリズムパターンで演奏されることがあります。
例えば、100BPMのアバンドラオなら200BPMのブレリアの語彙を入れていく感じです。
ソレアでも、ゆっくりテンポのサパテアードやファルセータに倍タイムのブレリアの語彙が入ったりするし、ティエントやタラントだと倍タイムのタンゴの語彙が入ってきたりしますよね。
フラメンコでは、こうやって他の形式の語彙を混ぜてリズムを細分化・複雑化させる手法をとることが多いのですが、こういうものが入ってくるとリズムカウントは混乱しそうです。
アバンドラオとブレリアのコンパスカウントを対応表にすると以下のような感じになります。
アバンドラオ6拍がブレリアの12拍に相当。○が付いた数字がアクセント拍です。
アバンドラオ
① ○ 2 ○ 3 ○ ④ ○ 5 ○ 6 ○
ブレリア
⑫ 1 ② 3 ④ 5 ⑥ 7 ⑧ 9 ⑩ 11
このように、アバンドラオに対して倍速のブレリアを当てる場合、主に2拍×3のブレリアのパターンが使われます。
ブレリアのコンパスパターンについては、こちらの記事をご覧下さい。
ファンダンゴ・アバンドラオのマルカールパターン
ファンダンゴ・アバンドラオの代表的なマルカールパターンは以下のようなものです。1行で1コンパス(12拍)の3拍子、○はコードチェンジ無しの拍、キーはポルアリーバ(Eスパニッシュ調)で記載します。
|E ○ ○|F ○ ○|G G♭ F|E ○ ○|
これはファンダンゴ・デ・ウエルバのマルカールをゆっくり演奏したものと考えられますが、コードの変わり目はウエルバ系のような3拍目・9拍目ではなく、4拍目・10拍目(3拍子の頭拍)となるのがポイントです。
間奏部分の他、歌の締めくくりでもこのパターンが弾かれます。
ファンダンゴ・アバンドラオの歌
ファンダンゴ・アバンドラオに属する形式は色々ありますが、歌のコード進行はほぼ共通です。
原則的にファンダンゴ・デ・ウエルバでやったCメジャーキー基調の6コンパスのものが基本になりますが、歌の種類や歌いかたによってサイズは伸縮します。
アバンドラオ系の歌は3拍単位で伸縮
ファンダンゴ・アバンドラオの歌は歌い手の裁量による伸縮が多いのですが、上で書いたカウント方法で数えた場合「3拍単位で伸縮」します。
このテンポでは6拍単位だと長すぎて歌の自由度が落ちてしまうためだと思われますが、先ほど解説した通り、アバンドラオの3拍は倍速のブレリアカウントだと6拍に相当しますので、実際の演奏ではメディオコンパス=3拍という感覚で違和感ありません。
歌のコード進行
以下に、ファンダンゴ・アバンドラオの基本的な進行例をご紹介しますが、実際の演奏サイズは伸縮が激しいので、大まかな展開だけ書いておきます。書式は次の通り。
- ()内のコードは省略されることもある
- 複数のコードの可能性があるところは「,」で区切る
- 1小節に複数のコードが入るところは「/」で区切る
- キーはポルアリーバ(Eスパニッシュ調)で記載
- 1行がファンダンゴ・デ・ウエルバの1コンパスに相当
(G7→)C
C→F,G7
G7→C
C→G7
G7→C
C7→F→G/G♭/F→E
ディグリー(度数)表記版
(♭Ⅲ7→)♭Ⅵ
♭Ⅵ→♭Ⅱ,♭Ⅲ7
♭Ⅲ7→♭Ⅵ
♭Ⅵ→♭Ⅲ7
♭Ⅲ7→♭Ⅵ
♭Ⅵ7→♭Ⅱ→♭Ⅲ/Ⅱ/♭Ⅱ→Ⅰ
アバンドラオで演奏される主な形式
ここからは、ファンダンゴ・アバンドラオとして演奏される代表的な形式をご紹介します。
ロンデーニャ(Rondeña)
ロンデーニャはロンダのファンダンゴがフラメンコ形式化したものですが、以下の2種類の演奏形態があります。
- アバンドラオで伴奏される歌
元々はこちらの形態。主にポルアリーバで演奏されます - リブレのギターソロ
ラモン・モントージャが創作したリブレ(自由リズム)のスタイルで、変則調弦(6弦をD、3弦をF♯に下げる)が特徴。次回、リブレ系ファンダンゴの解説でもう少し詳しくやります
ベルディアーレス(Verdiales)
ベルディアーレスはマラガのファンダンゴ系民謡がフラメンコ化したもので、フラメンコでは主にマラゲーニャの後歌として歌われ、ポルアリーバで演奏されます。
本場のマラガでは、現在でも民謡としてのベルディアーレスが盛んに演奏されていますが、本来のベルディアーレスはバイオリン・太鼓・カスタネットが入ったりする素朴でフォークミュージック色が強いものです。
ハベーラスとハベゴーテス(Jaberas,Jabegotes)
ハベーラスとハベゴーテスもマラガのファンダンゴがフラメンコ化したもので、アバンドラオのコンパスで演奏されます。
ハベーラスは豆売りの、ハベゴーテスは漁師の仕事歌が起源と言われています。
バンドラス(Bandolas)とファンダンゴ・デ・ルセーナ(Fandango de Lucena)
バンドラスは直訳で「山賊の歌」なのですが、マラガ山間部からコルドバあたりで歌われていたファンダンゴがフラメンコ化したものです。
他にコルドバ周辺のファンダンゴが元ネタになったものとしては、ファンダンゴ・デ・ルセーナがありますが、どちらの歌もアバンドラオのコンパスで演奏されます。
ファンダンゴ・デ・グラナダ(Fandango de Granada)
ファンダンゴ・デ・グラナダは、アバンドラオのコンパスで演奏されるグラナダの伝統的なファンダンゴで、カスタネットを使ったセビジャーナスに似た踊りが入ります。
ちなみに、同じグラナダのファンダンゴ系形式であるグラナイーナはアントニオ・チャコンが創唱したリブレ形式ですが、ファンダンゴ・デ・グラナダは土着民謡のカラーが強く、グラナイーナのように高度にフラメンコ化されているわけではありません。
その他のアバンドラオ系形式
これ以外でも、ファンダンゴ系の歌はアバンドラオのコンパスで演奏されることがありますが、原則的には、歌い回しの速いファンダンゴはウエルバ系、歌い回しがゆっくりのファンダンゴはアバンドラオ系で演奏されます。
ただし、ウエルバ系とアバンドラオ系の中間的なコンパスもあったりして、厳密に分けられるものでもありません。
また、ファンダンゴ系以外でも、12拍子の民謡系形式などは3拍子化(というか、元々は3拍子だった)してアバンドラオで演奏することもあるのですが、その場合は元の歌の種別で形式名が付くことになります。
――次回からはファンダンゴ系形式の発展形として、リブレ(自由リズム)形式の考察をしたいと思います。
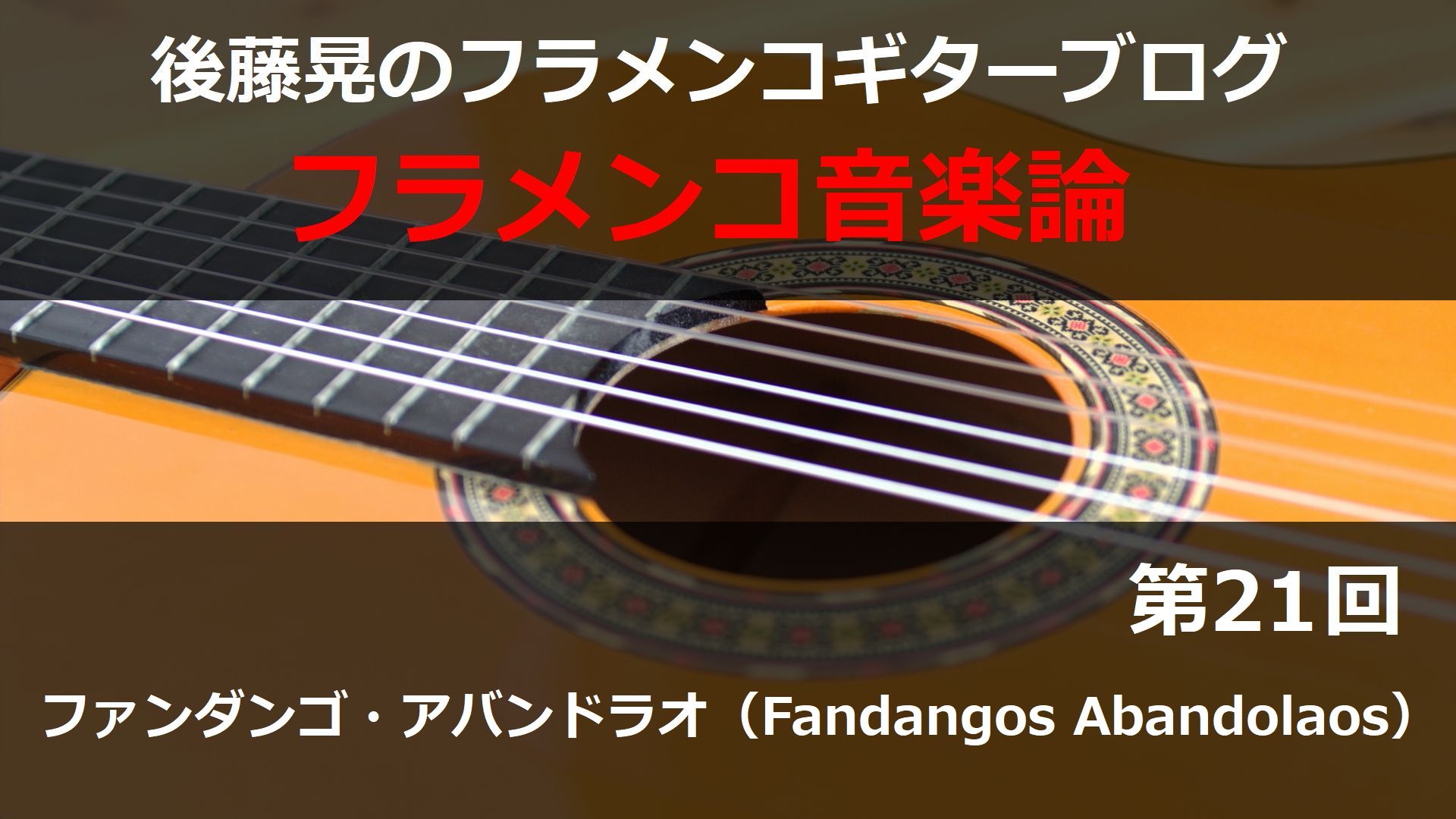
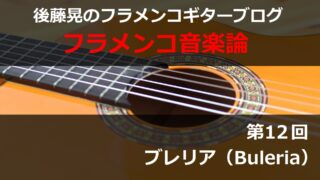
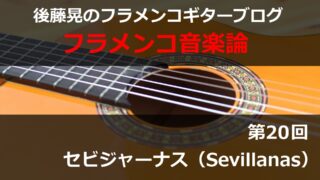
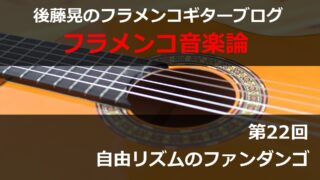
コメント