約4か月ぶりの連載再開になりますが、フラメンコ音楽論は今回から新展開です。
ここで今までのフラメンコ音楽論の内容を整理してみましょう。
- 第1回から第3回 基礎知識
- 第4回から第7回 コードとスケール
- 第8回から第31回 リズム形式
- 第32回から第38回 フラメンコ音楽現代史
今までこんな内容をやってきましたが、基礎的な知識が中心で、半分以上はリズム形式の解説に費やしています。
当初、この連載は他のサイトには無い実践的なものにしようと思い、第4回から第7回にかけてコードとスケールの事を書きましたが、次のリズム(=コンパス)を解説しようという段階で「ああ、これは時間をかけて形式説明から始めないと、無理だろうな」と感じました。
そこで一旦、実践的な内容は置いておいて、まずはリズム形式等の基礎知識を集中的にやることにしました。
結局、基礎知識の解説に1年以上を費やしましたが、今までの講座を一通り理解できたなら、フラメンコの音楽を演奏するための基礎的な知識としては十分ではないでしょうか。
これからまた実践的な内容をやってくことにしますが、第4回から第7回のコード・スケール編に続く「フラメンコ音楽論=実践編」第2弾として、フラメンコを演奏する上で最も重要かつ難しいものである「コンパス(フラメンコのリズム)の習得」というテーマを数回に分けてやろうと思います。
コンパス=サイクル理論
形式解説で沢山の形式をやりましたが、コンパスの種別も沢山あるし、カウント方法なども複雑でとても難解な印象を受けるのではないでしょうか?
ですが、実際の演奏でそんなに難しい事を常時考えていたら、刻々と変化する状況についていけません。
では、フラメンコ奏者の頭の中はどうなっているのか?というと、コンパスを一定の法則に従って単純化して捉えていると思うんですよね。
これを言語化・理論化したものが、これから解説する「コンパス=サイクル理論」です。
「コンパス=サイクル理論」は自分が考案したもので、他の人はまた違う捉え方をしていそうですが、自分自身がコンパスに悩みながら、長い時間かけて作り上げてきたもので、フラメンコの学習・演奏の大きなヒントになるのでは?と思い、このブログ上で記事にしてみることにしました。
「コンパス=サイクル理論」では、フラメンコの演奏で感じるリズムサイクルを、4拍サイクルと6拍サイクルの2種類にまで単純化しています。
ただし、シギリージャ系のコンパスだけは少し特殊です。
シギリージャ系も6サイクルでとることもありますが、コンパスの頭やフレーズの解決拍などがわかりにくい場合があるので、これだけは別枠にしました。
ですので、それを入れるとサイクルの種別は「4拍」「6拍」「シギリージャ」の3種類となり、以下「4サイクル」「6サイクル」「シギリージャサイクル」と呼ぶことにします。
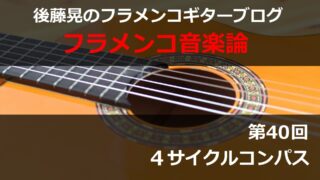
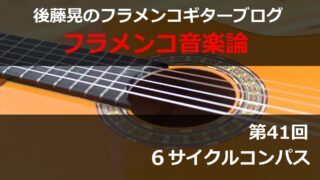
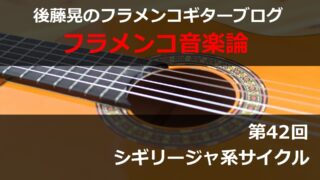
4サイクルは2拍子系形式に、6サイクルは12拍子系形式(変拍子系含む)と3拍子系形式に、シギリージャサイクルはシギリージャ系の形式に適用されます。
振りを覚えたばかりの踊り手さんは「12、1、2」とかカウントしたりするんですが、ギタリストや歌い手は声でカウントせず(出来ない)、足などでリズムをとって、この「4サイクル」「6サイクル」「シギリージャサイクル」を頼りに演奏します。
こうしてコンパスをブロック化することで、細かくカウントしなくても4拍や6拍のタイム感を基に、直感的な演奏ができるようになります。
このコンパスのブロック化の具体的手法を体系的にまとめたのが「コンパス=サイクル理論」というわけです。
フラメンコで使われるテンポ
フラメンコの実際の演奏ですが、大体やりやすいテンポ(BPM)が決まっています。
この講座では以下の5段階に分けて解説します。
超スローテンポ
65BPMから90BPM
踊りのソレア、踊りのタラントなど
スローテンポ
90BPMから120BPM
歌のソレア、歌のティエントなど
ミドルテンポ
140BPMから180BPM
ソレポル、カンティーニャ系、タンゴなど
ハイテンポ
180BPMから250BPM
ブレリア、ルンバなど
超ハイテンポ
250BPM以上
踊りの追い上げ、マチョなど
ちなみにですが「超スローテンポとミドルテンポ」「スローテンポとハイテンポ」などは、それぞれ半速・倍速の関係にあるので一定の互換性があります。
ギターなら右手の弾き方は大体同じで、左手のコードやフレーズの変化サイクルを変えてやることで半速・倍速のコンパスに対応出来たりします。
そういうことも考慮すると、テンポ的なバリエーションはそんなに無いです。
フラメンコのフレーズやリズムパターンは演奏しやすいテンポが大体決まっているため、踊りや歌も含めて全員が気持ちいいテンポ感・コンパス感で演奏すると、自ずとテンポ幅は限定されてくるわけです。
15パターンのリズムサイクル
コンパス=サイクル理論では、サイクル種別(3種)とテンポ帯(5種)によって、リズムサイクルは以下の15パターンに分けています。
- 超スローテンポの4サイクル
- スローテンポの4サイクル
- ミドルテンポの4サイクル
- ハイテンポの4サイクル
- 超ハイテンポの4サイクル
- 超スローテンポの6サイクル
- スローテンポの6サイクル
- ミドルテンポの6サイクル
- ハイテンポの6サイクル
- 超ハイテンポの6サイクル
- 超スローテンポのシギリージャサイクル
- スローテンポのシギリージャサイクル
- ミドルテンポのシギリージャサイクル
- ハイテンポのシギリージャサイクル
- 超ハイテンポのシギリージャサイクル
シギリージャ系は演奏してみるとわかりますが、12.のスローテンポ(90BPMから130BPM)でも相当ゆっくりなので、11.の超スローテンポ(65BPMから90BPM)はほとんど使われません。
弱起のリズム
個別解説に入る前に、全パターンに共通の傾向に触れておきたいです。
フラメンコのリズムは、サイクルの頭の音は強く出さない弱起の感覚があります。
通常のマルカールのときなどは、ブレリアの12拍目やタンゴの1拍目などの、サイクルの頭の音はあまり強く出さないことが多いですよね。
フラメンコに限らず、ラテン音楽全般の傾向ではありますが、ロックやクラブミュージックのようにサイクルの頭にベースドラムが入って強調されるのとは逆の感覚ですね。
サイクルの頭拍はしっかり感じつつも、音としてはあまり強く出さないことが多い、という感じです。
特に我々日本人はリズムサイクルの頭をとろうとして、サイクルの頭を強く演奏しがちですが、これだとニュアンスが全然違ってきてしまうので、この点は注意してください。
もちろん、場合によっては意図的にサイクルの頭を強く出すパターンもありますが「弱起になることが多い」ということは覚えておいてください。
次回からは今回の内容を踏まえて、サイクル種別ごとの個別解説をしていきます!

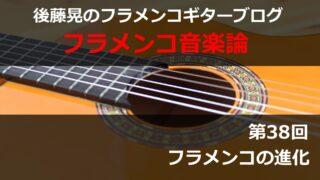
コメント