前回は民謡系の12拍子形式として、カーニャをとりあげましたが、今回は同じく民謡系12拍子のバンベーラです。
バンベーラは現在でも踊りの形式として、そこそこの演奏頻度があります。
バンベーラ形式概要
単数形:Bambera,Bamba
複数形:Bamberas
主な調性:ポルアリーバ(Eスパニッシュ調)とAマイナーキーの複合調
テンポ:130BPMから170BPM
バンベーラはバンバとも呼ばれます。
その昔、アンダルシア地方の村祭りでブランコに乗って歌を歌うという風習があったらしいのですが、その歌がバンベーラの起源と言われていて、歌詞にもブランコが出てきますよね。
フラメンコ形式としては、カンテ発展期の歌い手、ニーニャ・デ・ロス・ペイネス(La Niña de los Peines)がレパートリーに取り入れたのが最初と言われています。
他の民謡系の12拍子形式と同様に、初期はファンダンゴ系のリズムでも演奏されていたようですが、現在はソレア・ポル・ブレリアのコンパスで演奏されるのが主流です。
バンベーラの調性とギタープレイ
バンベーラの調性はポルアリーバとAマイナーの複合調(後述)で、カポタストの位置はソレアより少し低めに設定される場合が多く、女性歌手で6カポ(実音B♭スパニッシュ)、男性歌手なら3カポ(実音Gスパニッシュ)くらいが中心です。
ギターのマルカールは、ほぼポルアリーバのソレポルなんですが、バンベーラで特徴的なのは「1、2、3拍目をAm、G、Fと弾いて強調する」という頻度がソレポルより高め、という事です。
バンベーラの歌
バンベーラの歌はポルアリーバが基本ですが、最後がAmコードで終わります。
これって、歌だけ聴くとAマイナーキーなんでは?と思うんですが、他のセクションはソレアと同様のポルアリーバのパターンだし、ギターのマルカールもF→Eの動きが主体です。
ですので、歌の最後だけAマイナーに行く、「ポルアリーバ・Aマイナー複合調」と捉えるべきかと。
ちなみに、ファルセータに関しては、ポルアリーバとAマイナーキー、どちらのものでもマッチします。
バンベーラの歌のコード進行
バンベーラの歌のうち、最も一般的なもののコード進行をご紹介します。書式は以下の通り。
- 12拍子の1拍目を頭にした3拍子で記載
- 1行でメディオコンパス(6拍)
- ○はコードチェンジ無しの拍
- ()内のコードは省略されることもある
- 複数のコードの可能性があるところは「,」で区切る
- キーはポルアリーバ(Eスパニッシュ調)で記載
- コードは原則として3和音で記載
- コンテスタシオン(合いの手)は歌が休みになる部分で、普通は0コンパス(コンテスタシオン無し)から2コンパス
- ※マークが付いている行は省略されることもある
- 半コンパス単位でサイズが変わる事がある
|E ○ ○|○ ○ ○|
|○ ○ ○|○ ○ ○|
|○ ○ F|○ ○ ○|
|○ ○ ○|E ○ ○|
|○ ○ F|○ ○ ○|
|○ ○ ○|E ○ ○|
コンテスタシオン
|Am ○ ○|○ ○ ○|
|(F) ○ ○|E ○ ○|
|○ ○ F,G|○ ○ ○|
|○ ○ ○|E,C ○ ○|
|E ○ ○|○ ○ ○|※
|○ ○ ○|○ ○ ○|※
|E ○ ○|○ ○ ○|
|○ ○ ○|Am ○ ○|
ディグリー(度数)表記版
|Ⅰ ○ ○|○ ○ ○|
|○ ○ ○|○ ○ ○|
|Ⅰ ○ ♭Ⅱ|○ ○ ○|
|○ ○ ○|Ⅰ ○ ○|
|Ⅰ ○ ♭Ⅱ|○ ○ ○|
|○ ○ ○|Ⅰ ○ ○|
コンテスタシオン
|Ⅳm ○ ○|○ ○ ○|
|(♭Ⅱ) ○ ○|Ⅰ ○ ○|
|○ ○ ♭Ⅱ,♭Ⅲ|○ ○ ○|
|○ ○ ○|Ⅰ,♭Ⅵ ○ ○|
|Ⅰ ○ ○|○ ○ ○|※
|○ ○ ○|○ ○ ○|※
|Ⅰ ○ ○|○ ○ ○|
|○ ○ ○|Ⅳm ○ ○|
最後のⅣmは平行調マイナーキーのⅠmと捉えることも出来ます。
バンベーラの歌のバリエーション
バンベーラの歌のバリエーションとしては、踊り伴唱でよく歌われるA7→Dm→G7→C(Ⅰ7→Ⅳm→♭Ⅶ7→♭Ⅲ)という5度進行のものがあります。こちらもサイズは伸縮します。
次回は、未解説の12拍子系形式をまとめたいと思います。
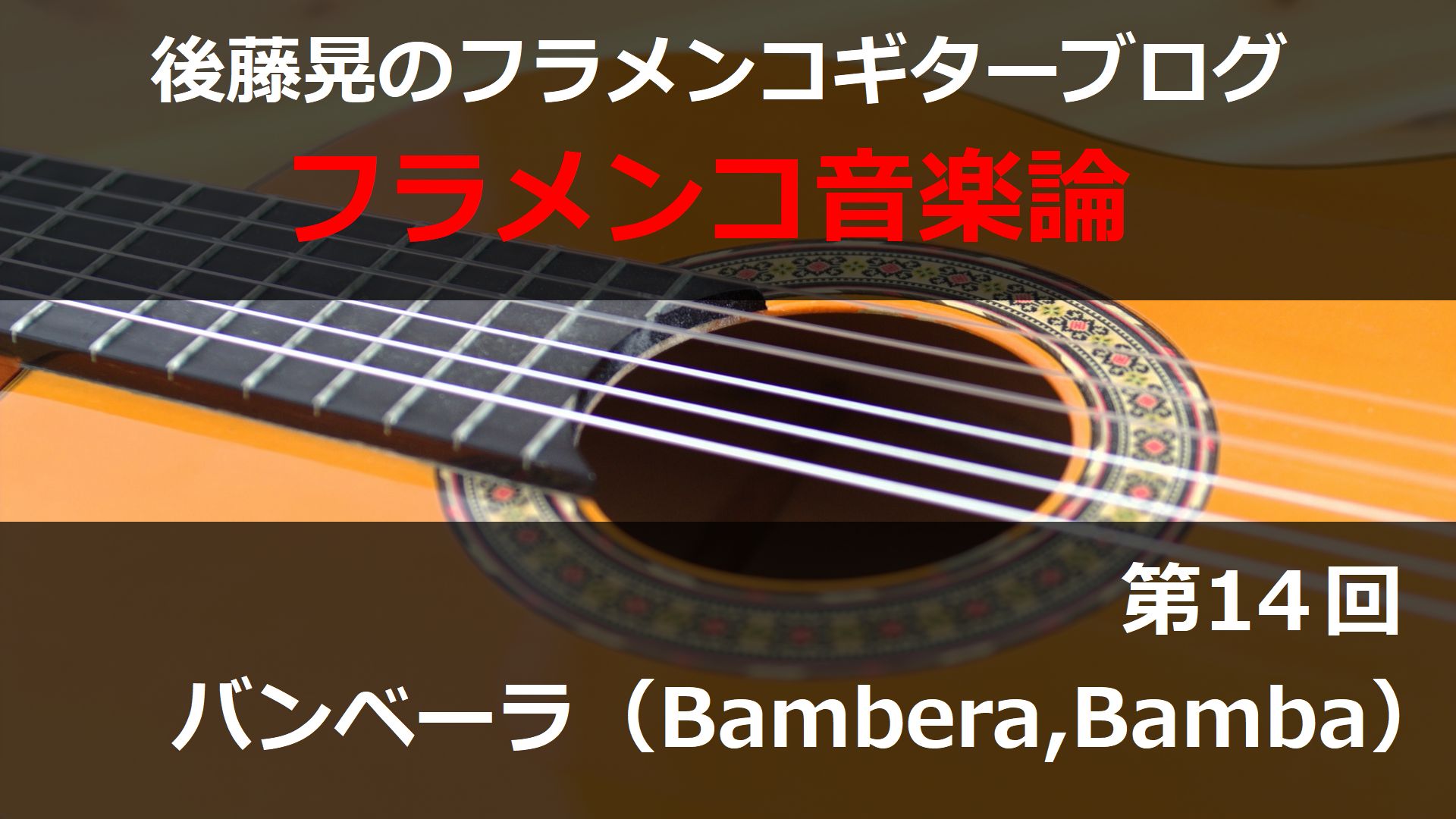
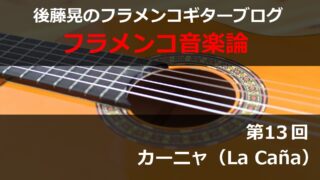
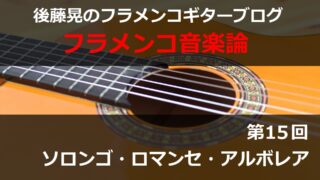
コメント