前回までで12拍子系のメジャー形式を、ほぼ網羅しましたが、今回は12拍子系の補完記事としてソロンゴ、ロマンセ、アルボレアの3つの形式を紹介いたします。
ソロンゴは民謡系の、ロマンセとアルボレアはヒターノ伝承系の起源を持つ歌です。
ソロンゴ(Zorongo)
単数形:Zorongo
複数形:あまり使用されません
主な調性:ポルメディオ(Aスパニッシュ調)、ポルアリーバ(Eスパニッシュ調)
テンポ:130BPMから170BPM(12拍子の場合はソレポルの、2拍子の場合はタンゴのコンパス)
ソロンゴはグラナダの民謡がフラメンコ化したもので、カーニャのラメントと似たリフレインが特徴です。
フラメンコ形式としては、12拍子(3拍子)で演奏される場合と2拍子で演奏される場合があって、12拍子の場合はソレア・ポル・ブレリアかブレリアで、2拍子の場合はタンゴのコンパスで演奏されます。
調性はポルメディオ(Aスパニッシュ調)かポルアリーバ(Eスパニッシュ調)で演奏され、ポルメディオの場合のカポタストの位置は、女性歌手なら4カポ(実音C♯スパニッシュ調)、男性歌手なら1カポ(実音B♭スパニッシュ調)くらいの高さです。
ソロンゴの歌のコード進行
以下に、代表的なソロンゴの歌のコード進行をご紹介します。コード進行表の書式は次の通り。
- 12拍子の12拍目を頭にした3拍子で記載(2拍子で演奏する場合もある)
- 1行でメディオコンパス(6拍)
- ○はコードチェンジ無しの拍
- ()内のコードは省略される場合もある
- 複数のコードの可能性があるところは「,」で区切る
- キーはポルメディオ(Aスパニッシュ調)で記載
- コードは原則として3和音で記載
- ※マークが付いている行は省略されることもある
Aメロ
|A ○ ○|B♭ ○ ○|
|A ○ ○|○ ○ ○|
|A ○ ○|B♭ ○ ○|
|A ○ ○|○ ○ ○|
Bメロ
|C ○ ○|(B♭) ○ ○|
|A,F ○ ○|○ ○ ○|
|C ○ ○|B♭ ○ ○|
|A ○ ○|○ ○ ○|
|C ○ ○|(B♭) ○ ○|※
|A,F ○ ○|○ ○ ○|※
|C ○ ○|B♭ ○ ○|※
|A ○ ○|○ ○ ○|※
リフレイン
|B♭,C ○ ○|B♭ ○ ○|
|A ○ ○|○ ○ ○|
|B♭,C ○ ○|B♭ ○ ○|
|A ○ ○|○ ○ ○|
|C ○ ○|○ ○ ○|
|(F) ○ ○|○ ○ ○|
|C ○ ○|B♭ ○ ○|
|A ○ ○|○ ○ ○|
|C ○ ○|○ ○ ○|※
|(F) ○ ○|○ ○ ○|※
|C ○ ○|B♭ ○ ○|※
|A ○ ○|○ ○ ○|※
ディグリー(度数)表記版
Aメロ
|Ⅰ ○ ○|♭Ⅱ ○ ○|
|Ⅰ ○ ○|○ ○ ○|
|Ⅰ ○ ○|♭Ⅱ ○ ○|
|Ⅰ ○ ○|○ ○ ○|
Bメロ
|♭Ⅲ ○ ○|(♭Ⅱ) ○ ○|
|Ⅰ,♭Ⅵ ○ ○|○ ○ ○|
|♭Ⅲ ○ ○|♭Ⅱ ○ ○|
|Ⅰ ○ ○|○ ○ ○|
|♭Ⅲ ○ ○|(♭Ⅱ) ○ ○|※
|Ⅰ(♭Ⅵ) ○ ○|○ ○ ○|※
|♭Ⅲ ○ ○|♭Ⅱ ○ ○|※
|Ⅰ ○ ○|○ ○ ○|※
リフレイン
|♭Ⅱ,♭Ⅲ ○ ○|♭Ⅱ ○ ○|
|Ⅰ ○ ○|○ ○ ○|
|♭Ⅱ,♭Ⅲ ○ ○|♭Ⅱ ○ ○|
|Ⅰ ○ ○|○ ○ ○|
|♭Ⅲ ○ ○|○ ○ ○|
|(♭Ⅵ) ○ ○|○ ○ ○|
|♭Ⅲ ○ ○|♭Ⅱ ○ ○|
|Ⅰ ○ ○|○ ○ ○|
|♭Ⅲ ○ ○|○ ○ ○|※
|(♭Ⅵ) ○ ○|○ ○ ○|※
|○ ○ ○|♭Ⅱ ○ ○|※
|Ⅰ ○ ○|○ ○ ○|※
大体こんな進行ですが、Bメロの2コンパス目・4コンパス目とリフレインの3コンパス目・5コンパス目は、ソレア風に中落ちにFコードを入れても良いし、A・B♭・Cの3つのコードのみでやっても良いでしょう。
Bメロとリフレインの繰り返し部分はあったり無かったりします。
踊りの場合、リフレインの後半部分はブレイク入りの仕掛けを作ったり、リブレにして演奏することも多いです。
なお、2拍子で演奏する場合も、基本的なコード進行は3拍子のものと同じです。
ロマンセ(Romance)
単数形:Romance
複数形:あまり使用されません
主な調性:ポルアリーバ(Eスパニッシュ調)
テンポ:140BPMから200BPM
ブレリアの解説記事でロマンセについても少し触れましたが、ヒターノの伝承歌にロマンセという語り歌(物語に歌をつけてきかせるもの)があって、それをフラメンコのコンパスに乗せて演奏することがあります。
この形式は、固有の歌やコンパスというより、ロマンセの歌詞を使っていれば形式名は「ロマンセ」ということになるので、歌を知らないと実体が掴みづらいかもしれませんが、よく演奏される型というのはあるので、ここでもそういうスタンダードな型を扱います。
ロマンセのコンパス
ロマンセのコンパスは、昔はソレアのコンパスに乗せて演奏されていたようですが、現在はソレア・ポル・ブレリアからブレリアの速さが中心です。
踊りの場合、レトラ部分はソレア・ポル・ブレリアのコンパスで演奏されるのが主流ですが、歌単体ならブレリアの速さのものも多いです。
ロマンセのコード進行例
ロマンセの歌の代表的なコード進行例をロマンセの主流であるポルアリーバ(Eスパニッシュ調)で書くと下のようになります。
E→Am→G→F→E(Ⅰ→Ⅳm→♭Ⅲ→♭Ⅱ→Ⅰ)
E→Amから始まる下降進行をベースに、途中で寄り道したり、一旦引き返したりする動きが基本で「Am、Gに何回か行った後にF→Eへと落ちが付く」というパターンが多いです。
アルボレア(Alborea,Alboreas)
単数形:Alborea
複数形:Alboreas
主な調性:ポルアリーバ(Eスパニッシュ調)
テンポ:140BPMから200BPM
アルボレアは、ヒターノの婚礼祝いで歌われていた歌がフラメンコ化したものです。
コンパスはソレア・ポル・ブレリアからブレリアくらいの速さの12拍子で、キーはポルアリーバ(Eスパニッシュ調)が主流です。
演奏頻度はあまり高くなく、自分も実は数回しか伴奏した機会が無い形式ですが、コンパス・メロディー共に、ロマンセとの共通性を感じます。
――「フラメンコ音楽論」では、ここ数回に渡って12拍子系の派生形式をやってきましたが、これらは土着民謡やヒターノ伝承歌がフラメンコに取り込まれる際に3拍子→12拍子に変化したものと考えられます。
つまり、これら12拍子系派生形式のコンパスは後付けされたものであるということですね。
ですので、学習する際も、ソレアやブレリアなどの12拍子系のフラメンコオリジナルな形式をマスターできたのなら、派生形式はその応用で、固有の歌や慣用句をおぼえていく作業となります。
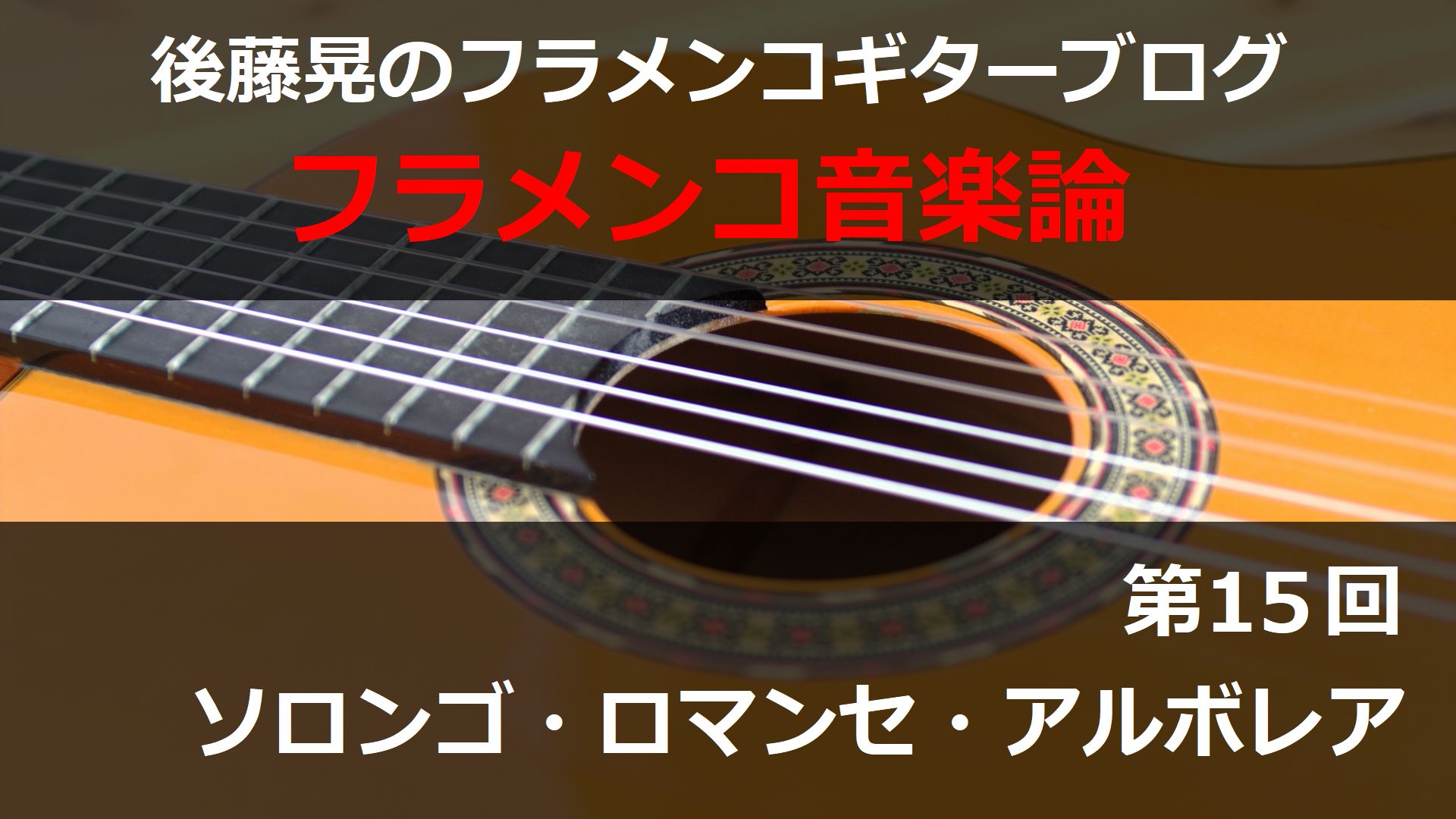
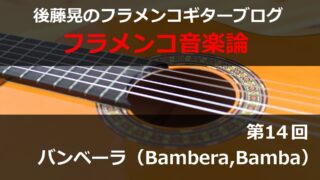
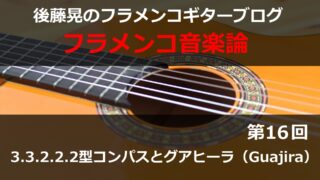
コメント