今、フラメンコ音楽論では変拍子(変則5拍子)系コンパス形式の解説をしていますが、今回は変拍子系形式のラスボス的な存在であるシギリージャと、その関連形式をご紹介いたします。
シギリージャ系形式の概要
シギリージャ系の歌は、数あるフラメンコ形式の中でも最も古い系統で、その起源は「フラメンコの母」ソレアよりもずっと古いものだと考えられており、カンテ・ホンド(深い歌)とカテゴライズされるカンテの中心的レパートリーですが、リズムや節回しの難解さもあってフラメンコを勉強する上で鍵になってくる形式群です。
シギリージャ系形式の起源
シギリージャ系の歌はトナ(Toná)と呼ばれる無伴奏の歌から派生したものです。
トナの近縁形式として、デブラ、マルティネーテ(これらの形式は、また後ほど紹介します)などがあり、これらシギリージャ系の無伴奏形式は、ギター伴奏が付く以前の、カンテの原初の形を現代に伝えています。
シギリージャ系の歌は、ヒターノの間で日常的に歌われていた仕事歌などが起源だと言われていますが、いったい何をどうやったら、ああいうリズムサイクル・節回しになったのか?ロマンを感じますよね。
ソレアとの関係
シギリージャとソレアは、どちらも古い起源を持つフラメンコの基本形式ですが、この2つは両方ともトナから派生したという説が有力です。
トナの直系がシギリージャ、後からバリエーションとして派生したのがソレアということでしょうか。
このあたりの事に関しては、録音はおろか文献もほとんど残っていないため不明な点が多いのですが、そんなところがまたフラメンコという芸術の神秘性を高めているのでしょうね。
2.2.3.3.2型コンパス(シギリージャ系コンパス)
同じ変則5拍子系のグアヒーラのコンパスサイクルは「3.3.2.2.2」というものでしたが、シギリージャ系は「2.2.3.3.2」というコンパスサイクルを持っています。
2.2.3.3.2型コンパスは、構造上2分割出来ないので、シギリージャ系にはメディオコンパスという概念はありませんが、歌い手の気分による1コンパス単位での伸縮は非常に多いし、さらにはカンテソロであれば、リズムを崩して1拍の長さがアバウトになる事も多いです。
最初は掴みどころが無いリズムに感じると思いますが、まずは、このコンパスを把握するためのベースとして、①変則5拍子②頭から12拍子で数えるカウント③ソレアの頭拍をずらしたカウントの3種類のカウント方法について考察してみましょう。
以下、カウント種別ごとに個別解説しますが、図の中の○が付いた拍がアクセント拍です。
変則5拍子
変則5拍子は、シギリージャのコンパスを単純化して5拍でとるカウント方法で、要するに「3拍目と4拍目が長い5拍子」というものです。
① ○ ② ○ ③ ○ ○ ④ ○ ○ ⑤ ○
スペイン人は、このカウントを使う人が多い印象です。
このカウント方法は、あまり細かい伝達には向きませんが、逆に、カンテソロなどで拍の長さがアバウトになるような場面では、このカウントでないと対処出来ません。
頭から12拍子で数えるカウント
シギリージャ系コンパスの頭拍を1として、1コンパスを12拍で数えるカウント方法です。
① 2 ③ 4 ⑤ 6 7 ⑧ 9 10 ⑪ 12
カウント方法としては分かりやすいと思いますし、拍の長さの正確性が上がるので細かい伝達にも適していそうですが、あまり一般的では無く、実際のリハーサルなどで、シギリージャの拍をこのカウントで言われても伝わらない事が多そうです。
ソレアの頭拍をずらしたカウント
もう一つ、ソレアの頭拍をずらしたカウント方法も考えられ、具体的にはソレアの8拍目を頭にとるとシギリージャのコンパスになるというものです。
⑧ 9 ⑩ 11 ⑫ 1 2 ③ 4 5 ⑥ 7
ソレアとアクセント位置のカウント(3と6と8と10と12)が同じなので、12拍子に慣れた人なら理解しやすい面もあるかもしれませんが、これも実用される機会は少ないように思います。
――実際の運用上は、シギリージャ系のコンパスを数字のカウントで伝達することはあまり無いように思いますが、この中だと一番上の変則5拍子のカウント方法が最も一般的だと思われますので、ここでも5拍子カウントを前提として解説していきます。
シギリージャ系コンパスのバリエーション
シギリージャ系コンパスのバリエーションとして、5つ目のアクセントを1拍(5拍子カウントだと半拍)後ろにずらしてパルマを叩くことがあります。
● ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ●
※●=強拍、○=弱拍
これは、ソレアの6拍目のアクセントを7拍目にずらすのと同様の感覚ですが、重くなりがちな締めくくりの拍をスキップすることでコンパスの推進力を増す感じですね。テンポが速くなるとこのリズムの比率が上がります。
シギリージャ系コンパスのテンポ
シギリージャ系のコンパスは自由リズムに近い形で歌われる場合もありますが、伝統的な歌のテンポという事だと、概ね120BPMから160BPMくらいで演奏されます。
これは、全シギリージャ系形式にいえることで、シギリージャ系の場合は、形式によって歌のテンポが全然違うということはありません。
ただし、踊りやギターソロでは展開次第で様々なテンポが考えられますが。
シギリージャ系形式のフレージング
シギリージャ系形式のフレージングには、以下のような共通の特徴があります。5拍子カウントを前提として書きます。
- コンパスの締めくくりは5拍目で、ジャマーダも普通5拍目で止まる
- フレーズは4拍目に解決していくものが多い
- コードの変わり目は1拍目と4拍目が多い
- 1拍目、2拍目を休んで3拍目から入るフレージングもある。この場合、ブレリアのフレージングがそのまま流用できる事もある
なお、シギリージャ系コンパスについて、実運用上のアイデアをこちらの記事で詳しく研究していますので、是非ご一読ください。
シギリージャ(単体形式)の概要
単数形:Siguiriya
複数形:Siguiriyas
主な調性:ポルメディオ(Aスパニッシュ調)
テンポ(歌):100BPMから160BPM
ここからは、シギリージャ系で最も演奏頻度が高いシギリージャ(単体形式)を集中的に解説していきます。
シギリージャはセギリージャ(Seguiriya)、などと記載されることもありますが、同じものを指しています。
ちなみにですが、セギディージャ(Seguidilla)というカステージャ地方に伝わる民族舞踊があって、これはセビジャーナスの原型と言われているものなのですが、一説によるとシギリージャにも影響を与えていて、その語源にもなったという話です。
この説をとるなら、Seguidilla→Seguiriya→Siguiriya、という変遷が想像できますよね。
シギリージャのコンパス
シギリージャのコンパスは上で書いた「2.2.3.3.2型」コンパスで、テンポ等も原則的には他のシギリージャ系形式と同様です。
ただし、踊りについては演奏テンポに幅があって、レトラ(歌振り)の部分はシギリージャ系の標準テンポよりもゆっくり(概ね100BPMから160BPMくらい)演奏される事が多いのですが、逆に、マチョの部分はかなり高速で、250BPMから300BPMくらいになることも。
一方、カンテソロは踊りのレトラよりテンポが速い場合が多いのですが、パルマ無しで歌う場合は、かなりテンポを揺らすことがあり、揺れ幅が大きいとリブレに近くなる場合もあります。
シギリージャの調性
シギリージャは主にポルメディオ(Aスパニッシュ調)で演奏されます。
ポルメディオの場合のカポタストの位置は、女性歌手なら4カポ(実音C♯スパニッシュ調)、男性歌手ならカポ無し(Aスパニッシュ調)あたりが中心です。
シギリージャのコードワーク
シギリージャでのギタープレイについて、ファルセータやエスコビージャの伴奏などではコードを展開させたりもしますが、歌とマルカール部分はコードをほとんど動かさないという特徴があります。
具体的には、B♭とAの2コードのみで展開させるのですが、色々やりすぎるとシギリージャの厳格な雰囲気を損ねてしまう、という事があるので敢えてやらないのでしょうね。
そして、2コード展開の単調さをカバーし、響きを豊かにするために使われるのがベース音指定コード=オンコードです。
ブレリア、ソレポル、タンゴ、シギリージャなどポルメディオの形式でオンコードを多用する事はソレア・ポル・ブレリアの解説で書いた通りなのですが、ほぼ2コードのみで展開させるシギリージャにおいては、オンコードの活用が殊更に重要になります。
下にシギリージャで弾かれるギターのマルカールの例を示します。数字は5拍子カウントでの拍で、1行で1拍(アクセント1つ分)です。
①B♭(onD)
②B♭9(onC)=C9
③B♭6(onG)
④A
⑤A
記述が煩雑になるのため、次のカンテのコード進行では、B♭系のオンコードは全て「B♭」と記載しますが、逆に言うとコードネームでB♭と書いてあっても、上のようなオンコードで演奏すると思って下さい。
他のポルメディオの形式でも同様のコードワークは使用しますが、シギリージャの場合は、通常マルカールのパターンがオンコードクリシェ込みになっているために、オンコードにしない普通のB♭→Aでやっても全く雰囲気が出ないのです。
シギリージャの歌
シギリージャの歌は、4行の歌詞を引き延ばして歌います。
引き延ばしすぎて、スペイン語がわかったとしても何を言ってるかわからない、みたいなことになっていますが、大抵、嘆き節・恨み節です。
シギリージャは形式自体のテーマが、ヒターノの迫害と労苦を反映した重苦しいものですので……。
歌の構成
シギリージャの歌の構成は、カンテソロの場合はそんなに決まった様式は無いのですが、踊り歌の場合、歌2つで1組にして歌われる事がほとんどで、歌と歌の間に中締めのジャマーダ(レマーテ)が入ります。
歌の長さは変化が多く、同じ歌でも歌い方で長さが変わるのですが、伴奏側からの捉え方としては以下のように考えるとシンプルです。
- 歌の最後のほうまでは、ひたすらB♭→Aで待ち
- G7→CとかC7→Fといった中締めが来る歌であれば、もうすぐ締めくくりが来る目印になるため分かりやすい
- 歌の最後(ジャー、ジャーとかが入ればわかりやすい)を捉えてジャマーダ(大抵はAコード一発)で締めくくる
シギリージャの歌のコード進行
以下に、スタンダードな踊り歌のコード進行を書きます。書式は次の通り。
- アクセント毎に小節線で区切る
- 1行で1コンパス(5小節12拍)
- ○はコードチェンジ無しの拍
- ()内のコードは省略されることもある
- キーはポルメディオ(Aスパニッシュ調)で記載
- コードは3和音で記載
- コンテスタシオン(合いの手)は歌が休みになる部分で、普通は0コンパス(コンテスタシオン無し)から2コンパス
- ※1の行は中締め。無い場合もある
- ※2の行は締めのジャマーダ
|B♭○|○○|○○○|A○○|○○|
コンテスタシオン
|B♭○|○○|○○○|A○○|○○|
|B♭○|○○|○○○|A○○|○○|
|B♭○|○○|○○○|A○○|○○|
|B♭○|○○|○○○|A○○|○○|
|B♭○|○○|C ○○|(F)○○|(F)○|※1
|B♭○|○○|○○○|A○○|○○|
|A ○|○○|○○○|○○○|○○|※2
ディグリー(度数)表記版
|♭Ⅱ○|○○|○○○|Ⅰ○○|○○|
コンテスタシオン
|♭Ⅱ○|○○|○○○|Ⅰ○○|○○|
|♭Ⅱ○|○○|○○○|Ⅰ○○|○○|
|♭Ⅱ○|○○|○○○|Ⅰ○○|○○|
|♭Ⅱ○|○○|○○○|Ⅰ○○|○○|
|♭Ⅱ○|○○|♭Ⅲ○○|○○○|(♭Ⅵ)○|※1
|♭Ⅱ○|○○|○○○|Ⅰ○○|○○|
|Ⅰ○|○○|○○○|○○○|○○|※2
踊り歌の場合、1つの歌がコンテスタシオン・ジャマーダ込みで8コンパスから10コンパス程度の長さが標準(上に書いたのは9コンパスのサイズ)で、前述の通り、1つの歌振り(レトラ)に対して2つの歌を繋げて歌います。
カンテソロの場合は、歌い手の裁量の範囲が広がるため、踊り歌よりもサイズ伸縮が増える傾向にあります。
マチョのコード進行
シギリージャの踊りの最後につくマチョはテンポが激速(250BPM以上)になることが多いですが、コードの進行のほうは以下の2パターンが主流です。
- Fコードから入って、Dm→C→B♭→Aの下降進行に行くパターン
- Fコードは飛ばして、Dmからの下降進行から入るパターン
なお、1つのコードの長さは歌い手の歌い回しかたによって1コンパス単位で伸縮します。
他のシギリージャ系形式
ここからは補足となりますが、シギリージャ以外のシギリージャ系形式を簡単にですが紹介しておきましょう。
コンパスは全て2.2.3.3.2型ですが、一部の無伴奏形式は自由リズムに近いものもあります。
リビアーナとセラーナ
単数形:Liviana,Serrana
複数形:Livianas,Serranas
主な調性:ポルアリーバ(Eスパニッシュ調)
リビアーナとセラーナはポルアリーバ(Eスパニッシュ調)で演奏され、原則として、この2つの歌は組にして歌われます。
なお、セラーナにはカーニャのようなラメントがあります。
カバーレス(カバル)
単数形:Cabal
複数形:Cabales
主な調性:Aメジャー
カバーレス(単数形はカバル)は長調で歌われるシギリージャ系の形式です。
単体で演奏される機会は少なく、大抵はカンテソロの際にシギリージャの後歌として歌われます。
トナとデブラ
単数形:Toná,Debla
複数形:Tonás,Deblas
主な調性:無伴奏
テンポ:自由リズムに近い
シギリージャ系形式の中でも、無伴奏のものはカンテの源流に近く、古い形式ほど自由リズムに近くなる傾向です。
最も古い形式であるトナは、前述した通り、全てのカンテの原型となった歌で、近縁種にはデブラという歌もあります。
マルティネーテとカルセレーラ
単数形:Martinete,Carselera
複数形:Martinetes,Carseleras
主な調性:無伴奏
マルティネーテは、カンテソロとしても、踊り歌としても良く歌われますが、無伴奏形式の中では比較的ハッキリしたコンパスで演奏されるのが特徴です。
カルセレーラスは「監獄の歌」(囚人の間で歌われていた?)と言われているマルティネーテの近縁種で、一緒に歌われる事が多いです。
サエタ
単数形:Saeta
複数形:Saetas
主な調性:無伴奏
テンポ:自由リズムに近い
サエタは、セマナ・サンタで歌われる宗教歌がカンテ化したもので、トナのような自由リズムに近い形で歌われます。
サエタは他のシギリージャ系の歌とは起源が異なるのですが、歌のフォーマットから考えて、カンテ成立初期の段階でフラメンコ化されたものと推測されます。
――今回は、フラメンコを学習する上で最難関の一つとなりがちなシギリージャ系形式を解説しました。
シギリージャ系の形式は、とくにコンパスが難解に感じると思いますが、ブレリアなどと比べるとリズムパターンもフレーズの乗せかたも固定的なので、一旦慣れてしまえば最初に受ける印象ほど難解なものではないと思います。
次回からは、ファンダンゴ系を中心とした3拍子系の形式に入る予定です。
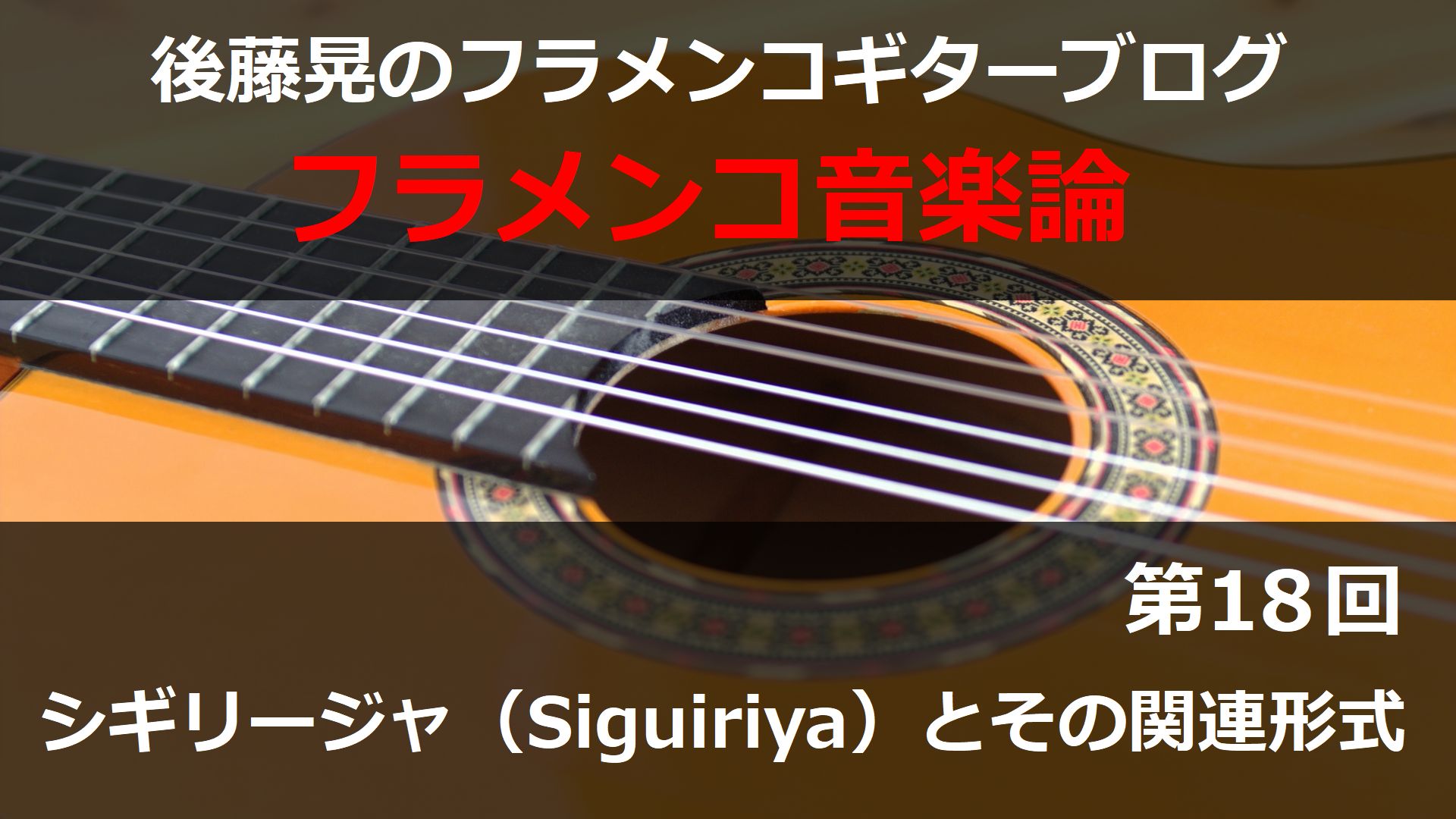
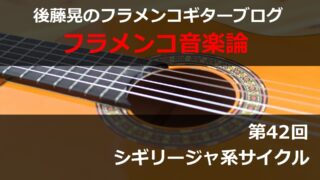
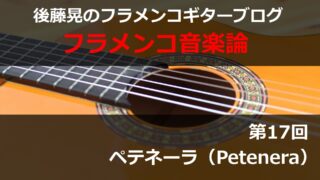
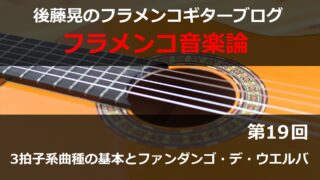
コメント