音楽理論ライブラリーでは前回、リズムの基礎や記譜方法をやりましたが、今回は「良く使われるリズムパターン」「音楽ジャンルごとのリズムの特徴」というテーマでお話します。
各リズムパターンの特性を知って、それらのパターンに対応する基本的な伴奏法を身に付けていれば、あとはコード譜さえあれば、その場でそれらしい伴奏をサッと付けることもできますよね。
それでは、リズムの系統別に見ていきましょう。
4拍子系
日本の音楽は最近のものを含めて4拍子系が主流ですが、世界レベルで見ても4拍子系のリズムパターンが圧倒的に多いです。
8ビート
8ビートはロックの代表的リズムパターンで、ベースドラムとスネアドラムを交互に打つものですが、ブラックミュージックの影響が色濃いブルーズロックなどを中心に、8ビートをシャッフル(3連符系の跳ねたリズム)にしたリズムも大変ポピュラーなものです。
2ビート
2分音符でベードラやスネアを打ち鳴らすので、2ビートと呼ばれますが、8ビートを早回ししたようなノリです。
スカとかスピードメタル系で聴かれ、メタル系だとさらにダブルベースドラムを駆使したりして疾走感を出します。
4ビート
ジャズの代表的なリズムパターンです。
いわゆるシンバルレガートでベースのビートを刻みますが、ブラックミュージック特有の跳ねたリズムで、表拍が長く、裏拍が短くなります。
ジャズでは、これを「スイング」と表現しますが、前述のシャッフルビートとほぼ同義であり、黒人音楽から派生した音楽ジャンルと特有のものです。
16ビート
8ビートよりリズムが細分化され、16分音符の表裏、裏裏を多用するリズムパターンです。
1960年代から1970年代にファンクが流行して、アメリカの黒人アーティストを中心に盛んに演奏されて確立されました。
ブラックミュージック由来なので、表拍(表表と裏表)が長く、裏拍(表裏と裏裏)が短くなる傾向です。
アレンジ上は細かいベースラインやエレキギターのカッティングが特徴です。
ラテン系ビート
ラテン系のリズムパターンは、戦後にラテン音楽、ラテンパーカッションのブームがあり、多くはそこで確立されたものです。
キューバ系(サルサとかルンバ)とブラジル系(サンバとかボサノバ)が二大ジャンルと思いますが、符点音符の多用、裏拍の多用、弱起リズム(ビートの頭を強く出さない)の多用、などが共通の特徴です。
アルゼンチンタンゴやフラメンコのタンゴ・ルンバも、ラテン系ビートの一種と言えるでしょう。
テクノ・EDM系ビート
テクノミュージックは1970年代頃に始まったシンセサイザーなどの電子楽器を駆使した音楽ジャンルです。
このカテゴリーには1970年代に流行したテクノポップ、1980年代に流行したディスコビートやユーロビート、1990年代から大流行したハウス、トランス、ダンスホールレゲエなどが含まれますが、現在はこれらをひっくるめて「テクノ系」や「EDM(エレクトリック・ダンス・ミュージック)」というくくりで扱われているイメージです。
特徴は打ち込みで作った機械的なリズムで、いわゆる「4つ打ち」(ベースドラムをひたすら4分音符で鳴らす)に象徴されるように、4拍子のビートを強烈に出して、誰もが踊れるように作ってあるものが多いです。
その他4拍子系
系統としてまとめられるのは上のようなものですが、4拍子系のリズムパターンは他にも世界中にたくさん存在します。
例えば、ボブ・マーリーによって確立されたレゲエのリズムパターンは8ビートの一種と考えることもできますが、リズムのハネかたや隙間の作り方が独特なので、独立したリズムパターンジャンルと捉えたほうが良さそうだし、そういうものが数多くあります。
3拍子系
3拍子は4拍子に次いで多くあるリズムですが、多くはヨーロッパ地域の民謡や舞曲が起源です。
ただ、3拍子系はリズムパターンとして系統づけられるものは少ないです。
ワルツ
クラシックの時代から3拍子の代表的リズムパターンにワルツがあります。
3拍子の後ろ2拍にアクセントがある「ずんちゃっちゃっ、ずんちゃっちゃっ」というアレですね。
ワルツは舞曲で、舞踏会などで踊るためのリズムであり、現在も社交ダンスのステップなどでそういう流れが受け継がれています。
ちなみに、ワルツ以外のメジャーな3拍子パターンは存在しないため、ワルツ=3拍子系ビート全般と捉えられることもあります。
フラメンコの3拍子
フラメンコは自分の専門なので、これも少しだけ触れておきます。
フラメンコのリズム形式は半分以上が3拍子系(6拍子、12拍子を含む)のリズムです。
ソレアやシギリージャなど、原始的なフラメンコには12拍子(6拍子)系しかなかったんですが、アンダルシア民謡から3拍子が採り入れられてミックスされながら、フラメンコのリズム形式が確立していきました。
ちなみに、フラメンコの2拍子・4拍子系の形式については、引き上げ移民が伝えた中南米の音楽が起源と言われているし、もともとフラメンコには4拍子の感覚は希薄だったと思われます。
フラメンコのリズムに関しては「フラメンコ音楽論」で詳しく扱っていますので、そちらをご覧ください。
6/8拍子
通称「ハチロク」と呼ばれたりする6/8拍子はクラシック音楽でも一般の音楽でも、かなりの割合で出てきます。
ハチロクは8分音符1つで1拍、8分音符6つで1小節というリズムで、アクセントの付け方によって、2拍子にも3拍子にもきこえますが、厳密には2拍子の一種です。
8分音符3つで1拍、2拍で1小節というのが基本ですが、これだと3連符の2拍子とほぼ同じですよね。
個人的には、ハチロクの特徴は「3拍子にも2拍子にもとれるという曖昧さ」だと思っていますが。
あと、ハチロクは16分音符で刻むケースも多く、その場合は一般的な16ビートと同じくシャッフルビートになることもあります。
クラシック系音楽のリズムの取りかた
クラシック系の音楽・奏者は、他のジャンルと違う特殊事情があります。
クラシックは基本的に譜面を再現するジャンルなので、他の音楽ジャンルと演奏に対する考え方が違うんですが、とくにリズムアンサンブルに関しては他と全く異質なものです。
ある程度以上の人数のアンサンブルには指揮者がつきますし、BPMの指定も速度記号でやるのでアバウトです。
BPMは指揮者の裁量でコントロールするか、少人数なら阿吽の呼吸で合わせる感じで、こうしたことが可能なのは、クラシックの楽曲の作り方によるところが大きいと思います。
打楽器や打ち込みでBPMをキープして、その上でプレイを展開するような現代の音楽ジャンルと比べて、クラシックの楽曲のリズムは表拍主体の単純なものが多いです。
そのかわり、フェルマータ等が多かったりして、BPMに縛られない表現を重視する傾向があります。
ただ、現代ではジャンルの垣根はどんどん取っ払われて、クラシックの奏者も正確なBPMでリズミックなプレイをすることも増えてきたし、とくに若い世代ではクラシック以外のジャンルも積極的に演奏したりして、他の音楽ジャンルとのギャップは小さくなってきているように思います。
あとがき
「音楽理論ライブラリー」では、前回と今回でリズムに関して簡単にですがまとめました。
これで、調性・コード・スケール・リズムという音楽の基本構成要素を一通り学習したことになります。
今回の連載の主旨である「音楽をアレンジしたり演奏したりするのに、知っておいた方がいい実用的な音楽理論をコンパクトに解説する」というのは大体達成できたと思いますので、「音楽理論ライブラリー」はこれで一旦終了といたします。
しかし「これで完璧」というわけにもいかないと思いますので、また必要に応じて加筆・修正をしていこうかと思います。
この連載講座の内容は「後藤晃ギター教室」で教えているカリキュラムの一部です。もし興味を持たれましたら、ギター教室へのお問い合わせをお待ちしています!
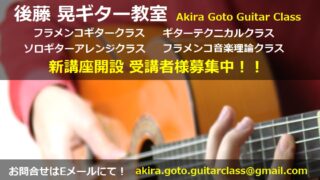
お問い合わせはEメールにて
akira.goto.guitarclass@gmail.com


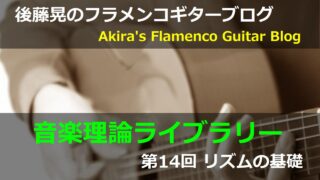
コメント