音楽理論ライブラリーでは前回までで、コードの基本からテンションコード、分数コードなど、コードの構造的なことをほぼ網羅できたと思います。
これから、前回まででやったコードの知識を踏まえて、調性の成り立ちなど、実際に音楽はどうやって作られているのか?というテーマに移っていきます。
今回は、メジャーキー・マイナーキーを構成する基本コードであるダイアトニックコードと、基本的なコード進行を学習します。
ダイアトニックコードとは?
音楽理論ライブラリー第2回でやったメジャースケールやマイナースケールの構成音はメジャーキー、マイナーキーを表現する基本要素になります。
調号で指定された音をそのキーの「ダイアトニックノート」、ダイアトニックノートで作られたコードを「ダイアトニックコード」といいます。
メジャースケールとナチュラルマイナースケールのダイアトニックコードが鳴っている間は、臨時記号が発生しない通常運転、ということです。
マイナースケールは3種類あるので、ダイアトニックコードもバリエーションが多いです。
ハーモニックマイナー及びメロディックマイナーに含まれる臨時記号の付いた音は、ルート音への導音として扱われ、例外的にダイアトニックノートの範疇になります。
上記以外の臨時記号が付いた音を「ノンダイアトニックノート」と呼び、ノンダイアトニックノートを含むコードを「ノンダイアトニックコード」といいます。
ノンダイアトニックノート、ノンダイアトニックコードについては解説が長くなるので次回以降にやることにして、今回はまずはダイアトニックコードについて学習しましょう。
ダイアトニックコードをおぼえよう
ダイアトニックコードはメジャースケール、マイナースケールの構成音だけで作られたコードで、コード分析やキーの判定の基本になります。
西洋音階は7音階なので、ダイアトニックコードも1つのキーに対して7つ存在します。
なお、当ブログの表記方法ですが、コードに関してはローマ数字(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲなど)の度数表記を採用しています。ルートから数えてどの音程の上に構成されたコードか?ということです。
Cメジャーキーのダイアトニックコード
以下にCメジャーキーを例にダイアトニックコードを一覧にします。
「3和音コード=3和音度数|4和音コード=4和音度数|コード機能」という書式で表記します。
- C=Ⅰ|CM7=ⅠM7|T
- Dm=Ⅱm|Dm7=Ⅱm7|SD
- Em=Ⅲm|Em7=Ⅲm7|T
- F=Ⅳ|FM7=ⅣM7|SD
- G=Ⅴ|G7=Ⅴ7|D
- Am=Ⅵm|Am7=Ⅵm7|T
- Bdim=Ⅶdim|Bm7(♭5)=Ⅶm7(♭5)|D
Aナチュラルマイナーのダイアトニックコード
Cメジャースケールの「ラ」をルートにとれば、Aナチュラルマイナーのダイアトニックコードができますので、同様に一覧にします。
- Am=Ⅰm|Am7=Ⅰm7|TM
- Bdim=Ⅱdim|Bm7(♭5)=Ⅱm7(♭5)|SDM
- C=♭Ⅲ|CM7=♭ⅢM7|TM/SDM※
- Dm=Ⅳm|Dm7=Ⅳm7|SDM
- Em=Ⅴm|Em7=Ⅴm7|DM
- F=♭Ⅵ|FM7=♭ⅥM7|TM/SDM※
- G=♭Ⅶ|G7=♭Ⅶ7|DM/SDM※
※メジャーキー上で♭ⅢM7、♭ⅥM7、♭Ⅶ7が出てきたときはSDMとして働く場合が多い。
マイナーキーのⅤコードは、Ⅴmも使われますが、ハーモニックマイナーおよびメロディックマイナーのダイアトニックコードであるⅤ、Ⅴ7(AマイナーならE、E7)が常用されます。
Cナチュラルマイナーのダイアトニックコード
Cメジャーキーとの違いを把握するために、Cナチュラルマイナーのダイアトニックコードも書いておきます。
- Cm=Ⅰm|Cm7=Ⅰm7|TM
- Ddim=Ⅱdim|Dm7(♭5)=Ⅱm7(♭5)|SDM
- E♭=♭Ⅲ|E♭M7=♭ⅢM7|TM/SDM※
- Fm=Ⅳm|Fm7=Ⅳm7|SDM
- Gm=Ⅴm|Gm7=Ⅴm7|DM
- A♭=♭Ⅵ|A♭M7=♭ⅥM7|TM/SDM※
- B♭=♭Ⅶ|B♭7=♭Ⅶ7|DM/SDM※
※メジャーキー上で♭ⅢM7、♭ⅥM7、♭Ⅶ7が出てきたときはSDMとして働く場合が多い。
マイナースケールのダイアトニックコード
マイナースケールには3種類あることをやりましたが、ハーモニックマイナー・メロディックマイナーにもダイアトニックコードがあります。
それらが出てくると臨時記号が発生することになりますが、同一のマイナーキーの範疇として扱います。
古典的なクラシックではメロディックマイナーは上りのみとか、いろいろルールがありますが、現代の音楽ではハーモニックマイナー・メロディックマイナーのフレーズやダイアトニックコードは自由に使われます。
Cハーモニックマイナーのダイアトニックコード
Cハーモニックマイナースケールのダイアトニックコードを一覧にします。
- Cm=Ⅰm|CmM7=ⅠmM7|TM
- Ddim=Ⅱdim|Dm7(♭5)=Ⅱm7(♭5)|SDM
- E♭(♯5)=♭Ⅲ(♯5)|E♭M7(♯5)=♭ⅢM7(♯5)|TM/SDM※
- Fm=Ⅳm|Fm7=Ⅳm7|SDM
- G=Ⅴ|G7=Ⅴ7|D
- A♭=♭Ⅵ|A♭M7=♭ⅥM7|TM/SDM※
- Bdim=Ⅶdim|Bdim7=Ⅶdim7|D
※メジャーキー上で♭ⅢM7♯5、♭ⅥM7が出てきたときはSDMとして働く場合が多い。
Cメロディックマイナーのダイアトニックコード
Cメロディックマイナースケールのダイアトニックコードを一覧にします。
- Cm=Ⅰm|CmM7=ⅠmM7|TM
- Dm=Ⅱm|Dm7=Ⅱm7|SD
- E♭(♯5)=♭Ⅲ(♯5)|E♭M7(♯5)=♭ⅢM7(♯5)|TM/SDM※
- F=Ⅳ|F7=Ⅳ7|SD
- G=Ⅴ|G7=Ⅴ7|D
- Adim=Ⅵdim|Am7(♭5)=Ⅵm7(♭5)|TM/SDM※
- B(♭5)=Ⅶ(♭5)|B7(♭5) =Ⅶ7(♭5)|D/SDM※
※メジャーキー上で♭ⅢM7♯5、Ⅵm7(♭5)、Ⅶ7(♭5)が出てきたときはSDMとして働く場合が多い。
メロディックマイナースケールは同主調のメジャースケールと1音しか違わず、3rdがm3かM3かという違いだけなので、メロディックマイナーのダイアトニックコードであるⅡm7、Ⅳ7、Ⅵm7(♭5)などが同主調転調の橋渡しに使われたりします。
ダイアトニックコード内の代理コード
同じキーの同じ機能のコード同士は「代理コード」と呼ばれて互換性があります。
例えばCメジャーキーでFとDm7は入れ替えても大丈夫です。
ノンダイアトニックなものも含めると代理コードにはたくさんの種類があるので次回から順次解説していきますが、今回は同一キー内でのダイアトニックコード同士の代理関係をおさえておいてください。
基本的なコード進行
ここで、よく使う基本的なコード進行についてお話ししておきます。
コード進行は結果が効果的なら、その解釈は後からつけたりできるし、こうしなければならない、というのはありません。
ですが、良く使われる基本的なコード進行というのは存在していて、曲を分析してみると、普通に聴こえる曲はほとんどがそういう基本進行の組み合わせで出来ています。
いくつか具体例を解説します。
ドミナントモーション
音楽を構成する一番基本的な要素にドミナントモーションがあります。
Ⅴ7→Ⅰ、Ⅴ7→Ⅰmという進行で、ドミナントコードからトニックコード(とくにルートコード)への解決という形です。
例えば、CメジャーキーならG7→C、DマイナーキーならA7→Dmになります。
Ⅴ7コードの3度音が半音上行して、キーのルートへ進行することで、ドミナント7thコードが内包するトライトーン(3全音)が解消され、安定したトニックコードへと解決します。
Ⅴ7→Ⅰ、Ⅴ7→Ⅰmという進行は、そのキーを一番シンプルに表現するものです。
5度進行
上のドミナントモーションはこの5度進行の代表ですが、ドミナントモーションになっていなくても、5度下(=4度上)に進行していくコード進行は安定感、安心感のある基本中の基本な進行です。
4度進行
5度進行の逆行パターンで、4度下(=5度上)に進行していくコード進行で、5度進行ほどではありませんが、耳慣れた常套句です。
順次進行(2度進行)
例えば、CM7→Dm7→Em7のように、隣り合ったダイアトニックコードに進行するもので、上行・下行の両方あります。
繋ぎに多用されますが、上手く使うと、次の展開への期待感を高めるような進行になります。
3度進行
3度上または下に進行するものですが、これは元のコードと同じコード機能のコードに行くことが多いので、ワンコードでやってもいい部分を色彩感を少し変えたいような場面で使います。
例えばCメジャーキーなら、C→Amとか、C→Emとか、よく出てくる進行ですが、これらの進行はCコード一発でやっても本質は変わりませんが、色彩感が出ます。
赤からオレンジとか、青から水色とか、同系色へチェンジするイメージですね。
――今回はダイアトニックコードと、基本的なコード進行についてやりました。
今のところ、臨時記号や転調のことにはあまり触れていませんが、次回からはそのあたりをやっていきたいと思います!

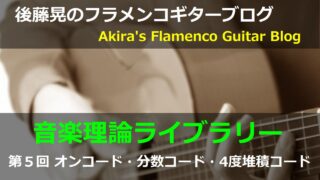
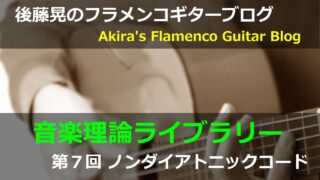
コメント