今回のファルセータ動画はティエントのPart2です。
ティエントはポルメディオ調の2拍子形式で、基本はタンゴをゆっくり演奏したものですが、リズムに独特のタメがあります。詳しくはこちらの形式解説をご覧になってください。
ティエント形式の解説
ティエントの歌伴奏と踊り伴奏
ティエントは踊りや歌の伴奏の機会が多い形式です。
この形式で注意したいのが、歌伴奏と踊り伴奏では、かなりテンポもリズム型も違うし、求められるファルセータも違うという事です。
ティエントは昨年の8月にも演奏していますが、その時演奏したファルセータは歌伴奏、踊り伴奏のどちらにも使えそうなものでした。
今回は2つのファルセータを演奏していますが、どちらも踊り伴奏向けのものです。
ティエントの歌伴奏と踊り伴奏の違いは下のようになっています。
テンポ
歌伴奏→100BPMから130BPM
踊り伴奏→70BPMから90BPM
リズム型
歌伴奏→粘り多め
踊り伴奏→粘り少なめか、全く粘らない
リズム型の「粘る」という表現は、上で案内したフラメンコ音楽論の記事に詳しく書いていますが、5連符を2:2:1で割ったような特徴的なリズムのことです。
粘りのある歌伴奏の形が本来のティエントの感覚ですが、パルマも入れたりしてやるとめちゃめちゃ合わせずらくなるので、踊りが入る場合はあまり粘らせません。
ぶっちゃけ、踊り伴奏ではティエントも、タンゴ・デ・マラガも、タラントも、ガロティンも同じようなノリになります。
ただし、踊り伴奏でもパルマの無いサリーダ(イントロ)や、レトラ(歌振り)の部分でリズムを粘らせることで、ティエントらしさを演出することはあります。
では、個別にファルセータを解説して行きます。
1つ目のファルセータ【ヘスス・デ・ロサリオ】
1つ目のファルセータの元ネタはスペインに居たとき(1996年か1997年)、アントニオ・カナーレス(Antonio Canales)が小さな劇場で地元の劇団とコラボした公演を見に行って、音を録音してきたものから耳コピーしたものです。
記憶が確かなら、ギターはヘスス・デ・ロサリオ(Jesus de Rosario、当時は本名のヘスス・ヒメネスを名乗っていた)です。
アントニオ・カナーレスの伴奏は、ホセ・ヒメネス(Jose Jimenez、El Viejin)とラモン・ヒメネス(Ramon Jimenez)がやっていましたが、ヘススはラモンの甥にあたり、当時まだ10代でした。
彼が単独でカナーレスの伴奏をするのを見るのは、その公演が初めてでしたが、ギタープレイと音楽の作り方が素晴らしく、持ち帰った録音を何回も聴いては耳コピーをしました。
ヘススはその後、2002年にサラ・バラス(Sara Baras)が自分の舞踊団で来日公演した時に、音楽監督・ギタリストとして参加していたのをおぼえています。その公演も音楽と踊りの作り込まれかたが素晴らしかったです。
このファルセータは、踊り伴奏の1歌と2歌の間で弾かれていたもので、原版はバックにガッツリとカホンが入ってカッチリとしたテンポでしたが、今回の演奏では、少しだけリズムを崩して緩急させて弾いています。
例によって、細かい部分は長年弾くうちにどんどん変わっているので、原版とは色々と違います。
2番目と3番目のコードの不協和音がたまらんですよね。D7(♭9)→A7(♭5)でしょうか?
ここのフレーズ、一瞬コンディミ(コンビネーション・オブ・ディミニッシュ)っぽい感じになってますが、ヘススは結構コンディミを使うんですよね。カッコイイなぁ。
2つ目のファルセータ【アドリアン・ガリアのビデオより】
2つ目のファルセータは、以前日本でも活動していたアドリアン・ガリア(Adrian Galia)のビデオに入っていたものです。
2002年あたりだったと思いますが、踊り伴奏の仕事をしたときに、ビデオを渡されて、このファルセータを弾いて欲しいと言われてコピーしたんですよね。
いきなりF♯マイナーキーへ転調して始まる印象的なファルセータで、自分もかなり気に入って、伴奏用ネタのレパートリーに加えてずっと弾いているものです。
前半部分はF♯マイナーキー/C♯スパニッシュ調の複合調です。
後半部分は自分が作り足したもので、本来のティエントのキーであるAスパニッシュ調(ポルアリーバ)に戻しています。
原版はどういう展開だったかおぼえてませんが、全く違った弾きかただったと思います。
このファルセータは、踊り伴奏のゆっくりテンポでないと、このゆったりした重厚感は出ないと思うので、踊り伴奏専用ですね。
テクニック面では、多彩なピカードの弾き分けも大きなポイントです。
ちなみに、そのアドリアンのビデオには伴奏ネタとして面白いファルセータがたくさん入っていたので、耳コピーして未だに使っているものも多いです。
昔はYouTubeとか無かったので動画コンテンツは貴重で、ビデオなどを入手したら骨の随までしゃぶり尽くすような見かたをしてましたよね(笑)
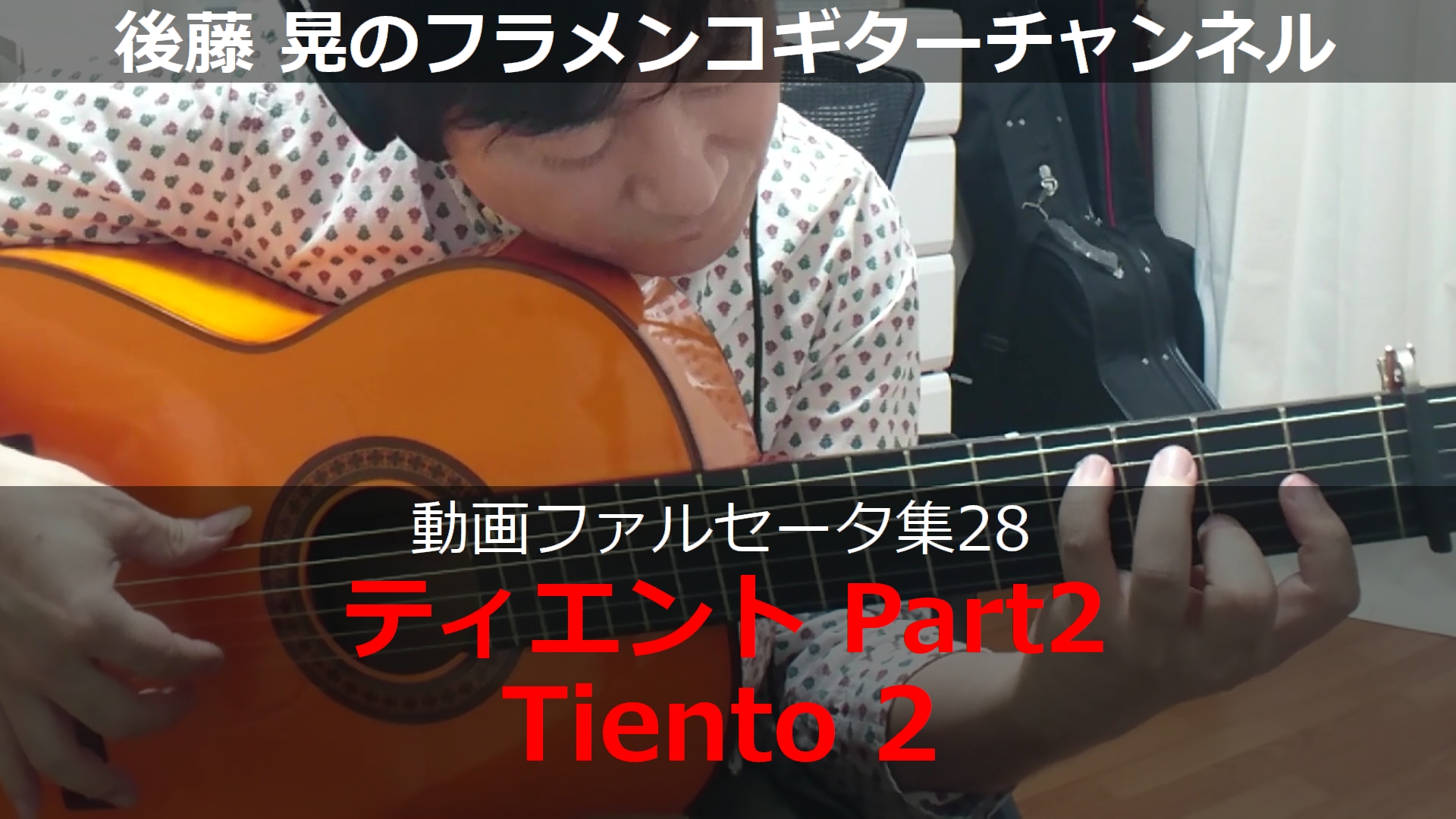

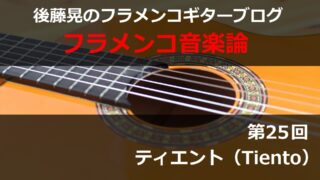

コメント