この動画は、今年の6月に「第1回フラメンコWebフェスティバル」に応募するために録画したものです。
そして、締め切りギリで何とか応募して、結果はエスアイイー賞をいただきました。
嬉しい~(*’ω’*)
フラメンコWebフェスティバルを主催した「フラメンコ2030」サイトへの掲載が8月末で終了したので、こちらに掲載してアーカイブしておきます。
フラメンコWebフェスティバルについて
この動画で自分がエントリーした「フラメンコWebフェスティバル」について少し説明いたします。
2月末頃から始まった新型コロナウイルス感染拡大によって、音楽や芸能の業界は大きな影響を受けました。
フラメンコの業界もまた大きな影響を受けたわけですが、具体的にはライブやグループレッスンなど、人を集めてやる催しは制限を受けるようになり、それは半年経った今も継続しています。
フラメンコは生演奏や人間同士の直接交流を重んじる芸術ジャンルなので、これはかなり致命的なことです。
そこで、フラメンコ業界の有志が集まって「フラメンコ2030」というプロジェクトを発足させます。
これは10年後のフラメンコの世界の事を考えて今できることをやっていこう、というプロジェクトです。
フラメンコ2030 Website
現状、非対面の発信チャンネルで最もスピーディーでローコストかつ表現力が高いのがインターネットです。
しかし、フラメンコの業界は「生」を重んじる考えを中心に回ってきたので、突然「Webで」と言われても、なかなか難しいものがあります。
そこで「フラメンコ2030」が旗をふって、動画コンクールという形式の企画を立ち上げ、動画制作やWebでの発信を促進しよう、というの趣旨で開催されたのが「第1回フラメンコWebフェスティバル」というわけです。
自分がフラメンコWebフェスティバルに参加した経緯
「第1回フラメンコWebフェスティバル」ですが、自分は5月から6月と多忙な時期に当たってしまい、開催は知っていたものの、あまり内容も見ていなくて、参加は見送ろうかと思っていました。
応募に気持ちが傾いたきっかけは「フラメンコWebフェスティバル、YouTubeやってるなら応募してみたら?チャンスなんじゃない?」という友人の一言でしたが、それをきっかけに募集要項を読んで、フラメンコ2030のサイトも見て、こんな風に考えました。
- この2年間、自分ができる中で最も有効な選択肢として動画制作を含むインターネットでの発信に力を入れてきた、ということがフラメンコWebフェスティバルの趣旨とマッチしている
- 演奏動画ならよく作っているし、Web発信という形なら、今のフラメンコの世界に最短距離で貢献できるんでは?
- 自分の事を知らなかった人の目に触れるこんなに良い機会は無いんでは?
こんな気持ちが芽生え、急激に「第1回フラメンコWebフェスティバル」に参加しようという気持ちに傾いたのが締め切りの3日前のことです。
そうなると、どうしても参加したくなる性格なので(笑)、時間的に厳しいのは重々承知していましたが「やれるだけやってみよう」となって、すぐに準備にとりかかりました。
2日間・合計6時間で制作
応募するなら未発表の動画で、自分で作曲したオリジナルが良いと思っていましたが、弾き慣れているオリジナルのギターソロ曲「Tango de Azul」を弾くことにしました。
しかし、曲を決めて録音準備を始めた時点で、締め切りまでに平日の2日間しかなかったので、実質6時間くらいで作らなければなりません。
あれこれ凝ったりする時間もスキルもないので、いつもの演奏動画と同じやりかたでいくことに。
最初は3分のサイズで録画を試みましたが、さすがに準備不足もあり、どうしても細かいところをミスったりしてテイク数がどんどん増えてしまいました。
こうなると焦りも出るし、テイクを選定する時間も足りなくなりそうなので、バッサリとサイズダウンして一番聴かせたいところ1分半くらいの演奏にして、そこだけ集中練習して録画しました。
このへんは普段演奏動画を作ってる経験が生きたかな。
こうして、練習・リズムトラック作成・録画・テイク選定・ミキシング・説明文執筆など、すべて含めて6時間の突貫工事でなんとか仕上げて、締め切り30分前になんとかアップロードしました。
受付順でエントリーナンバーが付くんですが、自分がラストだと思ったら、自分の後に7、8人いたのにはウケましたが(笑)
ファルセータ解説【オリジナル】
これの元ネタは一昨年録音した「Tango de Azul」(作曲は2008年)のイントロと、その後に続く2つのファルセータです。
タンゴ形式については以下の記事をご覧ください。
では、いつものファルセータ動画解説と同様に、セクションごとに解説していきます。
イントロ
イントロ部分はさらに遡って2006年頃作った「青い鳥のテーマ」がモチーフになっています。
キーは普通のポルメディオ(Aスパニッシュ)なんですがイントロの出だしはDm7→G7からなので、一瞬Aマイナーキーかな?と思いますよね。
ポルメディオの平行調のDマイナーキーのⅠm7→Ⅳ7という感覚で作りましたが、イントロ部分は調性が揺らぎながら進行してるので、どちらの解釈でも良いと思います。
1つ目のファルセータ
イントロが終わって1つ目のファルセータもイントロと同じAマイナーとDマイナーで揺らぐ調性で展開しますが、後半で一瞬Eマイナーキーに行ってから、ポルメディオ=Aスパニッシュ調に解決させています。
転調が多いですが、全て平行調・属調・下属調の範囲でやっているので転調無しでの解釈も可能なさりげないものです。
自分はこういうのを「調性の揺らぎ」と表現してます。
2つ目のファルセータ
2つ目のファルセータは曲の中のメインテーマ的な部分ですが、キーはDマイナーキー/ポルメディオで一貫していて、調性の揺らぎはありません。
メロディーの大きなアウフタクト(3拍半食って入っている)がポイントですね。



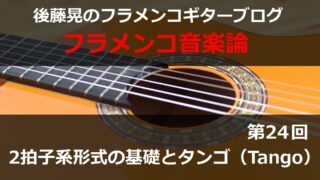
コメント