タンゴはブレリアと並ぶフラメンコの基本形式ですが、ファルセータ動画ではタンゴ形式をまだ一度もやってないので、今回はタンゴを演奏することにしました。
動画では2つのファルセータを弾いていますが、1つ目は2005年頃に自作したもの、2つ目は昔スペインで習ったものです。
タンゴ形式解説
今回はポルアリーバのタンゴ
タンゴ形式はポルメディオ(Aスパニッシュ)で演奏することのほうが多いですが、今回はポルアリーバ(Eスパニッシュ)のものをチョイスしました。
動画作成に当たって、タンゴを色々弾いてみたのですが、今回、1つ目に弾いている自作ファルセータが独自性があって気に入っているので、これをまず出したいなぁ、という理由でした。
ポルアリーバのタンゴは、伴奏ではそれほど演奏する機会がないのですが、少し変えれば、Aマイナーキーのタンゴ・デ・マラガやファルーカで使用することもできます。
とくに1つ目のファルセータはAマイナーキー寄りの作りなので、タンゴ・デ・マラガやファルーカでも使いやすいです。
では、今回のファルセータを個別に解説します。
1つ目のファルセータ【オリジナル】
1つ目のファルセータは前回(グアヒーラPart2)に続き、Galeria Rosada(以前自分がやっていたフラメンコポップバンド)のCDで弾いているものです。
Galeria RosadaのCD『Secrets of the world』に入っている「Again」という曲のイントロに使用しているものですが、このファルセータは歌が出来たあとに、この曲に付けるために作ったものです。
Galria Rosadaの活動
前半はマイナーキーの感覚で、後半でミの旋法に移行していますが、コードワークなど、かなり試行錯誤して作ったおぼえがあります。
なお、今回の演奏だと最後の方はメディオコンパスにしています。
2つ目のファルセータ【パコ・クルス】
2つ目は昔スペインで習ったものを最近思い出してよく弾いているものです。
スペインでパコ・クルス(Paco Cruz)に習ったものですが、他であまり聴かないので、恐らく彼の作かと思います。
1つ目のファルセータだけだと少し短いし、後につけるエストリビージョ(締めくくり)を色々考えていて、これをつけるが一番カッコよくまとまりそうだったのでチョイスしました。
4コンパスパターン2回+レマーテ2コンパスというシンプル構成ですが、コードワークとフレージングがフラメンコぽくて(半音ぶつかり+裏リズム多め)良いですよね!


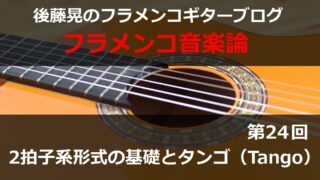

コメント