久しぶりのファルセータ動画です。今回はブレリアのPart3。
今回、2つのファルセータを演奏していますが、両方ともスペインでパコ・クルス(Paco Cruz)に習ったものです。
動画の詳細
年初にYouTubeチャンネルをはじめたとき、手持ちのファルセータを一覧にしてみたんですが、ブレリアが圧倒的に多いんですよね。
なので、ちょこちょこと出していかないと後半ブレリアばかりになりそうなので、今後も数回に1度はブレリアになりそうです。
ブレリア形式解説
以下、今回演奏しているファルセータを個別に解説していきます。
1つ目のファルセータ【パコ・クルス】
1つ目のファルセータは、もともと2弦をA音に下げる変則チューニングで演奏されていたものをレギュラーチューニング版にアレンジしたものです。
パコ・クルスは2弦A音チューニングをよく使っていて、これの他にも幾つか同じチューニングを使用したファルセータを教わりました。
変則チューニングは応用しずらいのでアレンジ
でも、変則チューニングのファルセータって、伴奏でもソロ曲でも使いづらいんですよね。
そこで、変則チューニングのファルセータは自分でレギュラーチューニング版にアレンジして弾いたりしています。
このファルセータは、いつでもどこでも使えるように一般的なポルメディオ(Aスパニッシュ調)にアレンジしました。
なので、オリジナルとはコードやフレージングが変わっています。
カルロス・ベナベントのベースフレーズが入っている
パコ・クルスいわく、このファルセータは踊り手のベレン・フェルナンデス(Belen Fernandez)の伴奏用に作ったものらしいです。
ベレンがカーレス・ベナベン(Carles Benavent)が弾いているベースのフレーズを気に入って、それをコピーして何か作って欲しいと言われて、渋々作ったらしいんですが、結局パコ・クルス本人もかなり気に入っていたようで、しょっちゅう弾いていました。
中盤、E♭M7で中締めが入った後のB♭からの低音上行リフがカルロス・ベナベントのベースのフレーズです。
2つ目のファルセータ【パコ・クルス】
2つ目のファルセータの詳細は分からないんですが、フレージングやコード使いからして、恐らくパコ・クルスのオリジナルと思われます。
後半のコード使いが特徴的
A→Dmから入るので一瞬シンプルに思うんですが、途中から不協和音的なコードがガンガン入ってきます。
パコ・クルスもそうですが、この当時(1990年代後半)のマドリードのギタリストの流行だったのか、sus4、♭5、♯5というような変化音・付加音が多く、ジャズ系とは違う使い方(緊張状態のまま解決させない、みたいな)なのでかなり特徴があります。
フラメンコ音楽論で形式解説が一巡したら、このあたりのマニアックなところもやっていこうかと。
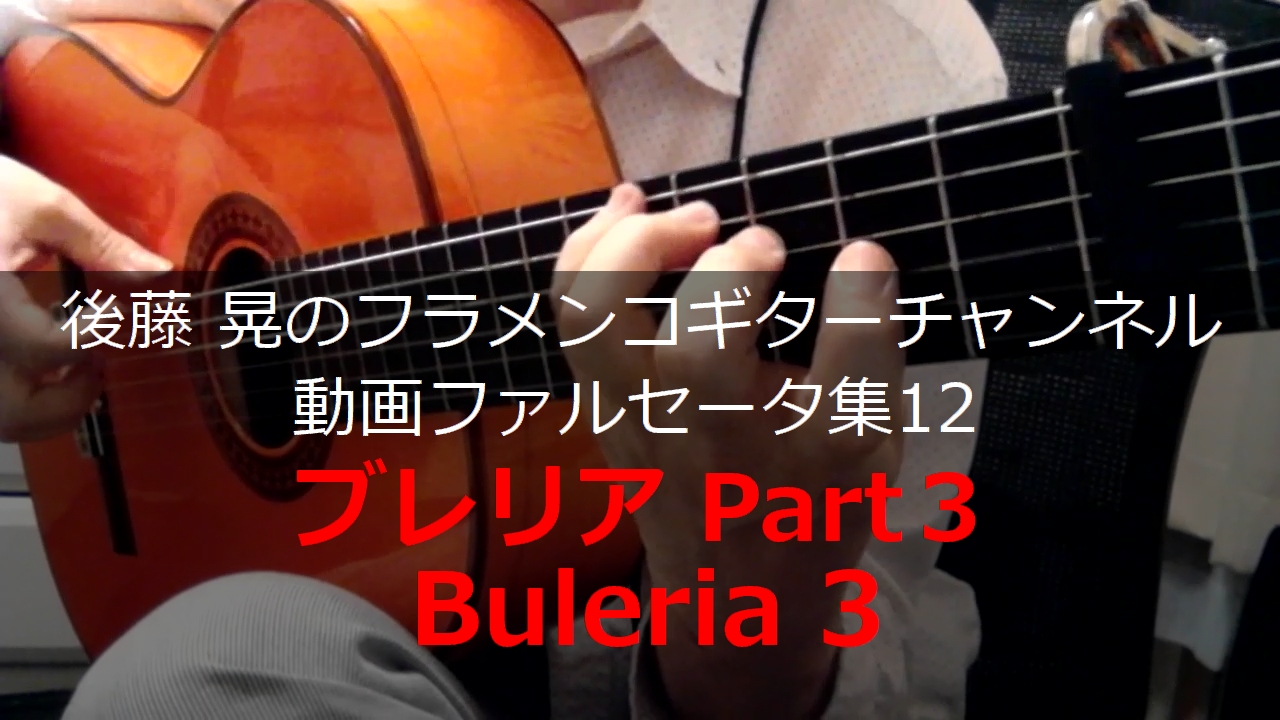

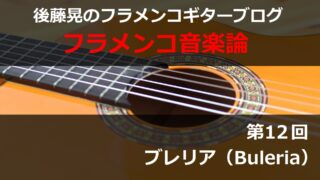
コメント