「Webで学ぶフラメンコギター」では前回までで、フラメンコギターの音の出し方、楽器、弦、爪の作り方などについて解説してきました。
今まではいわば準備編でしたが、これから具体的な演奏技術を学習していきます。
今回は、ギターの構え方と右手のテクニックの基本的な解説をします。
フラメンコギターの構え方
まずは奏法の土台となるギターの構え方から解説しますが、フラメンコギターとクラシックギターではかなり違います。
クラシックギターは左足に足台を使って左足を少し高くしておいて、左の太腿にギターを乗せ、ネックを立てて構えるのが一般的です。
ギターレストを使う場合もありますが、いずれにしてもクラシックギターの場合、左足の側にギターを乗せて構えます。
それに対して、フラメンコギターでは原則的に右の太腿にギターを乗せて弾きます。
これは、単音弾きの精度を追及したクラシックギターに比べて、フラメンコギターではコードプレイ・リズムプレイに重きをおいた結果でしょう。
フラメンコギターの演奏フォームを大別すると4種類の構え方があります。
①伝統的な構え方
まずは伝統的なフラメンコギターの構え方です。
少し膝を開いて座った状態でギターを右の太腿に乗せてネックを立て、右腕の内側と太腿でギターを固定します。

メリットはハイポジションが弾きやすいことですが、右手の運動性はやや制約されます。
サビーカス(Sabicas)やカルロス・モントージャ(Carlos Montoya)あたりの世代より上のギタリストは、ほとんどがこの構え方でした。
②足を組む構え方
次に足を組んだ構えです。
左の太腿の上に右足を乗せて足を組んで、右の太腿の上にギターを乗せて演奏します。
パコ・デ・ルシア(Paco de Lucia)がこの構え方をしていて、以後スタンダードなフォームになりました。

メリットは右腕が完全に自由になるので特にリズムプレイで有利になります。
欠点は腰を痛めやすいのと、ややハイポジションが弾きにくいことです。
③足を組まずに猫背で弾く構え方
①と②の中間的な構え方で、足は組まずに右の太腿にギターを乗せて、ネックは立てずに猫背になってギターに覆い被さるような形で弾きます。

メリットは2.と同様右手が自由になることと、両足が自由になるので足でサイクルを踏みやすいこと。
デメリットはギターが安定しにくく猫背にならないと弾きにくいのと、ハイポジションが弾きにくいことです。
④右足に足台を使った構え方
右足に足台を使って、少し高くした右太腿にギターを乗せて構えます。
マノロ・サンルーカル(Manolo Sanlucar)などはこの構え方でした。

※足台を持っていないので、ティッシュケースを足台にしてます(笑)
②だと腰に負担がかかるし、③だと猫背にならないとギターが安定しない、というのを足台で解消しようという構え方ですね。
しかし、足台は荷物が増えるのと、見た目的に「足台使用はフラメンコぽくない」という理由からなのか、あまり見かけません。
まぁ、右太腿が高くなっていれば良いので、椅子に右足をかけたり、③のフォームから右足だけつま先立ちでになって弾く人もいます。
右手のテクニックの基本
では、これから具体的な演奏テクニックの解説に入っていきますが、フラメンコギターで特殊な奏法が多くて習得が難しいのが右手のテクニックです。
個別に解説する前に、まずは右手のテクニックを総論的に整理・分類しておきます。
指使いの表記について
クラシックギターの楽譜では一般的な表記ですが、この講座では右手のテクニックを解説するにあたって以下の略号を使いますので、おぼえておいて下さい。
p→右手親指
i→右手人差し指
m→右手中指
a→右手薬指
ch→右手小指
アポヤンドとアルライレ
クラシックギターと同様に、フラメンコギターもアポヤンドとアルライレ(アルアイレ)という2種類のタッチの仕方を使い分けます。
アポヤンド
ある弦を弾いたら、その隣(低音側)の弦の上に指を置いて止めるタッチ。周囲の音に埋もれにくい太くてクッキリした音が出る。
アルライレ
ある弦を弾いたら、他の弦には触らずに空中に指を逃がすタッチ。きらびやかで繊細な音が出る。
右手のテクニックの分類
この講座では、フラメンコギターの右手のテクニックを4つのカテゴリーに大別して解説していきます。
- アルペジオ系
分散和音奏法。原則は1音ずつ弦移動する動きになる。ここではトレモロ奏法もアルペジオ奏法の一種と考えるが、トレモロは同一弦連打の動きになる。 - ピカード系
音階奏法。原則はアポヤンドのタッチのmi交互弾弦でスケールを弾く。 - 親指系
アルサプアを含む親指を使ったテクニック。ゴルペ奏法と併用される。 - ラスゲアード系
複数弦を一気に掻き鳴らすテクニック。フラメンコ奏法の象徴。
――次回からは、いよいよ本格的にフラメンコ奏法のテクニック解説に入ります!
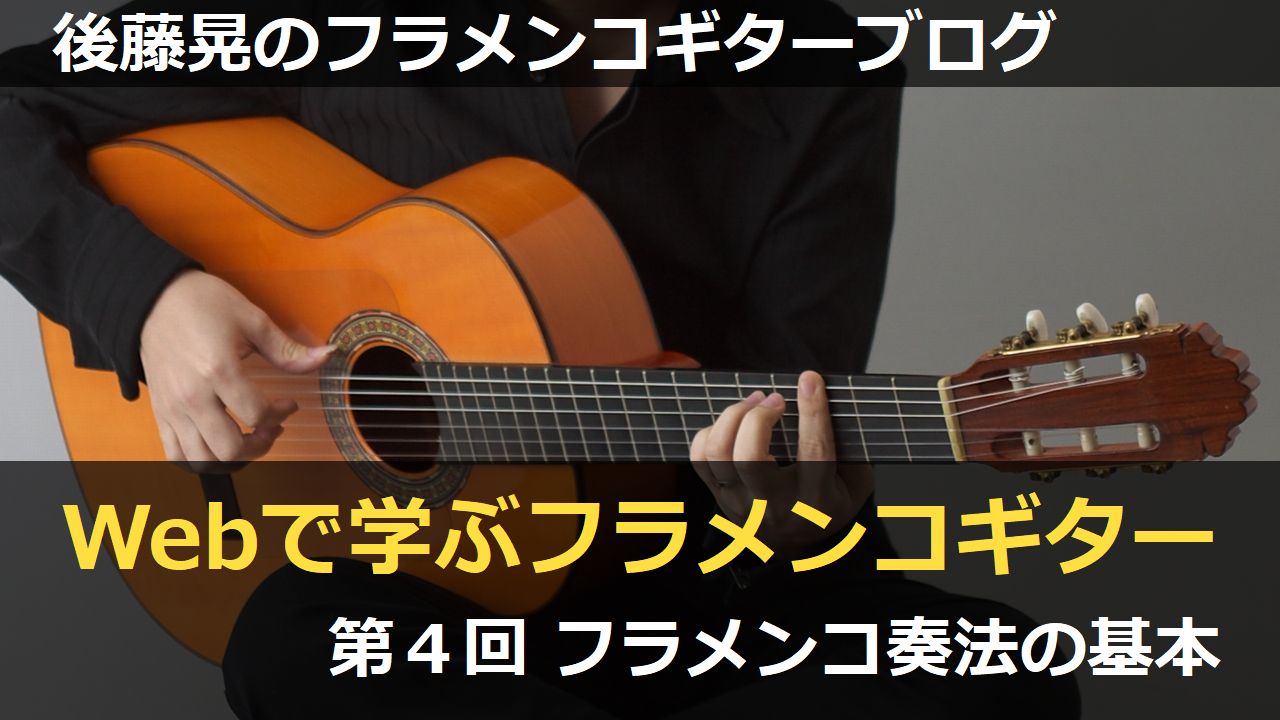
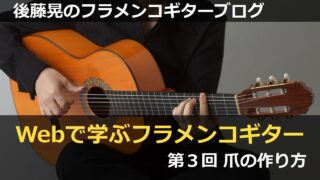
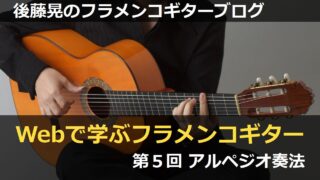
コメント