「Webで学ぶフラメンコギター」も5回目になりますが、今回の講座では前回分類した右手のテクニックのうちの「アルペジオ奏法」をやります。
アルペジオ奏法とは
アルペジオは分散和音のことで、コードを和音ではなく1音ずつバラバラに出すものです。
ギターのアルペジオ奏法の基本は、コードフォームを押さえたまま右手でパラパラと1本ずつ異なる弦を弾いていくのが一般的です。
フォークやロックなどでは、アルペジオ奏法といえば静かなところのバッキングかイントロ・間奏という用途がほとんどですが、フラメンコギターの場合はもっと用途が広く、メロディー的な使い方をしたり、親指奏法やラスゲアードに絡めて修飾音的に使ったりもします。
フラメンコギターのアルペジオフォーム
フォークギターのアルペジオフォームはピックガード上に右手小指で支えをとったりしますが、フラメンコギターでそれはやりません。
フラメンコギターのアルペジオ奏法ではpimaの4指を使い、右手親指を低音弦や表面板の上に置いて支えをとることもありますが、完全に宙に浮いた状態で弾く場合もあります。
クラシックやフォークの場合、アルペジオに使うタッチはほとんどアルライレのみですが、フラメンコではアポヤンドも積極的に使うのがポイントです。
もう一つ特徴的なのが、親指でメロディー(あるいはベースライン)を弾きながらアルペジオする動きが多く、pとiが同じ弦を弾くという場面もあるため、親指と人差し指が干渉しないようなフォームが望ましいでしょう。
人によって手の形が違うのでフォームも違うのですが、フラメンコで使う一般的なアルペジオフォームとタッチの仕方は以下の通りです。
- 弦に対してimaを「水平から45度くらい傾けた角度」の範囲で右掌を構える
- pとiの干渉を避けて指の自由度を上げるため、pは前(ネック側)に突き出すように構える
- pを6弦上(4,5弦上や6弦上側の表面板上の場合もある)に、imaを次に弾く弦上に軽く付けた状態が基本で、そこから指に付いている弦を1本ずつ外す感じで弾く。それが出来ない場合、空中から直接弦にタッチして弾く
- imaをアポヤンドで弾くときは、手首側をやや表面板に近づけて、第1関節を少し反らすようにタッチする

弦に対してimaを水平に構えたアルペジオフォーム

弦に対してimaを45度に傾けたアルペジオフォーム

アポヤンドのタッチのアルペジオフォーム
以上が基本的なアルペジオ奏法のフォームですが、フラメンコギターのアルペジオ奏法は用途ごとに弾き方が異なるので、以下に用途別の解説をしていきます。
一般的なコードアルペジオ
フラメンコギターでもフォークギターなどのバッキングに使うような一般的なコードアルペジオをする事もあります。
この場合は全部アルライレで弾くか、ベース音を強調したい場合、pだけアポヤンドで弾きます。
親指でメロディーを出すアルペジオ
pでメロディーを出すアルペジオはフラメンコ独特の弾き方です。
pで出すラインが主役ですが、残りの指はima3本使う場合もあるし、miの2本、さらにはiだけの場合(pi奏法)もあります。
基本はpをアポヤンド、他の指はアルライレで弾きますが、pが4弦より高音側の弦を弾く時は親指もアルライレにする場合が多いです。
修飾音的な速いアルペジオ
フラメンコギターでは、修飾音やリズムプレイの補助に使われるスピーディーなアルペジオが多用され、上の「親指でメロディーを出すアルペジオ」と組み合わせて使われることも多いです。
この手の速いアルペジオのコツは、脱力した状態からimaの瞬発力を使ってアルライレで音を詰め込むように弾きますが、場合によってはアポヤンド気味にブリブリと弾くこともあります。
imaをアポヤンドするアルペジオ
他のジャンルではみかけませんが、フラメンコギターではimaをアポヤンドで弾くアルペジオもあります。
用途としては、低音弦アルペジオでリズミックなプレイをしたり、アルペジオの最高音にメロディーを持ってきて強調するような弾き方をする時に使います。
最高音のみを強調したい場合は、aのみをアポヤンドで弾くことも。
これにpを併用してベースラインを入れることもありますが、その場合は親指をアルライレで弾くことが多いです。
トレモロ奏法
トレモロ奏法はpで伴奏を付けながらimaで同一弦を連打する奏法で、サスティンの短いナイロン弦ギターでロングトーンのメロディーと伴奏を同時に表現できるテクニックです。
imaは同一弦を連打しますが、弾きたいメロディーによっては弦移動が絡むこともあります。
アルペジオとは別の奏法とも言えますが、テクニック的にはほぼ同じようなフォームで弾けたりして共通項が多いので、ここで扱うことにしました。
トレモロ奏法はクラシックギターから採り入れられたテクニックで、フラメンコギターのトレモロはpiamiという指使いで弾く5連符のものが基本ですが、クラシックギターで一般的なpamiの4連符のトレモロも使われます。
何故5連符になったのか?というのは、フラメンコで良く使うテンポ帯(大体決まっている)で一番綺麗に聴こえるのが5連符だった、という事だと思いますが、全般的にフラメンコは5連符の音形がよく出てきますよね。
トレモロ奏法の弾き方は、上で解説したアルペジオ奏法のうち「親指でメロディーを出すアルペジオ」「修飾音的な速いアルペジオ」と近く、親指で低音弦をアポヤンドで弾きながらimaで高音弦をアルライレで弾いていきます。
コツとしては、piamiを弾き終わった後、次のpが遅れないように意識すると切れ目無く弾けるのではないでしょうか。
修飾的な単発のトレモロ
トレモロを連続させずに単発で使って、同一弦連打による修飾音を出すテクニックがありますが、これは上で解説した「修飾音的な速いアルペジオ」のトレモロバージョンですね。
基本はiamiはアルライレで弾きますが、とくに強調したい時はアポヤンドで弾く場合もあります(その場合はフォーム的にはピカード奏法に近くなる)。
――このように、フラメンコギターではアルペジオ/トレモロ系奏法はかなり幅広い用途で使われ、テクニックとしてもバリエーション豊富なのですが、色んなタイプのファルセータを弾きこなしていくうちに徐々に身についていくものと思います。
次回は、音階を弾くためのピカード奏法をやります。
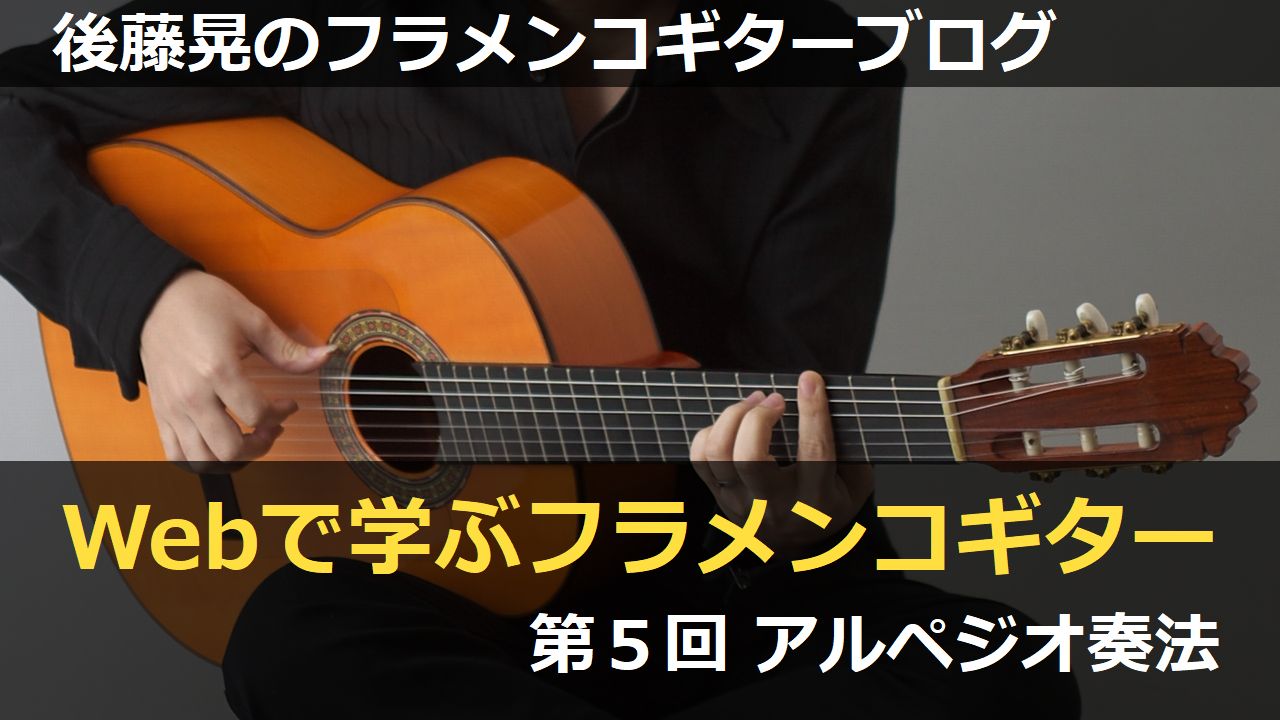
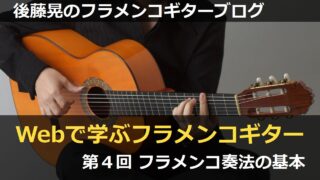

コメント