「Webで学ぶフラメンコギター」では前回「フラメンコギターらしい音」というテーマでお話しましたが、今回は、そういう音を出すための楽器や弦など、ハードウェア面のことをテーマにお話したいと思います。
楽器について
前回解説したように、クラシックギターとフラメンコギターでは求められる音の方向性が違うので、「良い楽器」の条件も異なってきます。
自分もよく「フラメンコギターとクラシックギターの違いは何ですか?」とか「クラシックギターでもフラメンコを弾けますか?」というような質問をよく受けるので、そのあたりまで突っ込んで話をしてみます。
クラシックギターとフラメンコギターの違い
クラシックギターとフラメンコギターの違いですが、最も目立つ部分としては側面板と裏板の材質が違います。
伝統的な側面板と裏板の材質は、クラシックギターならハカランダやローズウッドですが、フラメンコギターはシープレス(糸杉)が主流です。
近年は研究が進んで様々な木材が使われていますが、一般的にはクラシックギターは黒くて重い木材、フラメンコギターは白くて軽い木材が使われています。
そして木材の厚みも違います。
一般にフラメンコギターのほうが薄い木材で作ってあり、同じサイズの楽器でも重さが倍くらい違ったりします。
当然ながら、耐久性はクラシックギターの方が高く、フラメンコギターは割れやすいです。
両用フラメンコギター
フラメンコギターとクラシックギターの材質的な違いは、基本的には上記の通りですが、「黒」「ネグラ」などと呼ばれる、側面板や裏板がクラシックギターと同じ黒い木材で作られたフラメンコギターが存在します。
こういうギターは「両用」ともいわれ、設計はフラメンコギターですが、材質がクラシックギターに近いため、クラシックギターとフラメンコギターの中間的な音が出ます。
「黒」のフラメンコギターは、主にソロ演奏用とされていて、「白」と呼ばれる普通のフラメンコギターよりも低音の腰が強く、遠達性に優れている反面、音の立ち上がりは少し落ちます。
まぁ、これは一般的な傾向で、実際には楽器ごとの個体差や個人の奏法との相性からくる音質差のほうが大きく、「白」でソロを弾く人もいるし、「黒」で踊り伴奏する人もいますが。
ゴルペ板
フラメンコギターはボディーを叩くゴルペ奏法を多用するため、表面板にゴルペ板というプラスチック板が貼ってあります。
フラメンコギターはただでさえ薄い材質で作ってあるし、これが無いとあっという間にボロボロになります。
ゴルぺ板は単体で売っているので、後から自分で貼ることも可能です。
ボディー厚(奥行き)の違い
一般にクラシックギターよりもフラメンコギターのほうが薄く作ってあります。ボディー厚で1cmくらいは違います。
ボディー厚が薄くなると、音量が下がり、とくに低音が出にくくなって音の立体感は低下する傾向ですが、音の立ち上がりと演奏性は向上します。
弦高の違い
まともなフラメンコギターは弦高が低く設定できるように作られています。
演奏技術的には、ここが一番違いが出るところです。
弦高というと、指板と弦の距離というのが一般的ですが、フラメンコ奏法では「表面板と弦の距離」が重要になります。
具体的には駒の部分で表面板から6弦の一番上までの高さが1cm程度に出来れば問題ないのですが、クラシックギターだと駒の造りがそこまでサドルを下げられなかったり、下げられたとしても盛大にビビったりします。
安いギターだとフラメンコギターと銘打っていても、ブリッジなどの造りは大量生産のクラシックギターと同じパーツを使っていて(つまり弦高が下げられない)、ボディ材質だけ白い木で作ってあるものもあるので、ギターを選ぶ際には注意が必要です。
弦長(スケール)の違い
クラシックギターでは標準の弦長が650ミリで、女性や手が小さい人向けに630ミリのショートスケールの楽器も珍しくありません。
これに対してフラメンコギターでは現在主流になっているのは、650ミリから665ミリの楽器です。
古い楽器は640ミリなどのものも多いですが、新しい楽器は650ミリ未満のものはあまり見かけません。
これは以下の要因と思われます。
- スペイン人サイズ(身長はそんなに高くないけど、手は大きい)が基準になってる
- 女性や子供でフラメンコギターをやっている人が少ないのでショートスケールの需要が少ない
- どうせカポをつけると弦長は短くなるので、素の状態ではテンションが低い細い弦を張ってもしっかりした音が出るように、ある程度の弦長があったほうが良い
個人的にはショートスケールの良いフラメンコギターがあれば是非欲しいですが。
クラシックギターでフラメンコは演奏できるの?
昔からよくきかれる質問「クラシックギターでフラメンコはできるのか?」という質問への回答なのですが、結論から言うと、基本的な構造は同じなので、ゴルペ板を貼って、サドルを低く調整してやればクラシックギターでフラメンコも演奏はできます。
例えば、中学生がお小遣いで始めたいので、どうしても1万円以下の予算で!という場合は、激安のクラシックギターを買って、ゴルペ板を貼って、弦高を無理やり下げれば、音はビビりまくると思いますが、最低限の練習はできます。自分も最初の一年くらいそんな状態で練習してましたし(笑)
なんですが、クラシックギターとフラメンコギターでは音の出方や細かい演奏性が違うので、長期間クラシックギターで練習していると変な癖がついてしまうかもしれません。
本格的にやりたいなら、なるべく早い段階でフラメンコギターを一本入手したほうが上達も早いでしょう。
今なら5万円程度から手に入るし、中古も視野に入れて探せば安くても良い楽器はありますので。
弦の違い・弦の選び方
フラメンコギター用の弦に関してもよく質問を受けるのですが、基本的にはクラシックとフラメンコは弦は同じものを使います。
メーカーによってはフラメンコ専用弦というパッケージにして売っている場合もありますが、一般的なクラシック用の弦とそんなに大きな違いは無いです。
では、何の弦を張ったら良いのか?というと、こればかりは弦の銘柄と楽器の組み合わせの相性が非常に大きいので、実際に張ってみて時間をかけて弾きこまないと、なかなかベストの弦を選定するのは難しいでしょう。
フラメンコギターの弾き方との相性ということで言うと、自分の経験では以下のように感じます。
- 研磨弦は相性が良くないことが多い
- 同じテンションなら細いゲージのほうが音がボケない
- 少し柔らか目のテンションの弦を張ってしっかりタッチしたほうが良い
あとは、価格と耐久性、入手性、そして楽器との相性で選ぶわけですが、現時点で入手性が良くて、音も良い弦ということで、いくつかお薦めの銘柄を挙げてみます。
プロアルテ ノーマルテンション・ハイテンション
型番はJ45(ノーマルテンション)、EJ45(簡易包装ノーマルテンション)、J46(ハイテンション)、EJ46(簡易包装ハイテンション)。世界の標準弦。安定品質。入手性は最高。
最も無難な選択ですが、個性に乏しいとも言えます。ライトテンションもありますが、入手性が落ちるし、ノーマルテンションでもかなり柔らか目なので、ノーマルテンションがお薦めです。
サウンドハウスで購入

DADDARIO / EJ45 Pro-Arte Silver/Clear/Normal
ラベラ 2001フラメンコ
ブラックナイロンの高音弦はギターとの相性によってはとても良いですが、低音弦は少し癖のある音です。
サウンドハウスで購入
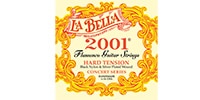
La Bella ( ラベラ ) / 2001 Flamenco – Hard Tension
サバレス
低音弦はカンティーガがお薦め。高音弦はアリアンス(フロロカーボン)、ニュークリスタル(ナイロン)などがあり、フラメンコ用にトマティートというセットも出ています。
サバレス弦は総じて煌びやかな音色ですが、音質劣化も早めな印象です。
カンティーガ・プレミアムは値段がやや高いですが、新素材で長寿命を謳っています。
サウンドハウスで購入
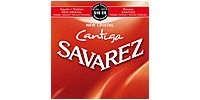
SAVAREZ / クラシックギター弦
ハナバッハ 黒・緑・黄
高品質、高音質。クラシック寄りの艶があって上品な音色です。
欠点はテンションのわりに高音弦が太くてやや音がボケやすいのと、4弦の巻弦が細くてヘタりやすい事です。
サウンドハウスで購入

HANNABACH / クラシックギター弦
オーガスチン 黒・赤・リーガル
価格が安くて暖かい音色です。
ただ、品質にばらつきがあって高音弦のピッチがイマイチという話も。
紫のリーガル(高音弦のみ)は値段は若干高くなりますが信頼性は上がります。
サウンドハウスで購入

AUGUSTINE / クラシックギター弦
ちなみに、自分は20年間くらいルシエール赤の低音とセシリア赤の高音の組み合わせで使っていましたが、どちらも入手困難になってきたので、今はプロアルテ、ラベラ、サバレスから楽器との相性でチョイスしています。
ルシエール(2021年3月加筆)
最近、ルシエール弦が製造再開したようです。
低音弦が音質、寿命ともに素晴らしいので、自分もまた使うつもりです!
サウンドハウスで購入
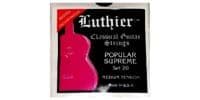
LUTHIER ( ルシエール ) / SET20
弦交換について
弦交換の時期についても良く質問されるんですが、ナイロン弦の場合、低音弦が痛みやすく、とくに4弦が一番早くヘタります。
低音弦は5ミリずらし
低音弦はフレットに当たる箇所が凹んできて、音質がボヤけてピッチが悪くなったら交換時期です。
演奏時間が長いと、1週間くらいでヘタってきますが、延命措置として弦を一度緩めて、5ミリくらいズラして張り直すとフレットに当たる箇所が変わるので寿命が延びます。
本格的にヘタる前に5ミリずらしをやっていきますが、数回やると弦がボコボコになってくるので、そしたらもう交換しましょう。
高音弦もピッチがあやしくなる前に換える
高音弦は目視でダメージがわかりづらいので長期間張りっぱなしにしてしまいがちですが、知らないうちにピッチが悪くなったり倍音が減ったりしていて、張り替えたら突然音が良くなって驚くことがあります。
音質は好みもありますが、チューニングがあやしくなるのは致命的なので、高音弦も早めに替えていきましょう。
自分も最近演奏動画を録るようになってから、動画チェック時に高音弦の音程が気になるようになって、それから高音弦の交換頻度を増やしました。
演奏時は気付きにくいですが、録画を後で聴くと弦のピッチの悪さが凄く気になるんですよね。
効率的な弦交換
趣味でやっている方でそんなに毎日何時間も弾くのでなければセット弦で買って「低音弦は何回か5ミリずらしして、いよいよ低音弦が死んできたら、高音弦も一緒に交換」というのがお薦めです。
プロや、それに近い時間演奏する人は、低音弦だけ多めに買って、低音弦を交換するとき、2回に1回は高音弦も変える、とか。
自分は練習用ギターは本格的にヘタるまで弦を張っていますが、本番や録音に使うギターは早め早めに、定期的な弦交換をしています。
本番用ギターの弦交換時、張ってあった弦のダメージが少なかったら、それをそのまま練習用ギターに張ったり。
ちなみに本番用より練習用ギターのほうが触る頻度は10倍くらい多いと思います。
自分もそうやってなるべくランニングコストを節約していますが、それでも年間で20セットくらいは弦を消費するので、バカにならない出費ですよね。
カポタストについて
フラメンコでは歌い手の声の高さに合わせるためにカポタスト(スペイン語ではセビージャという)を常用します。
ファルセータなどもカポタスト使用を前提に作ってあるものも多いし、カポタストを付けることで音が引き締まってフラメンコらしい音が出しやすくなるので、歌が入らなくてもカポタストを付けたりします。
カポタストには昔ながらの木製のネジ式のものと、ワンタッチ式のものがあります。
見た目などからネジ式を好む向きもありますが、ネジ式は左手に干渉するし、カポの位置を変えるときに少し時間をがかかったり、たまに本体と留め具を繋いでいる糸(ギターの高音弦?)が切れたりするので、ワンタッチ式のほうが実用的です。
ワンタッチ式のカポタストは、左手に干渉しない作りのものが良いでしょう。
よく使われているものに、昔からあるダンロップ製の布バンドのものと、Shubbのような金属製のものがありますが、ダンロップ製のものはずっと使っていると布バンドが突然切れたりするので(自分も経験あり)金属製のもののほうが信頼性は高いです。
Webで学ぶフラメンコギター 前回
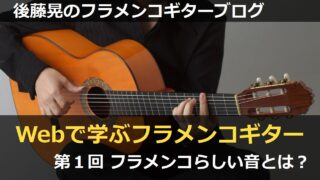
Webで学ぶフラメンコギター 次回
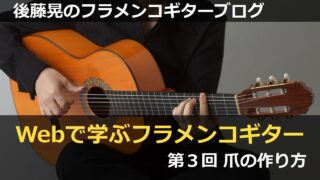
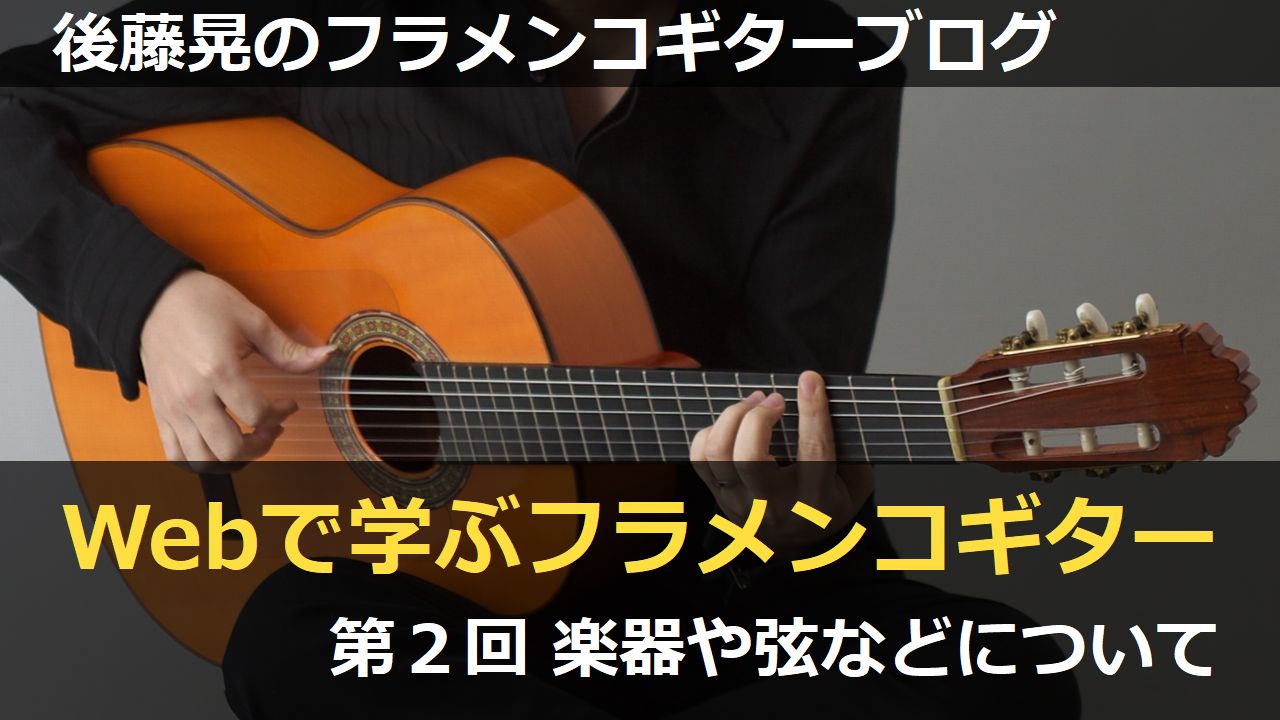
コメント