前回、フラメンコで使われる音階とコードについてやりましたが、今回は「コードスケール」の概念を使って、さらに掘り下げてみたいと思います。
一般的なメジャーキー・マイナーキーのものに関しては「音楽理論ライブラリー」を参照していただくとして、今回も「ミの旋法」中心の話になります。
今回も音楽系以外の方にとっては退屈かもしれませんが、考え方だけでもくみ取っていただければ、と思います。
フラメンコで求められる即興性
フラメンコギターでは譜面はほとんど使いません。
とくに伴奏では歌のコード変化や踊りのリズム変化・展開変更に即応しなければならず、手持ちのネタをその場で作りかえたり、アドリブで合いの手を入れたりする必要が出てきます。
ギタリストが2人いる時に、1人がもう1人のコードプレイに乗っかって、インプロビゼーションをとる場面もあるでしょう。
フラメンコではモダンジャズ等ほどの専門的なインプロビゼーションは必要とされませんが、咄嗟に合いの手を入れたり、踊りに合わせて、その場でファルセータを作ったりする能力はかなり重要です。
モードとコードスケール
今回はまだリズム要素には触れずに、コードや曲展開の変化(ファルセータの長さが急に変わったり)に対応するやり方を考えます。
具体的には「モード(旋法)」と「コードスケール」の応用です。
これは即興演奏だけでなく、リハーサルの現場でファルセータを指定サイズに作り変えたり、ファルセータを作曲したりするのにも必ず役立つと思います。
モードとコードスケールについては以下の記事で解説していますので、ご覧になってください。
ミの旋法にコードスケールを設定してみる
簡単にいうと、コードスケールは「コードとスケールを1対1で対応させて、スムーズに即興演奏が出来るようにしよう」という考え方ですが、このコードスケールの考え方をミの旋法に当てはめるとどうなるでしょうか?
前回と同様に、ポルアリーバ(Eスパニッシュ)を例にしますが、まずはG♯音を含まないダイアトニックコードについて考えます。
臨時記号がつかない範囲ということですが、これはCメジャー・Aナチュラルマイナーと平行調なので、7つのモードスケールがそのまま適用できます。
G♯を含まないEスパニッシュ調のコードスケールは以下の通りになります。4和音で書きます。
- Em7(Ⅰm7)Eフィリジアン
- FM7(♭ⅡM7)Fリディアン
- G7(♭Ⅲ7)Gミクソリディアン
- Am7(Ⅳm7)Aエオリアン
- Bm7(♭5)(Ⅴm7(♭5))Bロクリアン
- CM7(♭ⅥM7)Cイオニアン
- Dm7(♭Ⅶm7)Dドリアン
ルート音が違うだけで、Cメジャー、Aナチュラルマイナーと全く同じものですよね。
G♯音を含むコードのコードスケール
スパニッシュスケールはフィリジアンにM3(ポルアリーバならG♯音)を混在させたもので、ミの旋法のフラメンコ形式で最重要なルートコードとなるⅠ、Ⅰ7はスパニッシュスケールのM3音をⅠコードに反映させたものです。
ⅠとⅠ7の扱い
前回、ポルアリーバ(Eスパニッシュ)で出てくるG♯を含むダイアトニックコードのうち、ルートコードであるEとE7以外はほとんど使われない、という話をしました。
つまり、ノンダイアトニックコードを別にすると、ポルアリーバで(とくに難しいことをやらない場合)注意すべきはEとE7ということになります。
では、ポルアリーバでのE、E7のコードスケールはというと、これは前回やったEスパニッシュスケールを使います。フィリジアン+M3ですね。
構成音的にはハーモニックマイナー・パーフェクト5thビロウ(HMP5B=1,♭2,M3,P4,P5,m6,m7)でも間違いではありませんが、HMP5Bはドミナント用のコードスケールですので、単純にHMP5Bのフレーズを当てはめても、いまいちフラメンコぽくはならないと思います。
言葉で表現するのは難しいですが、Ⅰmへの解決を前提としたⅤ7解釈のHMP5Bと、ルート解釈のスパニッシュスケールではフレージングが違うんですよね。
ただし、ポルアリーバのE7でも次のコードがAmの場合、HMP5B的な動きになったりもしますが。
その他のG♯音を含むコードスケール
前回のフラメンコ音楽論04でやったように、スパニッシュスケールのM3を反映させたダイアトニックコードも考えられます。
これらのコードはEスパニッシュスケールをⅠ、Ⅰ7以外のコードに対して使った時に発生するものなので、スケールも「Eスパニッシュスケールの転回型」という感覚で良いと思いますが、ジャズ的な発想で個別にコードスケールを設定するなら以下のような感じでしょうか。ポルアリーバを例にして書きます。
- E7(Ⅰ7)スパニッシュ
- FmM7(♭ⅡmM7)リディアンマイナー(リディアン♭3)、メロディックマイナー
- G♯dim7(Ⅲdim7)ディミニュシュスケール
- AmM7(ⅣmM7)メロディックマイナー
- CM7♯5(♭ⅥM7♯5)リディアンオーギュメント、イオニアン♯5
- Dm7(♭5)(♭Ⅶm7(♭5))ロクリアン、ドリアン♭5
これでだいたいはマッチングがとれそうですが、こうやって細分化してスパニッシュスケール転回形以外の音が入ったスケールを使うと、フラメンコぽさは薄れてジャズに寄ったフレージングになっていきます。
ノンダイアトニックコードへの対応
では、ミの旋法の形式で出てくるダイアトニックトニックコード以外のノンダイアトニックコードにはどう対処したら良いのでしょうか?
ポルアリーバでよく使われるノンダイアトニックのコードスケールを例にして考えてみましょう。
セカンダリードミナント
フラメンコで出てくるセカンダリードミナントも一般の音楽と扱いは同じです。
ポルアリーバでの例を挙げると、D7→G、C7→Fなど、次にメジャー系コードに5度進行するコードならミクソリディアンを適用。
B7→E7、A7→Dmなど、次にマイナー系コードに5度進行するコードなら(ポルアリーバ上でのB7→E7、A7→Dmなど)HMP5Bを使用します。
ちなみに上記のB7→E7進行について、ルートコードのE7はM3を含みますが、ベースとなっている元のコードスケールがフィリジアン=マイナー系ですので、B7→E7はマイナー系ドミナント進行と捉えます。
弾いてみれば感覚的にわかると思います。
F7(♭Ⅱ7)とB7(Ⅴ7)
では、F7(♭Ⅱ7)とB7(Ⅴ7)はどうでしょう?
これらもフラメンコではよく出てくるノンダイアトニックコードで、表コーとド裏コードの関係になるドミナント7thコードで、どちらもⅠやⅠmに対して強いドミナント機能を持っています。
コードスケールは、F7(♭Ⅱ7)のほうはミクソリディアンでも可ですが、F7はFM7のリディアンが変化したものですので、リディアンの7thが半音下がったリディアン7th(1,2,M3,♯4,P5,M6,m7)が一番マッチします。
F7と表裏の関係にあるB7(Ⅴ7)のほうは、リディアン7thの転回形のオルタード(1,♭2,♯2,M3,♭5,m6,m7)でも良いですが、フラメンコの奏者はBハーモニックマイナーP5Bか、Bスパニッシュを使う場合が多いです。
フラメンコ的なミの旋法の平行移動
もう一つ、ノンダイアトニックコードで留意すべきなのは、フラメンコの場合「ミの旋法の平行移動による一時転調」が多用されるという点です。
例えばポルアリーバなら以下のような転調があります。
- A♭→Gの進行が出てきてGスパニッシュ調に行く=短3度転調
- B♭→A(またはAm7)がきてAスパニッシュ(ポルメディオ)に行く=4度転調
- C→B7がきてBスパニッシュに行く=5度転調
メジャーキーやマイナーキーの形式でも、平行調のスパニッシュ調や、さらに他のスパニッシュ調へ転調したりします。
例えば、Eメジャーキーのアレグリアスで平行調のG♯スパニッシュ調は普通に行きますが、Bスパニッシュ調(=平行調からの短3度転調)や、C♯スパニッシュ調(=平行調からの4度転調)などに行くこともあります。
コードスケールとしては該当のスパニッシュスケールを使用します。Gのスパニッシュ調に転調ならGスパニッシュスケールですね。
その他ノンダイアトニックコードへの対応
その他のノンダイアトニックコードへの対応については、フラメンコの場合、ギタリストによってまちまちなのが現状ですが、一般的なノンダイアトニックコードのコードスケールは以下の記事にまとめましたので参考にして下さい。
ちなみに、上の記事内でも扱っているオルタードやコンディミはジャズフレーズと一体になっているので、それをそのまま応用すると、どうしてもジャズっぽくはなります。
このあたりは、どうすればフラメンコの音楽に上手く溶け込ませることができるのか、自分もフレージングなどを研究中です。
音楽理論をやる意味
このようにコードスケールは「場面場面で使う音階をはっきり把握できる」というメリットがありますが、これが音楽の全てというわけでもなく、あくまで一つの方法であり「一般的な音楽ジャンルで作曲やインプロビゼーションをする際に違和感のある音を出にくくする」ためのものだと思います。
そして「このコードには絶対このスケールが正解!」というのも本当はありません。
ただ、あまりたくさんの可能性を意識すると、考えることが増えて反応が遅れたりするので、敢えて使うスケールを限定しておこう、という方向の理論体系ですね。コードスケールやモードは。
全ての音楽理論は音楽を演奏・作曲するのに、多くの人が自然の流れと感じる音の組み合わせを、最大公約数的に皆が共有できるように体系化してあるものです。
音楽理論が全てわかったからといって、それだけで良い音楽が作れたり、素晴らしい演奏ができるわけではありません。
しかし、音楽を論理的に把握するのに他に方法が無いのも事実で、中でも汎用性が高いコードスケールやモードの考え方は大変有用と思います。
前回、今回と解説したものは、これからフラメンコ音楽の謎に挑むに当たって「考え方の土台」として捉えていただきたいです。
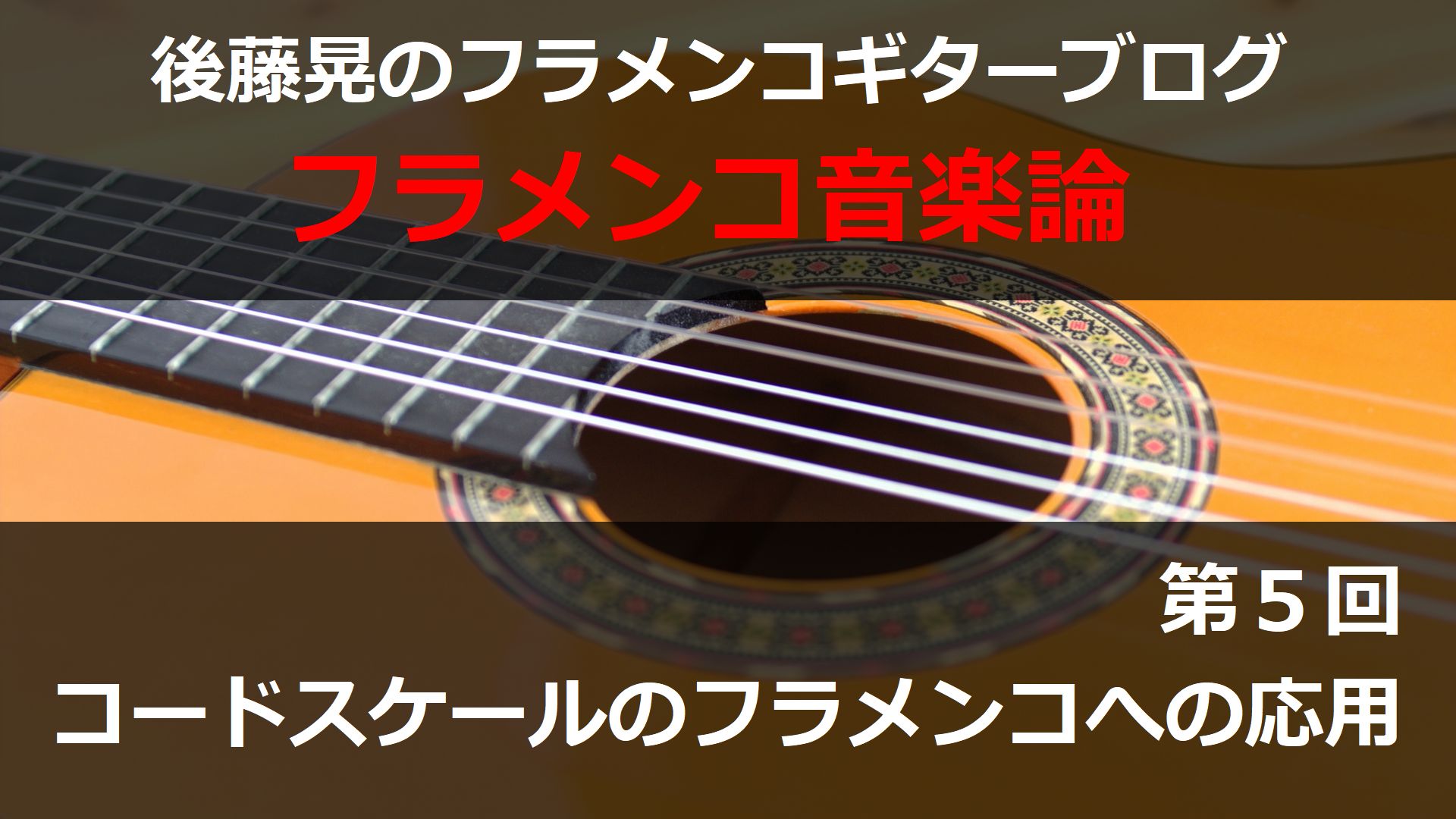
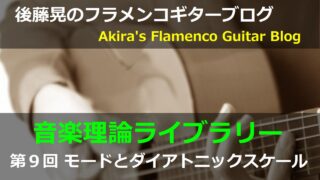
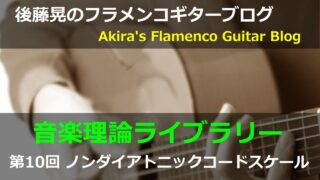
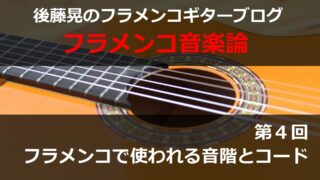
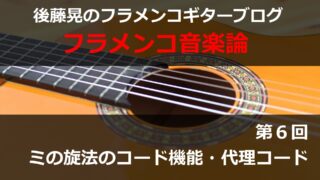
コメント