ファルセータ演奏動画集第38弾は、前回のブレリアPart9に続きブレリア2連発です。
今回のファルセータは、リズムの取り方がかなり面白いというか、理解しにくいかも知れないので、今回はブレリアのリズムの話から入ろうと思います。
ブレリアの6拍グルーヴ
ある程度フラメンコをやっている人は共通認識として持っている事と思いますが、ブレリアは最もフラメンコらしい形式であり、ブレリアのコンパスは現代フラメンコの屋台骨です。
ブレリア形式解説
この形式解説にも書いていますが、ブレリアは発生学的にはソレアがベースになりました。
それが、徐々にテンポが速くなって、リズムの遊びが増えて、という具合に発達してきたものですが、現在ではロックで言う8ビートのように、ブレリアの6拍グルーヴはフラメンコの最も基本的な共通リズムパターンとなっているのです。
フラメンコのリズム形式は沢山ありますが、12拍子、3拍子、さらにはシギリージャ系などにおいても、ブレリアのグルーヴやフレーズが応用されて、いたるところで顔を出します。
ちなみに2拍子系の場合はタンゴ(またはルンバ)の4拍グルーヴが使用されますが、ブレリアもタンゴも同じようなバックビートが強調されたリズムパターンであり、スペイン人は12拍カウントではなく「タンゴ+2拍=ブレリア」みたいな捉え方をしているような節はありますよね。
このブログでも「コンパス=サイクル論」で「6サイクルコンパス」として解析を試みていますので、是非ご一読を。
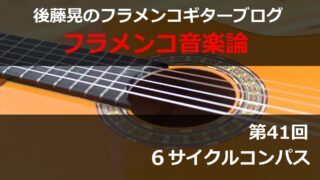
そんなブレリアの6拍グルーヴ発生の本拠地はヘレス・デ・ラ・フロンテラ(Jerez de la Frontera)という小さな辺境の街(実際に行くとソコソコの街ですが)で、そんなローカルなレアグルーヴが核となっているフラメンコというジャンルって、本当に一筋縄では行かないですよね。
今回演奏の2つのファルセータ
リズムの話が長くなりましたが、今回の演奏は、今書いたようなブレリアの6拍サイクルに習熟していないと難解に感じるかもしれません。
今回の2つのファルセータは両方ともマドリードでパコ・クルス(Paco Cruz)に教わったもので、基本的にはマドリードスタイルのブレリアですが、少しヘレス的なノリも入っていたりで、なかなか面白いフレージングですよね。
2つともメディオコンパス単位で作られていて、12拍でとると「あれれ?」となるので6拍でとりましょう。
ブレリアはソレアとの関係性から日本では12拍カウントで教わることが多いですが、上で書いた通り、実運用上はほぼ6拍子なのです。
以下、個別に解説いたします。
1つ目のファルセータ【パコ・クルス】
1つ目のファルセータはフレージングからしてパコ・クルス本人の作ではないかと思います。
コード的にはシンプルなように見えて、ピンポイントで変化音をぶち込んで来るのがカッコいいですよね。
とくにB♭7の7度音であるA♭の音の使い方がポイントですが、後半ではB♭mM7コード出てきたり、よく聴くとマニアックなファルセータです。
そしてリズムが裏ばかりなので、速いテンポで安定して弾くには相当の慣れが必要になります。
2つ目のファルセータ【パコ・クルス】
友人のギタリストからの情報によると、このファルセータの前半部分はどこかのバル(飲み屋)のマスターが作って、後半部分をパコ・クルスが継ぎ足して完成させたという話です。
このファルセータは冒頭のB♭9の2拍3連のインパクトが全てだと思うし、実質、そのバルのマスターの作と言って良いかと。
コード的にはメジャー7thコードの平行移動が多くて、なんというかプログレっぽい作り方ですが、フィーリングはしっかりフラメンコですよね。
そして、1つ目のファルセータに負けず劣らず、リズムキープがしんどいパターンで、テンポがある一定以上になると急激に難易度が増します。
ちなみに、動画の演奏は225BPMです。
235BPMくらいでも弾けないことは無いんですが、リズムが甘くなりがちで、テイク数が激増しそうな雰囲気だったので、少しテンポを落として演奏しました。


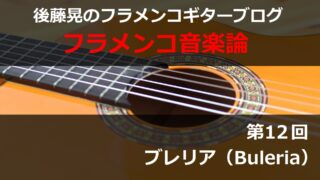
コメント