「フラメンコ音楽論」では、今回からリズム形式(パロ)に話を進めようと思っていましたが、リズム形式の解説に行く前に、フラメンコ音楽で使われる音階やコードについて触れておきたいです。
今回は音楽家・楽器プレイヤー向けの内容となりますが、専門知識が無くても理解しやすいよう書いてみようと思います。
ここで使われる表記や用語については「音楽理論ライブラリー」にて解説していますので、こちらの記事をご覧ください。
フラメンコで使われる音階
フラメンコの形式(曲目)で使われる調性は以下の3種類に大別できます。
- メジャーキー(長調)
- マイナーキー(短調)
- ミの旋法(ポルメディオ、ポルアリーバなど)
メジャーキー、マイナーキーに関しては一般音楽理論の範疇ですので「音楽理論ライブラリー」扱っています。
ここではフラメンコ音楽特有の「ミの旋法」についてお話します。
「ミの旋法」はモード(教会旋法)でいうとフィリジアン(ミの音から始める音階)に近いもので、コードスケールでいうとスパニッシュスケールになります。
このスパニッシュスケールと呼ばれる音階は、フィリジアンの音に加えてメジャー3rd(長3度、以下M3)の音も入ってきます。
このM3の絡め方が、フラメンコらしいフレージングということに繋がっていくわけですが、ブルース・ジャズ系音楽のブルーノートの使い方とちょっと似ています。
別の捉えかたをすると、ハーモニックマイナー・パーフェクト5thビロウに♯9が入った音階ともいえます。
ミの旋法=スパニッシュスケールの構成音は以下の通りになります。
- 1(ルート音。ポルアリーバならE、ポル・メディオならA、ポル・タラントならF♯)
- ♭2(減2度)
- m3(短3度)
- M3(長3度)
- P4(完全4度)
- P5(完全5度)
- m6(短6度)
- m7(短7度)
このうち、特殊なのがやはりM3の使い方です。
ポル・アリーバで解説すると、ルートコードであるEコードのメジャー3rdにあたるG♯音がEコード以外のコード上でも使われたりして、結果的にちょっと変わったテンションノートみたいになったりします。
これ、多分ですが、歌い手が遊びでコードの先取りとかをして伴奏とズラして歌ったりしていた感覚を、ギターで表現したものがフラメンコ的なテンション使いとして定着したものではないでしょうか。
そういう半音ズレたような響きがモデルノ系ギターのコードボイシングでもかなり使われるんですよね。
そういう音使いを自分は「フラメンコテンション」と呼んでいますが、これから度々出てくる言葉なので、おぼえておいて下さい。
ミの旋法で使うコード
コードボイシングの話が出ましたので、ミの旋法で使われるコードについてお話します。
メジャーキー、マイナーキーにはいわゆるダイアトニックコードという概念があります。
ダイアトニックコードは調性を構成する基本となるコード群です。
一般的なダイアトニックコードについては、詳しくは以下の記事を参照してください。
ミの旋法にダイアトニックコードを設定してみる
今までちゃんと理論化されていませんが、自分はミの旋法にもダイアトニックコードは設定出来ると考えています。
調号無しのCメジャーキーの平行調であるEのスパニッシュ調=ポルアリーバで説明します。
長3度音を含まないダイアトニックコード
まず、ルートコードEのメジャー3rdであるG♯音を含まないものを考えてみましょう。
これは要するにEフィリジアンと同じものであり、Cメジャー・Aナチュラルマイナーと平行調になるため、ダイアトニックコードもそれらと共通です。4和音で書きます。
- Em7(Ⅰm7)※ルートコードとしては下で出てくるⅠ7のほうを主に使います
- FM7(♭ⅡM7)
- G7(♭Ⅲ7)
- Am7(Ⅳm7)
- Bm7(♭5)(Ⅴm7(♭5))
- CM7(♭ⅥM7)
- Dm7(♭Ⅶm7)
となります。ノーマルな響きですね。
長3度音を含むダイアトニックコード
次にG♯音を含むものです。
- E7(Ⅰ7)
- FM7(♭ⅡM7)
- FmM7(♭ⅡmM7)※G♯音を3rdにとった場合
- G7(♭Ⅲ7)
- G♯dim7(Ⅲdim7)
- Am7(Ⅳm7)
- AmM7(ⅣmM7)※G♯音を7thにとった場合
- Bm7(♭5)(Ⅴm7(♭5))
- CM7(♭ⅥM7)
- CM7♯5(♭ⅥM7♯5)※G♯音を5thにとった場合
- Dm7(♭Ⅶm7)
- Dm7(♭5)(♭Ⅶm7(♭5))※G♯音(A♭音)を5thにとった場合
こちらは8音階だし、Aハーモニックマイナーのダイアトニックコードも含まれてきてかなり複雑になりますが、G♯音を含まないものに比べると、以下のコードが追加されることになります。
- E7(Ⅰ7)
- FmM7(♭ⅡmM7)
- G♯dim7(Ⅲdim7)
- AmM7(ⅣmM7)
- CM7♯5(♭ⅥM7♯5)
- Dm7(♭5)(♭Ⅶm7(♭5))
かなり不協和音ぽいのもありますが、この中で伝統的なフラメンコで使われるのはⅠのE/E7のみです。
他のコードは理論上は使用可能だし、自分としては凄く面白い可能性を感じますが、使われる場面は限られます。
前項目で触れたフラメンコ的な半音ぶつかり系のテンション=フラメンコテンションも、使われる形というのが大体決まっていて、具体的なギターコードについては、こちらの記事で詳しくまとめています。
ミの旋法で使うノンダイアトニックコード
ダイアトニックコード以外のコードをノンダイアトニックコードといって、一般的にはこれが出てくると譜面上で臨時記号が付くことになります。
ノンダイアトニックコードについては以下の記事で解説しています。
ミの旋法では、ポルアリーバを例にすると、G♯音が出てくると譜面上では臨時記号が出ることになりますが、上でダイアトニックコードを設定したようにG♯音をダイアトニックノートとして扱うので、ここでは、G♯音以外のノンダイアトニックトーンが含まれるコードについて解説します。
以下、ポルアリーバ(Eスパニッシュ調)を前提としてお話します。
ポルアリーバで出てくるノンダイアトニックコードですが、例えば、B7(Ⅴ7)とかD7(♭Ⅶ7)とかC7(♭Ⅵ7)あたりが良く使用されます。
これらはセカンダリー・ドミナントと呼ばれ、次のコードを5度上(=4度下)のドミナント7thコードで補強・強調するもので、あらゆる音楽ジャンルに出てきます。
上で挙げたB7、D7、C7の3つのコードを例にすると、B7→E、D7→G7、C7→F、A7→Dmというふうに使います。
ちなみに、ジャズの常套句のⅡm7→Ⅴ7→Ⅰは、フラメンコだとⅡ7→Ⅴ7→Ⅰという形のほうが多いです。
フラメンコではブルースやジャズみたいにあらゆるコードをドミナント7th化して演奏したりするんですが、とくにF7(♭Ⅱ7)のE♭音を強調するのはEへの進行でよくやる形で、フラメンコぽいと思います。
E♭音からⅠコードのルートであるE音に半音進行できるため、♭Ⅱコードのドミナント的働きを強化する音です。
ミの旋法で最も重要な進行
最後になりましたが、ミの旋法で使用されるコードのうち、最も重要な進行であり、一番力点を置くべきポイントがあります。
それは、♭ⅡからⅠ(ポルアリーバならFからE)への解決のさせかたです。
途中の展開は、全てそこに持っていくための過程というのが、ミの旋法上の音階・コード進行の特色です。
ここのフレージングがダサいと全て台無しなので、一番のポイントと言えます。
次回は、ミの旋法を「コードスケール」という概念に当てはめてさらに掘り下げてみようと思います。


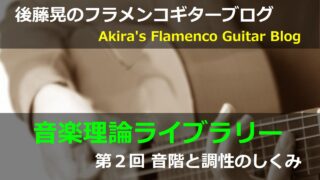
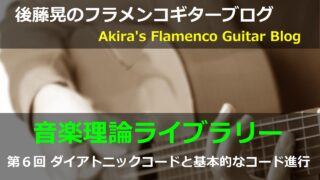
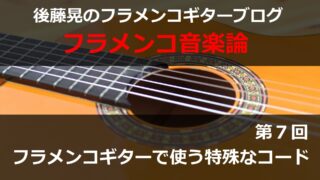
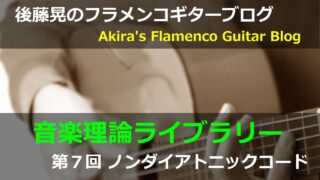
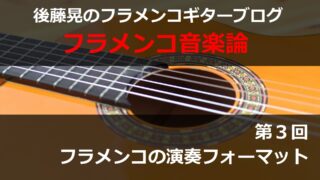
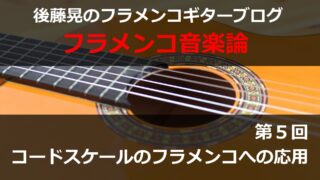
コメント
Cメジャースケールの平行調がAマイナースケール、Aマイナースケールの平行調がCメジャースケールというのが平行調という言葉の定義ですがこの場合はフリジアンスケールも平行調というのでしょうか?
>>ドリアンさん
メジャーキー、マイナーキーのみの一般的な概念だと
フィリジアンスケールは転回形=コードスケールの一つということになりますが
拡大解釈してIII、IIIm7(マイナーならV,Vm7)をI,I-7ととらえると
Eフィリジアン=Eスパニッシュ=Aマイナー=Cメジャー
つまり平行調としてとらえることが可能と思います。
一般的にはこのあたりはしっかり理論化されていないので、これは自分の解釈です。
この解釈は他のモードスケールでも成り立つので
音楽の可能性は一気に広がると思っているんですが。
返信ありがとうございます。
つまりフリジアン、スパニッシュ含め、イオニアンからロクリアンまで全てを平行調とみなすということでしょうか?
>>フリジアン、スパニッシュ含め、イオニアンからロクリアンまで全てを平行調とみなすということでしょうか?
そういうことになります。
フラメンコはフィリジアンベースですが、
例えばブルースなどブルーノート系の音楽は
ドリアン・ミクソリディアンをベースにした調性ととらえることもできます。
ブルース系の音楽まで拡大解釈するなら
Cメジャー=Dマイナーブルース(ドリアン)=Eスパニッシュ=Gメジャーブルース(ミクソ)=Aナチュラルマイナー
となります。
コードの並び方やメロディのフレージングでルートに感じる音が変化します。
ブルースでドリアンやミクソリディアンを使うときはm3とM3併用で、b5なんかも入ってきます。
ブルースメジャーをドリアン寄りで弾くかミクソ寄りで弾くか、ということになります。
ちなみにスパニッシュもm3とM3併用ですし、そのへん本気で解析するとかなり大変ですが
この考え方はモードスケール以外にも適用できるし
とくに民族音楽系の分析に役立つと思います。