「フラメンコ音楽論」では、そろそろリズム形式の解説に入る予定でしたが、リズム形式の解説が一番時間がかかると思いますので、その前にスケール・コードなどの音程関係のことを一通りやっておこうと思います。
前回までで、フラメンコの音楽で使用するコードやスケール、フラメンコ独特の語法である「ミの旋法」について学習してきました。
今回はさらにもう一歩進めて「ミの旋法」における「コード機能」「代理コード」という事を考えてみます。
今回の記事の基礎知識として「音楽理論ライブラリー」の記事を読んでいただくことをお勧めします。
コード機能
一般的な音楽にはコード進行があり、コードにはそれぞれ「コード機能」がついています。
コード機能についてはこちらの記事をご覧ください。
一般的な代理コード
同じキーの中でコード機能が同じもの同士は「代理コード」と呼ばれ互換性があります。
同じキーのダイアトニック同士の互換性については以下の記事の中で解説しています。
臨時記号が発生するノンダイアトニック系の代理コードはこちらで解説しています。
以上、基礎知識の部分は「音楽理論ライブラリー」にまとめてありますが、ここでは、フラメンコ音楽の場合はどうなるのか?ということを考えてみましょう。
以下にフラメンコの「ミの旋法」におけるコード機能・代理コード・コードスケールなどをまとめていきます。
ミの旋法にコード機能と代理コードを設定してみる
まず、ミの旋法にコード機能を設定する事は可能なのでしょうか?
前回までにやったポルアリーバのダイアトニックコードとコードスケールをベースに考えてみます。
ベースになるフィリジアンスケールはマイナー系なので、マイナー系のコード機能が中心になります。
♭ⅡとⅤはドミナント7th化したものが普通に出てくるので併記します。
左からコード名、コード機能、ディグリー、コードスケールの順で書きます。
コード機能は以下のように略してありますが、今後はコード機能はこれらの略号を使うので、おぼえておいて下さい。
- トニック→T
- ドミナント→D
- サブドミナント→SD
- トニックマイナー→TM
- ドミナントマイナー→DM
- サブドミナントマイナー→SDM
ミの旋法のダイアトニックコードのコード機能
では、ミの旋法で使うダイアトニックコードにコード機能を付けてみましょう。
フラメンコ音楽論第4回で解説したポルアリーバ(Eスパニッシュ調)のダイアトニックコードのうち、比較的使用頻度の高い10種のコードについて、コード機能を一覧にしてみます。
コードネーム(ディグリー表記)コード機能の順で表記します。
- E7(Ⅰ7)T
- Em7(Ⅰm7)DM
- FM7(♭ⅡM7)SDM
- F7(♭Ⅱ7)D
- G7(♭Ⅲ7)DM
- Am7(Ⅳm7)TM
- Bm7(♭5)(Ⅴm7(♭5))SDM
- B7(Ⅴ7)D
- CM7(♭ⅥM7)TM
- Dm7(♭Ⅶm7)SDM
コード機能の付け方については、あくまで自分の解釈ですが、実用上の代理関係などを考慮して設定してみました。
Am7(Ⅳm7)をトニックマイナーにした理由
ミの旋法へのコード機能設定ということを考えてみてやって改めて気がつきましたが、Eスパニッシュ=ポルアリーバはE7(T)とAm(TM)のダブルトニックではないか?と思いました。
ポルアリーバのフレージングはAmから始まるパターンも多く、E7→AmやG→Amの終止も多用されるので、AmコードはEコードの次に重要な主和音として働いているように思います。
ちなみにAmへの終止の場合、E7はドミナント的に働くので、Eスパニッシュ(ポルアリーバ)は、フレーズや進行によってAマイナーキーに寄るという性質があります。
CM7(♭ⅥM7)をトニックマイナーとした理由
CM7をトニックマイナーに設定した理由についてですが、まず、フラメンコの原型であるソレアの歌でも、途中一旦Cコードに不完全終止してからEに行く動きが多いのでトニック系だと考えます。
そしてEスパニッシュスケールのベースはEフィリジアンであり、マイナー系なのでトニックマイナーに設定しました。
F(♭Ⅱ)系コードについて
F系のコード機能設定は一番悩みましたが、FM7はサブドミナントマイナー、F7と裏コードのB7はEに向けて完全なドミナントモーションがかかるのでドミナントとしました。
つまりF→Eの進行はドミナント進行をはらんだサブドミナントマイナー進行、ということになります。
実用上、Fの代理コードとして使えるDm7とBm7(♭5)もサブドミナントマイナーに設定しました。
G7(♭Ⅲ7)とEm7(Ⅰm7)をドミナントマイナーに設定した理由
G7とEm7は実用上の代理関係にあるように思います。
ですので、この2つはセットでドミナントマイナーとしました。
G7はCへの、Em7はAmへの5度進行・トニックコードへの解決を想定したドミナントマイナー機能です。
EmはⅠmコードですが、実際のフラメンコのコード進行の中で出てくるとあまり終止感がなくて、どちらかというとE7よりG7と互換性が強いように思うので、トニックマイナーではなくドミナントマイナーとしました。
使用頻度の低いダイアトニックコードのコード機能
フラメンコ音楽論第4回で触れましたが、上で書いた使用頻度の高い10種のコード以外にも、スパニッシュスケール由来のダイアトニックコードは何種類か設定できます。
それらにコード機能を当てはめると以下のようになりそうですが、はっきり言って西洋音楽理論から外れた響きだし、コード機能は曖昧なものだと思います。
ポルアリーバ(Eスパニッシュ)を例にすると、以下のようになります。
- FmM7(♭ⅡmM7)SDM
- G♯dim7(Ⅲdim7)D
- AmM7(ⅣmM7)SDM
- CM7♯5(♭ⅥM7♯5)TM
- Dm7(♭5)(♭Ⅶm7(♭5))DM
ミの旋法での各種代理コード
ミの旋法上でも、一般の長調・短調と同様に、同じコード機能のコード同士の代理関係が成立します。
またノンダイアトニック系代理コードについても、裏コードやパッシングディミニッシュなど(詳しくは上にリンクした「音楽理論ライブラリー」の記事をご覧下さい)は普通に利用可能です。
同ルートのメジャー・マイナーへの一時的転調を考慮すればメジャー・マイナーのダイアトニック系コードの使用も可能でしょう。
ただし、ミの旋法に限ったことではありませんが、大きな構成音変化を伴う代理コードの使用は、いつでもどこでも、というわけにはいかないので注意が必要です。
歌い手が歌いにくくなったりすることもあるし、ギターがなどのコード楽器が2人以上居る場合は、打ち合わせが必要になる場合もあります。
――以上でフラメンコ音楽で使われるコードとスケールの基本部分をほぼ網羅したと思いますが、あとは一般の理論に当てはまらないテンションノートなどの問題が残ります。
自分が「フラメンコテンション」と呼んでいるものです。
今回やったM3音(ポルアリーバならG♯音)が入ったダイアトニックコードなどもこれに当たりますが、ここ数回でやった一般理論とは異なる発想の響きが多用されて、それが「フラメンコらしさ」を形づくっている、ということですね。
次回は、このフラメンコ独特の響きをギターでどんなふうに弾いているのか?というのをやろうと思います。



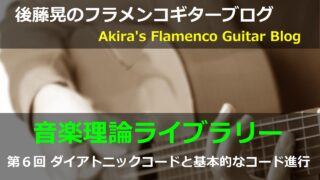
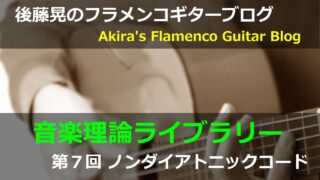
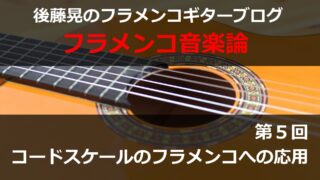
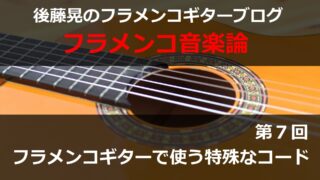
コメント