「フラメンコ音楽現代史」として、これまでに純フラメンコの現役アーティストを紹介してきましたが、今回は現代フラメンコが生んだ新たな形態である、フラメンコポップとフラメンコフュージョンの概要と歴史、そして代表的なアーティストを紹介いたします。
フラメンコポップ・フラメンコフュージョンの概要
まず最初に、ここで言う「フラメンコポップ」と「フラメンコフュージョン」という言葉を定義しておきましょう。
ここで言うフラメンコポップとは、歌が中心になったフラメンコ系のポップミュージックの事を指しています。
そしてフラメンコフュージョンは、楽器演奏が主体になったフラメンコ系の音楽の事を指していて、パコ・デ・ルシアが自身のグループでやっていた音楽が典型的です。
スペインでは1970年代からフラメンコのポップ化・フュージョン化の動きは大きなムーブメントとなっています。その結果、一般層までフラメンコ音楽が浸透し、スペイン国内のヒットチャートにはフラメンコ系のアーティストも普通にランクインして来ますよね。
フラメンコポップ・フラメンコフュージョンという言葉の意味はご理解いただけたかと思いますが、実態があまり知られていない音楽ジャンルだと思いますので、その概要と歴史をお話ししておきたいと思います。
フラメンコポップ&フュージョンの歴史
それでは、スペインで成立したフラメンコポップ&フュージョンの歴史をざっと見ていきましょう。
パコ・デ・ルシアとカマロン
スペインでは1975年にフランシスコ・フランコが没するまで独裁政治体制が続いていて、文化・芸能に対しても政治的な干渉があり、とくにポップ・フュージョン的なものは非常にやりにくかったものと思われます。
そんな中でフラメンコ音楽の改革の先陣を切ったのがギタリストのパコ・デ・ルシアです。
パコ・デ・ルシアはフランコ政権に陰りが見え始めた1970年代初頭からフラメンコギターに様々な要素を採り入れ始め、『二筋の川』(1973年)から『アルモライマ』(1976年)あたりの作品でフラメンコフュージョンの基礎を確立しました。
当時、パコはカマロンの伴奏者でもあったので、その新しい方法論はカマロンの音楽にも反映され、1970年代後半からはカマロンによるカンテの革新が開始されることになります。
パコが始めたフラメンコフュージョンはパコ・デ・ルシア・セクステッドに象徴されるような演奏形態に発展し、そこで活動していたホルヘ・パルド(管楽器)、カーレス・ベナベン(ベース)、ルベン・ダンタス(打楽器)、ティノ・ディ・ヘラルド(打楽器)などの人材は、その後のフラメンコポップ&フュージョンの発展において重要な役割を担うことになります。
パコとカマロンの音楽は、新しいアレンジ手法、オリジナルな歌詞とメロディーをもたらし、さらには商業音楽としての成功の道筋を示しました。
パコとカマロンがフラメンコ音楽の改革を開始した時代、スペインでは彼らの他にも個性的なアーティストが続々と出現してきます。
1972年結成のローレ・イ・マヌエル、1975年にキコ・ベネーノとパタネグラの2人によって結成されたグルーポ・ベネーノ、1978年に「ベルデ」をヒットさせたマンサニータなどのアーティストが、パコ&カマロンと共にフラメンコポップの草創期を形成しました。
1980年代
1980年代に入ると、パコとカマロンの新しいスタイルのフラメンコは完全に確立され、多数のフォロワーを生み出していきます。
また、ケタマとパタネグラという2つのバンドが出現して、フラメンコポップシーンを一気に広げ、それまでフラメンコを聴かなかったような層から新たなファンを獲得していきました。
そして、これはスペイン国外の話になりますが、1980年代後半からフランスのバンド、シプシーキングスが世界的に有名になり、フラメンコ系ポップミュージックが全世界的な成功に至る実例を示したのは大きかったのではないでしょうか。
ジプシーキングスは、音楽的にもスペイン本国のフラメンコ達がこぞって彼らのスタイルを逆輸入するくらいの影響力があったし、日本でもTVCMや『鬼平犯科帳』のテーマ曲に起用されたりして広く知られていますよね。
1990年代
こうして1970年代に始まり1980年代にその土台が醸成されたフラメンコポップ&フュージョンシーンですが、これが大きく開花したのは1990年代です。
新鋭のギタリスト、ビセンテ・アミーゴがソロデビューし、ケタマのサルサフラメンコがバカ売れし、ニーニャ・パストーリやディエゴ・エル・シガーラがデビューしました。
バンドでは、ナバヒータ・プラテア、マルティレス・デル・コンパス、バルベリア・デル・スールなどが人気化しています。
1990年代はパコ・デ・ルシアらの世代に加えて、さらに若い世代の歌手・ギタリスト・バンドが新しい風を吹き込み、それら全てが渾然一体となってフラメンコのポップ化・フュージョン化を押し進めた時代でした。
2000年代
2000年代からは、フラメンコポップ・フラメンコフュージョンというジャンルは完全にフラメンコの一部となり、純フラメンコと両輪のような形で発展してきています。
1990年代と比べても、さらに様々なジャンルの音楽や人材がクロスオーバーするようになり、オホス・デ・ブルッホのような特異な音楽性のグループも出現し、純フラメンコ系アーティスト達も、従来よりも幅広い音楽性を採り入れるような傾向がハッキリしていたように思います。
2010年代
2010年代からは、モバイルインターネットと動画サイトの普及で、さらに世の中の変化スピードが上がっているように思いますが、それに反してフラメンコポップ・フュージョンシーンはやや停滞気味の印象はあります。
その原因として、ポップ・フュージョン方向に出尽くし感が出てきたのと、スペインの若いアーティストの間で原点回帰・純フラメンコ重視の姿勢がトレンドになっている、というのはあると思います。
自分個人的には、歴史は繰り返すものだし。いずれまたパコやカマロンのような革命的な存在が出て、新しい音楽性を発展させていくものだと考えていますが……。
――フラメンコポップ・フュージョンの概要と歴史は以上ですが、ここからは個別のアーティスト達をご紹介していきます。
このカテゴリーにどのあたりまで含めるか?というのが難しいのですが、ここでは純フラメンコと一定以上の関連があるアーティストを紹介していきます。
ソロ名義のアーティスト
まずはフラメンコポップのジャンルで活躍するソロ名義のアーティスト(主に歌手)の紹介をします。
なお、純フラメンコに近いスタイルのソロ歌手はフラメンコ音楽論第35回「現役世代の歌い手」に含めましたので、そちらもご覧になって下さい。
マンサニータ(Mazanita)
マニサニータは1970年代から活動している、元祖フラメンコポップ歌手の一人です。
ガルシア・ロルカの詩をポップにアレンジした「Verde」(1978年発表)があまりにも有名で「ベルデの人」というイメージかと思いますが、血筋はゴリゴリのフラメンコで、マノロ・カラコールの甥っ子だったりします。2004年に48歳の若さで亡くなりました。
キコ・ベネーノ(Kiko Veneno)
フラメンコポップを語る上でキコ・ベネーノはキーパーソンとなる人です。
ケタマ(Ketama)やパタネグラ(Pata Negra)が結成される5年以上前の1975年にキコ・ベネーノはパタネグラの2人とグルーポ・ベネーノ(Grupo Veneno)を結成してアルバム(プロデューサーはリカルド・パチョン)を発表していますが、これがケタマとパタネグラからはじまる現在のフラメンコポップバンドの源流となりました。ベネーノが無ければパタネグラも無かったかもしれません。
そして、カマロンの1979年のアルバム『Legenda del Tiempo』に参加。このアルバムを通して、アレンジ面でカマロンにも影響を与えています。
そのあと、キコ・ベネーノのソロ名義になって長年に渡って活動しています。ベネーノのCDは自分も持っていますが、パタネグラよりロック寄りの音楽性です。
キコはマルティレス・デル・コンパス(Martires del Compass)の結成にも関与していたりして、プロデューサー的な側面が強い人ですね。
なお、ケタマ、パタネグラ、マルティレス・デル・コンパスなどのグループは後ほどご紹介します。
ディエゴ・カラスコ(Diego Carrasco)
ディエゴ・カラスコは1954年へレス生まれ。スペインが誇る鬼才でしょう。
元々はギタリストで、普通に歌や踊りの伴奏をしていましたが、やがて歌も歌うようになって弾き語りスタイルを確立していきます。
1984年にデビューアルバムを発表。以後はソロアーティストとして精力的な活動をしています。
ディエゴ・カラスコの音楽は「ブレリアをベースに色んな音楽を混ぜ込んでいく」というものから始まり、あらゆる音楽を取り込んで、唯一無二のものに進化してきました。
ライ・エレディア(Ray Heredia)
ライ・エレディアはケタマの初期メンバーですが、ケタマのデビューアルバム発表後(1987年)に脱退してソロ活動を始めています。
そして1991年にソロアルバムを発表しますが、その発売を待たずに亡くなってしまいました。
ですが、そのたった一枚のアルバムの影響力が半端ではないのです。伝説的名盤と言っても良いでしょう。
フラメンコポップ系のアーティストに影響を受けたミュージシャンの話をきくと高確率でライ・エレディアの名前が挙がります。
バルベリア(La Barberia)のネグリ(El
Negri)とは親戚関係で、小さいとき同じ家で育ったといいます。
余談ですが、ネグリの姉妹とライ・エレディアの妹(妻の妹だったかも)で結成された「Las Negris」というグループがあって、ライ・エレディアのカバーをやるガールズバンドでしたが、かなり人気があってライブも盛況でした。このグループ、今も活動しているようですね。
ホセ・ソト=ソルデリータ(Jose Soto “Sorderita”)
ホセ・ソト(通称ソルデリータ)はケタマの初期メンバーで、1992年にケタマを脱退すると同時にソロ活動を始めました。
ヘレス出身で、兄弟に歌い手のエンリケ・ソト、ビセンテ・ソトがいます。
ソルデリータのライブはスペインで良く観に行っていたのですが、ほとんどが弾き語りのスタイルで、完全ソロ、もしくは打楽器やベースのみ、というような2、3人の少人数編成でのライブが多かったです。
2001年の『Siete rios celestes』を最後に音源作品を出していませんが、ライブなどは継続している模様です。
トマシート(Tomasito)
トマシートは1969年生まれ、ヘレス出身の歌い手・踊り手ですが、ロック、ポップ、クラブミュージック、ブレイクダンス、ヒップホップなどの要素をごちゃ混ぜにして、歌って踊る、ラップもやる、というマルチなアーティストです。
マイケル・ジャクソンになりたかったんだとか。
1993年にデビューアルバムを発表。その後も何枚か音源作品をリリースしています。
最近また積極的に活動しているようですが、その芸風から「名物おじさん」的なキャラになりつつある気がします(笑)
ホセ・エル・フランセス(Jose el Frances)
ホセ・エル・フランセスは1971年モンペリエ生まれ。スペイン系のフランス人です。
1992年のデビューアルバム『Las calles de San Blas』がスペインで大ヒットとなり、一躍有名になります。
『Las calles de San Blas』は、あのデカいラジカセをかついだジャケット写真のアルバムですが、フラメンコポップ作品としては必聴盤と思います。
カマロン(Camaron)に憧れてカンテを学んだというホセ・エル・フランセスがカマロンとの共演を夢見て作ったというタンギージョ「Una Rosa Pa Tu Pelo」は、カマロンの遺作『Potro Rabia y Miel』(1992年)に収録されています。
ディエゴ・アマドール=チューリ(Diego Amador “El Churri”)
ディエゴ・アマドールは1973年セビージャ生まれの作曲家・歌手・ピアニストですが、個人的にはフラメンコ界随一の才人と思ってます。
歌、ギター、ピアノ、打楽器そして作曲、すべてが超一流の水準なのです。
ちなみにピアノは完全な独学であそこまで行ったらしいです。
パタネグラのライムンド(Raimundo Amador)とラファエル(Rafael Amador)の弟で、活動開始当初はパティータネグラ(Patita Negra)を名乗っていました。
1994年デビューアルバムを発表。パタ・ネグラも意外とメロディックな曲が多いんですが、ディエゴも同様のメロディーセンスがあります。
まぁ、ディエゴのほうが数段洗練されていてパタ・ネグラのような泥臭さは薄いですが。
あとはキューバ音楽要素が強いですよね。
パティータネグラ時代からオマーラ・ポルトゥオンド(Omara Portuondo)などと共演したりしてます。
キューバ音楽といっても、ケタマやバルベリアが採り入れたサルサではなく、オマーラなどがやっている叙情的なものが好みのようです。
このあたりはニーニョ・ホセレ(Niño Josele)、ハビエル・リモン(Javier Limon)、ホルヘ・パルド(Jorge Pardo)なんかと共通した感覚で、コンテンポラリー・フラメンコ・ミュージックの一つの典型と思います。
リカルド・モレノ(Rycardo Moreno)
リカルド・モレノは1981年、セビージャのレブリーハ生まれのギタリストです。
最近YouTubeで知ったギタリストの中では、ギタリスト紹介の時に取り上げたペペ・フェルナンデスと、このリカルド・モレノの2人が自分的に本当に衝撃でした。
この2人は現時点の知名度ということだと、今までに紹介した他のアーティストに及びませんが、是非紹介したいと思って記事に入れました。
リカルド・モレノはフラメンコとピックギタリストの二刀流で、その音楽性からフラメンコ・フュージョンの枠で紹介することにしましたが、素晴らしいコンパス感と独自のフレージング、アイデア満載の作曲など、特異な才能の持ち主と思います。
以前はフュージョン音楽をやっていたようで、2001年頃にフュージョンのバンドでCDを出しています。
フラメンコ系の音楽はいつ頃からやっているのか?は詳細がわかりませんが、土地柄、フラメンコには子供時代から親しんでいたようで、フラメンコギタリストとして知られる以前から地元のセビージャでフラメンコアーティストへの曲提供・プロデュースなどをしていました。
2010年頃からはフラメンコギターの腕前も知られるようになり、ギタリストとしてもフラメンコの主要アーティストと共演するようになります。
そして2015年にヘラルド・ヌニェス(Gerardo Nuñez)の手引きでソロデビュー、2017年にはセカンドアルバムを出しています。
ギター以外の楽器奏者
伝統的なフラメンコでは基本的に楽器はギターのみですが、1980年代くらいからパーカッションの使用が一般化したり、バンド形態のフラメンコ音楽が出てきたりして、ギター以外の楽器でフラメンコを演奏することも増えてきました。
ここでは、フラメンコフュージョン系の音楽に欠かせない「ギター以外の楽器プレイヤー」を紹介します。
このジャンルは演奏されるようになってからまだ40年程度と歴史が浅いという事もあり、創始者であるパコ・デ・ルシア(Paco de Lucia)のグループ人脈の影響力が未だに大きいです。
ホルヘ・パルド(Jorge Pardo)
ホルヘ・パルドはジャズ出身の管楽器奏者です。
長年に渡ってパコ・デ・ルシアのグループに参加していますが、ソロ作品も多数発表しています。
自分がはじめて聴いたホルヘ・パルドの作品は1991年の『Las Cigarras Sonquizasordas』でしたが、これは彼のファイバリッドアーティストであるマイルス・デイヴィス(Miles Davis)の曲のフラメンコアレンジがメインでした。
当時、フラメンコと平行して音楽学校でジャズを学習していた自分は非常に興味をそそられました。
そしてオリジナル曲がメインになった1993年の『Veloz Hacia su Sino』にはかなりの衝撃を受けました。
自分はスペインにいた時に彼のライブを何回も見ましたが、ポティートなどが参加してフラメンコ色が強い時と、ジャズ系ミュージシャンのみのフリースタイルで1曲30分とか延々と演奏していたり、かなり幅がありました。
ルベン・ダンタス(Rubem Dantas)
ルベン・ダンタスはブラジル出身の打楽器奏者で、パコ・デ・ルシアのグループに初期の頃から参加しました。
なにを隠そう、彼がフラメンコにカホンを導入した張本人なのです。
カホンですが、フラメンコでは1980年代から普及して、現在では欠かせない楽器となっています。
カホンはもともとフォルクローレなどで使われる南米の楽器(というか、多分、貧しくて楽器が買えない人が木の箱を叩いていたものと思われます)で、今はポップスなどの一般音楽ジャンルでも使われるようになり、「ドラムスに近い表現が出来る小さな楽器」ということで、小規模ライブやストリートライブに必須のアイテムです。
ティノ・ディ・ヘラルド(Tino di Geraldo)
ティノ・ディ・ヘラルドはフランス育ちのスペイン人で、本職は打楽器奏者ですが、複数の楽器と作曲、DTMでの音楽制作までこなすマルチなミュージシャンです。
フラメンコに関しては、上で紹介したディエゴ・カラスコのサポートをきっかけに、パコ・デ・ルシアのグループにも参加しました。
何枚かソロアルバムを出していますが、かなり実験的な感じで、フュージョンやパンクロック、アシッドジャズなどの要素が強いです。
余談ですが、自分は彼が作ったフラメンコ音源素材集を持っていますが、カッコいいリズムパターンが多いので、未だに使用することもあります。
パキート・ゴンサレス(Paquito Gonzalez)
パキート・ゴンサレスは1981年生まれ、カディス出身の打楽器奏者です。
カホンの教則本・DVDや、彼が監修したという、彼の名前が冠された「パキート・ゴンサレス・カホン」で有名です。普通に日本の大手楽器店で扱ってますからね。
フラメンコ打楽器奏者としては、2000年頃にマノロ・サンルーカル(Manolo Sanlucar)に見いだされて以降、フラメンコの主要アーティストと仕事をするようになり、ビセンテ・アミーゴ(Vicente Amigo)のツアーメンバーになっていたこともあります。
ピラーニャ(Israel Suarez “Piraña”)
ピラーニャは、本名イスラエル・スアレス、マドリード生まれ。パコ・デ・ルシアのバンドメンバーを10年以上務めたカホン奏者です。
バルベリアのリーダー、パケーテ(El Paquete)の弟で、カホン奏者としてはニーニャ・パストーリ(Niña Pastori)のサポートとしてデビュー。
それからはフラメンコの主要アーティストの公演になくてはならない人材となっています。
彼はフラメンコのみならず、レニー・クラヴィッツ(Lenny Kravitz)、リッキー・マーティン(Ricky Martin)、チック・コリア(Chick Corea)、パキート・ド・リベラ(Paquito D’Rivera)、ウィントン・マルサリス(Wynton Learson Marsalis)などの世界のビッグアーティストと共演しています。
それにしても、ラモン・エル・ポルトゲス(Ramon el Portugues、父)、グアディアナ(Guadiana、叔父)、パケーテ(兄)、みんな顔がそっくりで、猛烈な遺伝子を感じますね。
カルレス・ベナベン(Carles Benavent)
カルレス・ベナベン(カーレス・ベナベントなど、読みは色々です)はバルセロナ出身のベース奏者で、パコ・デ・ルシアのグループメンバーでした。
ソロアルバムも何枚か出していて、フラメンコ系のベース奏者というと名前が一番に挙がる人です。
本人はジミ・ヘンドリックスに触発されたと言っていますが、ジャコ・パストリアス(Jaco Pastorius)の影響も大きそうです。
彼のベース演奏は、縁の下で支えるベースではなく、速弾きもやるし、即興でオブリガードを大量に投入する派手なスタイルです。
1995年、事故で重症を負って引退状態となってしまって、復帰は難しいと思われていましたが、アルバム『Fenix』(1996年)を録音して復帰を果たしています。
その出来事は、自分は丁度スペインにいた時でしたが、一人で知らない土地で暮らす不安の中で元気付けられ、『Fenix』もすぐに近所のFNAC(スペインの書籍/CDチェーン店)で買い求めました。
現在、CDは場所をとるため、ほとんどmp3化して処分してしまったのですが、そのCDは処分せずにとってあります。1曲目のタンギージョは名曲ですね。
ハビエル・コリーナ(Javier Colina)
ハビエル・コリーナは、自分がスペインにいた頃、エル・ボラ(Agustin Carbonell “Bola”)のバンドでもベースを弾いていましたが、ウッドベースの名手です。
ホアキン・コルテス(Joaquin Cortes)の来日公演(1995年?)に同行してウッドベースソロでソレア・ポル・ブレリアを披露したのが凄いインパクトでした。
また、彼は鍵盤楽器(とくにアコーディオンが上手い)や作曲もこなし、深い音楽の素養を感じます。
スペインにいた時によく顔を合わせていましたが、いつもあちら側から話しかけてきて仲間の輪に入れてくれたりして、とても優しい人でした。
チャノ・ドミンゲス(Chano Dominguez)
チャノ・ドミンゲスはピアノフラメンコの創始者の一人として有名ですが、もともとプログレバンドにいた人で、その後ジャズに転向したという経歴を持っています。
1990年代以降、パコ・デ・ルシアと共演したりしてフラメンコ色を強めて、フラメンコジャズ系の作品を発表しています。
彼のスタンスはジャズサイドから、自らの出身地のルーツミュージックであるフラメンコにアプローチしているものと思います。
ざっくり言うと、純フラメンコの人がピアノを弾いているディエゴ・アマドールと、フラメンコ好きなジャズ奏者、チック・コリアの中間くらいのスタンスですね。
ドランテス(Dorantes)
ドランテスは1998年にデビューCDを発表して以降、フラメンコ系では最も意欲的に作品を発表し続けているピアノ奏者です。
ドランテスはチャノ・ドミンゲスと異なり、終始ピアノフラメンコとして創作、演奏しています。ジャズやクラシックの影響はかなり感じますが。
ドランテスが素晴らしいのは、その創作能力の高さでしょう。独創的な作曲と演奏をする人です。
ベルナルド・パリージャ(Bernardo Parrilla)
ベルナルド・パリージャは、マドリードで活動するヒターノのフラメンコ・バイオリン奏者です。
ギタリストのファン・パリージャ(Juan Parrilla)の息子で、パリージャ・デ・ヘレス(Parrilla de Jerez、歌伴奏で有名なギタリスト)とも親戚関係です。
1990年代まではフラメンコを専門とするバイオリン奏者は彼くらいしかいませんでした。
ノンビブラートで紡いでいくジプシースタイルの妖艶なフレーズが持ち味です。
――ここまででソロ名義アーティストとギター以外の楽器奏者の紹介をしましたが、後半はバンド・ユニットなどのグループ形態のアーティストと、フラメンコ系の音楽プロデューサーをご紹介します。
ユニット・バンド形態のアーティスト
フラメンコをベースとした音楽をユニット・バンドなどのグループ形態で演奏しているアーティストの紹介をします。
ローレ・イ・マヌエル(Lole y Manuel)
ローレ・イ・マヌエルは、1972年にドローレス・モントージャ・ロドリゲス(Dolores Montoya Rodriguez、歌)とマヌエル・モリーナ・ヒメネス(Manuel Molina Jimenez、ギター)によって結成された音楽ユニットです。
歌とギターという、純フラメンコ編成のユニットですが、その音楽内容は伝統的フラメンコの枠を越えるものも含まれ、活動年代を考えると「元祖フラメンコポップ」と言えます。
1970年代から1980年代に盛んに活動した後、1995年に活動を休止。
マヌエル・モリーナは2015年に亡くなりましたが、ローレ・モントージャは近年、ディエゴ・デル・モラオ(Diego del Morao)と共に音源作品を作ったりしています。
マヌエル・モリーナの娘に歌手のアルバ・モリーナ(Alba Molina)がいます。
ケタマ(Ketama)
ケタマは、スペインから出てきたフラメンコポップ系のバンドとしては1番有名なものだと思われます。
1980年代初頭にファン・カルモナ(Juan Carmona)、ホセ・ソト=ソルデリータ(Jose Soto “Solderita”)、ライ・エレディア(Ray Heredia)の3人によって結成されました。
その後、ライ・エレディアとソルデリータは脱退、リーダーのファン・カルモナの一族(アビチュエラ一家)からアントニオ・カルモナ(Antonio Carmona)とホセ・ミゲル・カルモナ(Josemi Carmona)を加えて活動を続けます。
アントニオ・カルモナは当初パーカッションの担当でしたが、ホセ・ソト(ソルデリータ)が抜けた後は、彼がメインボーカルをやるようになります。
1990年代に入るとスペインの若い世代に圧倒的に支持されるようになり、大きな成功を収めました。
ケタマの音楽性は、初期の頃はフラメンコ形式のリズムにこだわったマニアックなアプローチが多かったですが、やがて「ルンバ+サルサ」というスタイルのラテンポップ路線が中心になり、それが大当たりしました。
ケタマは1990年代を通して世界的に有名になりましたが、2000年前後からあまり活動の話をきかなくなり、2004年に解散しています。
ちなみに、ライ・エレディアとホセ・ソト(ソルデリータ)はケタマから離脱後にそれぞれソロ活動をしているのは前回記事で書いた通りです。
パタネグラ(Pata Negra)
パタネグラは、ケタマと並ぶ老舗フラメンコポップバンドで、ライムンド・アマドール(Raimundo Amador)とラファエル・アマドール(Rafael Amador)の兄弟によって1981年に結成され、1995年まで活動していました。
ちなみにチューリことディエゴ・アマドール(Diego Amador “Churri”)は2人の弟で、当初はパティータネグラという名義で活動していました。
パタネグラの音楽性はブルーズ、ファンク、レゲエといったアメリカン・アフロ系音楽とフラメンコの組み合わせで、全体に土臭さを感じるものでした。
バルベリア(La Barberia)
バルベリアは、ギタリストのファン・スアレス”パケーテ”(Juan Suarez “Paquete”、歌い手のラモン・エル・ポルトゲスの息子でピラーニャの兄)と、パーカッションのエンリケ・エレディア”ネグリ”(Enrique Heredia “Negri”、ライ・エレディアのいとこだか甥だか)、エレキギターのダビ・アマジャ(David Amaya、カルメン・アマジャの孫)を中心に1991年に結成されたグループです。
最初はラ・バルベリア・デル・スール(La Barberia del Sur)を名乗っていましたが、名前を短縮したようです。
初期はアビチュエラ一族のぺぺ・ルイス・カルモナ(Pepe Luis Carmona)がボーカルをやっていたり、その繋がりでケタマのホセ・ミゲル・カルモナが参加したりして「ケタマの弟バンド」みたいな扱いでしたが、バルベリアの音楽性はケタマよりポップロック寄りです。
ぺぺ・ルイスが抜けた後は、それまでパーカッションを担当していたネグリがボーカルを担当するようになりました。
そのへんも、ホセ・ソト脱退後にパーカッションのアントニオ・カルモナが歌うようになったケタマとそっくりですよね(笑)
2000年代前半まで活動していたようですが、ケタマが解散した2004年と同時期にバルベリアも活動を休止しています。
自分がスペインでギターを習っていたエル・ボラ(Agustin Carbonell “Bola”)の義理の兄がバルベリアのパケーテだった事もあって、バルベリアのライブは毎回のように行っていて、楽屋でギターやカホンで遊んでもらったりして、何かと思い出深いバンドでした。
ナバヒータ・プラテア(Navajita Platea)
ナバヒータプラテアは、ヘレス出身のペレとクーロの2人組ユニットで1992年結成。1990年代後半くらいからヒットして有名になりました。
ナバヒータプラテアの音楽性は「たまにフラメンコのコンパスが入るアコースティックなロック」という感じですが、基本的にギター(フラメンコ&エレキ)と打楽器主体のアレンジで構成されていて、男臭い硬派な感じのサウンドだと思います。
マルティレス・デル・コンパス(Martires del compass)
マルティレス・デル・コンパスは、チコ・オカーニャ(Chico Ocaña)が1995年に結成したグループで、結成にはキコ・ベネーノ(Kiko Veneno)が関与しています。
2000年にCDデビューし、数枚のアルバムを制作して2007年頃に解散しました。
マルティレス・デル・コンパスの音楽性はレゲエやファンクのカラーが強く、パタネグラからブルースとラテンカラーを引いて、レゲエとファンクの要素を増量したような感じですが、パーカッションの使い方とリズムパターンが独特で、何よりチコ・オカーニャのキャラが強烈です。
あと、トラディショナルなカンテ(しかも結構マニアックな形式)のラインをデフォルメした曲が多かったりして、フラメンコ度はかなり高めだと思うのですが、ちょっとふざけたパロディー的要素もあったりで、色々とアクが強いバンドでした。
オホス・デ・ブルッホ(Ojos de Brujo)
オホス・デ・ブルッホは、1998年頃結成されたバルセロナの8人グループです。
1999年にデビューアルバムを発表して2000年代に盛んに活動していました。
2ndアルバムの「バリ」はワールドミュージック部門でグラミー賞を受賞しています。
2011年に活動休止、中心メンバー数人がその後、レナカイ(Lenacay)を結成しています。
オホス・デ・ブルッホの音楽性は、フラメンコ+ポップ+クラブミュージック(ヒップホップ、ダンスホールレゲエ、ゴアトランスなど)+インド音楽などのワールドミュージックといった具合で、カオス状態になりそうなものですが、個性的な音楽性を打ち出すことに成功し、世界的に人気を博しました。
フラメンコ系の音楽プロデューサー
1970年代後半以降、フラメンコの音源作品でも様々なアレンジが導入されるようになり、音楽と音響の知識を持った音楽プロデューサーの必要性が高まりました。
そういう需要に応える形で出てきたフラメンコ系の音楽プロデューサーを何人か紹介します。
リカルド・パチョン(Ricardo Pachon)
リカルド・パチョンは、セビージャ出身の元祖フラメンコ系音楽プロデューサーで、カマロンと組んでフラメンコ音楽の革新を支えた、現代フラメンコの影の立役者です。
カマロンのほか、ローレ・イ・マヌエル、ベネーノ、パタネグラ、トマティート(Tomatito)、ラファエル・リケーニ(Rafael Riqueni)、マカニータ(La Macanita)などなど、1990年代までの主要なフラメンコやフラメンコ・ポップのCDの多くを彼が手掛けています。
イシドロ・サンルーカル(Isidro Sanlucar)
ギタリスト、マノロ・サンルーカル(Manolo Sanlucar)の弟で、イシドロ・ムニョス(Isidro Muñoz)ともいいます。
父親も同名のギタリストなので紛らわしいですが、1952年生まれの息子のほうです。
イシドロは音楽プロデューサー・作曲家・ギタリストとして現代のフラメンコ音楽に多大な貢献をしています。
エル・ペレ(El Pele)とビセンテ・アミーゴ(Vicente Amigo)の『La Fuente de Lo Jondo』(1992年)を皮切りに、ホセ・メルセー(Jose Merce)、マカニータなど、名だたるアーティストの音源制作を手掛けてきました。
ハビエル・リモン(Javier Limon)
ハビエル・リモンは、2000年代から活躍する音楽プロデューサー・作曲家・鍵盤奏者・ギター奏者・歌手で、とくにディエゴ・エル・シガーラ(Diego el Cigala)やニーニョ・ホセレ(Niño Josele)との共作が多いです。
音楽プロデューサーとして、リカルド・パチョンの後継者的な役割を担っていますが、彼自身がミュージシャンでもあるので、もっと守備範囲が広く、共演・曲提供という形で、フラメンコアーティストに直接的影響を与えています。
とくにシガーラやホセレのキューバ音楽趣味はハビエル・リモンの影響が大きいと思われます。
フラメンコポップ・フュージョンのまとめ
今回紹介したフラメンコポップ・フュージョン系のアーティストを大雑把に分けると、以下の5系統になるのではないでしょうか。
- パコ・デ・ルシアのグループから始まる正統派フラメンコフュージョン
- カマロンやローレ・イ・マヌエルから始まる純カンテをベースとしたフラメンコポップ
- ベネーノとパタネグラから始まるジプシーロック系
- ケタマから始まるラテンポップ系
- オホス・デ・ブルッホから始まるクラブミュージック系
この他に、ハードロック系のものなどもありますが、そのへんはあまり聴いてないので語れません。
それから、ジプシーキングス、フラメタルなどが世界的に有名ですが、今回は扱いません。
純フラメンコ要素が薄いものを入れていくと範囲が膨大になるので、今回はフラメンコポップの源流の部分、純フラメンコに近いところにいるアーティストに絞っての紹介とさせていただきたました。
自分がフラメンコポップやフラメンコフュージョンにはまって一番聴いていたのは1992年から2005年頃なので、その時代の事はそれなりに知っていますが、それから少しブランクがあり、最近はYouTubeで広く浅く視聴していて、最近のバンドにはそこまで詳しくありません。カッコいいのがあったら教えて下さい。
フラメンコポップやフラメンコフュージョンというジャンルは、今紹介したようなグループのメンバーや、前回紹介したソロアーティストと楽器奏者、純フラメンコ側のアーティスト、そういった人達が渾然一体となって進行中、といった状況が1980年代から現在まで続いている、と感じます。
――今回まで数回に渡って現役世代のアーティストの紹介をしてきました。
まだまだ紹介したいアーティストは沢山いますが、今どういうものが主流なのか?まず何を聴いたらいいのか?というのを考えて、数を絞って紹介しました。
ここ数回で現役アーティストの活動をご紹介してきましたが、次回は「フラメンコ音楽現代史」の総まとめをしたいと思います。
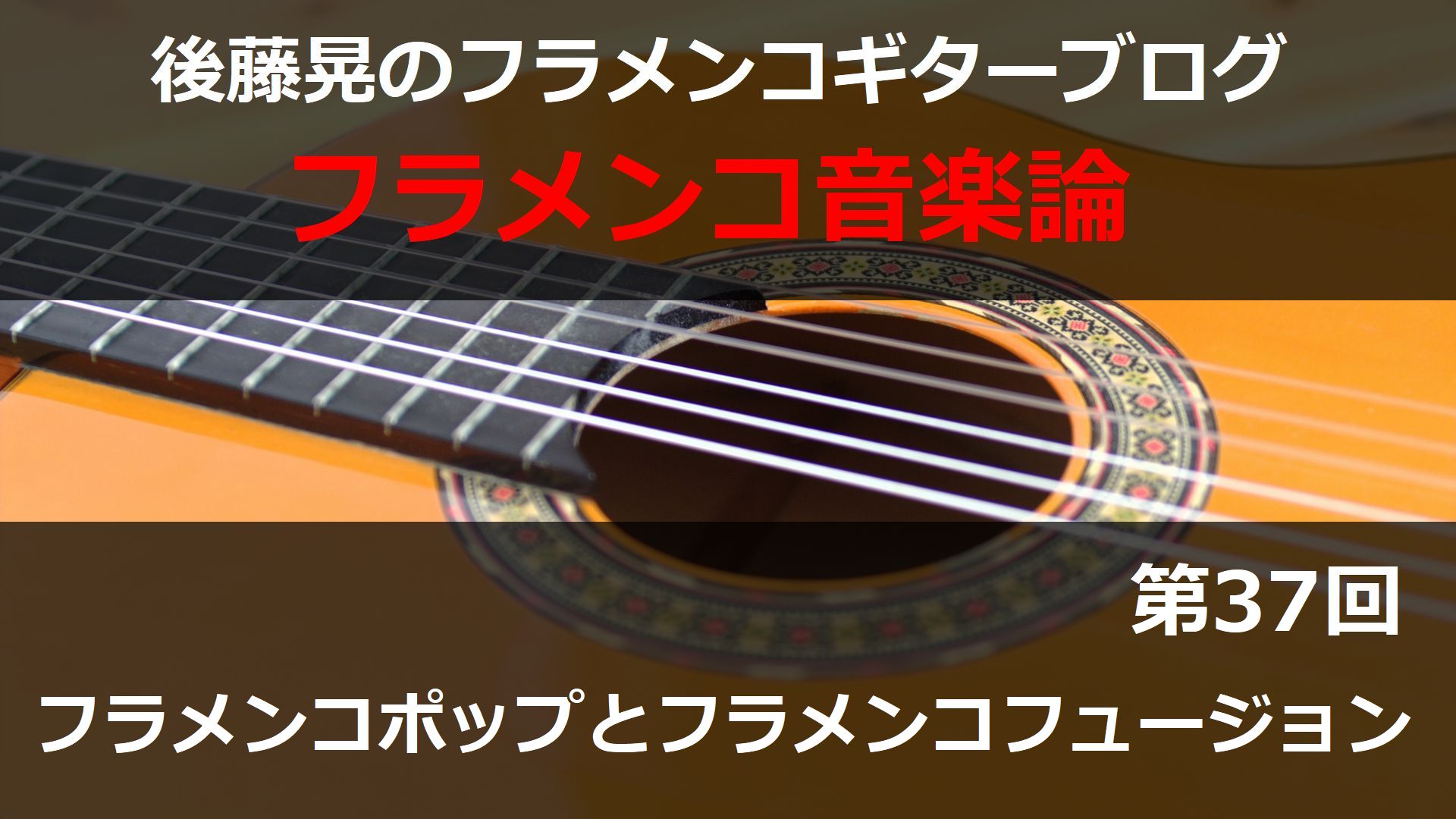
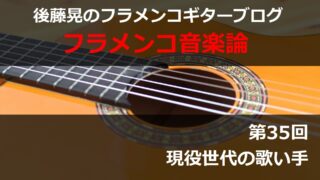

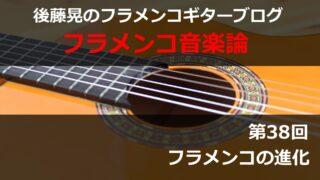
コメント