フラメンコ音楽論では、今回から個別形式の解説に入ります。
まずはフラメンコのリズムの根幹を形成する12拍子系からいきますが、今回は全ての12拍子系形式のベースとなっているソレアです。
ソレア形式概要
単数形:Soleá
複数形:Soleares
主な調性:ポルアリーバ(Eスパニッシュ調)
テンポ(カンテソロ):90BPMから130BPM
テンポ(踊り):70BPMから90BPM
ソレアは、「フラメンコの母」と呼ばれる12拍子の根幹形式で、フラメンコの曲種の中でも、シギリージャと並んで古く格調高い形式です。
ソレアの調性
ソレアの調性は、伝統的にポルアリーバ(Eスパニッシュ調)で演奏されます。
ポルアリーバの場合は、女性歌手なら7カポ(実音はBスパニッシュ)、男性歌手なら4カポ(実音はG♯スパニッシュ)あたりのキーになります。
女性歌手の場合、カポタストの位置の関係から、ギターで使える音域か大きく削られるため、ソレアの伴奏用ファルセータはカポタスト無しの状態で5フレットポジションくらいまで(高音側は8フレットくらいまで)で作っていないと演奏が難しくなります。カッタウェイ付きのギターならもっと上まで使えますが……。
こういう事情があるため、女性の歌い手の場合は2カポか3カポのポルメディオ(Aスパニッシュ調)で演奏されることもあります。
あとは6弦をB音まで下げて、グラナイーナのキー(Bスパニッシュ調)でやったりすることもありますが、これだとちょうど7カポ相当です。
ソレアのテンポ
ソレアのテンポは、12拍子系では最も遅い部類なのですが、踊りが入る場合と入らない場合で最大2倍近くの差があり、テンポ帯によってリズムの感じ方も変わってきます。
踊りが入らない場合
カンテソロ・ギターソロの場合は概ね90BPMから130BPMくらいで、ゆっくりしたソレア・ポル・ブレリアに近いテンポになる場合もあるのですが、昔のスタイルはそれくらいの速めのテンポで演奏されるのが普通でした。
カンテソロやギターソロの場合、完全なインテンポでは無く、テンポを揺らして演奏する場合も多いです。
踊りが入る場合
踊りが入る場合、踊りの中の歌が入る部分(歌振り、レトラ)はゆっくり、70BPMから90BPMくらいで演奏されます。
それに対して、サパテアード(足技)の部分は70BPMから200BPM以上と幅広いテンポで演奏されますが、最後はテンポアップしてブレリア(200BPM以上)になるのが一般的です。
ティエント、ガロティン、タンゴ・デ・マラガ、シギリージャ、グアヒーラなども同じ傾向があり、踊りが入る場合、レトラの部分はゆっくりのテンポになりますが、これは踊りの展開をよりドラマチックにするために緩急をつけてきた結果ではないでしょうか。
ソレアのコンパスの捉え方
ソレアは12拍子の基礎となる形式ですが、以下、ソレアのコンパスの捉え方を4つのケースに分類して考えてみます。
ベーシックな12拍子
まず最初に解説するのは、フラメンコの入門書などに書いてある最も一般的な12拍子で、1拍目から入って3・6・8・10・12拍目にアクセントがあります。
1 2 ③ 4 5 ⑥ 7 ⑧ 9 ⑩ 11 ⑫
※○の付いた数字がアクセント拍
このコンパスは、オーソドックスな歌の呼吸(間のとり方)がもとになっているものですので、ソレア本来の歌のテンポ(100BPMから130BPMくらい)が標準です。
バリエーションとして6拍目のアクセントを7拍目に変える事もありますが、そうすると、やや軽快な感じになってソレア・ポル・ブレリアに接近します。
1 2 ③ 4 5 6 ⑦ ⑧ 9 ⑩ 11 ⑫
3拍目が強い3拍子
サパテアードやファルセータで良く出現するリズムパターンに、3・6・9・12拍目にアクセントを感じるものがあります。要するに3拍目が強い3拍子ですね。
1 2 ③ 4 5 ⑥ 7 8 ⑨ 10 11 ⑫
このコンパスの時も、フレーズ的には1拍目から入って10拍目に解決することが多いので、10拍目にも潜在的にアクセントがあります。
このコンパスは、3拍ずつ綺麗に区切れるので、ファルセータなどは3拍子で作ったフレーズがそのまま適用可能です。
バイレ伴奏用のゆっくりしたコンパス
ソレアの場合、踊りの歌振りのテンポは、伝統的な歌(100~130BPMくらい)の半分くらいの速度(70~90BPMくらい)だったりして、全く別のリズムに感じるかもしれません。
踊りの歌振りテンポのコンパスは、アクセントなどの構造自体は「ベーシックな12拍子」や「3拍目が強い3拍子」に準じますが、テンポが非常にゆっくりなために倍タイムの16分音符が構成単位になっていて、演奏する感覚はかなり異なります。
倍速のブレリアの活用
バイレの場合、歌振りはスローテンポでも、サパテアードが入るとリズミックなコンパス表現になってきます。
サパテアードなどのパルマがバンバン入ってくるような場面では「ブレリア2コンパスでソレアの1コンパスとするとり方」が多用されます。コンパスカウントでいうと下図の通り。
ブレリア
⑫ 1 2 ③ 4 5 ⑥ 7 ⑧ 9 ⑩ 11
ソレア
1 2 ③ 4 5 ⑥
ブレリア1コンパスでソレアのメディオコンパスになるわけですが、この捉え方をすることで、ブレリアのフレーズを半速のソレアのコンパスに乗せる事が出来ます。
なお、ブレリア形式についてはこちらの記事を参照して下さい。
ソレアで使用するギターのコード
伝統的なソレアで使用するギターのコードは原則的に、E・F・G・Am・Cの5つ(3和音に単純化、テンションは考慮せず)で、コード進行は最終的にEコードに解決していきます。
一方、モデルノ系の伴奏やギターソロ曲だと積極的に複雑な響きを使っていく傾向が強いですが、前々回やったポルアリーバの項目にあるようなコードを活用していきます。
ソレアの演奏では、ファルセータや足の伴奏ではそうやってモダンなコードを使っていたとしても、歌が入ったら伝統的な雰囲気や歌いやすさを重視してシンプルなコードで伴奏するケースが多いです。
なお、昔から慣用句的に使われているテンションコードにFadd9やE(♭9)があります。
Fadd9

ソレアの代表的な定型フレーズのコード進行
ソレアの代表的なマルカール(基本パターン)のコード進行は以下のようなものです。○の拍はコードチェンジが無い拍で()内のコードは省略される場合もあります。
|Fadd9 〇 〇|C 〇 〇|F E F|E 〇 〇|
|Am 〇 〇|C 〇 〇|F E F|E 〇 〇|
|E 〇 F|(E) 〇 〇|F E F|E 〇 〇|
他にも色々ありますが、2つ目のコードにGではなく、Cを持ってくる事が多いのが他の形式にはない特徴です。
ソレアの歌について
ソレアの歌は、ほぼ型が決まっていて、現代の歌手も伝統的なラインの範囲で収める場合がほとんどです。
代表的な地域バリエーションとして、ソレア・デ・アルカラ、ソレア・デ・トリアーナ、ソレア・デ・ウトレーラ、ソレア・デ・カディス等がありますが、コード進行や歌のサイズ、節回しはどれも似通っています。
ソレアの歌のコード進行
ソレアの歌の構成やサイズを把握するために、コード進行を書いておきます。書式は以下の通り。
- 12拍子の1拍目を頭にした3拍子で記載
- 1行でメディオコンパス(6拍)
- ○の拍はコードチェンジが無い拍
- ()内のコードは省略される場合もある
- 複数のコードの可能性がある場合は「,」で区切る
- キーはポルアリーバ(Eスパニッシュ調)で記載
- コードは原則として3和音で記載
- コンテスタシオンは歌が休む合いの手の部分で、通常、0コンパス(コンテスタシオン無し)から2コンパス
- ※マークが付いている行は省略されることがある
|E ○ ○|○ ○ ○|
|○ ○ ○|E,Am,F ○ ○|
|(Am) (G) F|F,E ○ ○|※
|F,E F,E F|E ○ ○|※
コンテスタシオン
|E ○ ○|○ ○ ○|※
|○ ○ ○|E,Am,F ○ ○|※
|(Am) (G) F|F,E ○ ○|※
|F,E F,E F|E ○ ○|※
エストリビージョ
|○ ○ G|○ ○ ○|
|○ ○ ○|C ○ ○|
|(Am) (G) F|F,E ○ ○|
|F,E F,E F|E ○ ○|
|○ ○ G|○ ○ ○|
|○ ○ ○|C ○ ○|
|(Am) (G) F|F,E ○ ○|
|F,E F,E F|E ○ ○|
ディグリー(度数)表記版
|Ⅰ ○ ○|○ ○ ○|
|○ ○ ○|Ⅰ,Ⅳm,♭Ⅱ ○ ○|
|Ⅳm ♭Ⅲ ♭Ⅱ|♭Ⅱ,Ⅰ ○ ○|※
|♭Ⅱ,Ⅰ ♭Ⅱ,Ⅰ ♭Ⅱ|Ⅰ ○ ○|※
コンテスタシオン
|Ⅰ ○ ○|○ ○ ○|※
|○ ○ ○|Ⅰ,Ⅳm,♭Ⅱ ○ ○|※
|(Ⅳm) (♭Ⅲ) ♭Ⅱ|♭Ⅱ,Ⅰ ○ ○|※
|♭Ⅱ,Ⅰ ♭Ⅱ,Ⅰ ♭Ⅱ|Ⅰ ○ ○|※
エストリビージョ
|○ ○ ♭Ⅲ|○ ○ ○|
|○ ○ ○|♭Ⅵ ○ ○|
|(Ⅳm) (♭Ⅲ) ♭Ⅱ|♭Ⅱ,Ⅰ ○ ○|
|♭Ⅱ,Ⅰ ♭Ⅱ,Ⅰ ♭Ⅱ|Ⅰ ○ ○|
|○ ○ ♭Ⅲ7|○ ○ ○|
|○ ○ ○|♭Ⅵ ○ ○|
|(Ⅳm) (♭Ⅲ) ♭Ⅱ|♭Ⅱ,Ⅰ ○ ○|
|♭Ⅱ,Ⅰ ♭Ⅱ,Ⅰ ♭Ⅱ|Ⅰ ○ ○|
ソレアの歌は、全体で5コンパスから10コンパスの長さになります。
12拍子形式におけるコードチェンジのタイミング
歌のコード進行表を見てお分かりいただけると思うのですが、フラメンコの音楽はコードチェンジのタイミングが特殊です。
そして、その事がフラメンコの音楽に馴染みのない人にとって、コンパスを難解にしている大きな要因にもなっていると感じるのですが、とくに12拍子系形式はその傾向が顕著なのではないかと。
フラメンコのコードチェンジのタイミングは明確には決まっておらず、昔から弾かれている基本パターンも変わったコードチェンジをするものがあるし、感覚で作られた歌に合わせて後付けしたようなパターンも多く、一般の音楽に比べるとカオスでイレギュラーなものだと思いますが、ここでは、なんとか一定の文章化が出来そうなものに絞って解説を試みてみましょう。
1拍目と10拍のコードチェンジポイント
ソレアなどの比較的ゆっくりしたテンポの12拍子のフレージングの基本は、1拍目からコード進行がはじまって10拍目に解決していくものであり、フレージングの始点と終点に当たる1拍目と10拍目(修飾音が付く場合は9拍目から変わる)は重要なコードチェンジポイントになります。
そして、10拍目でフレーズが解決した後の10・11・12の3拍は10拍目のコードが維持されるのが普通です。
その他のコードチェンジポイント
フレーズの途中でもコードが変わるタイミングがいくつかありますが、その中で最も重要視されるのが3拍目です。
あとはテンポやフレーズによりますが、4拍目・7拍目にもコードチェンジポイントがあります。
歌伴奏は、歌の音程が変わったら直近のチェンジポイントでコードを追随させるのですが、ソレアの場合は上記の1・3・4・7・10(または9)拍目にコードチェンジポイントがあるということですね。
ちなみに、ブレリアのテンポ(180BPM以上)になると、12拍目や6拍目からのフレージングが増えるので、コードチェンジポイントもずれて、12・3・6・10(または9)拍目になるのでややこしいですが、各テンポのフレージングの特性に慣れれば、自然に理解出来ると思います。
ファルセータのコードチェンジポイント
最後に、ファルセータ上のコードチェンジポイントについてですが、ファルセータの作り次第で、どこでもコードが変わるので、複雑なファルセータに即興で伴奏をつけるのは至難と思われ、打ち合わせが必要となります。
――今回はフラメンコ形式解説第1弾として、ソレア形式を解説しましたが、12拍子系はフラメンコ形式の中でも理解が難しく、学習者にとっては最も厄介なものなのですが、12拍子系のコンパスこそがフラメンコをフラメンコたらしめているものだと思うし、敢えて一番最初にとりあげました。
全くの初心者の方には、敷居が高く感じるかもしれませんが、逆に言えば、ここさえクリア出来れば、フラメンコの語法のかなりの部分を感覚的に把握できるようになるので、あとは応用で何とでもなると考えて良いと思います。12拍子はそれほど重要な基礎なのです。
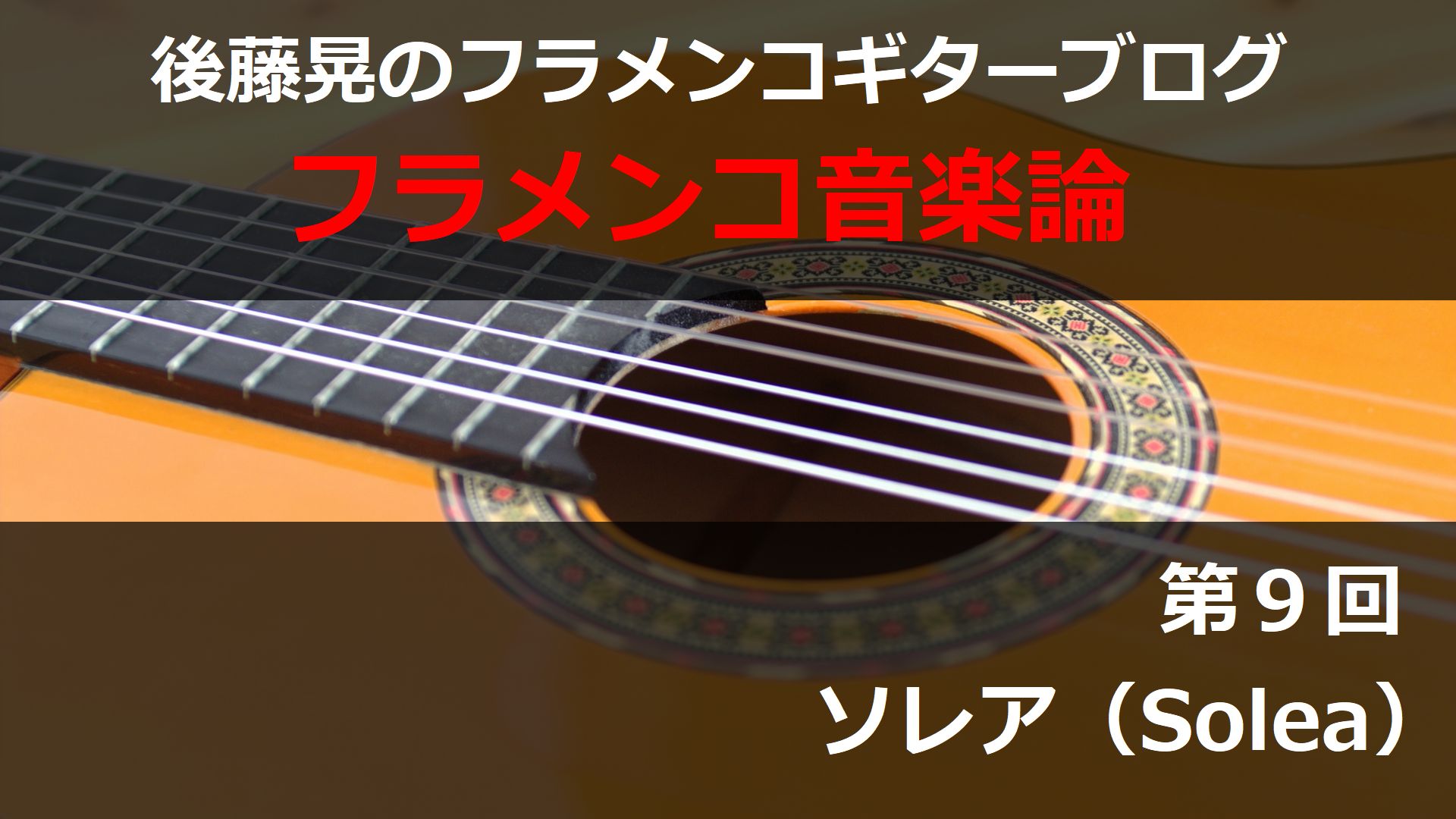
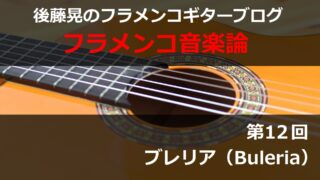
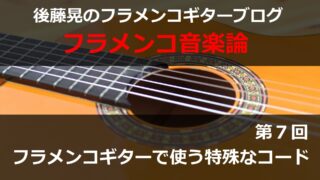
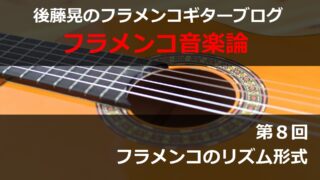
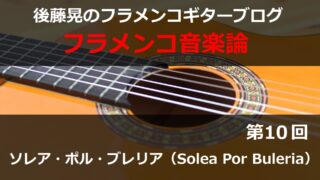
コメント