YouTube動画ファルセータ集の第8弾はタラントです。
今回演奏した2つのファルセータは、両方とも1996年頃スペイン留学中にマドリードのギタリスト、パコ・クルス(Paco Cruz)に教わったものです。
タラント形式について
タラントはファンダンゴの一種であるタランタに2拍子のリズムが付いたものですが、調性が独特です。
タラント、タランタを含む、いわゆるカンテ・レバンテ系の形式の多くはF♯スパニッシュ調で演奏されますが、ⅠコードにF♯7(♭9,11)という不協和音的なテンションコードをⅠコードとして使います。
ちなみに、今回の演奏動画では2フレットにカポを付けているので実音はG♯スパニッシュ調になっています。
タラント形式解説
では、今回演奏したファルセータを個別に解説いたします。
1つ目のファルセータ【パコ・クルス】
1つ目はイントロ向きのファルセータですね。
これの出だしのように、隣合った弦連打の修飾音をフラメンコギターではよく使うんですが、アルライレ気味のアポヤンドのタッチです。こういう細かいところが意外と難しかったりします。
コード進行的には、フラメンコ音楽論07で解説した特殊コードがいくつか登場します。
具体的には、GM7(onB)、DM7(onF♯)などです。
これらのコードは、現在ではF♯スパニッシュの形式で使うスタンダードなコードとなりつつありますが、使われはじめたのはパコ・デ・ルシア(Paco de Lucia)あたりからと思います。
こういう理論的に説明が難しいコードがスタンダードになるあたりが、フラメンコのフラメンコたる所以でしょうか。
2つ目のファルセータ【パコ・クルス】
2つ目のファルセータは全編3連符で構成されていて、3連符のエスコビージャ伴奏向けのものです。
リズムサイクルは倍速のタンゴになっていますが、偶数コンパスで出来ているのでノーマルのタラントのサイズでも使えます。
タラント含めたゆっくりの2拍子形式内での倍速タンゴとの切り替えについては、こちらの記事でも解説しています。
細かいところを見ていくと、まずは出だしのコードGM7→A13(onGの)変化がミソですね。
高音に移る所の駆け上がり3連フレーズ→シンコペーションでEm7に抜けるところは、このファルセータのクライマックスであり、一番美味しいところと思います。
後半は11thコードの平行移動ですが、この半音ぶつかりの11thコードはモデルノ系フラメンコギターではよく使われるボイシングです。


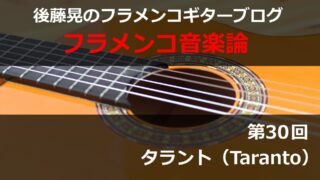
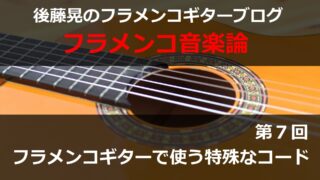
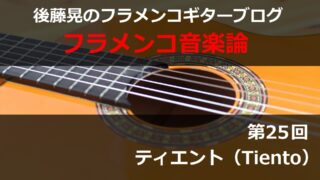
コメント