前回のファルセータ動画からだいぶ時間が空いてしまいましたので、ここらで一発いっておきたいです。
今回の演奏はファンダンゴ・デ・ウエルバです。
ファンダンゴ形式について
ファンダンゴはもともとアンダルシアの民謡ですが、フラメンコに取り入れられて以降、主にカンテを聴かせるための自由リズム形式として発展してきた形式群です。
そのなかで、ウエルバ地方のファンダンゴは民謡としての形を色濃く残していて、ハッキリした3拍子で演奏されます。
ファンダンゴ・デ・ウエルバ形式解説
ファンダンゴ・デ・ウエルバ(セビジャーナスも)はフラメンコになるのか?というと微妙なところですが、特に日本では踊りの初心者向けレパートリーとして不可欠の形式になっていて、セビジャーナスの次くらいに教わるものです。
ファンダンゴ・デ・ウエルバのリズム
ファンダンゴ・デ・ウエルバは3拍子なんですが、実はかなり難しいリズムです。
例えば、今回弾いた2つ目のファルセータがまさにそれなんですが「リズムは3拍、フレーズは2拍」で進行することがあります。
6拍・12拍のコンパスなので辻褄は合いますが、2拍単位でメロディが食って入るので慣れないと惑わされます。
これ、セビジャーナスにも同様のものがありますが、ファンダンゴ・デ・ウエルバのほうが顕著で、この形式の醍醐味=難しいポイントになっていると思います。
では、今回演奏したファルセータを個別に解説いたします。
1つ目のファルセータ【作者不詳】
1つ目のファルセータは1996年頃スペインでパコ・クルス(Paco Cruz)に習いましたが、このファルセータは当時のマドリードのギタリストの多くが弾いていて、ライブでも何度も耳にしました。
結局、誰の作なんでしょうね?謎です。
後半、Fでやっているアルペジオの下降フレーズは3連符で教わりましたが、長年弾いているうちに4連符(16分音符)のほうがしっくりくるようになって、今は4連符で弾いています。
2つ目のファルセータ【エル・ボラ】
2つ目のファルセータはエル・ボラ(Agustin Carbonell “Bola”)のもので、彼の2ndCD『Vuelo Flamenco』でも弾いているアルペジオ奏法主体のファルセータです。
ボラのバージョンはカポ無しでオクターブ上で弾いてますが、伴奏用に高いカポでも弾けるように1オクターブ下げるアレンジをしています。
エル・ボラはモダンスタイルのイメージが強いですが、こういう伝統的なフレーズもよく使います。
このファルセータも伝統的なファンダンゴ・デ・ウエルバのファルセータがベースになっていますが、その元のネタからして上で書いたような複合拍子(3拍子+2拍単位のフレージング)になっていて、全てのフレーズの頭がコンパスに対して2拍食って入っています。
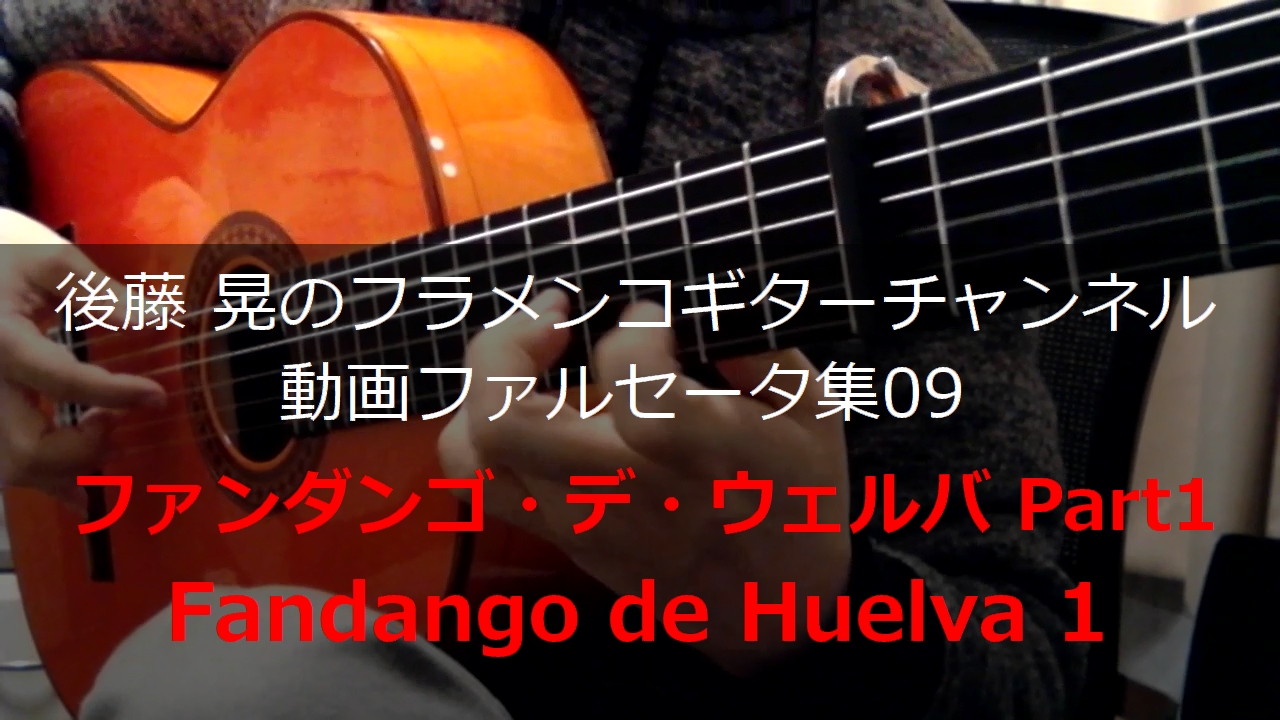

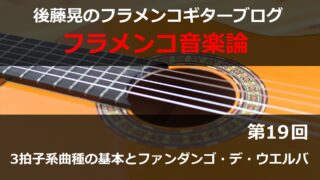
コメント