フラメンコ音楽論では前回まで12拍子系の形式をやってきましたが、今回から12拍子系の近縁のコンパスである変拍子系形式の学習に入ります。
今回は「3.3.2.2.2型コンパス」の概要と、その代表形式であるグアヒーラの解説です。
変拍子系のコンパスについて
変拍子系のコンパスは12拍子と同じく12拍のサイクルのなかに5つのアクセントを持つリズムですが、12拍子と異なり「アクセントとアクセントの間を1拍としてカウントする」ことが多く、その場合、1拍の長さが不均等な「変則5拍子」ということになります。
変則5拍子系のコンパスは、12拍子の一種と考えることも出来ますが、ソレア系の12拍子とは色々と異なる点もあるので、ここではカテゴリーを分けました。
変則5拍子系のコンパスは大別して2種類あります。
今回はブレリアの一型とも捉えられるリズムサイクルの「3.3.2.2.2型コンパス」を解説します。
3.3.2.2.2型コンパス
フラメンコの変拍子系形式は譜面にすると3/4拍子と6/8拍子の複合拍子で書かれることが多いですが、今回扱う3.3.2.2.2型の実態としては「ブレリアのたくさんあるリズムパターンのうち、一つの型に固定化したようなコンパス」です。
12拍子でのカウント
踊りの人は3.3.2.2.2型のコンパスを「12、1、2、」とブレリア式にカウントする事が多いのですが、これは、グアヒーラ・ペテネーラの踊りの振りが12拍子系形式からの流用が多いためと思われます。
ブレリア式の12拍カウントを書くと以下の通りです。
⑫ 1 2 ③ 4 5 ⑥ 7 ⑧ 9 ⑩ 11
※○の付いた数字がアクセント拍
リズムパターンとしては、ブレリアにも全く同一のものがありましたよね。
変則5拍子でのカウント
3.3.2.2.2型のもう一つのカウント方法として「1拍目と2拍目が長い5拍子」としてカウントするやり方があります。
① ○ ○ ② ○ ○ ③ ○ ④ ○ ⑤ ○
スペイン人はこの数え方の人が多い感じがするし、ブレリアとの差別化という点ではこちらの方が適しているのかも知れませんが、例えば「1拍目と2拍目の間の拍」などは5拍子カウントでは表現しにくいし、そういう細かいやりとりをするなら12拍子カウントのほうが優れているのではないでしょうか。
3.3.2.2.2型と12拍子系の違い
グアヒーラ(3.3.2.2.2)の音楽はアレグリアス(12拍子)と似ているし、ペテネーラ(3.3.2.2.2)の音楽はソレア(12拍子)と似ていますが、これらの最大の違いはコンパスへのメロディーの乗せ方(フレージング)でしょうか。
12拍子系は「1または12から入って10に解決するフレージング」が基本ですが、3.3.2.2.2型はブレリア式カウントで言うと「12から入って6に解決するフレージング」が主体です。
従って、コードの変わり目も12拍目と6拍目となります(3拍目で経過コードが入ることも多い)が、ジャマーダなどの終止拍はソレアやブレリアと同様に10拍目です。
ちなみに、これを変則5拍子カウントで言い換えると、フレージングは1拍目から入って3拍目に解決、コードの変わり目も1拍目と3拍目、ジャマーダなどの終止拍は5拍目、という事になりますね。
12拍子系ではコンパスもフレージングも多彩な変化がありますが、3.3.2.2.2型はそれに比べると固定的です。
グアヒーラ形式概要
単数形:Guajira
複数形:Guajiras
主な調性:Aメジャーキー
テンポ:130BPMから200BPM
今回は、3.3.2.2.2型コンパスの形式の中で演奏頻度が高いグアヒーラをご紹介しましょう。
グアヒーラは南国風(当時スペイン人が考える中南米のイメージ?)のメロディーが特徴で「逆輸入系形式」と呼ばれています。
逆輸入系形式はグアヒーラの他にコロンビアーナなどがあり、それらには共通の節回しがありますが、中南米のスペイン植民地からの引き上げ移民が伝えたメロディーがフラメンコに取り入れられたものだと言われています。
グアヒーラとコロンビアーナは拍子が違いますが、節回しは非常に良く似ています。注意すべきはグアヒーラのマチョで歌われる後歌でしょうか。
グアヒーラのマチョはブレリア(3拍子)で演奏する場合と、タンゴ(2拍子)で演奏する場合がありますが、歌はコロンビアーナの歌詞・メロディーを使うことが多く、ここの歌はブレリアで演奏する場合であっても、習慣的に「コロンビアーナ」と呼ばれます。
グアヒーラの調性
グアヒーラは主にAメジャーキーで演奏されます。
カポタストの位置は、女性歌手なら4カポ(実音C♯メジャーキー)、男性歌手なら1カポ(B♭メジャーキー)あたりが多いです。
グアヒーラのテンポ
グアヒーラの演奏テンポは、カンテソロの場合は速めの場合が多く、130BPMから180BPMあたりが中心ですが、踊りが入るとレトラの部分はゆっくりになって100BPMから150BPMくらいになります。
踊りの後歌はブレリアの速さ(180BPM以上)になりますが(前述の通り2拍子でやる場合もある)、コンパスとしては「3.3.2.2.2型に寄ったブレリア」という感じで、踊りの振りなどは、ほぼブレリアそのものです。
グアヒーラのギターコード
グアヒーラ形式で使われるギターコードの特徴は以下の2つでしょうか。
- ルートコード上でのM6→m6という動き
- 3コード以外の代理コードやパッシングディミニッシュの多用
1.は、Ⅳ→Ⅴ7(♭9)を内包した動きで、2.はパコ・デ・ルシア以降普及しました。3コード中心のカンティーニャス系より全体的に柔らかい音使いになりますよね。
グアヒーラの歌
以下に、最も代表的なグアヒーラの歌のコード進行を書いておきます。書式は次の通り。
- 変則5拍子の1拍目=12拍子でいう12拍目を頭にした3拍子で記載
- 1行でメディオコンパス(6拍)
- ○はコードチェンジ無しの拍
- キーはAメジャーで記載
- コンテスタシオン(合いの手)は歌が休みになる部分で、普通は0コンパス(コンテスタシオン無し)から2コンパス
- 歌の最後に2コンパスから4コンパス程度のエストリビージョが追加されることもある
|A ○ ○|E7 ○ ○|
|A ○ ○|○ ○ ○|
コンテスタシオン
|A ○ ○|F♯7 ○ ○|
|Bm7 ○ ○|○ ○ ○|
|○ ○ ○|F♯7 ○ ○|
|Bm7 ○ ○|○ ○ ○|
|E7 ○ ○|○ ○ ○|
|A ○ ○|○ ○ ○|
|○ ○ ○|F♯7 ○ ○|
|Bm7 ○ ○|○ ○ ○|
|E7 ○ ○|○ ○ ○|
|A ○ ○|○ ○ ○|
ディグリー(度数)表記版
|Ⅰ ○ ○|Ⅴ7 ○ ○|
|Ⅰ ○ ○|○ ○ ○|
コンテスタシオン
|Ⅰ ○ ○|Ⅵ7 ○ ○|
|Ⅱm7 ○ ○|○ ○ ○|
|○ ○ ○|Ⅵ7 ○ ○|
|Ⅱm7 ○ ○|○ ○ ○|
|Ⅴ7 ○ ○|○ ○ ○|
|Ⅰ ○ ○|○ ○ ○|
|○ ○ ○|Ⅵ7 ○ ○|
|Ⅱm7 ○ ○|○ ○ ○|
|Ⅴ7 ○ ○|○ ○ ○|
|Ⅰ ○ ○|○ ○ ○|
歌のコード進行の特徴としては、Ⅳコードの代理としてⅥ7→Ⅱm7が用いられます。2節目のF♯7→Bm7のところですね。
なお、踊りの後歌のコロンビアーナでは、本歌(レトラ)ではあまり使用しないⅣコード=Dが頻繁に使われます。
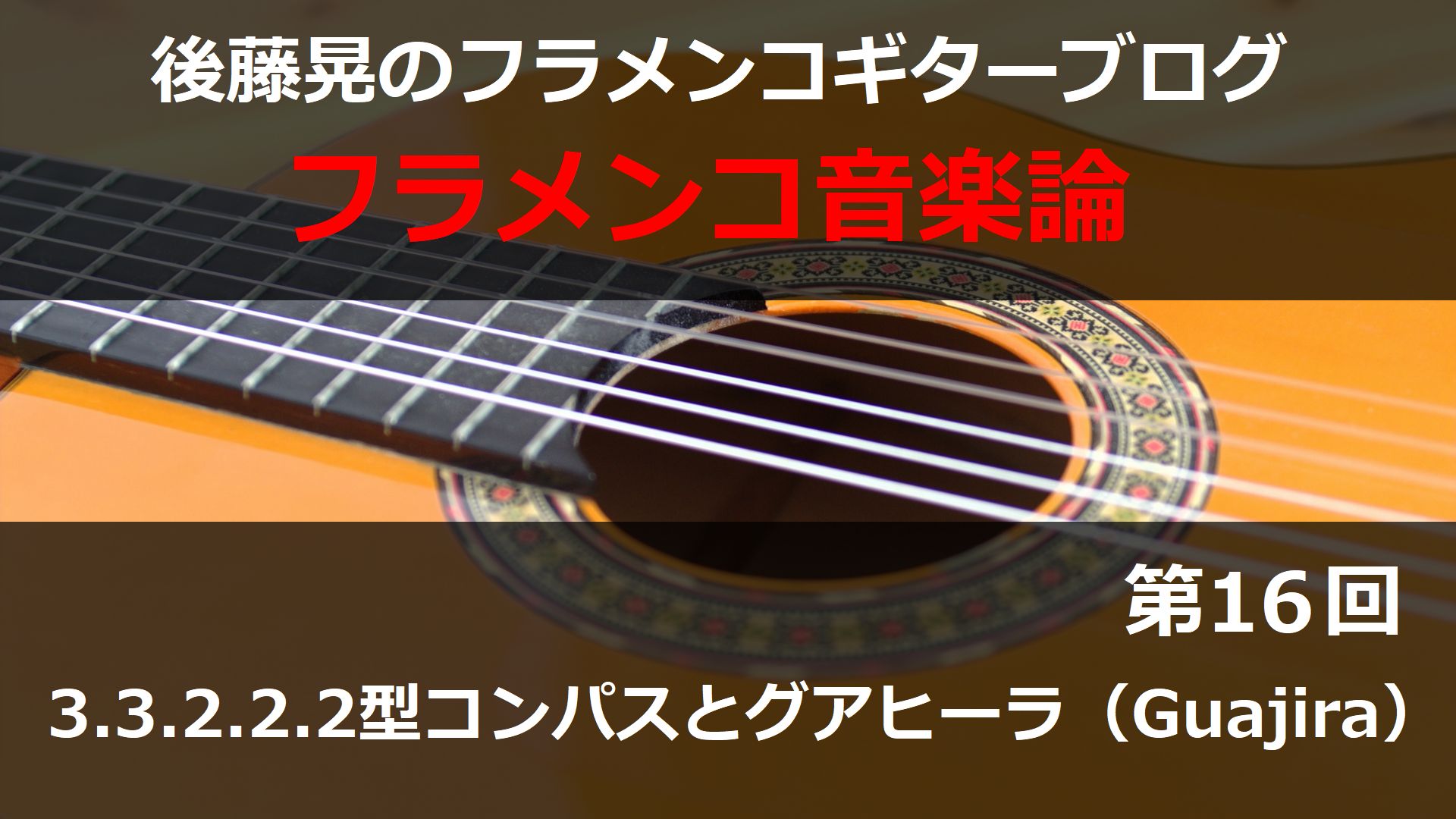
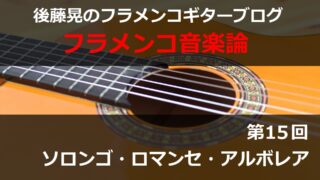
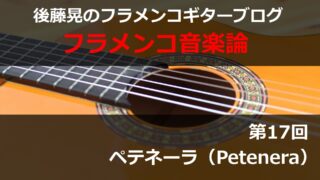
コメント