フラメンコ音楽論では12拍子系形式・変拍子系形式の解説を終え、今回からファンダンゴを中心とした3拍子系の形式解説に入ります。
「3拍子」というとシンプルなリズムと思われそうですが、この系統も12拍子に負けず劣らず奥深いものがあります。
ファンダンゴ系形式の分類
フラメンコの3拍子は、主にファンダンゴのリズムを起源としています。
ファンダンゴはアンダルシア地方の民謡ですが、かなり初期の段階からフラメンコに採り入れられてきました。
ファンダンゴ系の歌は、もともとはハッキリした3拍子のリズムでしたが、徐々にバリエーションが増えて、カンテの技巧を競う自由リズム形式としても発展しています。
ファンダンゴ系の形式を大雑把に分類すると、①ウエルバ系、②アバンドラオ系、③リブレ系の3種に分けられます。以下、個別にみていきましょう。
ウエルバ系
「ウエルバ系」というのは自分が勝手に設定したカテゴリーですが、ファンダンゴ・デ・ウエルバに代表される、主にアンダルシア西部で発展してきた軽いノリの3拍子のリズムを持つ形式群を指しています。
踊りの初心者向け形式として知られるセビジャーナスもこの系統のコンパスです。
特徴としては、ベースリズムは3拍子なのですが、フレーズは2拍で進行したりしていて、ちょっとしたポリリズム(異なるサイクルのリズムが同時に鳴っている状態)の様相になっています。
この系統のリズムの特殊性は、フラメンコのソレア系コンパスからの影響もあると思いますが、フラメンコ化されていない土着のファンダンゴ・デ・ウエルバやセビジャーナスも同じようなリズムなので、アンダルシア西部に民衆レベルで根付いている感覚なのでしょう。
この系統のリズムは、今回の記事の後半で詳細を解説いたします。
アバンドラオ系
アバンドラオは、ベルディアーレスやロンデーニャなどに代表されるアンダルシア中部・東部で発展してきたファンダンゴに使用されるリズムで、このリズムで演奏されるファンダンゴ全般をファンダンゴ・アバンドラオと呼びます。
ウエルバ系より重厚な印象ですが、フレーズがきっちりとした3拍子になっている事が多いので、ウエルバ系より分かりやすいかもしれません。
リブレ系
リブレ(自由リズム)系形式は、ファンダンゴのリズムを崩して自由に歌うものです。
リブレ系のファンダンゴは、カフェ・カンタンテの時代を中心に発展してきたもので、歌い手個人による数々のバリエーションが編み出されました。
代表的な形式としてはマラゲーニャやグラナイーナなどがあります。
フラメンコの自由リズム形式は、ファンダンゴ系だけではなく、シギリージャ系や2拍子系を崩して歌うものもありますが、形式数としてはファンダンゴ系が圧倒的に多いです。
また、リブレのファンダンゴのうち、アンダルシア東部のアルメリアや隣接地域のカルタヘナ、ムルシアなどの鉱山地帯を中心に発展した「カンテ・レバンテ」と呼ばれる独特の節回しの形式群があり、それらもかなり大きなグループとなります。
――このように、フラメンコの3拍子系形式はファンダンゴ系形式だけでもかなりの数にのぼりますが、今回は「ウエルバ系コンパス」と、その代表形式であるファンダンゴ・デ・ウエルバをとりあげます。
ファンダンゴ・デ・ウエルバ形式概要
単数形:Fandango de Huelva
複数形:Fandangos de Huelva
主な調性:ポルアリーバ(Eスパニッシュ調)
テンポ:130BPMから180BPM
ファンダンゴ・デ・ウエルバは、アンダルシアの西端に位置するウエルバ地方のファンダンゴで、軽快な3拍子が特徴です。
アンダルシア中部・東部のファンダンゴ・アバンドラオとともに、民謡としてのファンダンゴの原型を色濃く残していて、ファンダンゴ系形式を学ぶ上で基本になる形式です。
現在でも、ウエルバでは民謡・民族舞踊としてのファンダンゴのコンクールやイベントが頻繁に開催されています。
ウエルバ系コンパス
ファンダンゴ・デ・ウエルバなど、ウエルバ系のコンパスは頭の拍が強いシンプルな3拍子がベースになっていますが、フレージングに癖があります(後述)。
テンポは速めの場合が多いですが、結構幅があって、概ね130BPMから180BPMくらいです。
ウエルバ系コンパスのカウント方法
ファンダンゴ・デ・ウエルバのコンパスカウント方法は、コンパスの頭を1からカウントするのが普通ですが、踊りの場合ブレリアの振りからの流用も多いため、ブレリア式にコンパスの頭を12または6としてカウントする場合もあります。
基本は12拍で1コンパスですが、メディオコンパスも非常に多いです。
以下にファンダンゴ・デ・ウエルバの基本コンパスを表にします。○が付いた数字がアクセント拍。
頭拍を1からカウントする場合
① 2 3 ④ 5 6 ⑦ 8 9 ⑩ ⑪ 12
頭拍を12としてカウントする場合
⑫ 1 2 ③ 4 5 ⑥ 7 8 ⑨ ⑩ 11
ファンダンゴ・デ・ウエルバは、後ろから2拍目が締めくくりの拍で、1からのカウントだと11拍目、12からのカウントだとブレリアと同じ10拍目です。
12からのカウントのほうがブレリアと互換性があるので、人によってはそのほうが分かりやすいかもしれませんが、ここでは、1からのカウントを基準にして解説していこうと思います。
メディオコンパスで捉える
ファンダンゴやセビジャーナスなどの3拍子系形式は、12拍で捉えるより半分の6拍(メディオコンパス)で捉えたほうが何かと融通が効きます。
ファンダンゴ系の3拍子は12拍子系ほどはリズムバリエーションが無いため、6拍の基本リズムパターンとして以下の2つだけおぼえておけば大丈夫でしょう。
通常コンパス
① 2 3 ④ 5 6
締めくくりのコンパス(5拍目で終止)
① 2 3 ④ ⑤ 6
この2つのパターンが、全ての3拍子系コンパスの基礎となります。
なお、自分が考案した「コンパス=サイクル理論」では、3拍子系と12拍子系と3.3.2.2.2型コンパスを統合して、全て同じ「6サイクル」で捉えるという方法論を考案しましたので、是非そちらもご一読下さい。
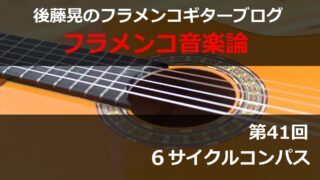
ウエルバ系コンパスのフレージング
以上のように、ウエルバ系3拍子のベースリズムはシンプルなのですが、その上に乗っかるフレーズが曲者なのです。
ファンダンゴ・デ・ウエルバやセビジャーナスのフレージングは1拍目から入って5拍目に向かうものが基本ですが、2拍単位でのフレージングが非常に多いのです。
その場合、コンパスは3拍×2で6拍ですが、フレーズは2拍×3で6拍となって、3拍目と4拍目にズレが生じることになります。下に図示します。
コンパス ① 2 3 ④ 5 6
フレーズ ① 2 ③ 4 ⑤ 6
コードチェンジポイントも、普通の3拍子は小節の頭である4拍目でコードが変わりますが、ファンダンゴ・デ・ウエルバの場合は、コードもフレーズに合わせて3拍目で変わるパターンが多いです。このポリリズムこそが、ウエルバ系コンパスのミソでしょう。
セビジャーナスを含むウエルバ系コンパスの曲種は、普通の3拍単位のフレージングと今解説した2拍単位のフレーズが混合したりするところが難しいところですよね。
ちなみに、ブレリアでも2拍×3と3拍×2がクロスする事は多々あるし、フラメンコとアンダルシア民謡に共通する普遍的感覚なんだと思います。
2拍ないし3拍食って入るフレージング
今書いた「2拍で進行するフレージング」ということの関連になりますが、ウエルバ系コンパスで特徴的なのが「前のコンパスから2拍ないし3拍食って入るフレージング」です。
メディオコンパスの6拍カウントでいうと「前のコンパスの4拍目か5拍目」から入るのですが、とくにギターのファルセータは昔からこれが多用されています。
自分自身も、慣用句ということで長年演奏するうちに慣れましたが、最初は「何故ここから?」みたいな違和感があったのをおぼえています。
――ファンダンゴ・デ・ウエルバやセビジャーナスは「初心者向け形式」とされていますが、こんな事情があるので、実は相当マニアックで惑わされやすいリズムだと思います。
ファンダンゴ・デ・ウエルバの調性
ファンダンゴ・デ・ウエルバは、通常はポルアリーバ(Eスパニッシュ調)で演奏されます。
歌の本体部分はEスパニッシュ調の平行調であるCメジャーキーが中心になることが多いですが、もう一つの平行調であるAマイナーキーや、その同主調のAメジャーキーで歌われることもあります。
そんな感じで、途中は色んなキーに行きますが、最後の落ちにはF→Eが来てミの旋法=スパニッシュ調へ戻っていくのが特徴です。
カポタストの位置はソレアよりやや低めで、女性歌手なら6カポ(実音B♭スパニッシュ調)、男性歌手は3カポ(実音Gスパニッシュ調)くらいが中心です。
ギターのマルカール
以下にファンダンゴ・デ・ウエルバで弾かれるギターのマルカールパターンを図示します。○はコード変化の無い拍、1行で1コンパス(12拍)の3拍子で書きます。
|E ○ Am|○ ○ ○|G F E|○ ○ ○|
基本パターンはこの12拍サイクルですが、このパターンがすでに2拍単位フレージングを内包していて、3拍目でAmにコードチェンジするのがポイントです。
ファンダンゴ・デ・ウエルバの歌
ファンダンゴ・デ・ウエルバの歌は、元ネタが「皆で踊るための民謡」ということがあって、サイズが6コンパスと決まっています。
ただし、フラメンコのファンダンゴ・デ・ウエルバは6拍単位での伸び縮みもあって、とくに踊りが入らない場合は、歌い手の裁量で自由に伸縮させる傾向です。
以下に、最も一般的な歌の進行をご紹介します。書式は次の通り。
- 3拍子で記載
- 1行でメディオコンパス(6拍)
- ○はコードチェンジ無しの拍
- 複数のコードの可能性があるところは「,」で区切る
- キーはポルアリーバ(Eスパニッシュ調)で記載
- 半コンパス(6拍)単位でサイズが変わる事がある
|C,G7 ○ ○|○ ○ ○|
|○ ○ C|○ ○ ○|
|C ○ ○|○ ○ ○|
|C7 ○ F|○ ○ ○|
|○ ○ G7|○ ○ ○|
|○ ○ C|○ ○ ○|
|○ ○ ○|○ ○ ○|
|○ ○ G7|○ ○ ○|
|○ ○ ○|○ ○ ○|
|○ ○ C|○ ○ ○|
|C7 ○ F|○ ○ ○|
|G F E|○ ○ ○|
ディグリー表記版
|♭Ⅵ,♭Ⅲ7 ○ ○|○ ○ ○|
|○ ○ ♭Ⅵ|○ ○ ○|
|♭Ⅵ ○ ○|○ ○ ○|
|♭Ⅵ7 ○ ♭Ⅱ|○ ○ ○|
|○ ○ ♭Ⅲ7|○ ○ ○|
|○ ○ ♭Ⅵ|○ ○ ○|
|○ ○ ○|○ ○ ○|
|○ ○ ♭Ⅲ7|○ ○ ○|
|○ ○ ○|○ ○ ○|
|○ ○ ♭Ⅵ|○ ○ ○|
|♭Ⅵ7 ○ ♭Ⅱ|○ ○ ○|
|♭Ⅲ ♭Ⅱ Ⅰ|○ ○ ○|
このコード進行はアバンドラオ系やリブレ系を含む、全てのファンダンゴ系形式の基礎となるものですので、良くおぼえておきましょう。
――次回は、歌の起源としてはファンダンゴ系から外れますが、ファンダンゴ・デ・ウエルバと共通のコンパスをもつ関連形式として、踊りの入門曲であるセビジャーナスを解説しようと思います。
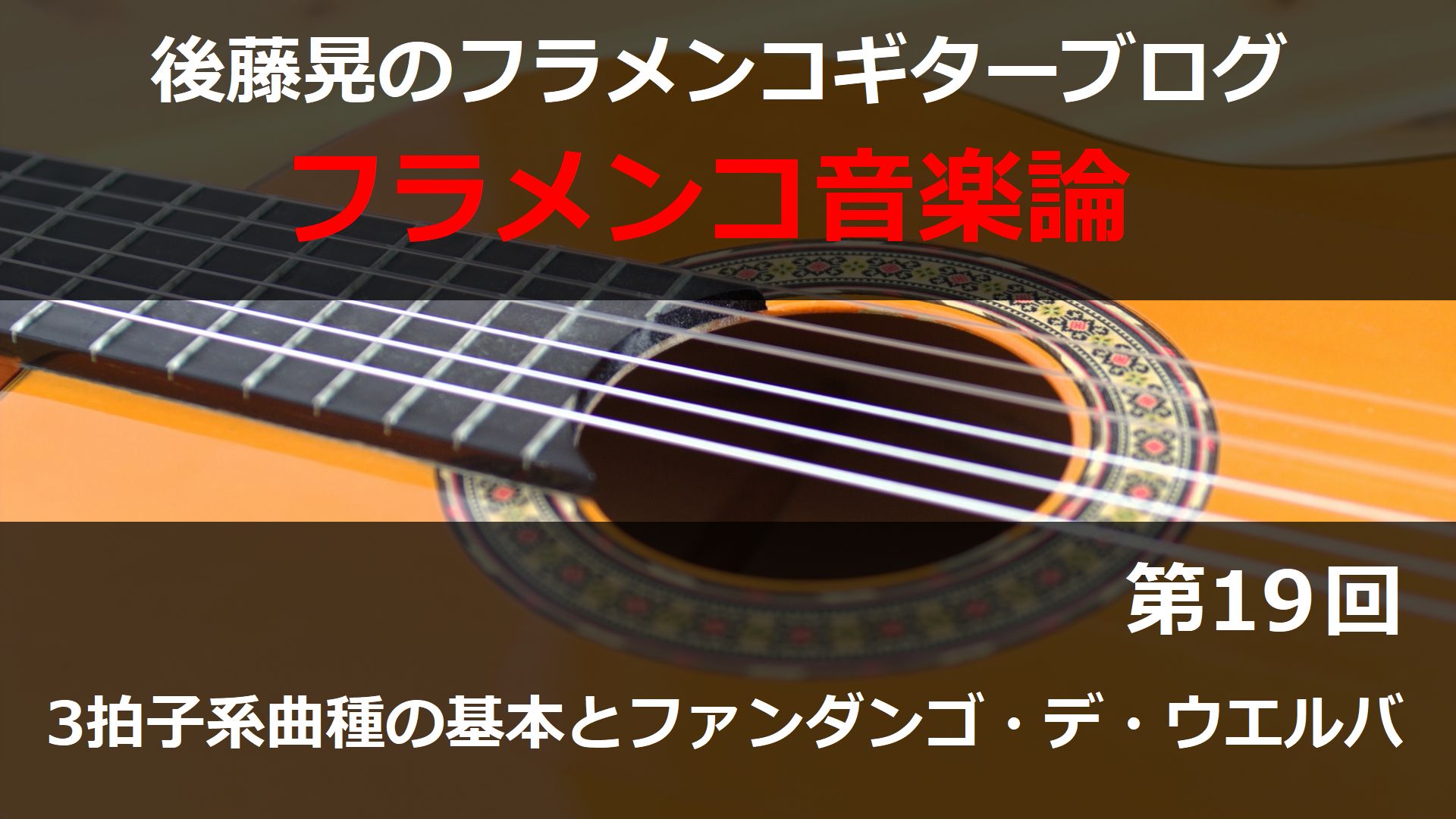
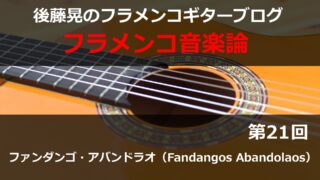
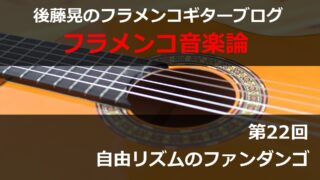

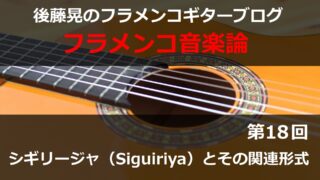
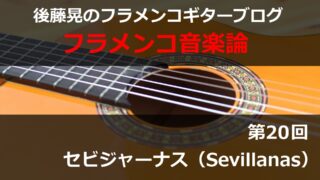
コメント