2018年7月12日に当ブログを開設してから、間もなく5年が経過しようとしています。今回はブログ開設5周年記念として「第2回人気コンテンツランキング」をお届けします。
- 今回の企画について
- ランキングのルールなど
- 第2回人気コンテンツランキング
- 第1位 様々なリズムパターン【音楽理論ライブラリー15】
- 第2位 フラメンコのリズム形式【フラメンコ音楽論08】
- 第3位 フラメンコで使われる音階とコード【フラメンコ音楽論04】
- 第4位 サウンドクラウド(SoundCloud)の音質
- 第5位 フラメンコギターで使う特殊なコード【フラメンコ音楽論07】
- 第6位 ブレリア(Buleria)【フラメンコ音楽論12】
- 第7位 フラメンコの専門用語【フラメンコ音楽論02】
- 第8位 シギリージャ(Siguiriya)とその関連形式【フラメンコ音楽論18】
- 第9位 2拍子系形式の基礎とタンゴ(Tango)【フラメンコ音楽論24】
- 第10位 楽器や弦などについて【Webで学ぶフラメンコギター02】
- 第11位 モードとダイアトニックスケール【音楽理論ライブラリー09】
- 第12位 モニタースピーカーについて【低予算で実現するコンテンツ制作03】
- 第13位 パルマのリズムパターン【フラメンコ音楽論44】
- 第14位 ソレア(Soleá)【フラメンコ音楽論09】
- 第15位 3拍子系曲種の基本とファンダンゴ・デ・ウエルバ(Fandango de Huelva)【フラメンコ音楽論19】
- 第16位 フラメンコ奏法の基本【Webで学ぶフラメンコギター04】
- 第17位 ノンダイアトニックコードスケール【音楽理論ライブラリー10】
- 第18位 ラスゲアード奏法【Webで学ぶフラメンコギター08】
- 第19位 ルンバ・コロンビアーナ・ミロンガ・サンブラ【フラメンコ音楽論31】
- 第20位 爪の作り方【Webで学ぶフラメンコギター03】
- 第2回人気コンテンツランキングまとめ
- 今後の予定など【近況と活動報告】
今回の企画について
3年前の2020年7月にブログ開設2周年記念企画として「人気記事・動画ランキング」を企画しました。

この記事では、当ブログを開設した2018年7月から2020年6月までの初期2年間の記事・動画のアクセス数をランキングにしてまとめました。
こういうランキングの目的は、ブログ内でどのコンテンツが良く見られているのかを把握することで、その後のブログ活動に役立てようというものです。
また、こういう節目の記事で記録にして残すことで、後から読み返した時に色々気付く事もあるのかなと。
今回は第2回という事で、第1回時点に比べてコンテンツ数も数倍に増えているため、どういうランキングになるのか自分自身とても興味深かったです。
Googleアナリティクスの切り替えという事情
今回の企画をやるに当たって、もう一つ大きなキッカケとなった事情がありました。
それは、自分がブログの分析に使っている「Googleアナリティクス」の旧バージョン(GA3=ユニバーサルアナリティクス)が2023年6月末をもって廃止となり、新バージョンであるGA4に切り替わるということです。
ここ一年ほど、Googleアナリティクスは旧バージョンとGA4を平行して使っていたのですが、GA4は更新タイミングが遅かったり使い慣れていなかったりで、直近の2023年6月末まで、主に旧バージョンのアナリティクスでアクセス分析をしていました。
ちなみにですが、GA3とGA4はデータを共有するわけではないので、GA4登録前の過去のデータはGA3上に残ったものを参照する必要があります。
今回の5周年記念企画は、GA3に残っているアクセスデータを整理して記録しておくという作業の一環でもあったわけです。
ランキングのルールなど
前回の2周年記念企画時は、ブログ記事とYouTube動画の両方のランキングを掲載しましたが、今回はブログ記事のランキングのみとしました。
前回の動画ランキングではっきりしたのですが、当ブログ連動のフラメンコギターチャンネル(YouTube)の場合、動画毎の人気差が小さく、古い動画ほど上位に来るという傾向なので、正直ランキング化してもあまり面白くないんですよね。
そういうわけで今回はブログ記事のみの集計になったのですが、そのぶん前回より大幅に拡充してTOP20までご紹介することにしました。
もう一つ、今回のランキングの集計対象期間ですが、2021年2月7日から2023年6月30日までとしました。
締め日の2023年6月30日は旧Googleアナリティクスの公式な最終日(実際にはこの記事執筆時点でもまだ集計が続いているようですが)ということですが、集計開始日の2021年2月7日というのは、URL(パーマリンク)変更の関係です。
2021年2月6日に当ブログとゲーム音楽演奏ブログの全記事のURLを日付ベースのものから内容が分かる文字列に変更をしたのですが(詳細は下の記事を参照)、これ以前の旧URLと新URLはGoogleアナリティクス上では別ページとして集計されるため、新旧URLのアクセスデータ統合作業が膨大になってしまいます。そんな理由で、新URLのみ(つまり2021年2月7日以降)の集計ということにしました。
こうしたほうが前回ランキングの統計期間(2018年7月から2020年6月)と被らず、前回からの変化がより明確になって良いかな?というのもあります。
他のルールとしては、トップページやカテゴリーページなどは含めず、個別記事のみの集計としました。
第2回人気コンテンツランキング
では、前置きが長くなりましたが「第2回人気コンテンツランキング」いってみましょー。
第1位 様々なリズムパターン【音楽理論ライブラリー15】
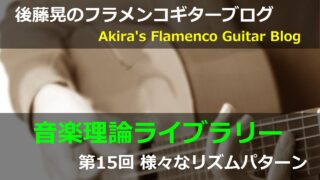
初版公開日:2020/6/10
今回の第1位は、音楽理論関係の話題をまとめた「音楽理論ライブラリー」のリズムに関する記事です。この記事ではフラメンコに限定せず、全音楽ジャンルの一般的なリズムパターンを簡潔に解説したものですが、一つのページでこれだけ網羅的にリズムパターンの解説をしているものは珍しく、需要も高いんだと思います。
第2位 フラメンコのリズム形式【フラメンコ音楽論08】
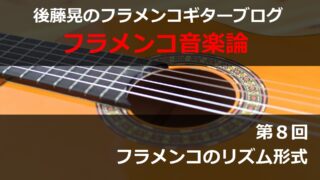
初版公開日:2019/2/17
備考:前回5位
自分としては、この記事が1位だと思っていました。このページは当ブログ最大の人気シリーズ「フラメンコ音楽論」の目次・ナビゲーション的な役割を果たしていて、このページから入って全個別型式の解説へ行けるように作ってあるので、結果として一番見られているのでは?と思っていました。前回5位に甘んじていたのは、このページからリンクを張り巡らせてポータル化したのが前回集計期間の終わりのほうだったせいだと思われます。
第3位 フラメンコで使われる音階とコード【フラメンコ音楽論04】
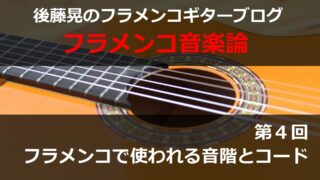
初版公開日:2019/1/17
備考:前回2位
フラメンコ音楽で使われる音階と和音の解説をした記事です。いわゆるミの旋法=スパニッシュスケールを中心にそれに対応したダイアトニックコードを考察するなど、結構踏み込んだ内容になっています。フラメンコみたいな民族音楽系のものを理論化して扱うのは限界があるのですが、こういう需要は確実にあると思うし、そのわりにフラメンコ音楽の理論化に挑戦しているページはほとんど無いので、必然的にアクセスを集める結果となっているのではないかと。
第4位 サウンドクラウド(SoundCloud)の音質

初版公開日:2018/11/28
これは初期の頃に書いた短いコラム的な記事ですが、ある時期から伸び始めて、それからずっと一定のアクセスを稼ぎ続けています。こういうプラットフォーム系の記事は、ハマると(ブログテーマに合致していて、かつ需要が高く、既存情報が少ない)安定したアクセス源になってくれます。
第5位 フラメンコギターで使う特殊なコード【フラメンコ音楽論07】
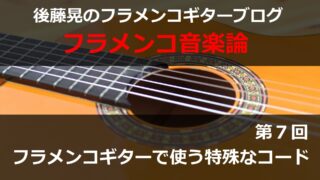
初版公開日:2019/2/9
備考:前回1位
この記事は、3位の「フラメンコで使われる音階とコード」の補完的なもので、ギターコードにフォーカスして具体的なコードフォームを掲載しています。前回はこれが1位だったのですが、フラメンコギターブログということで、ギターをやっている人のアクセスが多いものと思われ、それはギター教室の集客にも繋がるので大変ありがたい事です。
第6位 ブレリア(Buleria)【フラメンコ音楽論12】
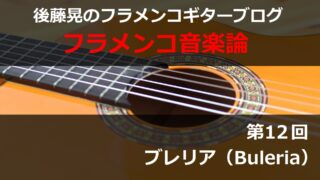
初版公開日:2019/3/31
備考:前回4位
「フラメンコ音楽論」の中で、形式解説系のトップに来たのはブレリアでした。ブレリアのコンパスはソレアから発展してきた流れを踏まえないと完全には理解出来ないし、変幻自在に変化するために体系化が難しいのですが、それに挑んだ記事です。フラメンコを始めて必ずといって良いほどぶつかる壁なので、当然ながら高い需要があると考えます。
第7位 フラメンコの専門用語【フラメンコ音楽論02】
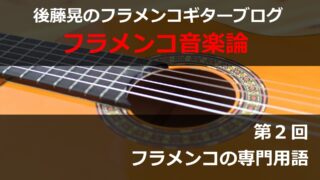
初版公開日:2019/1/4
備考:前回3位
「フラメンコ音楽論」の初期にアップした用語辞典です。フラメンコには業界内でしか通じない専門用語が多すぎるので、まずこれをまとめておく必要があると思いました。ただ、バイレ(踊り)系の用語を扱うページは結構あるので、ここではフラメンコの音楽面の用語を中心に据えることにしました。
第8位 シギリージャ(Siguiriya)とその関連形式【フラメンコ音楽論18】
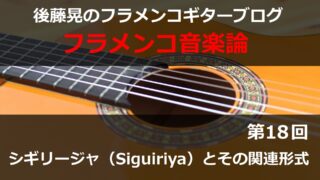
初版公開日:2019/6/6
ブレリアに続いて、形式解説系記事の二番人気はシギリージャです。シギリージャはフラメンコのリズムの中でも屈指の変態リズムで、一般的な拍子の発想では理解出来ないと思います。実際、このリズムを耳にして謎に思った人が検索して尋ねて来るのだと思います。
第9位 2拍子系形式の基礎とタンゴ(Tango)【フラメンコ音楽論24】
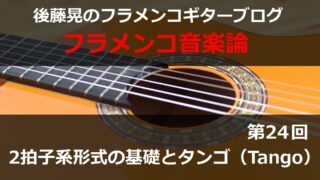
初版公開日:2019/7/26
形式解説系の三番人気はタンゴです。まあ、タンゴ個別形式というより2拍子系リズムの総論的な内容でもあるので、フラメンコの2拍子形式の事を知りたい人が見に来るページなんだと思います。
第10位 楽器や弦などについて【Webで学ぶフラメンコギター02】
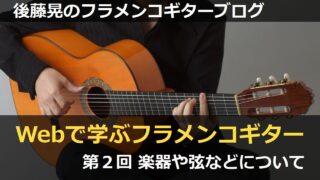
初版公開日:2020/9/16
「Webで学ぶフラメンコギター」は自分が教室で教えている内容の一部を文章化したもので、この記事は、楽器や弦など道具について解説したものです。フラメンコギターの初心者は、まず楽器や弦の銘柄の選び方で悩むと思うので、なるべく具体的にまとめました。
第11位 モードとダイアトニックスケール【音楽理論ライブラリー09】
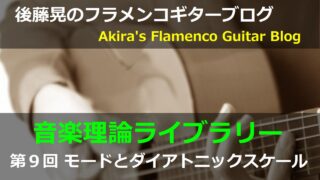
初版公開日:2020/4/26
これも教則的な内容の記事です。当ブログで教則的な内容を扱う記事シリーズは複数あるのですが、「フラメンコ音楽論」はフラメンコ全般の話題を、「Webで学ぶフラメンコギター」はフラメンコギターの技術的・物理的な話を、「音楽理論ライブラリー」はフラメンコに限定せず、全音楽ジャンル共通の音楽理論系の話題を扱っています。こういう教則系の内容は、ギタリストや他の楽器プレイヤーからの需要は高いものと思います。
第12位 モニタースピーカーについて【低予算で実現するコンテンツ制作03】

初版公開日:2020/11/9
ここで機材関連の記事が来ましたね。機材関連もDTMや動画制作が盛んな昨今、非常に需要が高い話題だと思いますが、なにしろライバルも多いジャンルなので、よほど有用性・独自性が無いとなかなか検索から来てはもらえません。自分の場合、こういう機材系の記事を書く時は、「ローコスト」というテーマを徹底し、基本的に実体験に基づいた内容にして他と差別化しています。
第13位 パルマのリズムパターン【フラメンコ音楽論44】
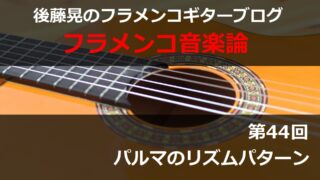
初版公開日:2020/8/19
パルマ(手拍子)はフラメンコアンサンブルの要となるもので非常に重要です。歌い手は常にパルマを要求されるし、踊りをやっていても、ある段階までいくと必ず他の人が踊るバックでパルマを叩いてコンパスを支える機会が訪れます。このように必須のスキルなのですが、日本語で体系的に解説されている情報は非常に少ないので、自分なりの体系化を試みたこの記事が役立ってくれたら嬉しいです。
第14位 ソレア(Soleá)【フラメンコ音楽論09】
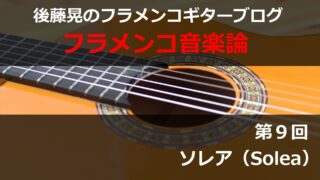
初版公開日:2019/2/27
形式解説系記事の四番人気はフラメンコの母、ソレアです。フラメンコを理解する上では最重要な根幹形式であり、アレグリアスもブレリアもカーニャもバンベーラも、さらに言うならグアヒーラやペテネーラも、12拍子系のリズムを持つ形式は全てソレアから派生したものなのです。でも、ソレアやシギリージャの解説ページが上位に入っているということは、ちゃんとフラメンコの根幹部分にも興味を持って学びたいという需要が少なからずあるのだと感じます。
第15位 3拍子系曲種の基本とファンダンゴ・デ・ウエルバ(Fandango de Huelva)【フラメンコ音楽論19】
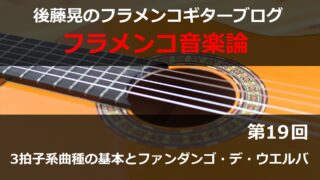
初版公開日:2019/6/14
形式解説系五番人気は、フラメンコの3拍子形式の総論から、その根幹となっているファンダンゴ・デ・ウエルバのコンパスを論じた記事です。9位の2拍子系と対になるものですが、「フラメンコ+2拍子」「フラメンコ+3拍子」といったワードで検索して来る方が多いのかな。
第16位 フラメンコ奏法の基本【Webで学ぶフラメンコギター04】
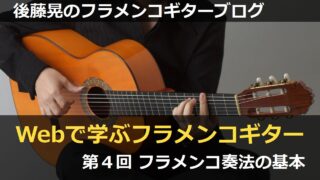
初版公開日:2020/10/22
教則系の記事です。これはフラメンコギターで使う奏法の概要を総論的に解説した記事で、もう少し上の順位かと思っていましたが(自分の願望?)、同じ「Webで学ぶフラメンコギター」の楽器と弦の記事みたいに、よりお手軽に回答が得られそうな記事が上位に来るだろう事も理解はできます。
第17位 ノンダイアトニックコードスケール【音楽理論ライブラリー10】
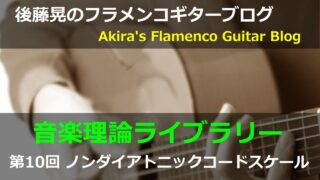
初版公開日:2020/5/5
「音楽理論ライブラリー」の記事です。ノンダイアトニックコードスケールとは、一つのキーの中で、転調までは行かないけど臨時記号(♯や♭)が付いたコード(ノンダイアトニックコード)が出てきた時、それに対処するための音階(スケール)なのですが、全ての音楽において臨時記号の付け方というのはセンスが現れる所だし、とりわけフラメンコ音楽ではミの旋法絡みの臨時記号の使い方は重要ものなのです。
第18位 ラスゲアード奏法【Webで学ぶフラメンコギター08】
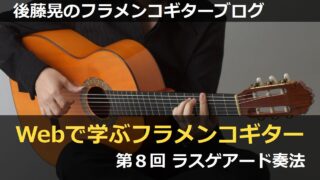
初版公開日:2021/1/11
このあたり教則系記事が固まっていますね。フラメンコギターの奏法の中でも、最も特徴的で効果も派手なラスゲアード奏法は他ジャンルのギタリストからの関心も高いようです。
第19位 ルンバ・コロンビアーナ・ミロンガ・サンブラ【フラメンコ音楽論31】
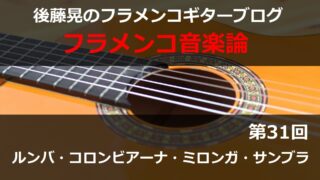
初版公開日:2019/10/17
形式解説系記事です。これは2拍子系形式解説の最後に「その他の2拍子系」としてオマケ的に書いた記事ですが、この中ではルンバが重要度が高く、具体的なリズムパターンを示して解説しています。ジプシーキングスをはじめ、フラメンコ周辺ジャンルではこのルンバのリズムは基本中の基本なので、関心も高いのではないでしょうか。
第20位 爪の作り方【Webで学ぶフラメンコギター03】
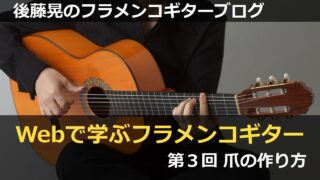
初版公開日:2020/10/15
第20位はギターを弾くための「爪」についてです。爪の作り方はフラメンコギターやクラシックギターを弾く上で音色やテクニックのスムーズさを決定付ける重要なもので、日常的に悩んでいるギタリストは多いと思うのですが、フラメンコギター向けの爪の作り方に関して掘り下げている情報は少ないので、自分の経験を基に細かいことまで分析しながら書いてみました。
第2回人気コンテンツランキングまとめ
今回のランキング企画、いかがでしたでしょうか?自分自身にとっても示唆に富む内容で、楽しみながら一気に執筆しました。
3年前の第1回ランキングで上位だった記事は、今回も全てTOP10に入っていて変わらぬ強さを示しました。ただ、第1回ではフラメンコ音楽論の記事が上位20位くらいまでを独占していたのが、今回は「音楽理論ライブラリー」「Webで学ぶフラメンコギター」等の記事も結構入って来ましたよね。
全体の傾向として教則的な内容の記事が人気であり、このブログはそういう「学び」の需要に支えられているのだな、ということを改めて感じております。
個人的には動画系の記事が1本もランクインしていなかったのが少し寂しかったです。
演奏動画やオリジナル曲音源は作るのが非常に手間がかかる(体感で文章のみのコンテンツの10倍とかそれ以上)のですが、動画はYouTubeのほうで再生されてブログの解説ページまで来てくれないことのほうが多いだろうし仕方ないのかな。いや、でもゲーム音楽演奏ブログのほうは動画ページが上位を占めてるしなぁ。
まあ、このブログとゲーム音楽演奏ブログでは運営方針も読者の層も違うので、こちらのブログは学び需要中心という事なのでしょう。時間が出来たら教則動画シリーズでも始めようかな。
今後の予定など【近況と活動報告】
本当は、この記事を出す前に「近況と活動方針2023年夏号」を公開する予定だったのですが、今、いろいろあって身の回りの状況が二転三転していて、自分自身の生活の方向性が定まってからでないとギター活動やブログの方針も立てにくいということで、ネタが決まっていた5周年記念企画を先に執筆・公開することにしました。
時期が来ましたら、改めて直近の報告と今後の方針などまとめたいと思います。状況によっては2023年夏号はパスして次は秋号か2024年新年号になってしまうかもしれませんが。
あと、今回の企画をするに当たって、ゲーム音楽演奏ブログのほうのコンテンツも同様にデータを取ってランキング化しましたので、近いうちにあちらのブログにて公開するかも知れません。今ハッキリと予定しているのはそれくらいです。
※2023年7月23日追記
ゲーム音楽演奏ブログでもランキング企画実施いたしました!
ギターやブログの活動自体は、(ここ数か月がそうであるように)諸事情から一時的に更新が滞ることはあるかも知れませんが、辞めることは考えておらず、出来るペースでの活動を続けていく所存ですので、これからもどうぞよろしくお願いいたします!
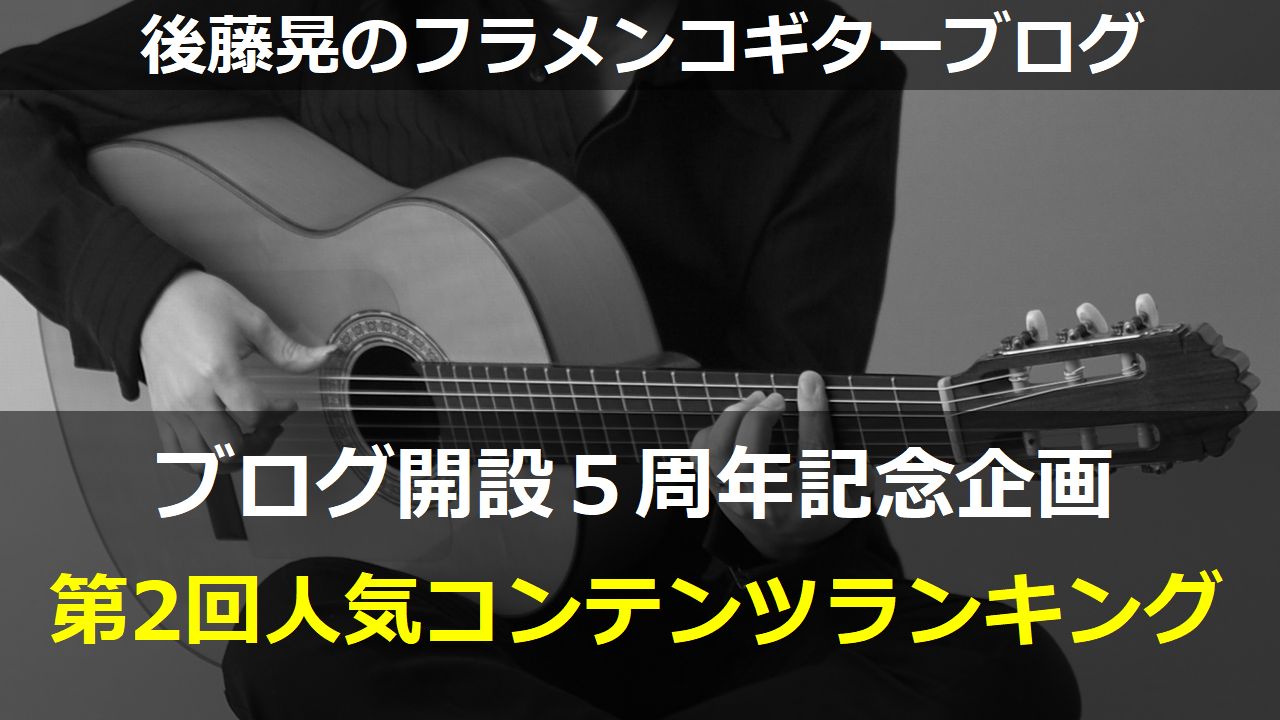
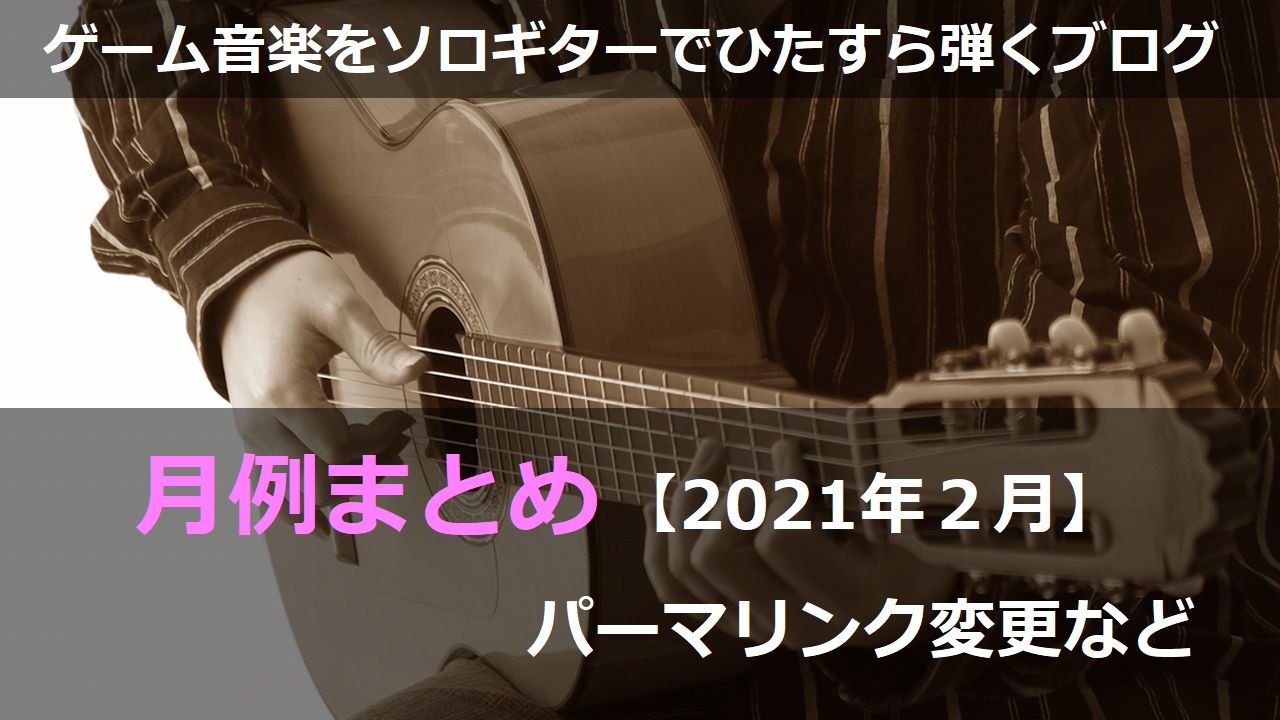
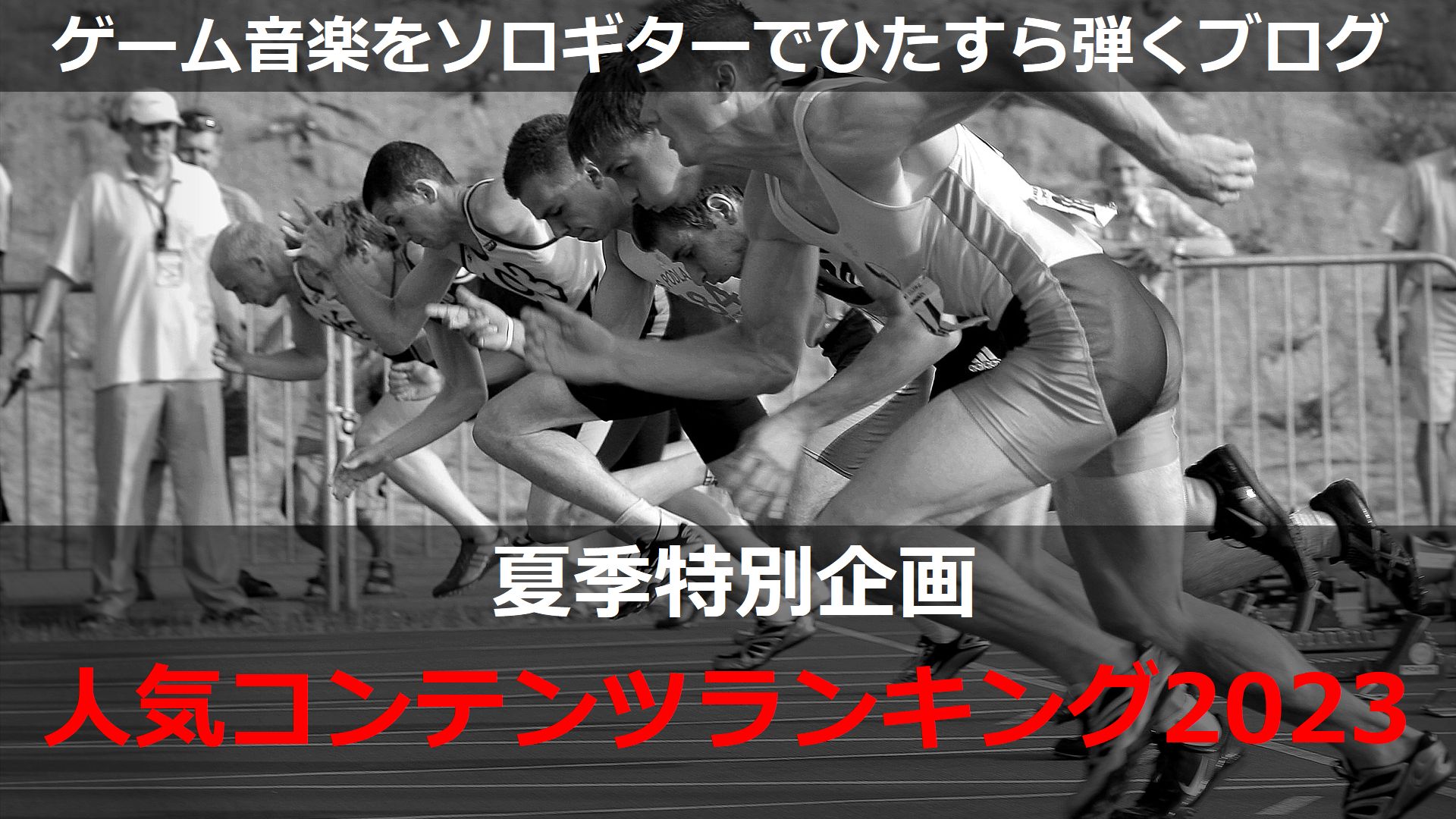
コメント